Manfred Eicher & his ECM
須永春彦

| ●注1 | Bob Degen(ボブ・ディーゲン)。西ドイツのenja(エンヤ)レーベルに数枚のリーダー作があり、特に「Children of the Night」(enja 3027)では日野皓正・元彦兄弟と共演している。また、ECMでは、アデルハルト・ロイディンガーの「Schattseite」(ECM 1221)に参加している。 |
| Adelhard
Roidinger Bass Heinz Sauer Tenor Saxophone Bob Degen Piano Harry Pepl Guitar Werner Pirchner Vibraharp, Marimba Aina Kemanis Voice Michael DiPasqua Drums, Percussion |

| ●注2 | Marion Brown(マリオン・ブラウン)。ECM第4作「Afternoon of a Georgia Faun」は彼のリーダー作である。マリオンさん自薦のアルバムだそうです。 |
| Marion
Brown alto saxophone, zomari, percussion Anthony Braxton alto and soprano saxophones, clarinet, contrabass clarinet, chinese musette, flute, percussion Bennie Maupin tenor saxophone, alto flute, bass clarinet, acorn, bells, wooden flute, percussion Chick Corea piano, bells, gong, percussion Andrew Cyrille percussion Jeanne Lee voice, percussion Jack Gregg bass, percussion Gayle Palmoré voice, piano, percussion William Green top o'lin, percussion Billy Malone african drum Larry Curtis percussion |
| ●注3 | 筆者は以前、御茶の水のdisc UNION1号店で、マンフレート・アイヒャーの参加しているレコードを見つけて感激したが、多分この時の吹き込みであろう。ああ、買っておけばよかった……。 |
『私にとって興味があるのは、いろいろな音楽の要素をひとつの流れに、もしくは新しい流れに組み入れていくことです。これを私は、フリー・ミュージックと呼びますが、この新しい流れは新しい芸術につながるわけで、つまり対話(ダイアローグ)と審美学を軸にして生み出される音楽を創り出したい、ということなんです。』
『当時(1960年代末)の西ドイツでは、MPSレーベルしか存在しませんでしたし、フリー・ミュージック、ジャズ、コンテンポラリー・ミュージックなどには援助らしい援助は行なわれていなかったのです。あるとき、私はミュンヘンにあるレコード店へブラリと立ち寄ったのです。そこには“ジャズを郵送にて”(Jazz by Post)という看板がかかっていたからです。[●注4] そこのオーナーであるエガーさんという人が、レコードを制作してみないかと話を持ちかけてきたのです。1969年のことでした。話がまとまって私とエガーさんとで会社をつくったのですが、その時はレコード会社の看板を掲げたわけでなく、単にレコードを制作するというだけのことでした。』
| ●注4 | この "Jazz by Post" という名称は、ECMの傍系レーベルであるJAPO(ヤポ)のもとになっている。というより、このミュンヘンで電気商会を経営しているエガー氏の会社そのものであって、最初はECMとは別に活動していた。1973年からプロデュースを始めたが、初めはミュージシャン自身で制作したテープを買い、ダイレクト・メールで(販売を)行なっていたが、ECMの発展に伴い、JAPOもECMのディストリビューションに乗せることができ、飛躍的に発展した。アイヒャーの片腕でもあるThomas Stöwsand(トーマス・ストゥーヴサント)が主にプロデュースを担当し(アイヒャーがプロデュースすることもある)制作関係はすべてECMで行なっている。マンフレート・ショーフ・クインテット、グローブ・ユニティ・オーケストラ、加古隆、オム、ステファン・ミカス等、今日まで40枚弱のカタログを残している。つい最近、近藤等則の加わったグローブ・ユニティの最新作を発表した。 |
■ JAPO Records Discography
Listed by Paul Geffen (trovar.com
)
■ Japo ("Jazz by
Post") Records Listing
(This list compiled by
Karl-Michael Schneider)
■ <S氏の大阪語講座>
この中に、S氏が設立後間もないECMのLPを現地で日本に仕入れたときのエピソードがあります。 (ベーシスト加藤真一氏のブログ内。トップページはこちら)

『彼(マル・ウォルドロン)は当時ミュンヘンに住みついて、よくエガーさんの店へ来ていたのです。私はといえば、彼のコンサートを聴いて、とても彼の音楽が気に入っていました。彼はしばらくレコードを出していませんでしたし、話をしてみるとレコードを出したいという意欲と情熱に燃えており、私のほうもこのチャンスをものにしようという気持ちに固まっていったというわけです。ある意味では彼のレコードは試金石でしたが、出はじめに500枚とか1,000枚売れたというだけでも、私たちにとっては大変な枚数でしたし、やがて私たちの期待をはるかに上回る売上が記録されるにいたったのです。というのも、ECMなんて無名のレーベルでしたし、プロデューサーとしての私の名前もまったく知られていませんでしたから。ですから最初の作品が成功したことは幸運でしたし、ツイてもいたわけです。それからはレコードを1枚ずつ、ゆっくりと時間をかけながら作りあげ、銀行に預金がたまったらまた新しいレコード制作に踏みだす、というふうにしていきました。ですから、会社を創立する時点での投資はごく少ないものでした。』

『最初の5枚でいいますと、特に進歩的な左翼系の批評家たちからのウケがよく、とりわけフランスで大きな反響を呼びました。いろいろな人々から精神的な支持や、もっとレコードを出しなさいというような激励もたくさん頂きました。でも、この種のレコードは量としてはそうたくさん生産するわけではありませんから、大変困難な時期もあったのです。まずこの種のレコードのためのマーケット探しから始まりましてね。世界中のさまざまな配給会社から発売の要請が舞いこむようになったのはその後のことなんです。だから、ECMはゆっくりしたペースで徐々に大きくなっていったといえます。故意に伸ばそうとか、大きくしようとか有名にしようとかそんなことは少しも頭にありませんでした。現在でも私たちの態度はそうです。いまだに小さなものだし、相変わらずノロノロとやっています。創立当時は3人しかいなかった社員が、いまは(1978年12月)秘書と私をいれて6人に増えたという程度の成長です。つまり規模としては小さいままなのですが、これはとても重要なことだと思います。というのは、全部に目が行き渡るようにするためには、人数の少ない方がいいからです。』

『マンフレートは、自分がプロデュースすべき内容を完全に把握している唯一のプロデューサーだ。つまり、どのミュージシャンで何をプロデュースすべきか、ということなんだけど、それを音楽以外の条件で変えることが絶対ないということをいいたいんだ。これが彼のレコードづくりのベースで、そのうえ彼は完全主義者だから、われわれの音楽的意図をくみとって質的内容を高めてくれるばかりか、それをあらゆる点で極限の形で実現させてくれる。アメリカのプロデューサーときたら、自分の独善的意向をミュージシャンの音楽的アイディアにかぶせるのが自分の仕事だと思っているのが多いんだから……。たとえば「Solo Concerts」(ECM 1035/37)のことなんだけど、3枚組のピアノ・ソロ・アルバムなんてアメリカの誰も耳を貸してくれなかった。マンフレートが引き受けてくれたとき、誰もが彼を気違い扱いしたもんさ。だけど、マンフレートは自分が信じた事にはリスクを負うことも恐れないんだ。結果は、マンフレートの勝ちとでてる。マンフレートは僕の音楽性を好いてくれているし、自分も彼の音楽的趣味と仕事のやり方を尊敬してる。自分の可能性のすべてを受け入れてくれたのは彼だけだし、アメリカのプロデューサーのように自分を一つの方向に縛りつけておくことはしないんだ。ECMに残したレコードの中の90%は不朽のものだって自負してる。』

『ふつう、プロデューサーがわれわれに協力できることは、余計なおせっかいをしないでいてくれることだけなんだけれど、マンフレートの場合は、われわれが現場にいて欲しいと願う唯一のプロデューサーだ。彼の協力で、ECMでは以前よりずっといい仕事を残していると自負してる。
マンフレートはまずミュージシャンであるし、彼のレコード制作の原点は音楽に対するあふれるばかりの愛情なんだ。彼の音楽的な理解度とセンスは、まったくただものじゃない。それにあの徹底ぶり。レコード制作の1から10まで彼の目が通ってないものはないんだ。たとえば、NYで録音したマスターのリミックスにオスロへ飛んだりシュトゥットガルトへ飛んだりするんだ。オスロとシュトゥットガルトのスタジオとエンジニア[●注5]が彼の知っているベストだという理由でね。ミックスに立会ったミュージシャンにはミックスの意図を完全に納得させてくれるし、立会えない場合はラッカー盤を切ってくれる。アメリカのレコード会社が“明日のメシのタネ”という発想でレコードを作っているいま、マンフレートは何年か先の“金の鉱脈”を掘り続けているんだ。彼のカタログは、いまでも多くの心あるリスナーから熱烈な支持を受けているけど、ECMの真価はまだそんなものではないと思う。彼のカタログの寿命は想像以上に永いと思うし、彼の仕事が一部の愛好者を超えて一般的に受け入れられるようになった時、その価値は計り知れないものになると確信している。』
| ●注5 | オスロは、タレント・スタジオのヤン・エリク・コングスハウク(テリエ・リプダルの1975年8月録音の"Odyssey"までは、アルネ・ベンディクセン・スタジオ)。シュトゥットガルト近郊のルートヴィッヒスブルクにあるトンスタジオ・バウアーのマーチン・ヴィーラント。特にタレント・スタジオのピアノの音は最高に気高く美しい。 |

『アイヒャーはプロデューサーであると同時にミュージシャンでもあると思う。彼はプロのベーシストとして多くのすぐれたミュージシャンと演奏したわけだが、同時に、私がこれまでに一緒に仕事をした中で最もすぐれたプロデューサーであるといえる。たとえば昨日のレコーディング[●注6]にしても、リッチー・バイラークの「ネプチューン」が、アイヒャーの示唆なくして、あのような素晴らしい作品になったかどうか……。
ミュージシャンというのは音楽は演奏できても、その作品をどのように表現し、プロデュースにまでもっていくかということまでは頭が回らないものだ。プロデューサーの役目というのは、演奏するミュージシャンたちに、いかにその曲にふさわしい表現を施し、作品としてプロデュースするかという示唆を与えることだと思う。ところが、プロデューサーの中にはミュージシャンをかねている人が多いから、全部が全部、いい助言を与えられるとは限らない。アイヒャーという人はとても繊細な人間で、そういう性格ゆえに、音楽のプロデューサーとしての感覚が非常にすぐれているのだと思う。特にはっきり言えることは彼がある種の音楽に対してとてもセンシティブであることだ。だから、私はもちろんのこと、彼と一緒にレコーディングした人は、みないい雰囲気の中で仕事ができたに違いないと思っている。』
| ●注6 | このインタビューは、1978年12月14、15日、オスロ・タレント・スタジオにおけるジョン・アバークロンビー・カルテットの「Arcade」(ECM 1133)のレコーディング直後に行なわれたものの一部である。 |
『システムとか、特別な技術や秘訣とかはありませんが、お互いを人間として扱いあうことが基本だと思っています。私自身も音楽的センスを持っていると思いますし、流行や政治的な理由で人のレコードを出すことは絶対せず、あくまでもその人物と音楽が好きだからその人のレコードを作るのだ、という気持ちに徹してプロデュースをするつもりです。私たちの仲間はみな同じ世代の人間ですから、話すときも直接的に同じ言葉を使っていると思います。互いを互いによく理解しあえるのもそのためでしょう。コンサート・ツアーにもよく一緒に出かけます。小さな要素のひとつひとつ、たとえばレコード作りにしても、ジャケットひとつにしても、皆で意見を一致させて合意に達してから物事を運ぶようにしているのです。私たちはそれによって本当の意味の音楽を創りだしたいと思っています。そのためには、すべてのレコード制作に私が直接関与しないかぎり、またミュージシャンの一人一人に私が直接の結びつきを持たないかぎり、今のような密度で仕事を続けることは不可能です。私はある思想をもってこの仕事に打ち込んでいます。それを言葉でいうのは難しいのですが、それはきっと私がつくりだす音楽に現れていると、私はそう信じています。』
『多分、私の興味が音楽そのものであって、他の付随的なものではないことを彼らが理解しているからではないでしょうか。私自身、なんらかの意味で聴かれるべき理由のないレコードはリリースされる必要がないと思いますし、もしその必要のないレコードをただ商業的成功の理由だけでリリースするのは恥ずかしいことだと考えます。また私がレコード作りをするときには、最高の音楽を生みだしたいと願っていることが、彼らに通じているからだと思います。他にも理由があるでしょうが……。お金の問題ではないはずです。なぜなら、ECM以外の他の会社の方が彼らにとって金銭的な待遇は上のはずですからね。』


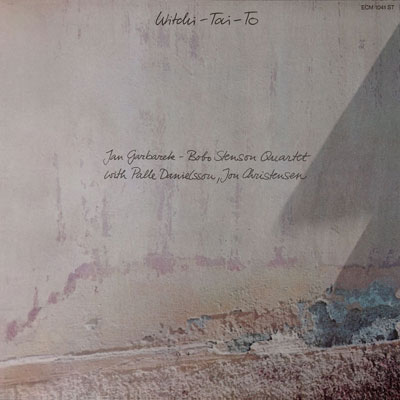
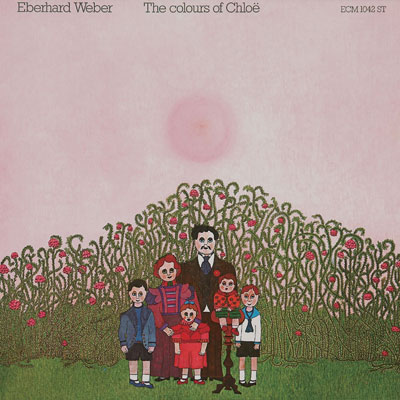



須永春彦
Haruhiko Sunaga
![]()