ECMのオト
一度知ったら二度とのがれられぬ禁断の花園須永春彦
ま、とにかく前置きはこのくらいにして、そろそろ本題にはいることにするけど、独断と偏見に満ちミチていることを最初にお断わリしておきマ〜ス!
ECMレーベルの音はいつ頃からあんなに良い音になったのですか?

レコード番号
ECM1001 “Free
at Last”(Mal Waldron Trio)からなの。つまり、処女作からして音が良かったってこと。もちろんウハウハするほどいい音じゃないけど、第1作からして音にきらめきとツヤがあったことは事実ヨ。
では、その“Free at Last”が録音された日付とスタジオは?
時は1969年11月24日、ところは西ドイツ、シュトゥットガルトのルートヴィッヒスブルクにある“トンスタジオ・バウアー”(Tonstudio Bauer)です。ついでに言うと、エンジニアはクルト・ラップ(Kurt Rapp)。1973年
or 74年までは、この人がトンスタジオ・バウアーのチーフ・エンジニアだったようだけど、その後、あのマーチン・ヴィーラント(Martin Wieland)にかわったのね。
とすると、ECMの常用スタジオはトンスタジオ・バウアーなのですか?
ドイツでレコーディングする場合はそうよ。でもね、ノルウェーのオスロにもう一つの常用スタジオがあるの。その名も“タレント・スタジオ”(Talent Studio)!
実をいうと、ECMサウンドとは、このスタジオで録音された音のことをいうの。トンスタジオ・バウアーやアメリカのスタジオで録られた音とは、品位がまるで違うんだから。
では、そのタレント・スタジオで録音された最初のECMアルバムは?
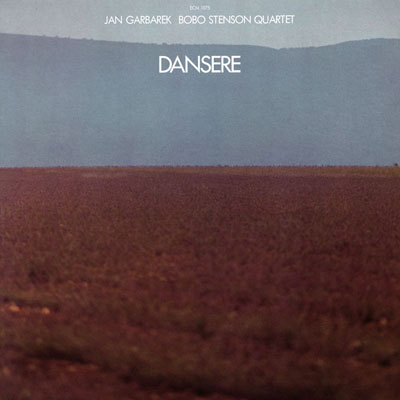
1975年11月録音の、レコート番号
ECM1075 “Dansere”(Jan Garbarek, Bobo Stenson Quartet)ヨ
。エンジニアは、あのヤン・エリク・コングスハウク(Jan Erik Kongshaug)。この人、ブ男だけど、アタシ大好き(はあと)
おやおや、先程の“Free at Last”の録音年月に比べると随分あとのことですね。ECMのオスロ録音とは、そんなに後になってから始まったのですか?
うーん、中々鋭い指摘ダワ。実はね、初期のECMオスロ録音は、タレント・スタジオじゃなくって、“アルネ・ベンディクセン・スタジオ”(Arne Bendiksen Studio)だったの。要するに、途中で常用スタジオを変えたわけ。ただし、ミクサーのヤン・エリク・コングスハウクは変わらないワ。あの人のレコーディング・テクニックと音楽的感性はまったくただものじゃないわネ。
それでは、そのアルネ・ベンディクセン・スタジオ録音の記念すべき第1作は?

1970年9月22、23日録音のレコード番号ECM 1007 “Afric
Pepperbird”(Jan Garbarek
Quartet)です。
あれま、またガルバレクですか…
あったりきよーっ!! 文句あっか!! フガフガ…(解答者、思わず興奮)
では、いわゆるECMサウンドが確立されたのは、だいたいどのあたりからなんですか。ひょっとしてこのレコードなのかな?

ううん、このレコードじゃないと思うの。やっぱりなんといっても、チック・コリアの“ピアノ・インプロヴィゼイション”(ECM 1014)やキース・ジャレットの“フェイシング・ユー”(ECM 1017)、そしてポール・ブレイの“オープン、トゥー・ラヴ”(ECM 1023)といった、あの一連のピアノ・ソロ・アルバムを待たなきゃだめね。あのシャープでソリッドな輝くばかりの音はほんとに個性的で、当時(1971〜72頃)のジャズ&オーディオ・ファンを驚かせたものよ。



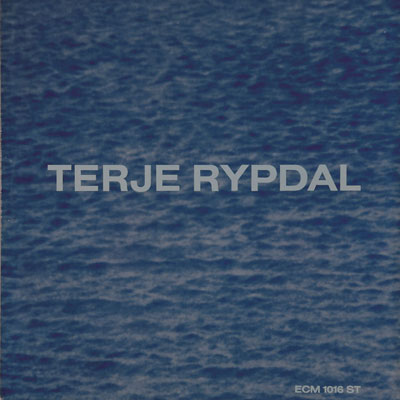
初期の頃、結構多かったアメリカ録音はどうですか?


そうねえ。最近もやたら多いけどね。あの頃も、チックの“Return to Forever”(ECM 1022)を始め、New York 録音も多かったわねぇ。ただ、レコーディングはアメリカでやっても、ミックスはトンスタジオ・バウアーかアルネ・ベンディクセン・スタジオでやってるからそんなに聴き劣りはしないけど…。でも、音のシャープさとか気品とか今一つなのよね。やはり、お国柄や気候風土の違いなんじゃないかしら。もちろんいいものもあるわよ。例えば、キースとジャック・ディジョネットのデュオ“Ruta & Daitya”(ECM 1021)。そう、SJ誌で最優秀録音賞をとったやつよ。ピアノの定位は物足りないけど、スケールが大きくクリアーなオトで立派なものよ。さっきいった“Return to Forever”、これもステキだわ。音楽と音がピッタリマッチしててね。とってもさわやかで。
そしていよいよ、キースの“Solo Concerts”(ECM
1035/36/37)の登場ですね?



さーすがぁ、よくわかってるじゃん!!
このアルバムが録音された1973年のECMレーベルは、“花ひらくECMサウンド”といった感じで充実してたわね。このアルバム以外にも、テリエ・リプダルの“What comes after”(ECM 1031)、ラルフ・タウナーの“Diary”(ECM
1032)、アート・ランディ=ヤン・ガルバレクの“Red Lanta”(ECM
1038)、ヤン・ガルバレク=ボボ・ステンソン・カルテットの“Witchi-Tai-To”(ECM
1041)、エバーハルト・ウェーバーの“The Colours of Chloë”(ECM 1042)といった、名演奏名録音の目白押しで、思わずズキズキしちゃうわ。キースの“ソロ・コンサーツ”のピアノの音なんか、はっきりいって現実のピアノという楽器の音からはかなりかけ離れたものだと思う。アーティフィシャル(人工的)だっていう人もいるけど、これだけ美しく磨き上げられ昇華された音ってそれまでなかったと思うの。シャープに繊細に切れ込むピアノの一音一音の粒立ち。その刹那、あたかも水面に同心円を描いて拡散するがごとき余韻の美しい儚さ。それらを土台から支える豊かで深い低音弦の響き。ああ、恍惚の世界だわ……。

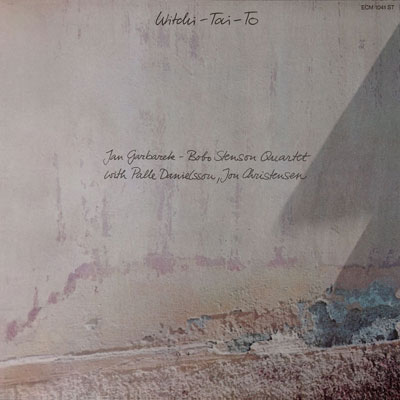
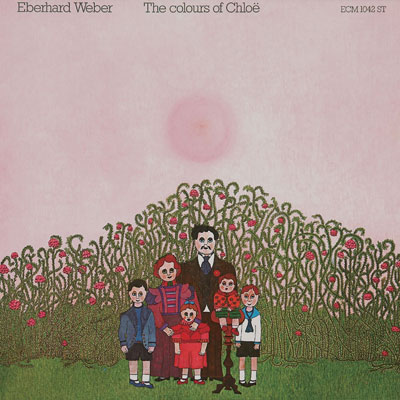

なるほど、そうだったんですか…。まあ、とにかく“ケルン・コンサート”こそECMサウンドの頂点だということになるわけですね。

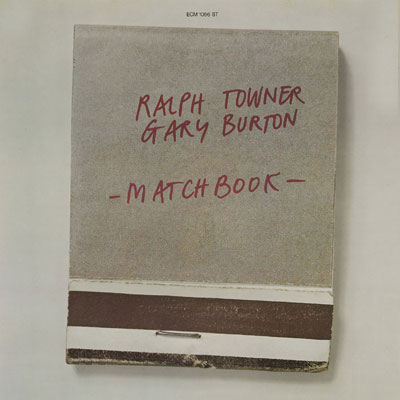
と思うでしょ。でも違うのよネ。ECMサウンドがその頂点に達したのは、“ケルン”よりももうちょっと後の、1976年に入ってからのことなの。さっき、1973年はECMサウンドの開花期ということで、数枚の傑作を並べたけど、そのうちタウナーの“ダイアリー”、キースのライブ、E.ウェーバー以外のアルバムは皆オスロのアルネ・ベンディクセン録音なわけ。そして、続く74〜75年のECMサウンドというと、今度は西ドイツのトンスタジオ・バウアー録音が凄く良くなってくるわけ。例えば、74年7月録音の
Gary Burton Quintet with Eberhard
Weber“Ring”(ECM 1051)と Ralph
Towner = Gary Burton“Matchbook”(ECM 1056)、この2枚はトンスタジオ・バウアー録音の中でもトップクラスの音だし、75年3月録音の
John Abercrombie の“Gateway”(ECM
1061)とかキースの“Arbour
Zena”(ECM 1070、75年10月録音)などなどみんなステキだわ。



で、いよいよ問題の1976年へと……
ちょっと待って。その前に思い出してもらいたいことがあるの。さっき、オスロのスタジオが途中で変わったっていったでしょ。それなのよ、それ。それこそ
Key Point なの。
要するにスタジオが変わったんで音が良くなったという……

ダメヨ、そんなに話を早くもっていっちゃ。まあ聞いて。ECMのオスロ録音は、1975年8月録音のテリエ・リプダルの大作“Odyssey”(ECM
1067/68)まではアルネ・ベンディクセン・スタジオで、その年の秋、ミクサーのヤン・エリクちゃんはピアノかついで(?)お引越ってなもんで、タレント・スタジオへ移ったの。そしてそれ以降のオスロ録音はすべてこの“Talent Studio”で行なわれているわけ。これからもずっとそうなるだろうし、そうじゃなきゃイケナイんだぞっ!!
ウムム……くわ〜〜〜っ!!
アイヒャー!! ピアノの録音はここでヤレイッ!!
オドリャ〜〜、何考えとんじゃ〜〜!!
まあ、そうコーフンしないで。マママ、オサエテ、オサエテ…
ウ〜〜〜
…… ホッ……
フハ〜〜 あっ、シチレイイタシヤシター、ドモ
スンマセン、チマチマ
で、それからどないしたんネン
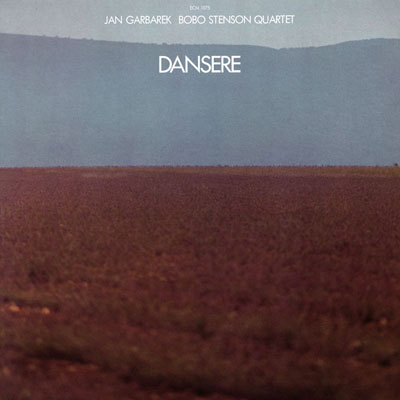
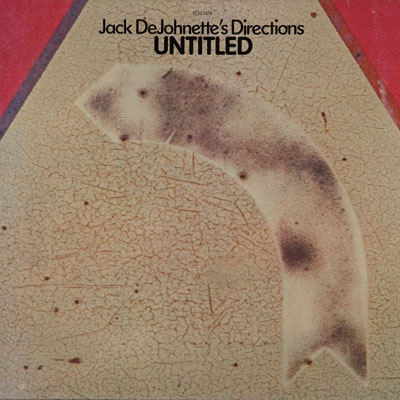
それでねーえ、最初にいったけどォー、タレント・スタジオにおける記念すべき第1作は1975年11月録音のヤン・ガルバレク“Dansere”(ECM
1075)なんだけど、不思議なことにこのアルバムのオト、むしろそれまでの“アルネ・ベンディクセン・サウンド”そのものなのね。ひょっとしてクレジット・ミスじゃないかって思えるくらい。でも次の1976年2月録音の
Jack DeJohnette's Directions“Untitled”(ECM
1074)と比べれば一聴瞭然!!
クラシックのレコーディングにも通じるような品位の高いオトに生まれ変わっていることが誰にでもわかるはずよ。
そんなに違うんですかぁー?(思わずウタガイのまなざし)
ゼーンゼンちゃうの!
そしていよいよお待ちどうサマ〜。ECMサウンドの頂上を築く銘録音盤の数々。すなわち…

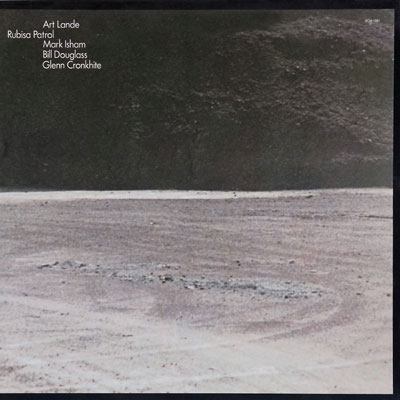
John Abercrombie, Ralph Towner “Sargasso Sea”(ECM 1080)
Art Lande “Rubisa Patrol”(ECM 1081)〔SJ誌 1977年度最優秀録音賞受賞〕


Terje Rypdal “After The Rain”(ECM 1083)
Eberhard Weber “The Following Morning”(ECM 1084)

Arild Andersen “Shimri”(ECM 1082)
あのー、少々お尋ねしますけど、ひょっとしてアナタ、ビョーキじゃあ…
そうです。アタシ、ホトンドじゃなくって完ペキなビョーキなんですの。オホホホホホ!
ケゲッ、ヒェ〜〜〜〜〜〜ッ
そんなにおののかないで。まあいいじゃない。広い世の中、こんなパッパラパーが一人くらいいたって。
そーすネェー フニャフニャ
さ、また容赦なく続けるわネ。この5枚に共通して言えることは、とにかく気品あふれるツヤヤカなオトだということ。特に、アート・ランディ盤とアリルド・アンデルセン盤に聴かれるピアノの音の良さといったら、もう最高!!
こんなに美しいピアノ、クラシックの録音でもそうざらにはないと思うわ。そして、あの広々とした幻惑的とさえいえる音場空間…。“アタシにはシビレルしか能がないワ”。
あっ、またまたお決まりのフレーズだしてやぁんの、ダセェー
ヘン、ウッセィ、動揺するもんか!!
まだジュダマ(←
珠玉[しゅぎょく]?)は出しておらんぞっ!!
(約10秒のインターバル)
あのー、ここで一応、オスロのスタジオが“アルネ・ベンディクセン”から“タレント”に変わったことによる音の変化の原因を分析して欲しいんですけど…。
そうネェ。まず、エンジニアのヤン・エリクちゃんもいってるように、“アルネ・ベンディクセン”よりも“タレント”の方がルーム・アコースティックが良いってこと。つまり、スタジオの音響特性が異なるってことは、想像以上に音を変化させる要因だといえるし、ECMのように音の空気感、響き、余韻、音場空間を大切にするサウンドの場合、決定的な相違を生み出すのは論をまたないところ。次に、当然のことながら録音機器がどんどん良くなっていくっていうこと。さらには、エンジニアのレコーディング&ミキシング・テクニックの熟練。また、ピアノに関しては楽器そのもの(Steinway のC型グランドのこと)がめったやたらに良く、ピアノが最も良い状態で鳴るように、スタジオの空気をほど良く乾燥させているということ。まあ、この点は、アルネ・ベンディクセン・スタジオ時代も同様かもしれないわネ。だいたいこんなところかな。
(Jan Erik Kongshaug; Norway / Talent Studio)
マンフレート(・アイヒャー)と最初に仕事をしたのは、1970から71年にかけて、アルネ・ベンディクセン・スタジオでヤン・ガルバレクの録音をした時でした。当時、私はとても若かったし経験もありませんでした。しかし、われわれの間には、なにか相性のようなものがあったようです。とても気持ちよく仕事ができました。「ECMサウンド」について語るのは難しい。もし、そんなものがあるとすれば、楽器の間で最善のバランスをとることだと言えるかもしれません。ほとんどのジャズ・プロデューサーは、フィルターとかイコライザーとか、その手のものを使うんですが、われわれはやらないのです。マンフレートはより自然な音を好みます。そう、サウンドは年毎に変わってきますよ。10年前よりはずっとよくなっています。Arne Bendiksen Studio から Talent Studio に移って音がよくなりました。そりゃ、タレント・スタジオの方がアコースティックがいいですからね。テクニカルな変化について話せと言われても難しい。われわれのやっていることに規則なんかないのです。セッションによって違うんですから。エコーの使い方ひとつだって、これは好みの問題ですが、それぞれ違ったやり方をしています。たとえば、時にベースにエコーを使ったり、使わなかったりする。結局のところ、強調しておきたいたった一つのことは、いいバランスを見つけるということです。楽器間の関係ですね。単純なことですが、ほとんどのプロデューサーは、このことをきちんと頭にいれてないんですよ。
(スイング・ジャーナル 1979年11月号より抜粋)
そして、ECMサウンド黄金時代は続く…
そうなのヨ。これ以降、1977年3月頃までのタレント・スタジオ録音のECMアルバムは、みんなツヤツヤした輝くばかりの気高い音がしてイイのよー。
すなわち、


Egberto Gismonti “Danca Das Cabecas”(ECM 1089)
The Gary Burton Quartet with Eberhard Weber “Passengers”(ECM 1092)

Jan Garbarek “Dis”(ECM 1093)



Ralph Towner - Solstice “Sound and Shadows”(ECM 1095)
Collin Walcott “Grazing Dreams”(ECM 1096)
Pat Metheny “Watercolors”(ECM 1097)

John Taylor “Azimuth”(ECM 1099)
そして、その後の、レコード番号でいうと、100番台から120番台あたりまでの、音のツヤはやや後退したけど、過渡特性が良くなって音が軽やかになり、ハイスピードで実にのびのびとしたサウンドへと変わっていくわけ。断っておくけど、それはあくまでも“Talent Studio”録音に限るのよ。ドイツの“トンスタジオ・バウアー”録音はまた別の個性を出してきているし、アメリカ録音はホトンド論外です。
そのトンスタジオ・バウアー録音なんですけど、オスロ録音とはどう違うんですか?


実はね、オスロ録音とドイツ録音のちがいがはっきりしてくるのは、オスロのECM常用スタジオがタレント・スタジオに変わってからなの。それまでは、オスロ録音もドイツ録音もそう極端には違わないのよ。要するに、アルネ・ベンディクセン・スタジオのサウンドは、タレント・スタジオのサウンドほど品位の高い美しいサウンドじゃないし、1975年頃までのトンスタジオ・バウアー・サウンドも、今のようにアクの強いくらい個性的なサウンドでもなかったからなの。でも、タレント・スタジオに移ってからのECMオスロ録音は、力強さやパワー感よりも一音一音をより美しく磨き上げた耽美的サウンドを指向し始めたでしょ。だから、ドイツ録音はこれとは対照的な方向へ音を持っていったんじゃないかしら。つまり、よりパワーフルでガッツがあり力強い音、音楽でいえば、より
Jazzy なサウンドに向くような音。特に、ドラムスの音の凄みは、ちょっと普通ぢゃないわね。だから人によっては、特に
Jazz fan は、トンスタジオ・バウアー・サウンドの方が好きなんじゃないかしら。また、エコー処理なんかもかなり違っててね、例えば、トンスタジオ・バウアー録音のアルバムの中の、そうねえ、Kenny Wheeler “Around
6”(ECM 1156)なんか聴いてごらん。不思議なことに、スタジオ内の雰囲気が見えてくるような、まるで自分がトンスタジオ・バウアーにいて演奏を目のあたりにしているような、そして時には、まるでコンサート・ホールにいるようなとってもリアルな感じがするのよ。ところが、タレント・スタジオ録音の場合、例えば
Rainer Brüninghaus “Freigeweht”(ECM
1187)なんかいい例なんだけど、スタジオやホールにいるというよりは、もっと広々とした野外を連想させるような、空とか地平線とか宇宙とかそういう空間へと飛んでいっちゃうような感じになるわけ。もちろん、音楽の内容にもよるけど、逆に言えば、音楽によって、またアーティストによってスタジオを選ぶっていう傾向もECMにはあるのよ。例えば、ヤン・ガルバレクやテリエ・リプダルのアルバムをドイツで録るなんてことは、まずあり得ないわね。
つまり、ECMサウンドといっても2通りあるわけだ。
そうなの。だから、ある程度ECMに通じてくると、新譜が出た時なんか、スタジオのクレジットを見ただけで、どんな音がするかだいたい想像がつくわね。ただ、ECMサウンドの基本的な特徴は、スタジオが違ってもそう変わるもんじゃないわ。アメリカ録音にしたって、ミックスはオスロかドイツでやるし、最近の
N.Y. パワーステーション・スタジオ録音なんか、わざわざオスロからヤン・エリク・コングスハウクが出向いていってるくらいだから。
(Martin Wieland; W. Germany / Tonstudio Bauer, Chief Engineer)
ECMの創作物では、いずれもが楽器本来の自然な音を響かせようとする。実際にイコライザーは使われていない。室内で鳴る音にできるだけ近づけようとするし、よい機器とスタジオ・モニター・スピーカーを使って、それをそのままテープに移しかえようとしている。時々、音楽を比較的低い音量で聴いてみる。これは音を吟味するのによい指針となるし、チェックになる。大音量で聴くと音楽に圧倒されやすい。音楽にとって一番大切なのは、もちろんミュージシャンである。私が思うに、ECMが選ぶミュージシャンはおおむね、テクニックと同時にサウンドに対しても本物の感じ方を持っている。私は音楽といっしょに歩もうとする。そしてミュージシャンが使う現実のナチュラルなサウンドと共に仕事をしてきた。1969年、つまりECMが始まった頃と較べて、マンフレートと私がやっている方法に変わりはない。変わったことと言えば、器機がますます大きくなったことだ。ご存知のように、われわれ二人共音楽と共に育ってきた。われわれは同時にスタートした。10年を振り返って、われわれの理解はもはやサウンドについて話し合う必要のないところまできている。いつでも、当然しなければいけないことを、まったくスポンテニアスにしているように思う。
(スイング・ジャーナル 1979年11月号より抜粋)
じゃあ最後に、ECMサウンドの特徴をまとめてほしいんですけど。
ハーイ。まかしといてネッ!! まず第一に、各楽器の音がものすごくリアルだってこと。ミュージシャンの発する一音一音を、ツヤヤカに緻密に際立たせる録音テクニックは大変なものよ。要するに、各楽器の音色を決定づけるハーモニック・トーン(倍音)をとても大切にしているのね。
なるほど。まあ、だいたいわかったような気がします。で、今回はこの辺で終わりたいと思うんですけど、次回の予告もかねて何か一言!!
あーら、もうおしまい?
つまんないの。
まあ、今回はECM初期の100枚、年代にして1969年から1977年頃までのアルバムを通して、ECMサウンドの変遷といった感じでしゃべくってみたんだけど、次回は1977年から現在までのECMサウンド、レコード番号でいうと、100番台から200番台の終わり頃(たぶんそうなるハズ)までをまとめてみることにするワ。それからネ、最近のECM録音、かなり問題があるのよネー。例えば、ピアノ録音のまずさ(特にトンスタジオ・バウアー録音)、スタジオ選択のミス・マッチetc. そのあたりを探りつつ、できることなら、ECMサウンドの再生の仕方!!についてもブチアゲテみたいと思いますワ(はあと)。
![]()