マンフレッド・アイヒャー様。

76年以来、この部屋でずっと仕事をしてきました。その頃から、考えていることも、やっていることも何ひとつ変わっていません。69年に、新しい美学(エステティック)の探究をプロデューサーと音楽家が共同して行なえるような環境をつくるということを念頭に、この会社を始めた時とまったく同じです。もっとも、オフィスについていうならば、スタジオにいる方が断然好きですが。
今の時代、音楽も本も多すぎます。すべてがトゥーマッチで、かといってクオリティが必ずしも上がっているわけではない。我々に必要なのは孤独であることです。入ってくる情報を制限して、本質に集中すること。しかし今の音楽業界はそれができずにフラストレーションが蔓延しています。「コンセプトとアイディアの不在」によって、自分の首を自ら締めているのです。その点、私には69年当初から実現したいアイディアがいっぱいありました。だからフラストレーションはなかったし、もちろん今もありません。

アイディアというものは、ときにユートピアです。当然それは、現実という障壁によって、実現を阻まれることもあります。契約の問題、タイミングの問題、物理的なあるいは文化的な距離の問題。ですから時には実現に何年もかかります。しかし、そうやって長い時間をかけて実現したなら、そのことで現実は違った方向へと向かっていくものです。そうやってECMは進んできたのです。

マイルス・デイヴィスに手紙を送ったんです。キース・ジャレットと製作したバロックオルガンのアルバムが素晴らしい出来だったから、もう一度、同じ教会で、今度はマイルスのトランペットを加えて録音したいと申し出たんです。しかし何の返事もなかった。当時マイルスはコロンビアレコードの支配下にいました。何年後かにコペンハーゲンで本人に直接会う機会があったので聞いてみたら、そんな手紙知らないと。レコード会社が握りつぶしたんです。ただ、キースのアルバムは聴いていたそうです。もし、彼に仕事を選ぶ自由があったなら、きっと実現していたかも知れません。しかし今となっては伝説です。
私はプロデューサーですが、時に父親や先生の役割も果たさなければなりません。アーティストの資質を見極め、それが未熟であったり、隠されていたり、焦点が定まっていなかったりするときに、私はとことんそのアーティストと対話を重ね、その資質に磨きをかけていかなければなりません。私がプロデューサーとして秀でた資質を持っているとするなら、それは「聞く耳」を持っているということでしょう。それは、誰かのサイドメンとして演奏している若い才能を発掘する「耳」でもあり、また個々のアーティストの欲求や不満、悩みや希望を聞いてやることのできる「耳」です。
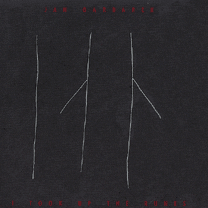
マンフレッドは自分が何を求めているか、いつもはっきりとわかっているんです。それも腹の底から。ですから、常に全幅の信頼を置いています。僕は優柔不断なんです。ひとつのフレーズがあると、そのヴァリエーションを4つも5つも考えちゃって、結局どれが一番いいかがわからなくなるんです(笑)。それをマンフレッドは、「これだ」ってすぐに示してくれる。迷いはありません。マンフレッドには必要な音がすべてわかっているのです。彼なくしては私の音楽はありえない、といってもいいくらいです。
人を愛するために、結婚しなくてはいけないってことはないでしょう。
我々が得た収入は、すべて音楽に還元されます。
レインボウ・スタジオの何が特別か。それはヤン・エリックの存在です。彼自身、音楽家でもある。だからとんでもなく耳がいい。
よく聞かれるんだよ、どんなマイクを使って録ってるのかとか、どんな機材使ってるかとか。でも秘密なんかないんだ。その楽器が一番よく聴こえるように録音しているだけなんだ。そこで奏でられる音楽に忠実でいること。音楽第一、それだけ。ま、しいて言うなら、ピアノかな。調律師が重要なんだ。今まで20〜30人くらいの調律師に頼んだけれど、一人だけだったよ、「これだ」という人は。今はずっと彼に頼んでいるよ。
ECMは音楽レーベルであって、ジャズレーベルとして構想されたことは一度もありません。ジャズという言葉が指し示す範疇は少々窮屈なものですから、私はその代わりに「即興演奏」という言葉を使います。即興演奏は音楽によって発明された最も自由な言語です。その一方でクラシックの規律にも同様に惹かれます。私の興味は、それぞれの美的要素をバランスよく保ちながら、伝統的な音楽言語と今日の音楽言語の双方によって醸造された音楽をつくり出すことなのです。そして、「伝統的な」というとき、そこにはジャズもクラシックも、もちろん非西洋音楽も含まれます。



私たちの音楽は、「明晰さの探究」と呼ぶことができます。ルシディティ、クラリティ、トランスパランシー、そしてミステリー。それがECMの音楽です。

敬具
2003年12月15日
若林 恵
Kei Wakabayashi
![]()