
| Joe Maneri Barre Phillips Mat Maneri Tales of Rohnlief Joe Maneri alto & tenor saxophones, clarinet, piano, voice Barre Phillips double-bass Mat Maneri electric 6-string and baritone violins |
| Rohnlief A Long Way From Home Sunned When The Ship Went Down The Aftermath Bonewith Flaull Clon Sleare Hold The Tiger Canzone Di Peppe The Field Nelgat Elma My Dear Third Hand Pilvetslednah |
Recorded:
June 1998 Hardstudios, Winterthur Engineer : Martin Pearson Cover : detail from the diorama “Unruhiger Planet Erde”, Museum Mensch und Natur, Munchen Photo / Design : Dieter Rehm Layout : Sandro Kancheli Produced by Steve Lake ECM 1678 |
「ロゥンリェス・ヴラス・デュゥン、フレェッド・モゥルシュ、ロゥフォン・ズィ、スロァ‥‥」
「あれはジョーがノートに書き留めてた詩みたいなものなんだ。アイヴズやホイットマン、シェーンベルクといった彼のヒーローたちの名前を切り刻んで並べ換えた一種のアナグラムで、彼が朗読してるんだが、ダダ的というよりまるで古代の言語みたいに聞こえるだろう。こりゃ「ベーオウルフ」(8世紀頃のゲルマン英雄叙事詩)だなと思ったんだ。」
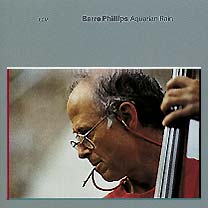
「今回は向こうから声をかけてきたんだ。それで彼らがECMに録音したCD3枚を聴いてみて、音楽のランゲージが似てると思ったね。メロディやハーモニーの感覚が近いんだな。スティーヴ・レイク(後述)が私を呼んだわけがすぐわかったよ。特にサウンドにしろ演奏の進め方にしろ、ジョーの唯一無比の存在感に大いに「食欲」をそそられたんだ」
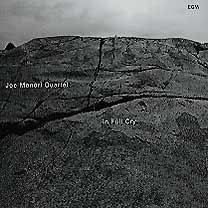
「彼らは小刻みに加速・減速を行って縦割りのリズムを排し、演奏のパルスを埋もれさせてしまうんだ。決してパルスがないわけじゃないんだけどね。それが微分音程の使用とあいまって何ともアンビギュアスな厚みをつくりだす。けれど、この微分音システムは決して頭で考えただけのものじゃない。ここで私が加わった演奏はマット作曲の1曲を除いて、すべてフリー・インプロヴィゼーションなんだが、即興を通じてシステムの内部に入り込むとそのことがわかってくる。別の景色が見えてくるんだ。そうするとシステム自体のことは気にならなくなって、彼らのやることに反応を返していけばよくなってくる。私の思うところでは、これはむしろエモーションを直接に表現するためのものだ。そのために平均律の枠組みを取っ払って、サウンドそれ自体へと肉薄し、その内側に入り込んで、どんどん深く潜っていこうとする。深層に横たわる音が生まれ出る現場、未加工の生なサウンドのたゆたいへとね。レコーディングを終えた後、『息子と共演できる弦楽器奏者をようやく見つけたよ』とジョーが言ってくれたんだ。速弾きで技巧をひけらかすことなく、スライドを巧みに用いたマットのやり方は、他に類例のないものだ。重弦奏法の時の微分音程を効かせた色彩感とかね。演奏の過程を通じて、彼らとはとても深く精神的な交感を果たせたと感じている。古くから知っている友人みたいなね。」
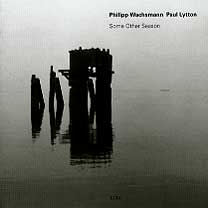

福島恵一(音楽批評)
Kei-ichi Fukushima
![]()