
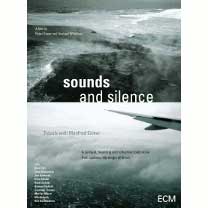
| Peter Guyer Norbert Wiedmer Sounds and Silence - Travels with Manfred Eicher |
| Switzerland
2009 ECM 5050_Blu-Ray ECM 5050_DVD |
Music for the Film
Sounds and Silence
|

稀勢の里を中心にドラマが交差したいい秋場所だった。テレビ観戦をしていて、グルジア、トビリシ出身と場内アナウンスが流れる(幕内に二力士いる)と、ECM好きのわたしの耳には暖かなオーケストラの響きと弱々しく震える老人の歌声が聴こえはじめる。現代音楽の作曲家ギヤ・カンチェリの作品を指揮するヤンスク・カヒーゼ(1936-2002)じいさんが、62歳のときに心臓疾患から奇跡的に生還した歓びを故郷グルジア、トビリシのムタツミンダ山にかかる月を想って歌ったものだ。ECMのスタジオでその私的な録音を総帥マンフレート・アイヒャーがレーベルを代表するノルウェー出身のサックス奏者ヤン・ガルバレクに聴かせると、ガルバレクは即座に感銘しそのデモ・トラックを中心に据えて自らの集大成的な2枚組大作『Rites』(1998)を描いた。
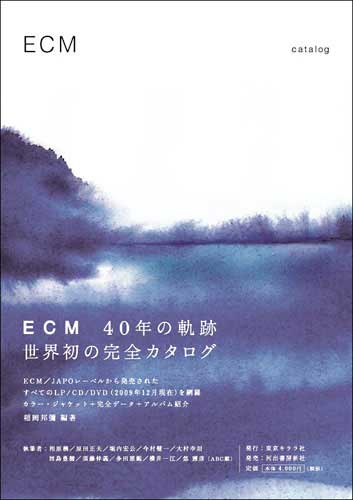




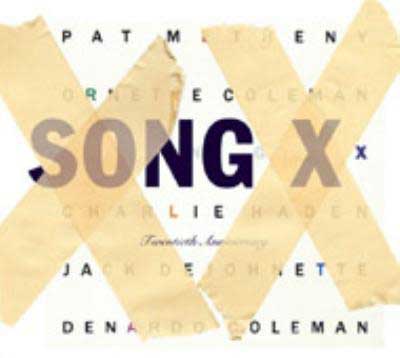


多田雅範
Masanori Tada
![]()
