February 10, 2012
|
| 今週の批評から Reviews
of the Week
|
|
|
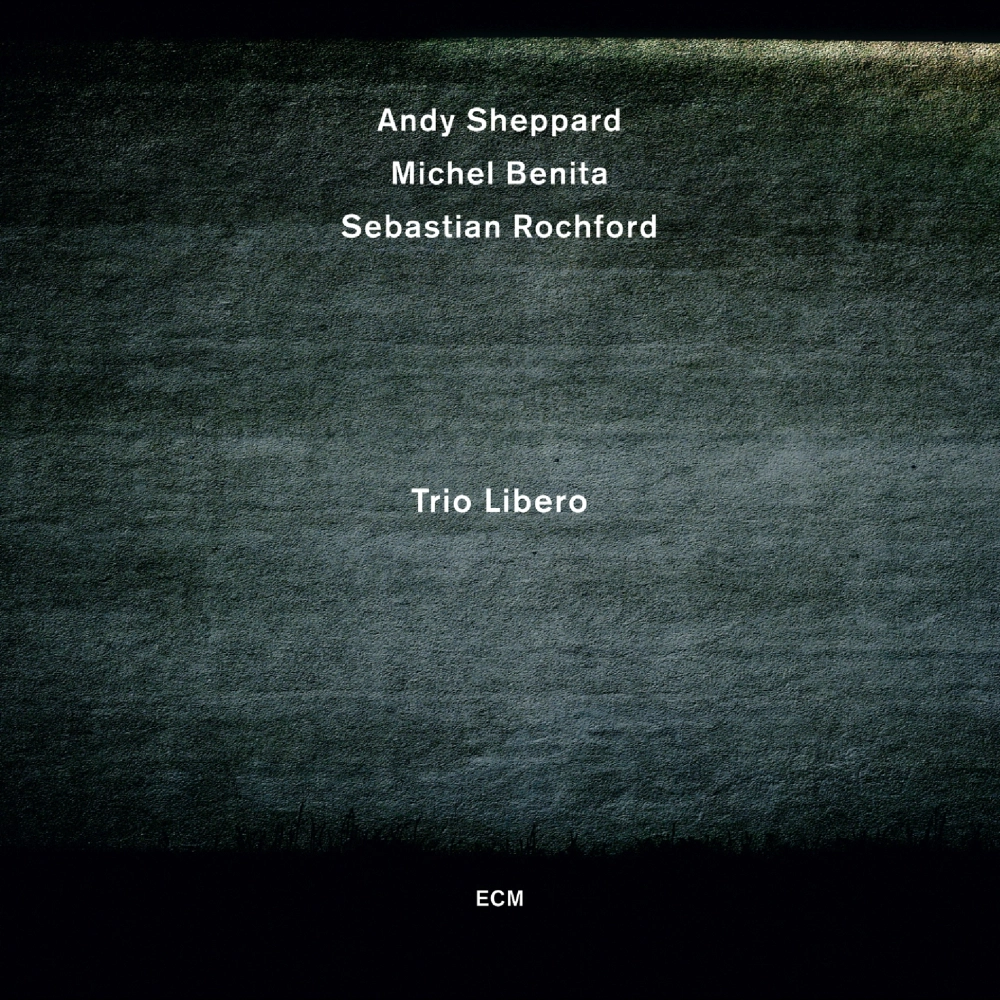 |
アンディ・シェパード
Andy Sheppard の《トリオ・リベロ
Trio Libero》(ECM 2252)への英国プレスの反応。
|
|
| |
アルバムの幕開けとなる「Libertino(リベルティーノ)」は軽やかな足取りで進むシェパードならではの旋律をもった曲だが、気の利いた嘆きという予感をどうにか辛うじて創出している。ほんの一握りの音の断片をテナー・サックスが吹いて、そこにトムトムの音が隠し味のアクセントを振りかけつつ次第に静謐なスネア・ドラムの連打へと移り変わる。本作に収録されている曲の中での唯一のスタンダード「I'm Always Chasing Rainbows (虹を追って)」[訳註:ジェセフ・マッカーシー作詞、ハリー・キャロル作曲。ショパン作曲「幻想即興曲
嬰ハ短調 op.66」の中間部を基にアレンジして大ヒットした]では、シェパードがヤン・ガルバレクを彷彿させる漂流者然としたソプラノ・サックスを聴かせてくれる。ミシェル・ベニータ
Michel Benita のベースとの間で繰り広げられる優しい駆け引きも、この曲の聴きどころとなっている。また、長い持続音とベースのアルコ(弓弾き)が特徴的な曲「Spacewalk(宇宙遊泳)」のパート1とパート2は、清純な佇まいと震えるような美しさに満ちており、アルバムの最後を飾る「When We Live On The Stars... 」はゆっくり落ち着いた格調高いポップ・ソングの質感を感じさせる。そして同時に控え目ではあるが人生の燃えるような輝きを内に宿している。
ジョン・フォーダム John
Fordham
ガーディアン紙 The
Guardian
|
|
| |
サックス奏者アンディ・シェパード
Andy Sheppard の小鳥の囀りを思わせる特徴的なトーンと、その即興演奏に備わる周囲を警戒させる特性は、長きに亙って彼の存在をこの分野における巨匠の地位へと導いた。しかしながら、ベース奏者ミシェル・ベニータ
Michel Benita とドラマーのセバスチャン・ロッチフォード
Sebastian Rochford ──その打法はポール・モーシャン[モーション/モチアン]
Paul Motian の音楽的流儀を強烈に意識させる──と共に新しく立ち上げた今回の新作アルバムでの三者が同等の立場で関与するトリオによって齎(もたら)されたサウンドの成果は、シェパードの存在を全く新しい次元へと押し上げるものとなった。「I'm Always Chasing Rainbows (虹を追って)」は原曲を相当に歪曲したヴァージョンだが、あらゆる局面が音楽の素材を提供しており、至る所に美が偏在していることに瞠目させられる。さらにアルバム全体を通して見れば、悠遠な探求者の気質で覆われていることもまた確かである。三人の演奏からは彼ら自身が今後ライヴ・パフォーマンスの現場で次なる展開を期待している気持ちがはっきりと感じ取れる。 フィル・ジョンソン
Phil Johnson
英国インディペンデント・オン・サンデイ紙
Independent on Sunday
|
|
| |
|
|
 |
ティム・バーン Tim Berne 《スネイクオイル Snakeoil》(ECM
2234)へのプレスの反応、続報。
|
|
| |
この30年間を振り返ってみて、ジャズ或いはその周辺の分野でティム・バーン
Tim Berne に比肩し得るほどに独自の音楽語彙を発達させてきたミュージシャンは数えるほどしかいない。透き通った、だが逞しさも備えた音色を有し、即興演奏のための戦略をいくつも手の内に控えた──たとえば溢れるような音への食らいつきと跳躍、奇妙な構造、無骨な発音といったような──アルト・サックス奏者ティム・バーン氏は、どうにも散漫だが、しかし同時に直接的とも言える姿勢へと捩じ曲げられたその独特な作曲様式によって、何を聴いても容易に彼の音楽だと識別することのできる個性をもっている。その潜在的な主題と同様に揮発性を備えた中枢神経系から生じるもの、もとより、それが作品のすべてである。 ネイト・チネン
Nate Chinen
ニューヨーク・タイムズ New York Times
|
|
| |
作曲と即興を混ぜ合わせることを試みた同時代の音楽家で、このアルト・サックス奏者ほどの成功を収めた者はほとんどいないのではあるまいか。事実、ティム・バーン
Tim Berne は、作曲と即興という区分を時代遅れのものに追いやって、見かけ上では矛盾しているこの二つの音楽的実践をまったく継ぎ目を感じさせないような仕方で統合しているのである。(中略) 《スネイクオイル
Snakeoil》によって、バーンはこれまでの彼の音楽とは一線を劃した全く新しい局面に入り込んでいるという印象を受ける。そして、ティム・バーンがこの録音に先立つ二年間に亙って、楽器を手に実際の演奏を通じて共に試行を重ねてきたこのグループの面々は──クラリネットのオスカー・ノリエガ
Oscar Noriega、ピアニストのマット・ミッチェル
Matt Mitchell、ドラマーのチェス・スミス
Ches Smith──、バーンがどこへ向かって進んでいるのかを的確に察知しているように思われる。 コーマック・ラーキン
Cormac Larkin
アイリッシュ・タイムズ Irish Times
|
|
| |
ブルックリンを拠点に活動するこの名うてのサックス奏者は、もって生まれたその猛々しい本能を、しっかりと事前のリハーサルで準備された上で自由な流れを実践する叙情的な室内楽的ジャズ・クァルテットという範囲内に抑え込んでおり、すなわち、このグループの音楽は、譜面上に堅固に作られた構造によって──そこから流砂のように気分を切り換えて展開を見せるのだが──即興演奏が齎(もたら)す自由を和らげているのである。不規則な鼓動と爆発的な打音を響かせるドラム奏者チェス・スミス
Ches Smith、雰囲気に富むマット・ミッチェル
Matt Mitchell のアコースティック・ピアノ、そしてティム・バーンは力強い音色と有無を言わさぬアーティキュレーションでメロディを急回転させ、その曲がりくねったテーマの上にオスカー・ノリエガ
Oscar Noriega の木の温もりを感じさせるクラリネットがサックスの音色と対照をなすと同時にその引き立て役を演じるかたちで加わっている。 マイク・ホバート
Mike Hobart
英国フィナンシャル・タイムズ Financial Times
|
|
| |
|
|
 |
ジョヴァンナ・ペッシ
Giovanna Pessi とスサンナ・K・ヴァルムルー Susanna K. Wallumrød の《イフ・グリーフ・クッド・ウェイト
If Grief Could Wait》(ECM 2226)へのコメント。
|
|
| |
スサンナ・K・ヴァルムルー Susanna K. Wallumrød の本作でのアプローチの目新しさは──それは彼女の共同制作者であるバロック・ハープ奏者ジョヴァンナ・ペッシ
Giovanna Pessi に対しても言えることだが──、その誠実な純真さにある。彼女たちは、ニック・ドレイク
Nick Drake やレナード・コーエン
Leonard Cohen のいくつかの歌を(パーセルの曲もそれらと同じスタイルで取り上げられているのだが)、何も“クラシック音楽”に変形させようとしているわけではない。バロック・ハープ
Baroque harp、ヴィオラ・ダ・ガンバ
viola da gamba、ニッケルハルパ
nyckelharpa (これはヴァイオリンと鍵盤楽器の中間のような外見をもつ、古風な仕掛けからなる民族楽器)という独特な楽器編成によって、かくも優しく演じられ美しく録音されている。 トム・ハイゼンガ
Tom Huizenga
ニュー・パブリック・ラジオ New Public Radio
|
|
| |
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.

|
|
| |
※本記事は、ECM が発信する最新情報を ECM Records の許諾を得て翻訳掲載するものです。(musicircus) |
|
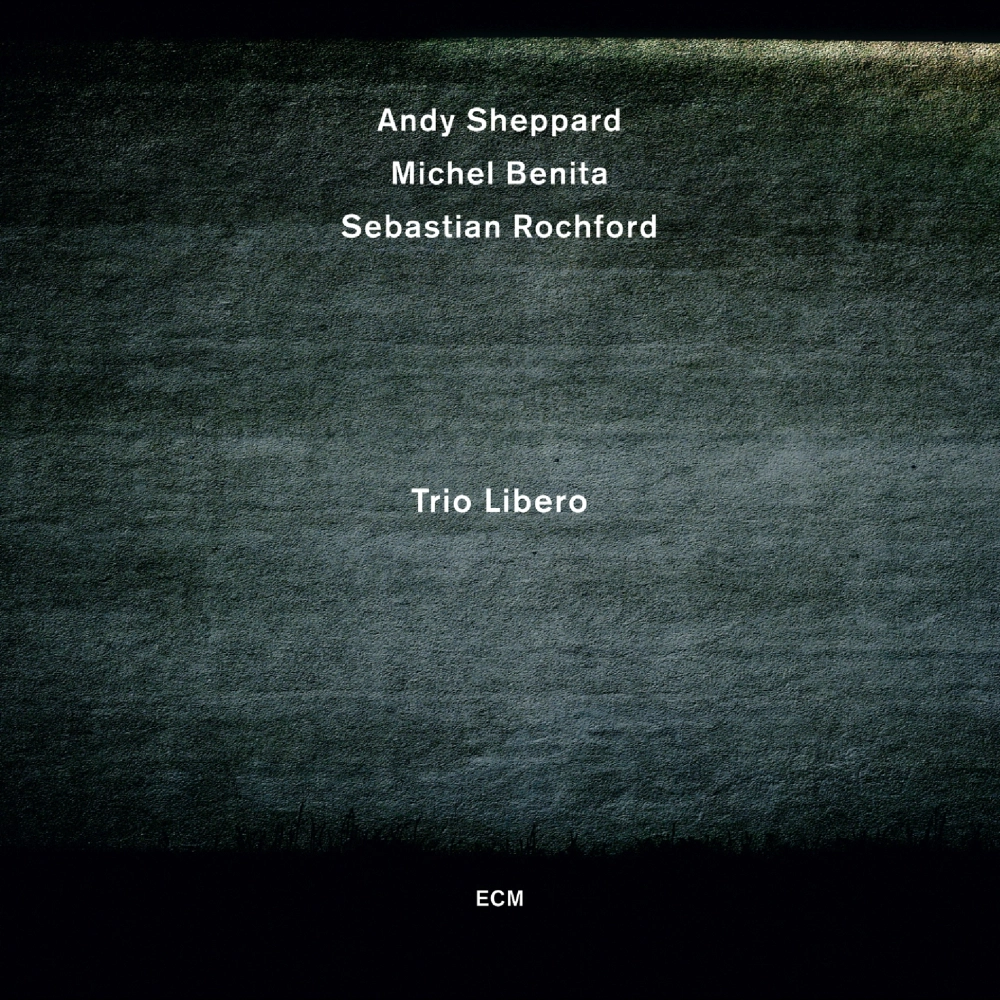


![]()