February 3, 2012
|
| 今週の批評から Reviews
of the Week
|
|
|
 |
トルド・グスタフセン
Tord Gustavsen の新作《ザ・ウェル
The Well》(ECM 2237)への英国インディペンデント誌
The Independent のレヴュー。
|
|
| |
ほとんど完璧に近い三枚のピアノ・トリオ・アルバムをリリースした後、現在の四人のミュージシャンの編成となり──トルド・グスタフセン
Tord Gustavsen、リード奏者のトーレ・ブルンボルグ
Tore Brunborg、ベースのマッツ・アイレットセン
Mats Eilertson、ドラムのヤーレ・ヴェスペスタ
Jarle Vespestad ──、幾分か新たな試みを感じさせるアンサンブルによる前作の録音を経て、今作《ザ・ウェル
The Well》は、グスタフセンの作曲家としての次元の高い真剣さと、格好良さ、ゴスペル風のバンプ等々を統合した内容となっている。収録曲の中では、「サークリング
Circling」が、そうした統合を分かりやすく実践しているトラックだと言える。この曲は、ヴェスペスタが囁き声に近い静かな音で叩き続けるドラムンベース風のリズムで推進力を獲得した荘厳な子守唄のテーマをもった小品だが、これに類した音楽的な傾向が本作では終始一貫して見出される。 フィル・ジョンソン
Phil Johnson
英国インディペンデント・オン・サンデイ紙
Independent on Sunday
|
|
| |
|
|
 |
ティム・バーン Tim Berne の《スネイクオイル
Snakeoil》(ECM 2234)へのプレスの反応。
|
|
| |
このところ、米国出身の作曲家でサックス奏者のティム・バーン
Tim Berne が一段と影響力を増してきつつある。彼がマルク・デュクレ
Marc Ducret やネルス・クライン
Nels Cline といった型破りのギター奏者たちとフリー・ファンクの冒険を試みたアルバムを最近聴く機会があったが、現時点でのティム・バーンの最新のバンドの演奏を収録した本作《スネイクオイル
Snakeoil》の内容は、それとは全く異なるストーリーをもっている。バーンは本作でも従来と同様に、各奏者が常に連動することで生じるリズムに根差したメロディを、痛ましい現代の叙情と釣り合わせようと企図している。だが、今回のバンドは──メンバーは、オスカー・ノリエガ
Oscar Noriega のクラリネット、マット・ミッチェル
Matt Mitchell のキーボード、チェス・スミス
Ches Smith のドラムス──これまでよりも遙かに室内楽的なサウンドを聴かせており、また、エレクトリックな生硬な音を控え目に扱っている点で、バーンの以前のバンド・サウンドとの違いが際立っている。たとえば、1曲目の「Simple City」では、曲の冒頭は憧れに満ちた不協和音へと分解し続けるアコースティック・ピアノの美しい旋律で始まるが、その音の動きに添ってドラムが登場するやいなや音の風景は変転し、そこを今度はノリエガのバス・クラリネットが漂いながら横切って行く。さらに、バーンのアルト・サックスの長く延ばした音を仄かに光り輝かせようと、こうしたいわば物腰の柔らかい乱闘然とした状態が曲の最後に至るまでじわじわと展開されていくのである。2曲目「Scanners」と5曲目「Not Sure」に登場するポスト・バップの力強いテーマは、バーンならではの典型的な作品だろう。彼が最も得意としている複雑に入り組んだ織機で描き出した鋸歯状の輪郭線と聴き手を煽り立てるような震動を併せ持った音楽である。本作《スネイクオイル
Snakeoil》はおそるべきアルバムであり、そしてまた作曲と即興との均衡という問題や、アコースティック・バンドならではの潜在的な音色の可能性などについて考察するための素晴らしい実例ともなっている。 ジョン・フォーダム
John Fordham
英国ガーディアン紙 The
Guardian
|
|
| |
ティム・バーン
Tim Berne と彼のグループは、本作《スネイクオイル
Snakeoil》を制作するに当たって──このサックス奏者の全キャリアを通じての画期的事件といえる作品である。──とりわけ“自由”に注目し、意味合いを異にする複数の“自由”が継ぎ目を意識させずに合流し共存することで、さまざまな音楽的な関係性を創出することに成功している。(中略) 《スネイクオイル》は何度も再考された作業手順(modus operandi)に従って体現した作品であるとも言える。また本作では、アイヒャーとの共同作業によって、各メンバーの個々の特殊性とその同期性に対して一層強く焦点が当てられており、この新しいグループの作品は、うまくするとECMとの長く実りのある関係の始まりになることが期待される。 ジョン・ケルマン
John Kelman
AllAboutJazz
|
|
| |
|
|
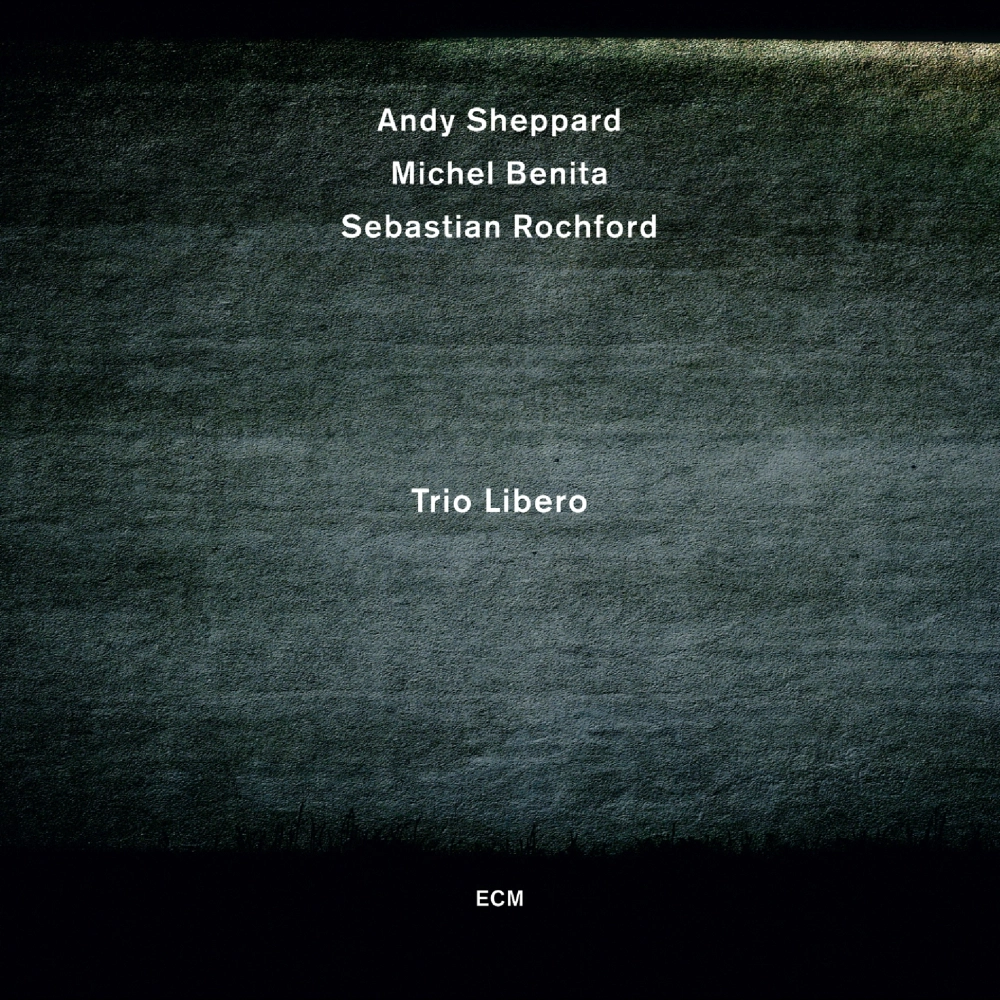 |
ロンドン・ジャズ London Jazz に掲載されたアンディ・シェパード
Andy Sheppard の《トリオ・リベロ
Trio Libero》(ECM 2252)についてのレヴュー記事。
|
|
| |
自発性と同時にお互いを熟知した交感の融合が、即興演奏の緊張感を保ちながら進むこのトリオによる演奏の全ての部分に染み渡っており、またそれぞれの音楽家が個々の曲の輪郭を明確に把握していることが鮮明に伝わってくる演奏を聴かせている。しかもなお、その統一感からはみだすことなく、一人ずつが違った特色を示して独自の道を歩むという、きわめて高度な座標を描き出すことに成功している。これらの音楽における諸力の合成は、アンディ・シェパード
Andy Sheppard が持つさまざまな強い力──すなわち、胸を締めつけるようなメロディを探り出す確かな耳や、その独自のサックス・サウンドへの彫刻的アプローチ、また自由と構造の間を何の継ぎ目も感じさせずに移動する才能──などの混合に留まらず、ミシェル・ベニータ
Michel Benita の並外れた多才さや、音楽が進展する局面に沿ってまさにその瞬間が要求するシンバルやドラムの正しい一打を精確に選び出しバンドのサウンドを巧みな仕方で潤色しているセバスチャン・ロッチフォード
Sebastian Rochford の神秘的な能力とも合体したものだ。本作の全編を覆っている印象は、多くのECMファンにはポール・モーシャン[モーション/モチアン]
Paul Motian がECMに吹き込んだ一連のアルバム群を想起させるかもしれないが、トリオ・リベロ
Trio Libero の音楽の力とその特徴は、三人のそれぞれ全く違った個性をもった音楽家がひとつのユニットにゲル状に固まり、だが矛盾を感じさせることなしに、各人の存在を消さずに活かしきっているという、たおやかな気品と優雅な佇まいの中から生じているのである。 クリス・パーカー
Chris Parker
ロンドン・ジャズ London
Jazz
|
|
| |
|
|
 |
ディノ・サルーシ Dino Saluzzi の新作《ナビダッ・デ・ロス・アンデス(アンデスのクリスマス)
Navidad de los Andes》(ECM 2204)へのイタリアのプレスの反応。
|
|
| |
ディノ・サルーシ
Dino Saluzzi が本作で創出している深い悲しみを描いた旋律の運びと和声の織物は、ドイツ出身のチェロ奏者アニヤ・レヒナー
Anja Lechner との20年に及ぶコラボレーションや、弟のフェリックス・サルーシ
Felix Saluzzi との理想的な、かつ几帳面な共生があってこそ齎(もたら)されたものだと言える。(中略) その響きは──軽く、単純で、どこか捉えどころのなさを感じさせながら──山裾の森に住む鳥たちの呼び交わす鳴き声を思い起こさせ、聴き手の心を魔術的リアリズムの手法で描かれたアンデスの御伽噺の世界へと導いていくように思われる。しかしまた、それはどこかしら、舞踏場の喧騒を暗示している音のようでもある。ディノ・サルーシ
Dino Saluzzi、アニヤ・レヒナー
Anja Lechner、フェリックス・サルーシ
Felix Saluzzi の三人による本アルバムは、日常の生活を描いた絵画であり、そこでは、バンドネオン、チェロ、クラリネットとテナー・サキソフォンの響きが異文化間の語彙を呼び交わしながら、ジャンルの狭間で──この音楽はジャズでもなければクラシックでもタンゴでもない──穏やかに溶け合っている。おそらくこの音楽は、ジャンルにおいて理解すべきものではなく、バンドネオンの名手の内奥に刻まれた個人的な痕跡をさまざまなかたちで相互参照した、いわば音の文体論上のひとつの試みであるように思われるのである。 フランチェスコ・ペルーゾ
Francesco Peluso
フェデルタ・デル・スオーノ Fedeltà del Suono(イタリアのオーディオ専門月刊誌)
|
|
| |
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.

|
|
| |
※本記事は、ECM が発信する最新情報を ECM Records の許諾を得て翻訳掲載するものです。(musicircus) |
|


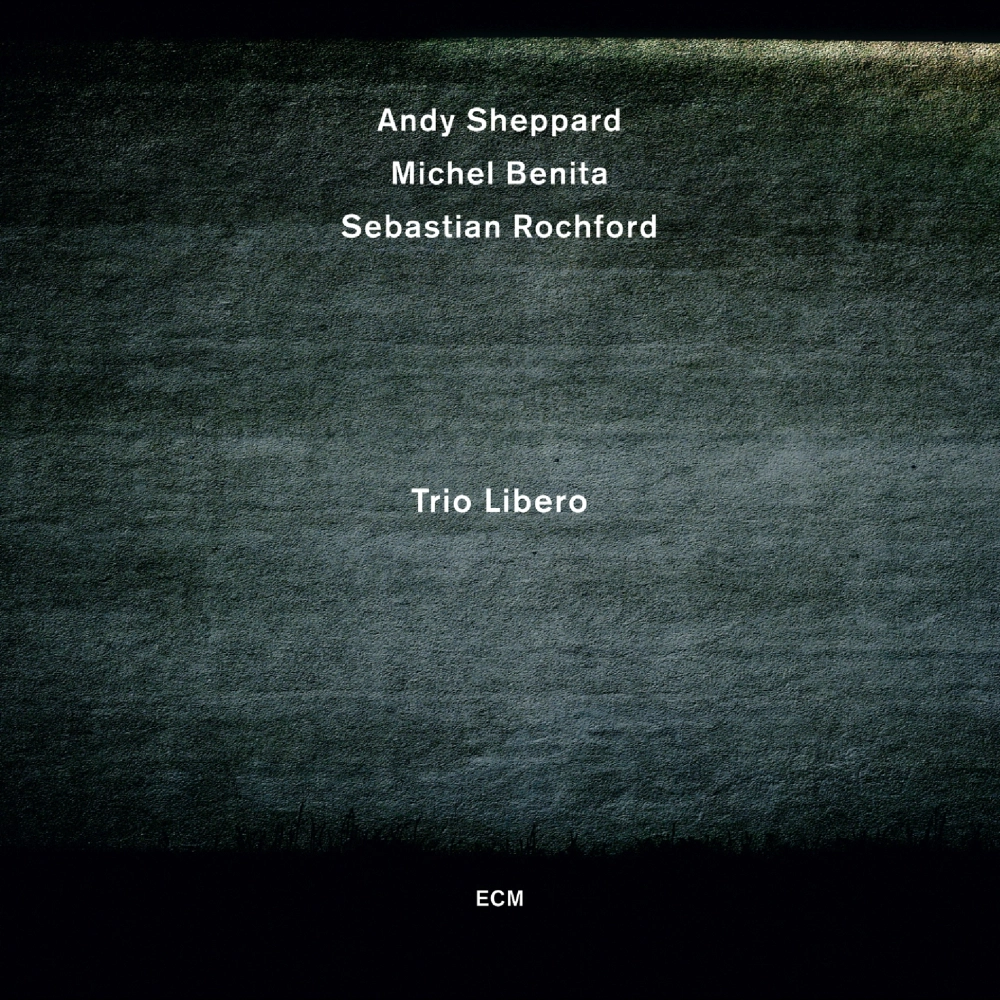

![]()