June 1, 2012
|
| 今週の批評から Reviews
of the Week
|
|
|
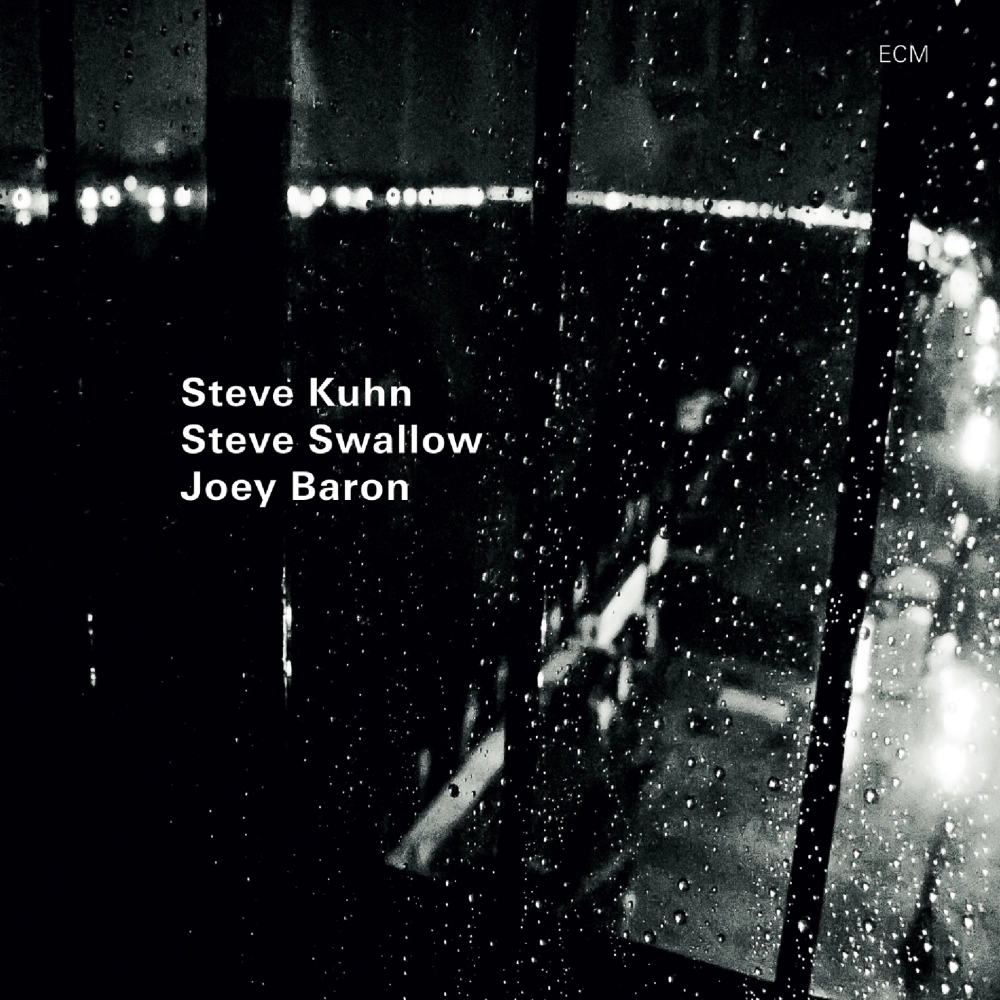 |
スティーヴ・キューン・トリオ
Steve Kuhn Trio の新作《ウィステリア
Wisteria》(ECM 2257)を聴いた米国の批評家がその興奮と感動を記しています。
|
|
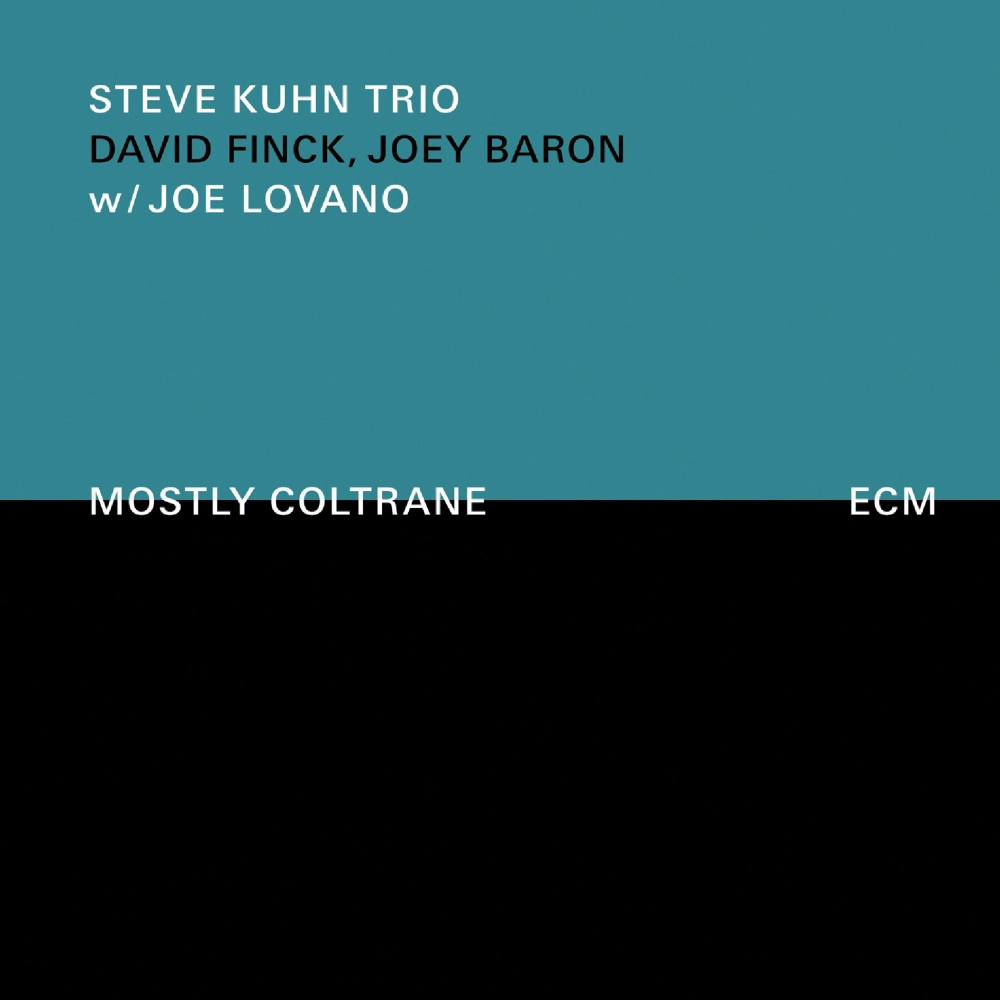 ECM 2099
|
ピアニストのスティーヴ・キューン
Steve Kuhn とベーシストのスティーヴ・スワロウ
Steve Swallow が、今回のECMにおける新録音アルバム《ウィステリア
Wisteria》に収録されているタイトル・ナンバーを初めて共演したのは、1960年代の始め頃のことだった。当時二人はこの曲を作ったアート・ファーマー
Art Farmer のバンド・メンバーの一員だった。以後数十年に及ぶ活動歴のなかで、二人は数多くの共演を重ね、心の通い合う関係を築くまでに至った。そして今回、ウィステリア・トリオの第三のメンバーとして録音に参加したジョーイ・バロン
Joey Baron は、スティーヴ・キューンが2009年にリリースしたモストリー・コルトレーン・プロジェクトのメンバーでもあった〔Steve Kuhn Trio w/ Joe Lovano 《Mostly Coltrane》(ECM 2099)〕。翻ってみれば、本盤《ウィステリア》はこのトリオにとって初の単独レコーディング・アルバムに該当する。三人のミュージシャンがそれぞれに培ってきた音楽性の最良の部分を存分に披露した、まさしく偉大な模範的な演奏である。(中略) おそらくは、メンバーの三人とも、長い期間に亙ってダウンタウンのアヴァンギャルド・シーンに精通していたことが大きい。この三人のミュージシャンはそうしたシーンの中で余人を以て代え難い功績を摘み取ってきた。新作《ウィステリア》には親しみ易さと挑戦的な姿勢が同居しており、なおかつアルバム全体のどこを取り出しても極上の質感で統一されている。本盤こそ、行き届いた紹介がなされて多様なジャズ・ファンに広く聴かれてほしい作品である。
グレッグ・バーブリック Greg
Barbrick
Blindedbysound.com
|
|
| |
ピアニストのスティーヴ・キューン
Steve Kuhn がベーシストのスティーヴ・スワロウ
Steve Swallow と久方振りにトリオ・フォーマットで共演した新作《ウィステリア
Wisteria》がリリースされた。この二人の交流は1960年代半ばにまで遡るが、その頃の二人はアート・ファーマー
Art Farmer のバンドで一緒にプレイしていた他、スティーヴ・キューンはスティーヴ・スワロウのベース、ピート・ラロカ
Pete La Roca のドラムと組んで、スティーヴ・キューン・トリオ
Steve Kuhn Trio を名乗って活動を行なっていた。私たちが実際に見聞してきたことを振り返ってみれば、現存の著名なジャズ・ピアニストのなかで、アーマド・ジャマル
Ahmad Jamal を例外として、スティーヴ・キューン以上に長期に亙ってピアノ・トリオのフォーマットで成功を収め、しかも偉大な実績を残してきたミュージシャンが果たして他に存在するだろうか?(中略) この顔ぶれでは本盤が初のレコーディングになるが、これがその最後の録音機会とならないことを願うばかりだ。
ロイド・サックス Lloyd Sachs
ジャズ・タイムズ誌 Jazz Times
|
|
| |
|
|
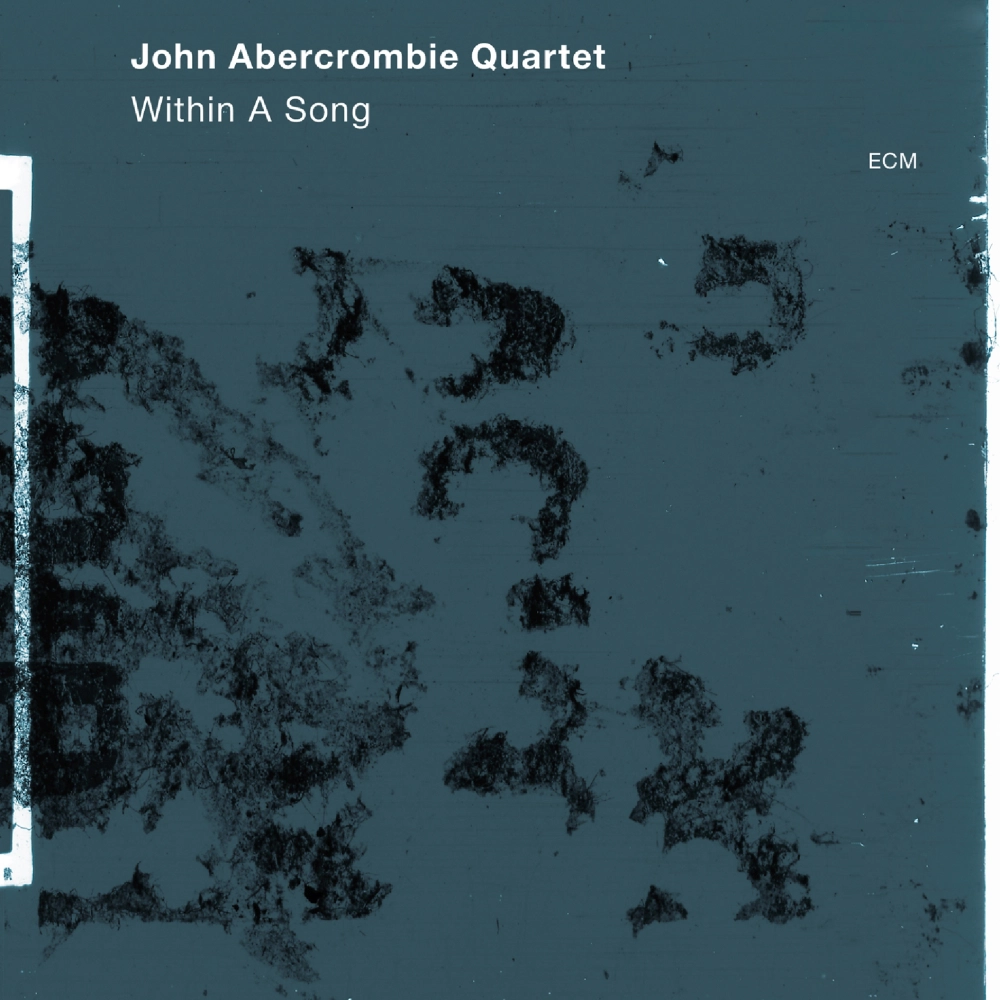 |
英国のメディアに掲載された、ジョン・アバークロンビー
John Abercrombie の《ウィズイン・ア・ソング
Within A Song》(ECM 2254)への批評。
|
|
 ECM 1683
|
アバークロンビーというギタリストならではの暖色系の音色、そして精確な演奏技巧は、テナー・サックス奏者のジョー・ロヴァーノ
Joe Lovano が作り出す気ままに漂うサウンドとじつに相性が良い[訳註:ジョー・ロヴァーノがアバークロンビーの作品に参加するのは、《オープン・ランド
Open
Land》(ECM 1683)以来のこと]。それが功を奏して、本盤ではサウンドの実体がさらに強力なものとなっている。慎み深いニュアンスで抑え気味の微妙な味わいの響きを奏でるドラムのジョーイ・バロン
Joey Baron と揺るぎない指先をもつベース奏者ドリュー・グレス
Drew Gress は、ジョー・ロヴァーノが生み出す、か細くざらついているがしかし完璧と言える音のラインを一緒になって駆り立てながら、しかも同時にお互いの音を一本の線に縒り合わせるべく、見事な脇役を演じている。
マイク・ホバート Mike Hobart
英国フィナンシャル・タイムズ Financial Times
|
|
| |
|
|
 |
フライ・トリオ Fly Trio 〔マーク・ターナー Mark Turner(t-sax)、ラリー・グレナディア
Larry Grenadier(b)、ジェフ・バラード Jeff Ballard(d)〕の新作《イヤー・オブ・ザ・スネイク
Year Of The Snake》(ECM 2235)への米国ジャズ・タイムズ誌
Jazz Times の批評。
|
|
| |
ベースとドラムを従えたテナー・サックスのトリオという編成は、放縦だったり不明瞭だったりする過去のジャズ・ミュージシャン達が残したイメージを喚起させる。いずれにしても、ソニー・ロリンズ
Sonny Rollins やジョー・ヘンダーソン
Joe Henderson といったテナー・サックスのヴィルトゥオーゾにとっては、サックス・トリオという編成は、いつでもあらゆる身の危険を引き受けつつ、ぴんと張られた一本の綱の上を安全ネットなしで踊るための舞台であった。しかしながら、自らを「フライ(翔ぶ)」と称する、この新しいテナー・サックス・トリオが奏でる音楽は、そうしたジャズの伝統との明白な断絶を体現してみせている。「フライ・トリオ
Fly Trio」 ――マーク・ターナー
Mark Turner(t-sax)、ラリー・グレナディア
Larry Grenadier(b)、ジェフ・バラード Jeff Ballard(d)――が奏でる音楽は、三種類の楽器からそれぞれ幅広い色彩とテクスチュア(肌合い)を引き出した相互作用的なチェンバー・ジャズ[室内楽風のジャズ]であり、聴き手の知性に訴えかけつつ、心をしっかりと掴んで離さない。(中略) 「フライ」の音楽は洗練されており、一切の誤魔化しの利かない極めて優れた能力に裏打ちされている。
トーマス・コンラッド Thomas
Conrad
ジャズ・タイムズ誌 Jazz Times
|
|
| |
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.

|
|
| |
※本記事は、ECM が発信する最新情報を ECM Records の許諾を得て翻訳掲載するものです。(musicircus) |
|
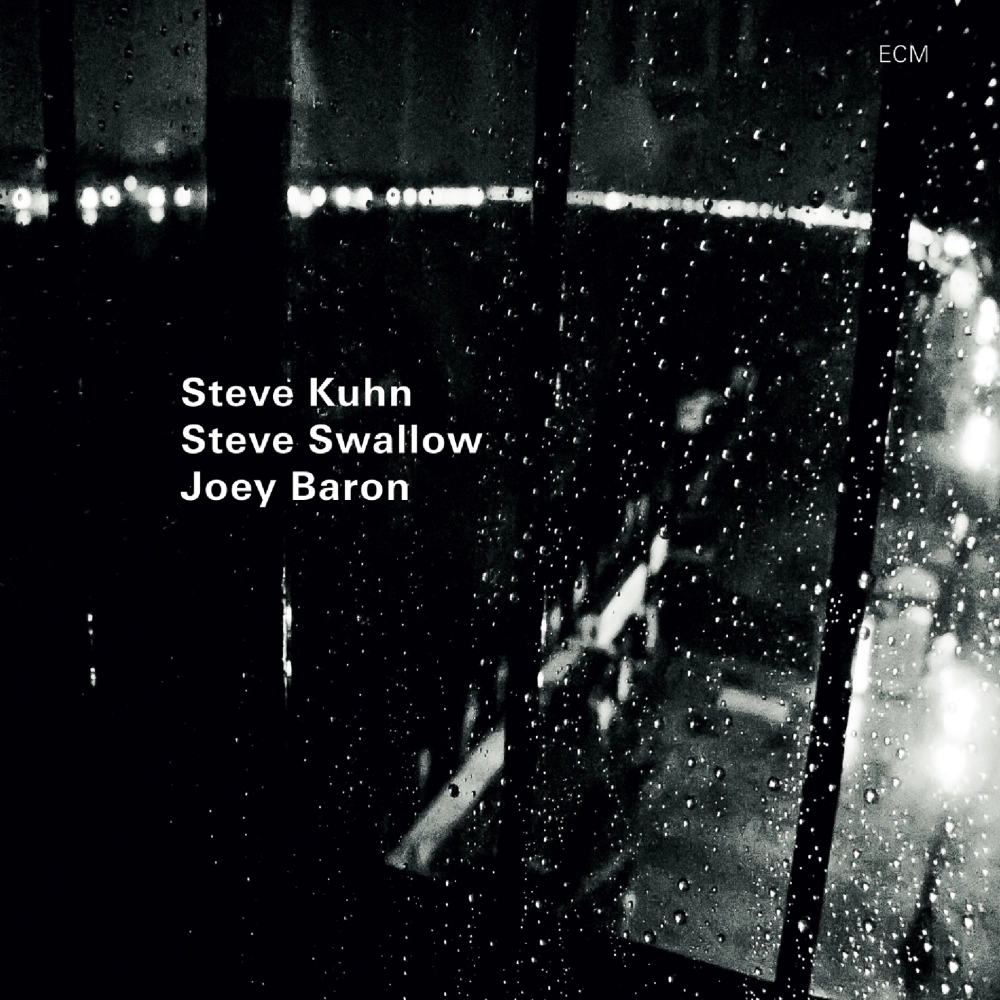
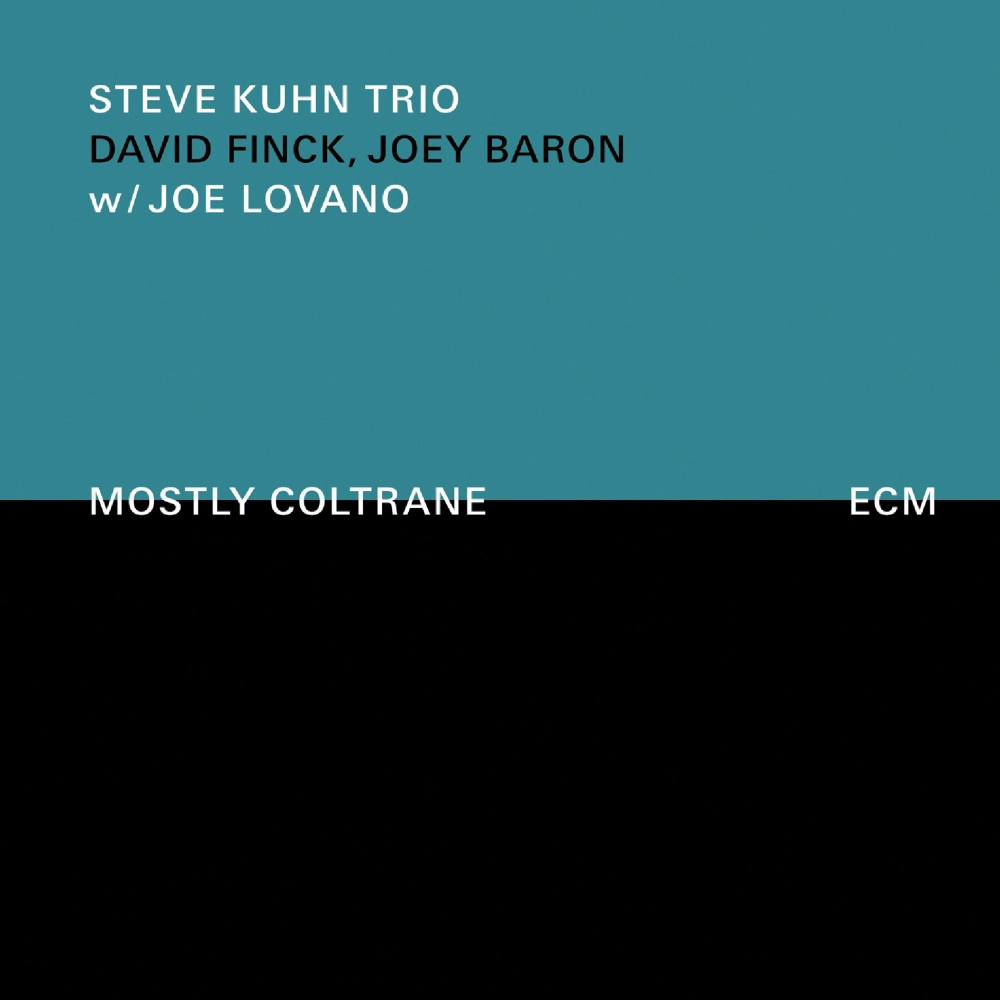
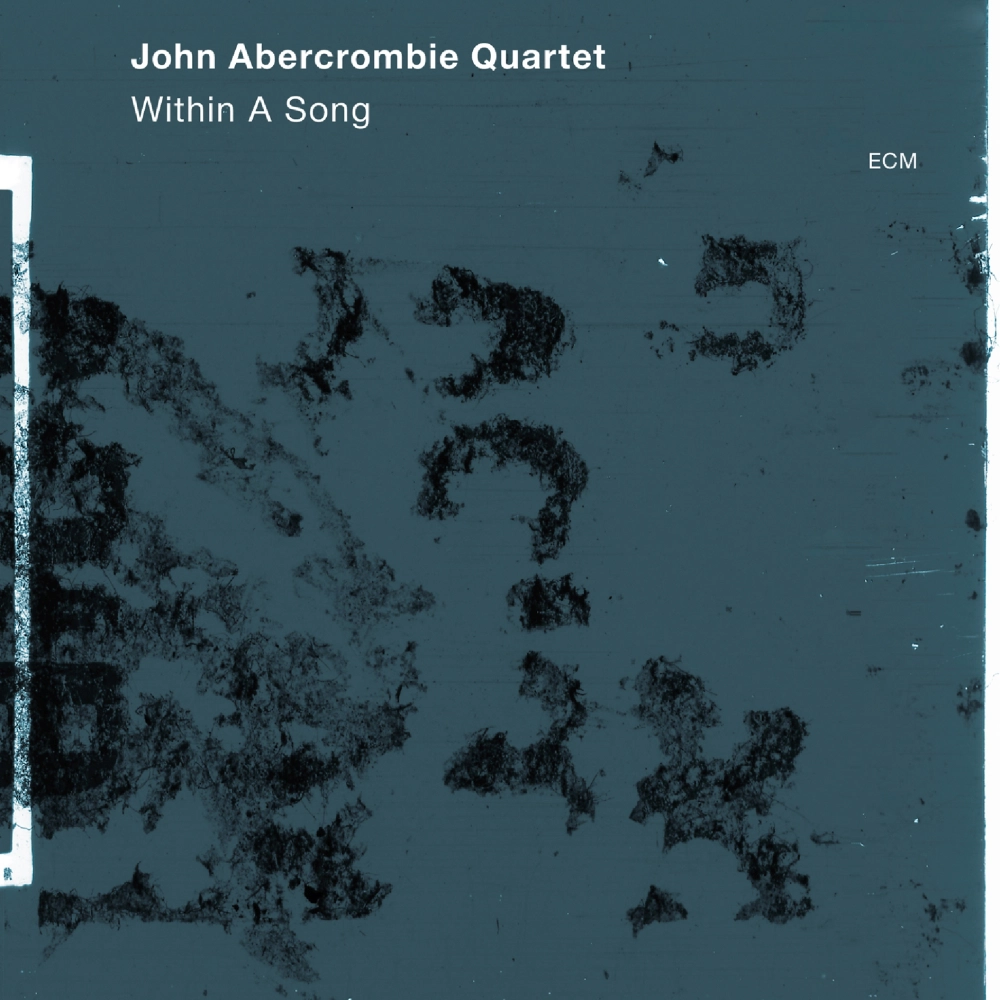


![]()