June 22, 2012
| 今週の批評から Reviews of the Week |
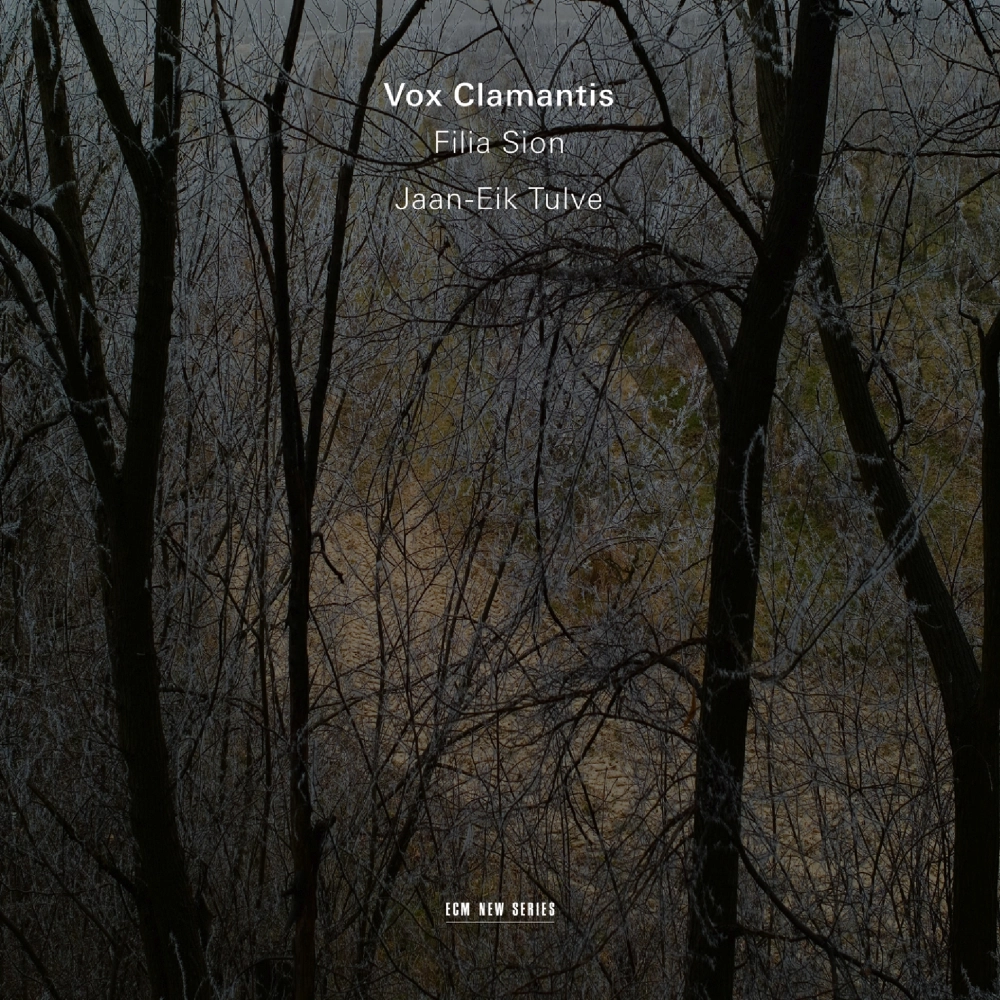
スティーヴン・ペティット Stephen Pettitt
サンデー・タイムズ Sunday Times
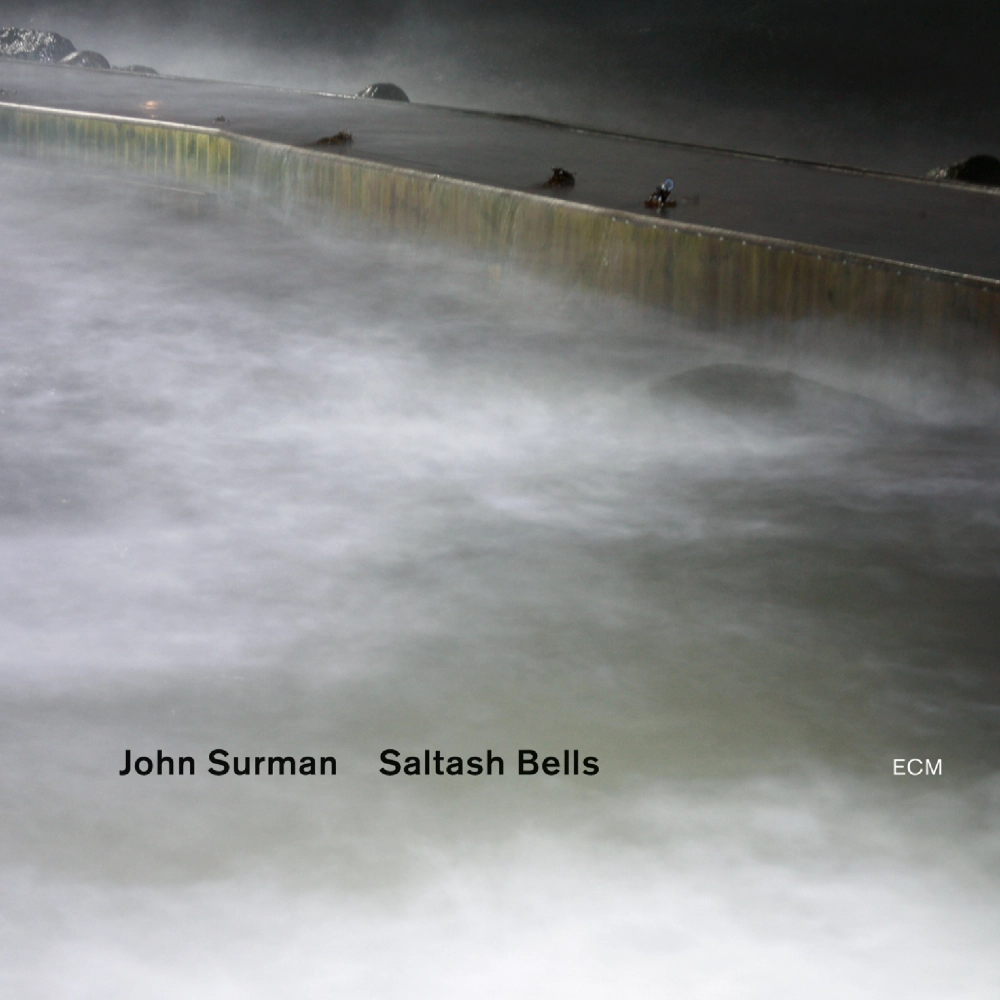
ジョン・ワトソン John Watson
ジャズカメラ Jazzcamera
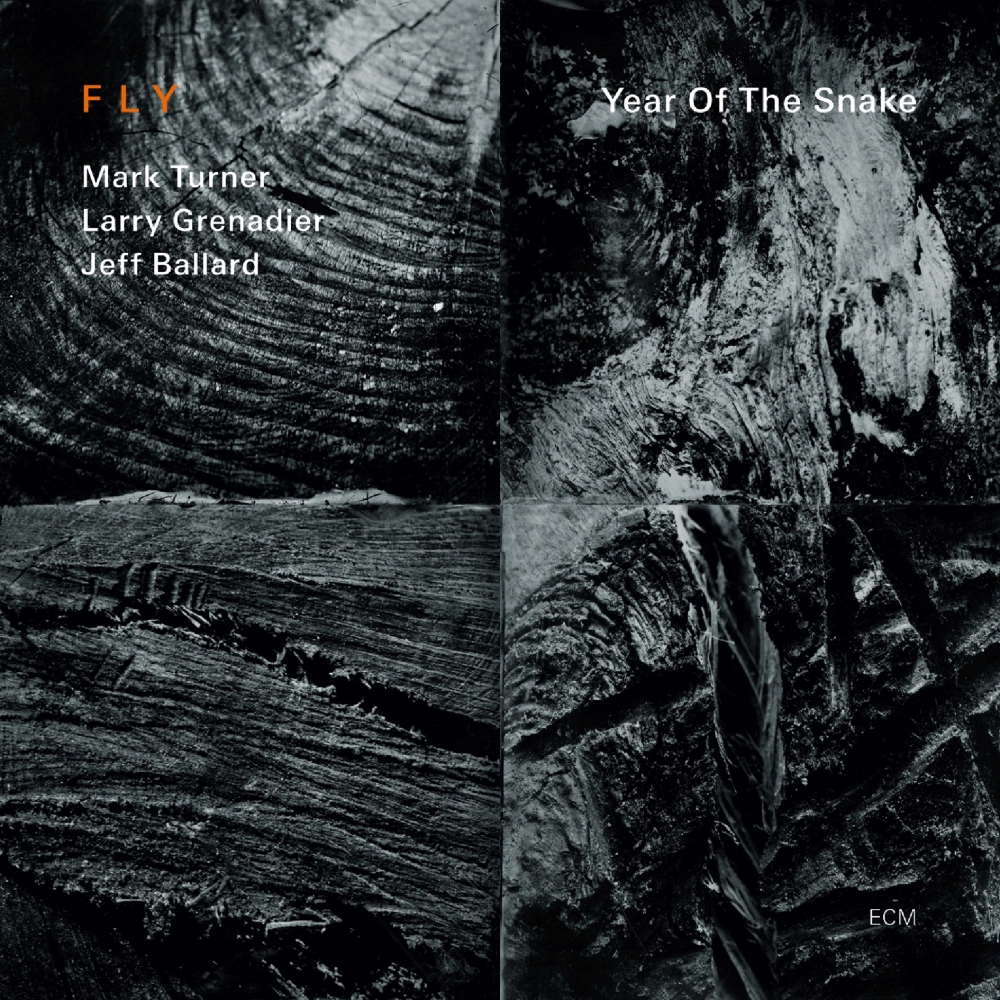
ネイト・チネン Nate Chinen
ニューヨーク・タイムズ New York Times
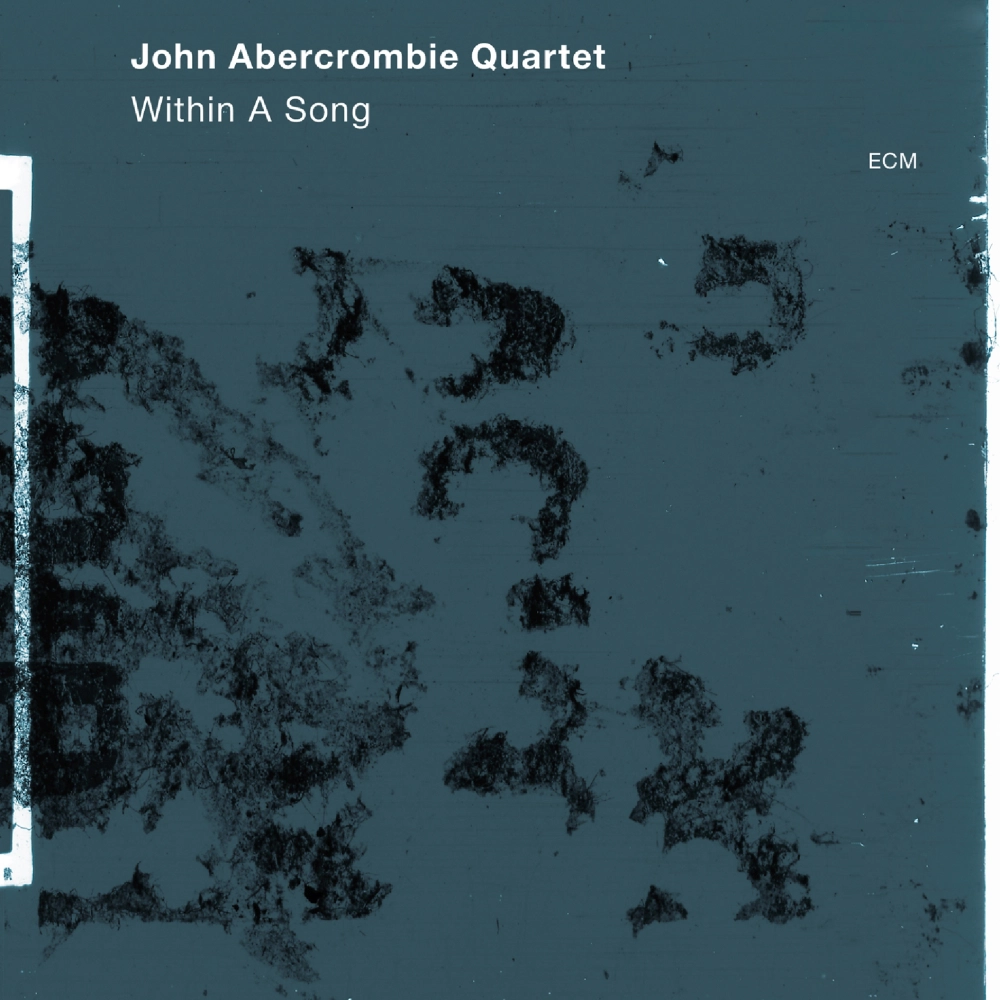
コーマック・ラーキン Cormac Larkin
アイリッシュ・タイムズ Irish Times
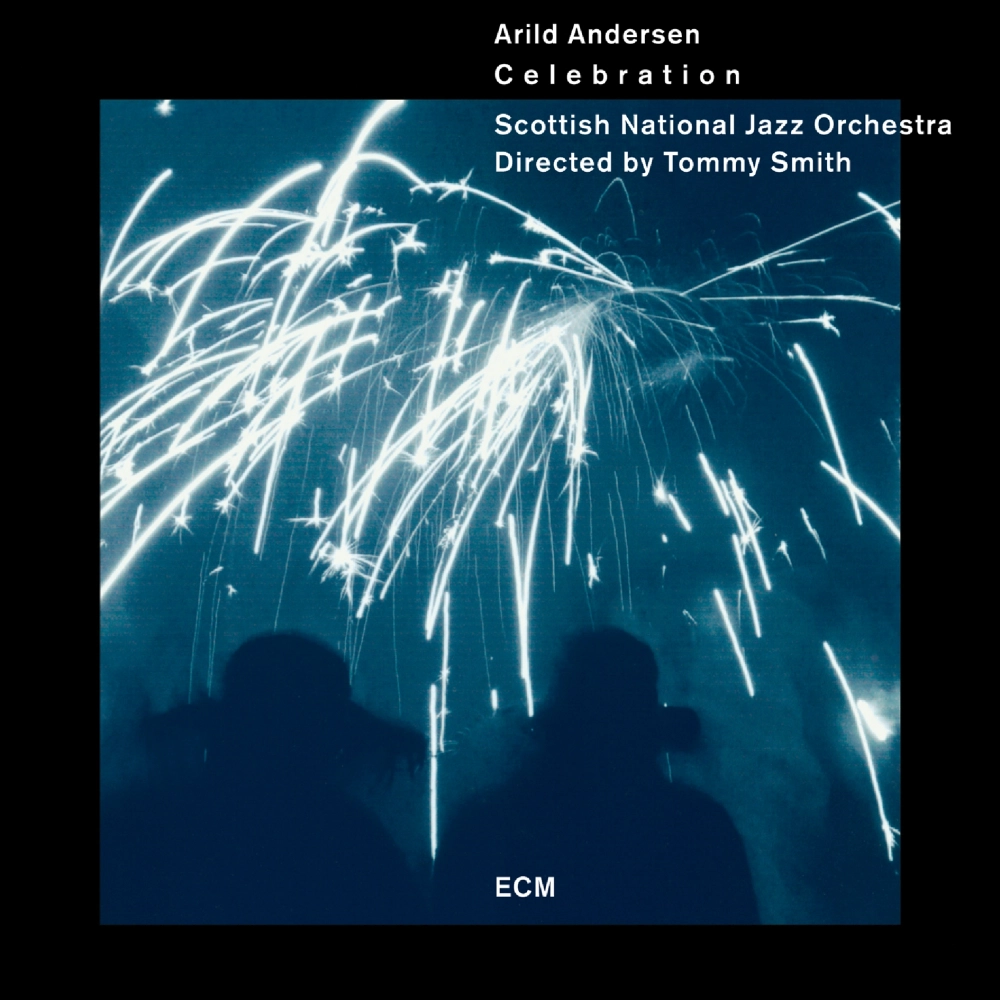
トーマス・コンラッド Thomas Conrad
ジャズ・タイムズ誌 Jazz Times
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.
![]()