|
|
|
|||||||
 |
《ディスアポイントメント-ハテルマ Disappointment-Hateruma》 土取利行 Toshiyuki Tsuchitori 坂本龍一 Ryuichi Sakamoto CD: KICS 1137
綾 (Aya) |
||||||
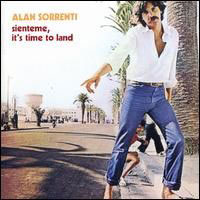 |
『シエンテマ、イッツ・タイム・トゥ・ランド/アラン・ソレンティ』 アラン・ソレンティはナポリ出身。デビュー作《アリア》(1972)ではジャン・リュック・ポンティ(vn)などをゲストに迎えて、吹きすさぶ風の中で狂気を帯びた叫びとファルセット・ヴォイスを雲間に走らせる吟遊詩人、なんていう形容がぴったりな、結構実験的なことをやっていましたが、この1976年の作品あたりから方向転換。明快で分かりやすいポップスにシフトして、音作りの拠点もアメリカ西海岸に。 イタリアでナンバー・ワンを獲得した次作《フィグリ・デッレ・ステッレ Figli Delle Stelle》(1977)こそ彼の頂点を築いたと思いますが、今年新たに入手した本作(国内盤CD)も、色褪せた記憶の風景というか、独特なフラジャイル感を漂わせていて味わい深いです。憂いを含んだ優しさの「シーガル・ソング」など、海辺の午後の微睡まどろみと潮風を運んでくれるような。 |
||||||
 |
『密教 阿字観瞑想』 2005年夏、高野山を再訪した折に宿泊した一乗院で、阿息観あそくかんの手ほどきを受けました。密教の瞑想法は阿字観あじかんとして体系化されていて、その基本はすべて呼吸にあるのです。阿字観の入門段階として呼吸法を整えたものが阿息観。禅宗の座禅では、想念を消すことが重視されますが、密教での座禅に当たる阿字観では、瞑想中に何を想っても感じても構わないのです。ただし呼吸のイメージだけは、かなり具体的で厳密に定められています。 オリジナルは1978年に製作された2枚組LPレコード。一部を除きほぼすべてが高野山での現地収録のため環境音が多く入っています。空間の気配やざわめきは無意識下に強く働きかけてきます。「場所」の記憶や霊は、すべて「音」に宿るのではないでしょうか。 CD1で、真言宗の僧侶が唱える声明は、時にはわらべうたを思わせる動きを見せながら、ダイナミックにうねり、波立ち、滔々と流れていきます。そこにかぶさる高橋大海による理趣経の現代語訳朗読は、ややオカルティックかも…。(真言声明といえば、高野山声明の会のCD《常楽会じょうらくえ》が昨年度の芸術祭賞を受賞しています) CD2には「密教瞑想法の実修」として、阿息観あそくかん、月輪観がちりんかん、阿字観あじかんの実際が、真言密教瞑想の第一人者、山崎泰廣やまさき たいこう師の語りの導きによって体験できます。またCD2最後のトラック「空海請来五鈷鈴の振鈴」は、LPでは付録シングル盤という体裁でしたが、空海が持ち帰った密教の秘具を鳴らした音です。その霊気たるや、録音を通して聴いても相当なもの。 |
||||||
 |
『ハイ/ブルー・ナイル』 崇高な音世界。孤高のバンド、ブルー・ナイルのアルバムは、世界の片隅からそっと発信される貴重なシグナルです。その4回目の合図を見逃していて、今年ようやくキャッチ。このスコットランドのグループは20年以上の活動でアルバムを4枚しかリリースしていません。というのも、音楽を生活の糧を得るための職業とはせず、純粋に作りたいものを作りたいときに作るというスタンスを取っているからです。 寓話的あるいは象徴的な歌詞と、空を鳥が滑っていくような穏やかで美しいメロディ・ラインが心に残すイメージは、全体が曖昧でありながらも細部は明晰というまるで夢のような世界。時の流れと隔絶したままひっそりと立ち続ける一本の枯木。そこにポツリと降り注ぐのは、キリストの贖罪との対話から滲出してきたとおぼしき寛容の滴しずく。透明な悲しみを鞄に詰めて、精神の深い坑道を旅してきた者だけが生み出せる至高の輝きがここにあります。 |
||||||
 |
『アヴェ・マリア/本田美奈子』 本田美奈子のどこに惹かれていたのか。それは、歌詞の一節ごとに思いを込めて歌う説得力、透き通った声の魅力、ポジティヴな努力家だとかそういうことではなく、むしろ彼女自身のストイックな姿勢から生み出される意識の震えのようなものでした。 メロディの動きに身をまかせて気分や感性で歌うのではなく、旋律を追い求め、追い詰め、そして縋すがりつこうとする姿勢の“結果”として、感情のドラマ、詩の核心コアが立ち上がってくるというプロセス。そこを大事にしていたからこそ、彼女の歌を聴いていると、上辺のテクニックやオペレーションで作られた体験とは異質な、存在の“裂け目”を覗くような瞬間を味わうことになるのだと思います。 以前、ギタリストの故・芳志戸幹雄が、「ころんだ子供が、泣き声をあげる前に一瞬息をつめるでしょう。いわばそのような瞬間を、音楽の中でぼくは表現していきたいんです」──と語っていました。つながりを感じます。そこにはグレン・グールドもエリック・ドルフィー《アウト・トゥ・ランチ》も谺こだましているような……。 本田美奈子の歌は、声だけですべてを描き切ってみせるといういわゆる天才歌手が執り行なう秘儀とは違っていました。エラボレーション(磨き上げること)を通じて顕あらわれてくる自らの“化身”としての歌、そのなかに吹き込む“魂”を造形することに賭けたという意味で、彼女はなによりもすぐれた彫刻家でした。そして、その手に刻まれた傷にいつも微かに滲んでいたのは、懐かしくも甘い香りを含んだ温かい血のサクリファイス(犠牲の捧げもの)。音楽は、究極的には祈りのかたちをしているのだと思います。 |
||||||
 |
『エクスポウズド (DVD)/マイク・オールドフィールド』 1979年に行なわれた《呪文》と《チューブラー・ベルズ》をメイン・プログラムとした欧州ツアーのライヴDVDが、なぜか今頃になって公式リリースされました。このツアーのライヴ音源としては、すでに《エクスポウズド》(1979)というレコード/CDがありますが、今回のDVDはすべて初出音源となります(英国ウェンブリーのカンファレンス・センターでの収録)。 《呪文 Incantations》(1978)は、オリジナル・レコードでは2枚組の各1面ずつを使った四部からなり、6拍子+5拍子の11拍のリズムと5度音程のオスティナートが12音を順番に巡っていく循環モチーフをベースにした端正な構成感をもった作品です。そのシステマティックな仕掛けが文字通り「呪文」のような不思議な印象を強めているわけですが、自然への畏怖と憧憬といったアニミズム(精霊崇拝)的雰囲気を感じさせ、宗教音楽のようにも響きます。 このライヴDVDは2枚組で4種類のマルチ・アングル仕様、つまり4回違う映像で楽しめるという贅沢なつくりです。気になったのは、ステージ背景に映像作家イアン・イームス Ian Eames によって投影されていた海の映像がまったく出てこないこと。《プラチナム》(1979)発表の翌年に行なわれた11名編成のバンドでのヨーロッパ・ツアーでも、海上の波やグライダーが滑空するイメージを使った彼の映像プロジェクションがステージ後方に映し出されていたこともあり、当時のマイク・オールドフィールドにとっては重要なファクターだったはず。これはちょっとした謎。 アンサンブルは細かい傷が多いものの、次々と変幻を重ねる音楽の瑞々しい流れの勢いもあり、多少の澱みや水跳ねはあまり気になりません。「呪文」パート2(Youtube ■)でのスタジオ・オリジナル盤以上に透明な抒情を湛えるマディ・プライアー ――英国トラッド・ロックの代表格スティーライ・スパンのヴォーカルとしても有名―― の歌声や(彼女は《チューブラー・ベルズ》の最後「セイラーズ・ホーンパイプ」で会場内を踊り回る)、「呪文」パート4(Youtube ■)で特徴的な5度音程が積み重なるヴィブラフォンのフレーズを奏でる故ピエール・モーレン Pierre Moerlen とブノワ・モーレン Benoit Moerlen の兄弟、そして舞台奥で淡々とベースを弾く20歳代後半にして仙人然としたペッカ・ポーヨラ[ポホヨラ] Pekka Pohjola など見どころが満載。そしてなによりも背筋をぴんと伸ばしピックを口にくわえたまま右手5本のフィンガリングで個性的なギター・フレーズを縦横無尽に繰り広げる眼光鋭いマイク・オールドフィールド(当時25歳)の雄姿。《ギルティ》で踊っている合唱の女の子たちもほんとに楽しそう。 この人の場合、演奏技巧がどうこういうよりも明確な独自の声(ヴォイス)を持っていて、旋律とハーモニーが醸し出す独特なセンスや突出したヴィジョナリーな(音が映像を喚起させる)資質に惹かれるものがあります。エンヤがデビューした頃のインタヴューで、最も影響を受けた音楽家として(クラナドを除けば)モーツァルトとマイク・オールドフィールドの名前を挙げていました。2006年には、3枚組のベスト盤CD"the platinum collection"が発売されます。 |
||||||
 |
『復活祭から一年後に/クリスティアン・ヴァルムルー・アンサンブル』 繊細な美意識とインテリジェンス。ジャズ、現代音楽、クラシックといった区分を遙かに飛び越えた地点から発せられる、菌類(きのこ)のように空気中を漂い、偶然に姿を現わしては消えていく独特な音楽世界。クリスティアン・ヴァルムレーは、「気配」と「意識」の綾取りが流れるように生成消滅していく過程を客観的にスケッチすることができる類稀な才能の持ち主である。 本作のパーソネルは、クリスティアン・ヴァルムルー(p, harmonium, toypiano)、ニルス・オクランド(vln, Hardanger fiddle, viola d'amore)、アルヴェ・ヘンリクセン(tp)、ペール・オッドヴァール・ヨハンセン(ds)の四人。楽器編成から想像できる以上の豊かなソノリティを引き出しているが、それはカラフルというよりはむしろモノトーンな世界で、かすれやにじみ、筆勢や間隔を重視した響きの身振りの背後には東洋的価値観の存在が強く感じられる。 音の表面的な印象としては、慎ましく、物静かな風情から中世のゴシック音楽を思わせ、また、ゆったりとした平行移動音からはアルス・ノヴァの音楽を想起させる。その上に、感覚的というよりは描写と暗喩に従事している装飾的な音の身振りが何層ものヴェールとなって重なっていく。聴き手の心に広がるのは、絵巻物を眼で追っていく体験であり、自然の風景を切り取った淡い水彩スケッチの「気配」である。 この感覚はどこかにあったはずだと考えてみたら、エリック・サティの音楽だと思いあたった。たとえば、どの曲も限定された音素材と色彩による短い単位から成ることや、展開と表現の拒否。サティを「午前9時の白い音楽」と評したジャンケレヴィッチは、その音楽の向かう先を「魂の平静(アタラクシア)と無感動(アパシー)の選択」と洞察した。これは、クリスティアン・ヴァルムルーの音楽と深い次元で共通する資質ではないだろうか? 興奮や酩酊から逃れて、あからさまな感情の吐露を恥じらうように、澄みきったまなざしが投影する純粋な感覚の造形。そのとき音楽は、押しつけや感情のドラマとは無縁に、音そのものがただそこにあるというだけで周囲の見え方を変えてしまう域にまで到達する。 本作のタイトル「復活祭から一年後に」は、ジョン・ケージの著書「月曜日から一年後に」を念頭に置いて名付けられたものだという。サティ、ケージ、ヴァルムルーとつながる円環の至福。国内盤ライナーノーツは若林恵さんの執筆で、アーティストへのインタヴュー取材なども織り込んだ内容豊富かつ読みやすいテキストになっています。 |
||||||
 |
『いのちのことば/相田みつを&ジョン・ケージ』 ジョン・ケージと相田みつをの出逢い。これは、男女二人の俳優がケージの初期プリペアド・ピアノ作品(WERGO音源)をバックに、相田みつをの言葉を語っていくオーディオ・ドラマCD。全体の構成・演出は元NHKラジオドラマ担当ディレクター千葉守さん、効果音は元NHK効果団の生音の達人、大和定次さん。途中三箇所で、生前の相田みつをさんの講演録音が挿入される。 相田さんには、悟得者の余裕や諦念とは真逆の、むしろ不安と迷いに染め抜かれた者だけがもつ、希望をもとめて不器用にもがく固い身振りがあるようだ。固さゆえに、柔らかくゆがんで曲がろうとする思いが、光をもとめ、あるいは水と養分をもとめて伸びる植物の動きに重なっていく(苦しいときに根が育ち、努力のはてに花がひらく)。そこに、あの独特な書体が生れてきた秘密があるのではないだろうか。 相田みつを美術館を訪れたときに、私が最初に歩を止めたのは、「不」あるいは「ゆ」一文字の大きな書と向き合った瞬間だった。そして別の展示室で、夥しい書き込みが残された岩波文庫版の『正法眼蔵隋聞記』を見ているうちに、このCD制作の構想が固まっていった。「トイレの日めくり」として有名になった言葉の数々は、ありきたりな人生訓でも思いつきの詩でもなく、厳しい自問自答と禅の探究の果てに到達された、慈愛に満ちたエキスだったのだ。 このCDでは、言葉と音楽が、それぞれ自らを主張することなしに、しかしどちらも「いま、ここ」、「あるがまま」を指し示して充溢している。ものごとはつねに変化を続け、よき出逢いは新しい道を生む。ケージと相田さんの相性は本当にぴったりで、まるでケージがこのCDのために新たに作曲したかのような印象さえ受ける。 |
||||||
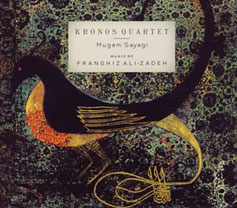 |
『フランギス・アリ=ザデー作品集』 アゼルバイジャン出身の女性作曲家フランギス・アリ=ザデーの作品集、演奏はクロノス・カルテットと作曲者自身のピアノ、ほか。アリ=ザデーはピアニストとして新ウィーン楽派、メシアン、ケージをアゼルバイジャンに紹介した過去をもつ。作曲家としてはイランと接する辺境の地の利を生かし、旧ソ連当局の目を逃れて自由に新しいスタイルに取り組んできた。西欧の価値観や基準で規定される一元化したものの見方は、すでに実践の現場では意味をなさなくなっている。主題の展開と発展で物語を伝えるやり方ではなく、部分の対比と交替で風景の境界を揺らして遠近法を超えた地点を目指すやり方。こうした音楽を聴く耳を、グローバライズされた世界は持っていない。 《アプシェロン五重奏曲》(2001)はピアノ(一部プリペアドで音色を変更)と弦楽四重奏のための作品。巨大な講堂(あるいは伽藍)の扉が次々と引き剥がされ、荒涼とした外気が一気に吹き込んでくるようなオープニングから、やがて微分音を含むイスラム風のモードが入れ替わり登場し、太陽光線が照らす立ち込める塵の柱となって辺りを取り囲む。あっという間の出来事。アリ=ザデーは自らの伝統との対峙を経て、激しい情景転換の持続からなるムガームの様式を取り入れ、新たな創作を行なってきたが、その成果が大胆なまでに提示されている。 アリ=ザデーの音楽は、静かな空間で集中して聴かれることを求めている類の音楽である。串刺しにした食物を火にかざす手付きで差し出された音が、人々の凝視と沈黙のなかでゆっくりと醸成されていく。東西の合わせ鏡のあいだを旅するヨーヨー・マのシルクロード・アンサンブルと異なるのは、彼らが演奏家として体験したものをステージで料理として提出するのに対し、アリ=ザデーの音楽では、聴き手がみずからの想像力で熱を与えて料理を完成させねばならない点にある。 風にしなう草のように、弦楽器の上に現れるケマンチェの微分音をはらんだ音の身振りは、音の表面をそっと波立たせ、ひそやかな歌を彼方へと運んでいく。《オアシス》の背後で(テープ再生によって)鳴り続ける水滴と人々のつぶやき声の響きにも、そうした風のそよぎと厳しい寂寥感が漂う。風に運ばれる歌は、どこにたどりつくのだろうか。歌の続きはだれも知らない。しかし、黙して従属することを選ばないのであれば、その場所がどこであれ、自らのうたを歌い始めねばならないのだ。 差異の強調や自己主張に基づいた表現に飼い馴らされた耳と心に、これらの音楽は、別の存在の仕方と配慮の作法を暗示しているように受け止められた。 |
||||||
 |
『海童道/海童道祖老師』 これはLPレコード(未CD化)。海童道祖わたづみどうその最後のレコード録音(1978)である。このレコードへの一般的な評価は(少なくとも直接耳にした範囲では)あまり芳しいものではない。 確かに、この録音では道祖のトレードマークともいえる人間業とは思えない強烈な吹き込みが抑えられているし、また、音程間をいつまでも不安定に揺れ続けているような場面も多い。そのため、「やはり老師も歳をとって力がなくなってしまった」という声が上がり(間章もそうした評価を下していた)、また本作の録音と同じ頃に国立劇場に出演した際の演奏──正しくは“海童道”では演奏とは言わずに「吹上」と言う──が似たような傾向であったこともネガティヴな見方を助長させたようである。 だが今年、道祖の高弟であったお二人から直接話を伺うという貴重な機会に恵まれて、晩年の老師の姿がだいぶ違って見えてきた。証言によれば、道祖は最晩年にいたるまで呼吸の強靭さを保っていたし、新たに音程間に潜む響きの探究も行なっていたようだ。その過程の一部が、本レコード録音や国立劇場出演の際に現れていたということも分かった。 本作で聴けるのは、障子越しに揺れる木々の影だとか、庭に舞い降り飛び交うスズメが地上に落とす影だとか、そういう間接的な事物の気配を表象する姿勢である。とはいえ、もとより道祖にとって最も大切なことは表現ではない。対象を直接的に「描く」ことは目指されず、むしろエネルギーが自ずと泡立ち「描き上がる」ミクロな場面に立ち会うことのほうが重要とされた(だから、音は二の次なのである)。したがって私が聴いた「影」というのも、情念の源泉となる固定した像ではなく、むしろ光と影のゆらめきそのものを体験したというべきなのかもしれない。 たとえば、モノに触れる手を直前で止め、そのわずかな隙間を保とうとするならば、手は緊張を強いられる。これが修行。やがて手はモノと離れていながら一体化し、エネルギーの渦が生まれてくる。これが自由。このレコードに記録された音からは、そうした渦の存在感を感じる。激しい渦ばかりか、穏やかで微かな渦や、静止した渦さえも、ここにはある。燃える薪が空気の加減で急にはぜるような、そうした外部のきっかけを拒まない「作為なき持続」との格闘とでもいおうか──。その生々しさは、体温さえ変えてしまうほどだ。 |
||||||
 |
『春の祭典──ストラヴィンスキーの音楽によるサイレント・ムーヴィー』 (DVD) 《春の祭典》の音楽にセリフのない映像を加えた作品。ヨーロッパでは、こうしたクラシック/現代音楽に後から映像を構成して作った作品が数多く存在する。本作とは関係ないが、欧州では放送局が文化活動として芸術制作に取り組むことも一般的で、放送劇(Hörspiel)という音楽作品ジャンルも確立されており、また実験的なジャズなども放送局の委嘱で作曲初演される機会が多い。 この作品はグロテスクな狂気で綴られた非常に衝撃的な内容で、聖なるもの、神が支配する世界観を背景にして、欲望、猜疑心(被害妄想)、復讐心、といった混沌に満ちた意識の暗黒と退廃が、冷徹な目で観察されている。次々とモンタージュされる場面は共感や暗示を排したソリッドな展開を見せ、分子化した人間存在を抉り出し、残酷に放り出す。本編38分(他にボーナス・マテリアル約90分収録)という時間以上の濃密な体験が残る。演奏はサー・サイモン・ラトルとベルリン・フィルによる新録音(2003年1月録音、PCMステレオ、ドルビー・デジタル5.1ch、DTS 5.1ch)。 「神」によってクッキーを焼くように造り出された三人の主人公──ノイローゼに陥った脳外科医、性的虐待を受けているニンフォマニアの女子学生、夫の死を嘆いて情緒不安定となった未亡人──が交錯しながら、映像はひたすら抑圧的に、不気味に、醒めた狂気を振りかざしながら突き進む。やがてブードゥー教とも関わりのある秘教「サンテリア」の天使が登場し、さまざまな宗教を溶け合わせた南海の島で、恐怖と不安を除去するための通過儀礼が執行される。 自意識が切り刻まれ精神が虐殺されていく無残な「生贄」状態に晒された現代人を象徴的に描いた力作であるが、ふつうの日本人には理解しづらい作品ではないかと思う。むしろ嫌悪感を抱く人のほうが圧倒的に多いだろう。これはヨーロッパ精神ならではの切実かつリアルな表現・表明であって、たとえば今年日本公演も行なわれた「武満徹マイ・ウェイ・オブ・ライフ」の演出家ペーター・ムスバッハ──ベルリン州立劇場支配人を務める彼は音楽の他に精神医学も修めており、以前ミュンヘンの精神病院に長期滞在した際に、そこで芸術の本質を考察した──の意図が、日本では生理的に受け入れられなかったことにも通ずる。このことは、いかにアメリカナイズされたといっても日本人の文化精神構造までもが完全に西欧化されていない証左とも言える。 監督のオリヴァー・ヘルマンは、本作完成直後の2003年9月に40歳の若さで逝去、これが遺作となった。制作にはサイモン・ラトル自身が深く関わったらしく、DVD内にもインタヴューで登場している。 |
||||||
 |
|
||||||