|
|
 |
|
|||
  |
『瞑響・壁画洞窟──旧石器時代のクロマニョン・サウンズ/土取利行』 The Sounds of Prehistoric Painted Cave Playing in the Cave of Cougnac, France Toshi Tsuchitori 土取利行の久々の新譜は、旧石器時代の壁画が残る南フランスの洞窟奥深くで奏でられた、太古の音楽世界との内的感応の記録。著書『壁画洞窟の音──旧石器時代・音楽の源流をゆく』(青土社)も同時に刊行。 25,000年前の人間がどんな音を奏で何を聴いていたのか。それを知るための記録は当然ながら何も残されていない。だが、闇に包まれた洞窟の奥深く、壁に残る壮麗な絵を前にして立ち、聖なる空間が巨大なひとつの楽器のごとく共鳴する衝撃的な音を体験した瞬間、土取利行はそこに音楽の誕生があったと直観し、確信する。原初の音の内実は時の隔たりを超えてわたしたちを裸形の存在へと引き戻す。 祖先から培われた智恵を忘れ葬り去ることで築かれていく文明の価値とは何なのか。自然や世界との絆の再構築へ向けた取り組み。音楽は、その実現のためのひとつの果敢な方法でありうる。
|
|||
 |
『Selk'nam
(Ona) Chants of Tierra del Fuego, Argentina』 土取利行の上記新譜および新著の刊行と併せて、古代日本三部作《銅鐸》、《サヌカイト》、《縄文鼓》もリマスターでの復刻(SHM-CD盤)が実現した2008年夏、各地で記念の古代音楽のレクチャーが開催された(東京では二日連続で馬喰町のART+EATと吉祥寺のサウンド・カフェ・ズミ)。ART+EATでは講演後ミニ・ライヴも行なわれ(■)、歌とも叫びともつかない「声」の拍動と共に紐を通した木の実が振られた瞬間、場内は一瞬で異次元空間へと変貌した。 翌日、その発声の原典が明かされた。DZUMIでのレクチャー開始前に流されたセルクナムの歌がそれだった。 近年まで旧石器時代の生活文化を留めていた南米フエゴ諸島のセルクナム族。このレコードに関しては、土取利行の著書『縄文の音』(青土社)でも触れられている。フォークウェイズ・レコーズによる貴重な録音。現在はスミソニアン博物館が音源を管理していて、ウェブサイトからダウンロード販売も行なわれ、希望者にはCD-Rのかたちで頒布している。(■) |
|||
 |
『郡上のうた』(■) 旧石器時代と言わずとも、日本ではほんの数十年前まで長く受け継がれてきたわらべ唄や仕事唄、民謡の数々が急速に姿を消してしまった。こどもたちの遊び方が変わり大人たちの労働(仕事)の内実が変質した果てに、唄だけが元のまま残るというはずもない。暮らしの変貌は文化の変貌でもある。信じて前へ進み続けた足がぬかるみに沈み込んで身動きがとれなくなり、進歩と利便性の限界の前で途方に暮れながらようやく気がつく。振り返ることなく切り捨ててきたもののあまりの多さに。 この二枚組CDは、岐阜県郡上八幡に移り住んだ土取利行と桃山晴衣が、地元で歌われていた民謡・仕事唄・わらべ唄を録音して記録した貴重なテープの存在を知り、そこから厳選して構成したもの。音楽とはなにか、うたとはなにかという問いへの大切な答えのひとつがここにある。 |
|||
 |
『現地保存会による岐阜・奥美濃 白鳥おどり』(■試聴/■) 郡上(ぐじょう)は民謡・民俗芸能の宝庫。このアルバムには白鳥町で踊り継がれてきた演目が収録されている(2007年7月16日 四日市大学スタジオでの録音)。三味線や太鼓の伴奏入りで、観賞用として録音されているためか、ゆったりとしたテンポの演奏だが、実際はもう少し早い。有名な郡上踊りと比較するとお囃子の趣が違っていて面白い。 2008年2月、初台の新国立劇場で行なわれた世界民俗芸能フェスティバル(文化庁主催・入場無料)では、「拝殿踊り」という楽器伴奏を一切伴わずに歌い踊られるかたちを見ることができた。こちらは急速調のリズムを特徴とし、輪になった踊り手達の履いている下駄が床を叩く音が生み出す眩惑的なパルスがすごい。そのうねりは険しい急流を走る水の姿のごとく、運動と静止がぴたりと重なって時間を忘れさせる。主役の歌い手は全体の輪の動きとは逆方向に動きながら、踊りを導いていく。 これほどの洗練とダイナミズムを誇る豊かな芸能が、明治時代の欧米化政策を受けて、明治7年に盆踊り禁止の通達を出されていたという史実。単眼的な勤勉さがもたらすいびつな情熱は、日本のネガティヴな部分だ。 |
|||
 |
『熊送り(イヨマンテ)──神と二風谷アイヌの語らい』(■試聴/■) アイヌ民族における最も神聖な儀礼が熊送りである。数年間飼育した仔熊を神の国へ返すためにあやめる。北海道では禁止通達が出されていたが、2007年に約50年ぶりに撤回された。動物保護団体からは今なお異論も出ているが、自然との共生のなかで神への祈りを儀礼化したアイヌの精神文化を尊重することでは反対派も同意見のはず。もちろん興味本位や観光目的での供犠の真似事は論外である。 町田宗鳳・著『縄文からアイヌへ──感覚的叡智の系譜』(せりか書房)は、人類のさまざまな宗教儀式においてなぜ犠牲が要請されたのかを解き明かしていく。その鍵は、人間と神との贈与の運動が儀礼として様式化される経緯のなかにあった。永続する生命感覚。すなわち、個々の命が小さな輪であり、その輪が連続して連なった中を糸のように走るものが、個を包摂して偏在する命の本体であるという認識。自然の前で謙虚であるしかない人間の切実な祈りが前提としてあり、そこに「供犠」が導入される宗教的な真理、本当の意味での「畏怖」と「崇高」の感情が生じる。これは知識以前に出会うべき智慧ではないか。 |
|||
 |
『音曼陀羅/石坂亥士』 2008年3月に甲府市の桜座で「土取利行ソロ・コンサート」があり、最後にゲストとして客席から招かれジャンベを叩いていたのが石坂亥士その人だった。群馬県桐生市を本拠地に、楽器、人、場所との魂の交感を注意深く探究する日々の活動は、ホームページとブログを通じて知ることができる。桜座でのライヴのことも記されている(■)。 石坂亥士 Official Website
"Dragontone" ■ 2008年夏に発表された本作では、神楽太鼓の倍音の渦が大気中に溶け込んだ緑の森となって、まさに龍(Dragon)の如く空間を攪拌し波立たせる。ここにはデジタルに置き換え可能なビートや拍節リズムは存在しない。心臓の鼓動を基盤として時空を斬り出していく雄渾な所作があるだけだ。自然が語りかける律動に耳をすまし、周囲の呼吸、気の流れに働きかけていく作法。それは石坂亥士の二人の師、土取利行とミルフォード・グレイヴスの音楽世界に連なる。 ミルフォード・グレイヴス Milford Graves が2000年に TZADIK からリリースしたアルバム《Stories》(TZ 7062)(■)。特殊な楽器セットでオーバーダビングなしで行なわれた即興演奏。「音楽以前」という言い方もあるだろうし、「音楽を超えた」と言っても構わないが、これこそ根源的な音楽とは言えまいか。音楽は聴き手に生命力と勇気を授ける呪術的な祝祭なのだ。 2008年10月4日(土)桐生の有鄰館で行なわれた土取利行と石坂亥士のパーカッション・ライヴ「螺旋のグルーブ」では、音の向こうに二人がこれまで各地を旅して出会った人々、その気配までもがゆらめき、弾み、会場全体が浮き上がって別世界へと通じる巨大なトンネルが姿を現わしていた。
|
|||
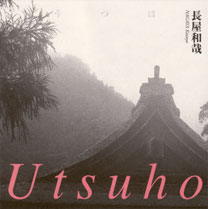 |
『うつほ/長屋和哉』 土取利行《縄文鼓》(2008)のジャケットを飾っている写真は、「縄文鼓プロジェクト」の準備から実現に至る過程を丹念に撮影した渡辺眸によるもの。東大全共闘をただ一人内側から撮影し、そのネガを封印から解いて出版した写真集が話題となったが(■)、アジアの異界を捉えた『天竺』、『西方神話』、さらには『猿年紀』、『てつがくのさる』といった写真集、この世ならざる蓮の姿を幻視した作品からは、時空を超越して永続する命の震動が静かに語りかけてくる。眸さんの写真を見ることは、here と there が交替する場所に立ち会う稀有な体験だ。 その渡辺眸さんから教えられたのがこのアルバム。聴いてみると、きらめく透明な金属系の音響がまばらな気泡のごとく空間を充たして漂っている。まるで太陽の光を浴びた静かな池をみつめながら、光のゆらぎや魚の影、小虫の動きを眺めているような風情。部屋の中に深山の聖地に立ち籠める霊気が広がる。 ここに掲載したジャケットは1999年の初回版。「うつほ」とは、『うつほ(宇津保)物語』の「うつほ」なのか、それとも高野山の僧侶が日常身につける法衣の名称「空衣(うつほ)」のことなのか。ブックレットには、「うつほとは、古木などにできる虚(うろ)のこと」とあり、続けて「うつほは、音霊にみちている」と記されている。だがその数行以外に解説めいたものは一切なく、使用楽器も書かれていない。タスキ裏の短い文章から、奈良県吉野郡川上村の由緒ある神社がダム造成のため水没することになり、本作はその聖なる場所に捧げるために録音されたのだと分かる。 その後しばらく品切れが続いたらしく、2006年に新装ジャケットで再プレスされた。そちらも購入したところ今度は解説文が付されており、作品成立の背景を詳しく知ることができた。神社が水没した後、たまったダムの水が山肌を崩して危険な状態となり、放流の後再び水底から神社の姿が現れたという話には、地神の明確な意志を感じるほかない。 |
|||
|
||||
 |
『むすびひめ 〜万葉に遊ぶ〜』 笙から立ち昇る音は不思議な光のようだ。直ぐ目の前で演奏されているのに、背骨の上方から、腰骨の周辺から、自分の眼底から放射されるように音が響いてくる。きっとその音が、神経や血液と共に身体を廻り、かたちを超えたかたちを示しているからだろう。 龍笛の音は、山脈を越え、河を渡り、緑のざわめきと星辰との対話を重ねて旅する風の記憶であろうか。強さはしなやかさの証であり、優しさは厳しさの揺籃を経ることで不思議な円みを帯びてゆく。 そうした光や風を天地自在にめぐらせるままに遊ばせようとするとき、雅楽の楽器を相手に作為や工夫を凝らすことはまったく似合わない。むしろ自分自身を空(ウツ)に保つ作法こそがどれほど豊かな世界を引き寄せることか。ウツはウツワ(器)となり、そこに宿り来る気配のウツロヒ(移ろい)をウツクシ(美しい)と感受した万葉の心を、「むすびひめ」の演奏会を聴きに行くたびにいつもおもう。日本の音楽はすべて言葉から生まれている。そして言葉以上のものへと超出していく。 |
|||
 |
『三善晃
合唱音楽の夕べ/藤井宏樹 樹の会』 2008年3月9日の杉並公会堂。作曲者・三善晃も、そこにいた。この2枚組ライヴCDを聴きながら、この日、客席で自分のなかに刻まれた特別な感覚に再び包まれる。音の向こうにある「思い」が波のように打ち寄せる。その波動が尊く、眩しい。 三善晃の合唱作品は非常に難しいが、難しいのは譜面ばかりではない。詩句の底に潜んでいる種々の感情や思いが一音ずつ汲み取られているため、そこへ降りていくための道筋が見つからないかぎり、本当の意味で歌うことの意味をつかむことができない。音楽を支える命、意識の震え。三善晃の作品はそうした本質の在り処を顕在化させる。 《五つの日本民謡》はこうした三善芸術の核心に触れた作品だが、Ensemble PVD による演奏は高度な表現を達成しており、この作品の本質的極致を伝えている。 |
|||
 |
『天籟地響/廣瀬量平
作品集』 廣瀬量平は日本・東洋の精神文化の古層に基盤を置き、西洋音楽のイディオムを介さない独自の芸術的達成を示した作曲家だった。2008年11月24日歿。78歳。京都市立芸術大学名誉教授。同大に日本伝統音楽研究センターを設立し、初代所長(2000−2004)、京都コンサートホール所長(2006以降)を歴任。 1930年函館生まれ。早くから邦楽器を使った作曲にも取り組み、LP『尺八1969』(芸術祭優秀賞)は現代邦楽の隆盛を導いた。1973年以降はアジア的作風を深めたが、民俗音楽の引用ではなく、また中世から江戸時代の「邦楽」のにおいを感じさせない、音楽の原初的エネルギーと瞑想的拡がりを実現した数々の名作を残した。吉田秀和が書いた評論「二つの道、廣瀬と武満」(1970)はいまこそ再び読まれるべきだろう(『吉田秀和全集第12巻』所収)。 このアルバムは平成元年の文化庁芸術作品賞を受賞したもので、収録されているのは、《天籟地響(てんらいちきょう)》(1976)、《トルソ──5つの楽器のための》(1963)、《渺(びょう)──尺八独奏のための》(1972)、《「みだれ」による変容──十七絃のための》(1980)、《魂ふり──長管尺八のための》(1982)の五作品。なかでも《天籟地響》(1976年度文化庁芸術祭優秀賞)には圧倒されるほかない。 縄文から弥生にかけての日本の「音」が秘めていた「霊力」を引き出す「作曲」の達成は、廣瀬量平の「創意」であると同時に、現代日本が失ってしまった自然の呪力との対話、彼岸と此岸を往還する精神世界への「遡及」でもあった。 廣瀬量平の音楽世界は今後さらに探究されていくことだろう。《天籟地響》の未曽有の音響世界を前に、小泉文夫や柴田南雄も思わず目を瞠ったという。 |
|||
 |
|
|||
|