|
|
|
||||
 |
『三善晃+谷川俊太郎
合唱作品集「木とともに 人とともに」』 このライヴ盤は当日客席で聴いた印象とあまりに違っていたので驚いた。座った席がよくなかったのか。CDのほうが全体のバランスが格段に良い。 これまで、最も「しつこく聴いた」曲のひとつは、三善晃さんが作曲・編曲したTVアニメ・ドラマ『赤毛のアン』のオープニング「きこえるかしら」。約4時間30分リピートで聴き続けたことがあり、ということは、一曲2分26秒だから連続111回ということになるようだが…。「きこえるかしら」が好きな人なら、本CD最後に収録されたアンコールで特別にピアノ伴奏つきで演奏された『木とともに
人とともに』はお薦めだ。また、思春期心身症の少年少女たちへの詩篇に作曲した『やわらかいいのち』では、不協和音の鋭い痛み、ウッドブロックのカタコトいう内面への呟きが心を捕らえる。原爆を主題にした『その日
─ August 6─』(2007)は、演奏する行為、聴く行為それ自体が、祈りと反省と覚悟をもたらす。 |
|||
 |
『神々のしらべ 日本の神様と音霊』 伶楽舎の定期公演で作品を聴いてから関心のある雅楽奏者・作曲家の東野珠実さんが参加していることで購入。他に、Ikuko、稲葉明徳、吉野裕司の各氏が参加している。元々このCDは『日本の神様カード』の著者である大野百合子さんの存在を中心に編まれたもののようだ。ちょうど神道の音に関わる仕事を進めていて、そうした関係の本を読んだりしていた時期だったので、このCDの背後に流れる神さびた雰囲気を素直に感じ取ることができた。CDの最後に、約20分間、自然音を交えての誘導瞑想のコーナーが収録されている。 |
|||
 |
『シルキー・アドヴェンチャー/山本邦山+佐藤允彦』 米国ツアーの合間に生まれた作品を、帰国後にスタジオ録音した珠玉のデュオ・アルバム。山本邦山さんのジャズ演奏は『銀界』こそが最高傑作だと思っていたが、本作を聴いてその認識は完全に覆された。これは日本の『レッド・ランタ』だ! |
|||
 |
『ゆめのよる/波多野睦美+高橋悠治』 主にフランス近代の歌曲をあつめたアルバム。揺れあい、揺られあう歌とピアノ、微光を発して明滅する意識のあわい。昨年度に耳にしたなかでも極上のCD。もったいなくて、あまり聴いていない。ブックレットに掲載された高橋悠治さんによる歌詞の日本語訳もすばらしい。 |
|||
 |
『琵琶法師の世界「平家物語」/今井勉』 800年以上の伝統をもつ平家琵琶語りだが、盲目の演奏者による口承の伝統はこの今井勉検校が最後のひとりとなった。このたび薦田治子先生のご尽力でまとまった録音が刊行されたのはまさに壮挙である。本作は昨年度の芸術祭レコード部門大賞を受賞。長く手元に置いておきたい大切なCDだ。ジャケット・デザインは、桃山晴衣さんのCDデザインも手掛けられた辻修平さんによるもの。銀の箔押しの「月」が特殊紙に映えて美しい。 |
|||
 |
『Peiwho/Arianna
Savall』 古楽演奏一家に生まれ、エスペリオン・ヴァンテアンでも活躍するアリアンナ・サヴァールだが、即興表現でも閃きに満ちた感覚を研ぎ澄ませており、また自作を中心とした創作活動も行なっている。本作のタイトルは、岡倉天心の『茶の本』の第五章「琴には琴の歌をうたわせよ」にも引用されている琴の名手・伯牙。「音楽が目指すものを楽器にゆだねるうちに、琴が自分なのか、自分が琴なのか、本当には分からなくなった」という挿話。ジャケットに写っているトリプル・ハープを中心とした透明感のある繊細な響きが流れ出る。ルーミー(メヴラーナ)の詩篇にも作曲しているが、このイスラム神秘主義を代表する人物については、わたしは昔からずっと気にかかっている。いつかきちんと向き合ってみたいものだ。 |
|||
 |
『タージ・マハル旅行団=ライヴ・イン・ストックホルム1971』 1971年の7月から9月にかけてストックホルム近代美術館で開催された「ユートピア&ヴィジョンズ 1871‐1981」に招待されたタージ・マハル旅行団 The Taj Mahal Travelers の演奏がCDで聴ける日が来るとは思わなかった。昨今相次いでいる貴重音源の復刻や初出盤のなかでも、これは特に酔わされたもののひとつ。このフェスティヴァルに参加するにあたっては、旅費の不足分等を補うために、当時多くのアーティストが支援のためのコンサートに関わった。 ストックホルムでの演奏後、タージ・マハル旅行団はインドのアグラのタージマハールを目指し、各国を演奏しながら旅を続けた。その模様は、大野松雄さんが提供した撮影機材とフィルムによって、撮影スタッフとメンバー自身の手で記録された。帰国後、それを大野さんが編集・構成して完成したのが映画『ザ・タージマハル・トラベラーズ――旅について――』である。 旅の終盤は撮影フィルムが盗まれてしまったため、後半はスチール写真のスライドや8ミリ撮影によるシーンが続く。編集後の映像試写を見ながらメンバーが語る声がぼそぼそとよく聞き取れない音で被さっているのも大野さんによる構成だ。日本帰国後の1972年7月、この映画のために真鶴岬の海岸で行なわれた彼らのパフォーマンスが冒頭に収録されている。大野さんによれば、この日は台風が近づいていたので波が高く、撮影が大変だったとのこと。大野さんは、この映画について次のように語っている。 「最初に草月で試写やったときに、面白い現象が起きた。あれは、1973年ぐらいです。あのね、20歳代前半と60歳過ぎ[の観客]にウケたんです。ようするにね、管理社会に組み込まれた連中は理解できない。ていうのは、なんにも説明がないんです。だから、その、説明してもらわないと、わからない人たちはだめなんです。ところが、20代前半ていうのは、ようするに好奇心でしょ。だから、おもしろいわけです。それから、60歳過ぎると、もう、説明なんてどうでもいいってなって。(笑)とくに、そういう映画を見にくるのはね。だから、瀧口[修造]さんなんかは、えらい褒めてくれました。」 辛うじてというか、奇跡的にというか、ともかく、偶然が重なって大野さんの手元に残ったフィルムは、褪色が進んでほぼ白黒映像のようになっていたが、カラーに補正した上で、上記のCDと同じタイミングでDVDがリリースされ甦った。こちらも素晴らしい内容だが、ただし、色補正で赤味が勝ってしまっていて、モニターで色調整する必要があるのが残念。オリジナル版の映画では登場する場面の時系列をわざと前後させていたが、このDVDを出すにあたって大野さんはそれを改め、全体の時間も短めに再編集している。 参考:当時タージ・マハル旅行団に同行して渡欧した方のエッセイ |
|||
 |
『日本の音風景100選 まるかじり』(本作の紹介と試聴 ■) 「日本の音風景100選」とは、1986年に環境庁が公募の上選定したもので、発表後すぐにビクターのスタッフが各地を廻って綿密な記録を残し、当時ビデオ・カセットに編集して発売されていた。その元になった録音素材を新たに編集し、音だけのかたちで今回初めて発売。2枚のCDに79分57秒ずつ(49トラックと51トラック)、たっぷりと収録された高品質フィールド・レコーディング・サウンド集である。付属解説書には、和文解説47p、English Liner notes(英文解説)37pを掲載。 環境音を聴く体験とは、その場所の眺めや空気の温度、風景全体の彩度や密度、たちこめる気配などを、視覚や触覚で体感するのではなく、すべて耳を通して思い描くことだとも言える。それは、ラジオドラマを聴く体験のように、実際にそこにいる以上に生々しい「現実体験(リアリティ)」に近づく手段ともなる。思えば、すべての日本の音楽の原点は、自然の音に耳をすますことにあった。 |
|||
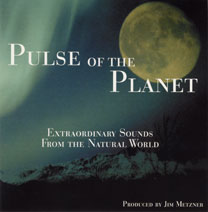 |
『Pulse of
the Planet - Extraordinary Sound From the Natural World(パルス・オブ・ザ・プラネット/驚異のサウンド)』 これは世界各地の美しく貴重な自然のサウンドを集めた素晴らしいCD。若尾久美さんのレーベル「Mesostics」から、丁寧な日本語の解説訳が付いた国内盤仕様で発売されている(■)。若尾さんはジョン・ケージの「ミュージサーカス」の演奏をオーガナイズして、その記録をビデオで発表されている。 収録音源; <生活の音> <動物王国> <自然の利用> <大地の音> <宇宙の音> このサイトで部分的な試聴ができる(■)。眼を閉じて、耳を五感全てに拡張してこうした響きを体験していると、やがて自分自身を超脱する空白(ブランク)に満ちた瞬間が何度も訪れる。時に虫となり、そよぐ草になり、風になり、光となり、闇となる。音は地球をとりまいて物質の波動を呼吸している昼と夜のシグナルであろう。 |
|||
 |
『VIVA! /La Düsseldorf
(ヴィヴァ!/ラ・デュッセルドルフ)』 これは自分が最初に買ったロックのレコードのひとつ。1980年のこと。30年前か。当時はジャーマン・エレクトロ・ミュージックの傑作と謳われていたが、シャウトするパンキッシュなヴォーカルとノイジーなギター、ドイツ民謡に基づくと思われる素朴な旋律と和声、きらきらした玩具のようなシンセ、子供がドラム缶を延々と叩くのにも似た無垢な情熱が迸るドラムスが織りなす、手作りのオンボロ自動車が蜿蜒(えんえん)と続く田舎道をかっとばすようなその音楽は、ともかくじつに人間的な温かみに溢れたものだった。 今年の正月休みに多田さんのニセコ日記にラ・デュッセルドルフが登場して、おっと思い、いつもはLPで聴いている『ヴィヴァ!』を初めてCDで聴いてみる気になった。さっそく調べると日本盤紙ジャケCDも出ていたが、2008年にアメリカで復刻されたCD盤があったので、店頭で確認してから後者を購入。そこに掲載されていた詳細なライナーノーツから、たくさんの興味深いことを初めて知った。たとえば、今は亡きクラウス・ディンガーが、クラウト・ロックの典型と言われることを厳しく拒んでいたとか、また彼のドラムの特徴である単一なビートについて、よく「ハンマー・ビート」という工場機械やテクノ特有の人工的で無機質なイメージで形容されるが、自分のドラムはその対極にあるもので、機械ではなく心臓の鼓動そのものだと語っていたことなどが紹介されている。 他にもA面3曲目のタイトルが、別れた彼女の名前アリエッタと本作にも参加しているニコラウス・ヴァン・リーンの名前の合成であることとか(それなら、曲名の読み方もこれまでと違ってくるか…)、白いオーヴァーオールを身に着けていた理由や、さまざまなエピソードが紹介されており、いつも自分の身近にあった好きな音楽の向こう側を知ることができたのはラッキーだった。 そしてB面全部を占める「CHA CHA 2000」で、人間性のポジティヴな変革(Cha Cha Cha Cha Change)を強く切実に呼びかけていた理由についても、納得できる記述があった。本作のリリース前、ドイツでは極左組織によるテロ事件が相次いでおり、それにどう対応するのかが、ロックを含めて、あらゆる創作現場にいる者にとって無視できない問題だったのだという。この曲で途中のピアノが静かに奏でる子守唄の場面も、そうした背景を知ると聴こえ方が変わってくる。歌詞の裏に込められた思いに灯がともる。 この2008年盤CDのライナーノーツ筆者は、本作『VIVA!』が1970年代を通過したヒッピーの理想主義の最終段階の答申だったという趣旨のことを述べている。時代へのアンチテーゼではなく。したがって、クラウス・ディンガーは「ノイ!」を含めパンクのオリジンと一般に言われるが、その判断はサウンドの外面だけに注目した間違ったもので本質はそうではないのだ、と、このライナー筆者は断ずる。なるほどと思った。 A面4曲目は森の中で鳥の声をフィールド・レコーディングしただけのトラック。クラウス・ディンガーのつくり出す音楽は、どれも本当にあきれるほど単純で、先にドイツ民謡と記したが、短い定型をくりかえすわらべ唄といったほうが近い。芸術性とは無縁だし、作曲・演奏技術も貧しい。けれどもいつも明るく、どこまでも果てしなく続く青空のように肯定的だ。おおらかで、建設的な意思と姿勢に貫かれ、袋小路の焦燥をユーモアと共に提示するフィーリング。そこにはひとかけらの気取りのポーズもなければ、屈折したルサンチマンやよそよそしさとも無縁である。基本となる生活が聴こえてくる音楽。そこがいい。
|
|||
|