|
|
|
| 2009年は、中・東欧とかスラヴとかバルカンの音楽が好きな人間には、チェコからイジー・スチヴィーン(JIŘÍ STIVÍN ■)、ブルガリアからテオドシー・スパソフという珍しい来訪があってなかなかごきげんな年だった。スチヴィーン来日は3月だった。演奏ツアーのためにきたのではなく、チェコ・センター主催のイジー・スリーヴァ風刺画展の前祝いパーティに出るためだった。スチヴィーンとスリーヴァは長年の親友とのことだった。当然、演奏もあるだろうという情報を知人の赤塚若樹氏からいただいたが、私は残念ながら仕事を都合できなかった。チェコ・ジャズ史に燦然と輝く巨星スチヴィーン。フルート、サックス各種の名手で、ジャズの他にもフルートとリコーダーによるバロック音楽、中世音楽の演奏家としても高名な人だが、「ジャズもうまいクラシックの人」とか、「クラシックもうまいジャズの人」という形容では間に合わないような、器の大きい音楽家だ。なのに演奏が聴けないなんて、よほど日頃の行いが悪いんだなぁ。そんな反省が天に届いたのか、後日お会いすることができた。 |
||||
| 第一印象、想像したように巨匠の風格が漂う人物だった。トンカツに興味があるということで、紀伊国屋書店の地下にあるW店に落ち着いた。すぐ音楽の話になり、おしゃべりな青年に豹変した。笛の話になると、ジャケットの内ポケットに手をやり、すっと笛を2本とりだしたかと思ったら両手で2本同時に吹き始め、和音をつくり、しかも鼻息でもかっこよく鳴らすだけじゃないよ、胸にかけていた小さいペンダントを口にあてて、吹き鳴らすのだった。2本吹きもペンダント吹きも余興ではかたづけられない立派な古楽的ジャズ演奏で、新宿のトンカツ屋から中世のプラハの街角へトリップしたような気がしたくらいだった。周囲のテーブルのお客さんたちにも非常にウケた。 |
||||

|
その後、秋にチェコ・センターで「チェコ・ジャズ入門」という講演をさせていただくことになったこともあって、かつて親しんだディスクを聴きなおしたり、新しく入手して聞いたりした。講演では時間もかぎられているので、スチヴィーンをフィーチュアした。下準備で特別リピートして楽しんだものを挙げると、スチヴィーンでは、『Výlety(excursion)』=1=、『Status
Quo Vadis』=2=、『Inspiration by Folklore』=3=だ。『Výlety(excursion)』、『Status Quo Vadis』は、ともに想像的な中世音楽旅行と言ってしまおう。『Inspiration by Folklore』は中欧の詩情・哀愁に満ちたバラード「ドナウ」の決定的名演で名高いフォーク音楽集だ。 |
|||
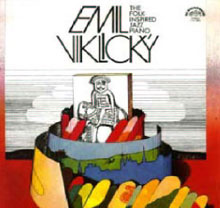 |
次いで、ピアニストのエミル・ヴィクリツキー(■)もそこそこフィーチュアした。最近の「シンフォニエッタ第3楽章」もいいが、私にとってエミル・ヴィクリツキーはまず『フォーク音楽を源泉とするジャズ・ピアノ』=4=収録の「課外授業」だ。モラヴィア・リリシズムの結晶だ。 |
|||
 |
スチヴィーン、ヴィクリツキーは、それぞれ、キャリアの初期に
SHQ というグループに在籍した時期があるので、SHQ のリーダーの故カレル・ヴェレブニーを最後に紹介することにした。SHQ で1曲あげろといわれたら、「神経症の犬と歩けば」あたりになる。LP『sh jazz quintet』=5=に入っている。 |
|||
 |
チェコにはジャズファンの人口比が高いのだろうか。クラウス大統領は大統領府のあるプラハ城の部屋を活用して、定期的に「お城でジャズ」と銘打ったジャズ・コンサートを主催するほどのジャズファンだ。上記のスチヴィーンの65歳誕生日記念コンサートがそこで催され、CDになっている(『Koncert na hrade』=6=)。現在の駐日チェコ大使もかなりのジャズファンだそうだ。チェコ・センター責任者はそれ以上だそうだ。ぜひスチヴィーンの公演とかチェコ・ジャズ祭なんかを企画していただきたいと懇願した。 |
|||
| ブルガリアのテオドシー・スパソフはブルーノート東京に出演した(11月)。スパソフが演奏する楽器はカヴァルという名の伝統的な笛で、トルコのネイの演奏と似たような構えで吹奏する。カヴァルの音はネイや尺八を思い出させる。ファーマーズ・マーケットのメンバーとして来日したブルガリアのサックス奏者トリフォン・トリフォノフが少しこのカヴァルを吹いたので、耳覚えがあることと思う。スパソフはブルガリア出身のピアニスト、ミルチョ・レヴィエフの感動の名盤として知られる『Gourbet Mohabet』に参加しているので、度胆を抜かれた人も少なくないはずだ。 ブルーノートでは文字通り超絶技巧も交えながら、バルカン調の音楽の数々を披露した。その中で私が格別に感銘を受けた曲が1曲ある。スパソフが曲名を何とアナウンスしたか聞き取れなかったが、聞き覚えのある非定型的な3ビートのパターンとトルコ風味も嗅ぎとれるバルカン調のメロディが始まって、すぐ、ああ、あの曲と思った。バルカン音楽のファンにはお馴染みの、アルバニア民謡として知られるラヴ・ソング「丘の上のあなた、丘の上のわたし」だ。1960年代のフィールド録音を入れたディスクのライナーノーツでは、バルカン全土にこのメロディの変化形が聴かれるというような記述がある。この曲をギリシアのサヴィーナ・ヤナトウがほぼ忠実に再現して歌い『地中海の歌』に収録したとき、その記述も引用されていた。だからスパソフがこの曲を演奏してもなんの違和感もない。 |
||||
 |
同じブルガリアでは、若いピアニストのディミタル・ボドゥロフがトリオ編成でこの曲の変型らしき曲を『Stamps from Bulgaria 2008』=7=に入れたときは、ブルガリアのトラッドとクレジットしていた。マケドニアのギタリストのヴラトコ・ステファノフスキも『Vlatko Stefanovski Trio』でやはりこの曲の変型らしき曲を入れてマケドノニアのトラッドとクレジットしていたこともうなずける。当のスパソフがこの曲のヴァリエーションを入れたCDはあるのでしょうか。入れていればどんな曲名なのか、ご存じの方はぜひご教示いただきたいと願っている。例のフィールド録音やヤナトウにいちゃもんをつけるつもりではないが、この兄弟旋律のルーツは本当にアルバニアなのだろうかと、気になってしかたがないのだ。 |
|||
 |
フランスのリヨンから、想像的民俗音楽探究協会(ARFI)のプロジェクトのひとつであるフェスタン・ドレイユ(耳の宴会)の来日公演(日仏学院「フランス:食の祭典」6月)をみれたのもラッキーだった。クリスチャン・ロレ(drums)、ジャン・メリュー(トランペット)、ギィ・ヴィラール(サックス)という
ARFI 創設期からのメンバー3人が結成したトリオ「エ・ギジェクリ」が、90年代に着手したのがフェスタン・ドレイユだ。これは演奏光景を見なければ絶対に満喫できない。だって、その場で腕の立つシェフが2人コラボして料理するのと同時進行して演奏があり、最後は料理を客席にふるまうというプロジェクトだ。日仏では、映像アーティスト氏も絡んで、楽しい映像を背景に投影していた。耳の宴会どころか、耳と目と鼻とお腹の宴会だ。クリスチアン・ロレがボールと撹拌器をもって立ち、シュワシュワシュワシュワとリズムを刻んで演奏開始。ARFI のグループに共通するのは、遊び心と、緻密な計算・演出を両立させるジャズだが、フェスタン・ドレイユもその点例外ではない。俗な言い方に過ぎるだろうけど、みんなマルチな芸達者だ。CD『Festin d'Oreille』=8=でも、グザヴィエ・ガルシア(エレクトロ・アコースティック)、ジャン・フランソワ・バエス(アコーディオン)も参加して彩りを増やす他、耳だけでも楽しめるような配慮が多々なされている内容なので、お薦めしたい。 |
|||
| トランペットのジャン・メリューが宴会幹事然としたシャベリで仕切る司会で進行するなか、硬軟おりまぜた演奏がシェフをあおる。ドン・チェリーとアルバート・アイラーの2管みたいなシークエンスもあった。実際サックスのギィ・ヴィラールはいろんなディスクからもかなりアイラーの音楽を愛していることがうかがわれる(たとえば、ヴィラール/アイラー・カルテット名義の『One Day…』)。クリスチャン・ロレは今回が2度目の来日だった。最初は、90年代前半に今は亡きモーリス・メルルと2人でやってきた。それはなんと、スタレヴィッチの著名な実写アニメとの共演で、ロレとメルルは画面に即して演奏した。2人は演奏に入る前、日本語と親し気なみぶりそぶりで、子供達にわかるようにたくみに映画のことを説明した。そう、児童向けのコンサートだったのだ。演奏が終わり、片づけをはじめる前の2人をつかまえてあいさつした。あのとき、来日情報を教えてくれたのは、惜しくも昨年亡くなられた大里俊晴氏だった。大里さんのおかげで私は
ARFI に関心を持つことになった。大里さんがパリから帰国した頃、私は「季刊ジャズ批評」というジャズ専門誌に勤務していた。伝説の江古田のアパートにたずね、いろいろお話をうかがい、レコードを貸していただき、連載も頼んだ。その「フレンチ・フリージャズ・レトロスペクティヴ」に書いてくださった
ARFI や、フランソワ・テュスクや、NATO の回は、フランスのジャズをそれまでの自分とは別の角度から見直すための大切な指南役となった。 |
||||
| ポーランド出身の映画監督イェジ・スコリモフスキとクシシュトフ・コメダの関係ということで短文を書かせていただく機会があって、手持ちのコメダのディスクをいろいろ聞きなおした時期もあった。60年代のポーランドでもジャズが使われた映画は少なくなかった。短編、長篇、ドキュメンタリー、アニメをあわせれば、コメダは70本ほど担当している。ひっぱりだこだったのだ。 |
||||
 |
コメダを映画にひっぱりこんだのはロマン・ポランスキ監督ということもあり、コメダの映画音楽というとポランスキの『水の中のナイフ』が決定版としてまず上がるのはそれはそれでいいと思う。スコリモフスキはつい最近、新作『アンナと過ごした4日間』が話題になったばかりだが、ジャズファンにとってスコリモフスキといえば60年代の『バリエラ』『出発』だ。その音楽もコメダが手がけている。『バリエラ』はコメダお得意の珠玉の哀愁メロディの宝庫。『出発』はクラッシュするのかとヒヤヒヤさせられながらカッコいいジャズに浸ることができる。いま『バリエラ』はどのCDで入手しやすいかよくわからないが、私がもっているのは全23巻の「The
Complete Recordings of Krzysztof Komeda」シリーズの『vol.11 Film Music』=9=だ。『出発』の日本盤は音が悪い。今回初めて『手を挙げろ!』をみた。4つ目に描かれた巨大なスターリンの肖像画が出てくることがいけなかったらしくて、すぐ上映禁止になった映画だ。象徴的なシーンが多い映画で、当時の東欧の国に関心のある人にはたまらない描き方が頻出する。冒頭の方の、白粉を塗り片手を挙げての群舞のシーンの音楽にコメダの魅力を再確認した。ポランスキの『ローズマリーの赤ちゃん』のあと、コメダは不慮の交通事故で意識不明になり、数カ月ももちこたえたが、結局亡くなってしまった。予定されていてキャンセルになったコメダの映画音楽の仕事のひとつがスコリモフスキの新作だった。スコリモフスキはジャズ・ドラマーだった時期があり、コメダのグループについてまわった時期があるという。いわゆるボーヤだったのかどうか、もしスコリモフスキに会うご予定のある方は、そこのところ訊ねてみてもらえませんか? |
|||
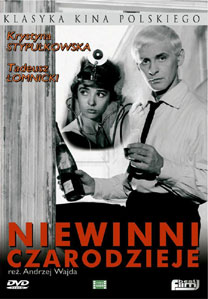 |
コメダ好きには、ワイダ監督の『夜の終わりに』=10=は何回もみても飽きない映画だ。スコリモフスキが脚本に参加するだけでなく、情けないボクサー役で出演しているし、ポランスキも役者としてコメダのジャズバンド仲間のベース奏者役を演じているし、コメダは音楽だけでなく役者でも参加している。これがちょっとキザな感じの演出なので、どうも語り伝えられているコメダのイメージとずれているけど、ま、どうってことないか。 |
|||
| コメダの曲をカヴァーしたポーランドの若手ジャズ・ミュージシャンはいろいろいるが、ずばり『KOMEDA』というタイトルでアルバムを出したマルチン・ヴァシレフスキたちのトリオが筆頭に上がるだろう。年が変わり、今年つい最近(2010年2月)、レシェク・モジュジェルの渋谷(トウキョウ・メイン・ダイニング)でのソロ・ピアノ・コンサートでは、頭の方で「スヴァンテティック」を実に切れ味よく弾き切っていてうっとりさせられた。2010年もなにかとごきげんな年になりそうな予感がする。 |