|
|
| ここ数年、年末年始にかけて『ジャズ批評』誌から年間ベスト盤選出の依頼があるだけでなく、この1年で耳にした音楽がどんなものだったのかを個人的に振り返るために、何となく習慣化しているベスト10選考。しかし、いずれかのメディア上で、たまさか私が良いと思ったとか、よく聴いたとかいうCDを紹介することに、如何なる意味があるのか、毎度ながら釈然としないままである。とは言え、今回は特にどこかに発表するというつもりもなく、年始の挨拶時に某所で原田正夫氏に紹介したところ、望外の好評を得たことに気を良くして、このような事態に至ったわけである。 |
||||
| 2009年は2010年に引き続き、突出した作品=何かしら新しい表現領域や新しい聴取感覚/演奏感覚を、言葉として明確化できないまでも朧気ながらでもイメージさせるような「傑作」は見当たらなかったというのが正直なところ。一方、10(テン)年代の初年と言うことで、00(ゼロ)年代の総括的な印象の佳作は多く見出せる。また、00年代は30代半ば〜40代くらいを中心世代として、それに続くべき若い世代の姿が見えにくい状況が続いていたが、20代〜30代前半くらいの若手が先行世代とは違った傾向を見せ始めていることも確認できた。それは、モダン回帰ではなく、プレモダンの、プリミティヴな感覚を全面に推し出そうとしているものと言えそうだ。そうした動きの一方、「触覚性」に自覚的なサウンド作りや、同時並行する異なるタイム感覚がそれぞれに生起するようなアンサンブルが広く定着してきており、自分の関心領域との重なり具合に確信を深めたりなぞもしている。 |
||||
 |
1) Chris Lightcap's Bigmouth : Deluxe (Clean Feed Records CF 174 CD) Chris Cheek - tenor sax (right); Tony Malaby - tenor sax (left); Craig Taborn - wurlitzer electric piano, piano; Chris Lightcap - bass; Gerald Cleaver - drums; Andrew D'Angelo - alto sax. recorded at Brooklyn Recording, Brooklyn on October 8-9, 2008. 2000年の“Lay-up”(Fresh
Sound New Talent FSNT-074)、2002年の“Bigmouth”(Fresh
Sound New Talent FSNT-148)に続く、実に8年ぶりのリーダー作。2008年6月にレコーディングの予定を聞いて<■>から2年余り、個人的には長らく待たされたリリースだった。“Lay-up”がスタティックなリズム隊に乗ったアドリブの応酬をじっくり聴かせるタイプだったとすれば、“Bigmouth”はダイナミックなリズムに対照的なサックスが絡み合うファナティックなムードといった具合にやや異なる性格は持っているものの、前2作は簡単に言うと“変形ハード・バップ”とでも呼ぶべき範疇だった。特に後者は、ストレートにラテン的な熱情をぶつけるトニー・マラビーと、それをはぐらかすように素っ頓狂なフレーズを繰り出すビル・マクヘンリーとの対比が大きな魅力を生んでいる。 |
|||
 |
2) Gerald Cleaver Uncle June : Be It As I See It (Fresh Sound New Talent FSNT-375) Andrew Bishop - flute, soprano & bass clarinets, soprano & tenor saxes; Tony Malaby - soprano & tenor saxes; Craig Taborn - piano, keyboards; Mat Maneri - viola; Drew Gress - bass; Gerald Cleaver - drums, percussion, voice; Ryan MacStaller - electric guitar; Andy Taub - banjo; Jean Carla Rodea - voice; John Cleaver - voice. recorded at Scrootable Labs, Brooklyn on October 21, 2009. こちらも2001年の“Adjust”(Fresh
Sound New Talent FSNT-112)、2008年の“Gerald Cleaver's Detroit” (Fresh Sound New Talent FSNT-301)に続く3作目。上記同様、2008年6月には録音予定を耳にしており、待望久しいリリースであった。3作とも異なるバンド名義および編成で、90年代の閉塞感を引き摺ったダウンタウン・シーンを如実に反映した“Adjust”(名盤!)、変わりゆく故郷デトロイトへの郷愁を表現したためか、一転してストレート・アヘッド回帰とも受け取れる“Gerald Cleaver's Detroit”と、音楽自体も相当趣きの違うものを提示してきただけに、今回はどうなっているのか、興味と期待は膨らむばかりだった。 |
|||
 |
3) Ches Smith and These Arches : Finally out of My Hands (Skirl Records SKIRL 014) Tony Malaby - tenor sax; Andrea Parkins - accordion, organ, electronics; Mary Halvorson - electric guitar; Ches Smith - drums. recorded at Trout Recording, Brooklyn. (P)2010. ドラマーのリーダー作、およびトニー・マラビー参加繋がりで選出。ティム・バーンやマーク・リーボウ、メアリー・ハルヴァーソンのバンドで頭角を現してきたチェス・スミスのソロ以外では初となるリーダー作。 |
|||
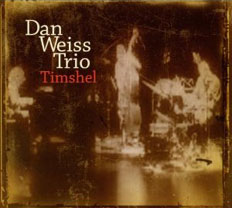 |
4) Dan Weiss Trio : Timshel (Sunnyside Communications SSC 1242) Jacob Sacks - piano; Thomas Morgan - bass; Dan Weiss - drums, voice. recorded at Acoustic Sound, Brooklyn in September 2008. 次もドラマー繋がり。チェス・スミスに先行して売れっ子となったダン・ワイスは、2009年のニューヨーク・タイムズWeb版において「いま聴かれるべき5人のドラマー」<■>の一人に挙げられている(残りの4人は、マーカス・ギルモア、ケンドリック・スコット、タイション・ソーリー、ジャスティン・フォークナー)。マンハッタン音楽学校での正規教育の一方で、タブラ奏者、サミール・チャテジーから10年以上に亘って指導を受けている。そのためとは限らないが、本作を聴く限り、彼の音楽はドラム奏法に留まらず、作曲面においてもインド音楽〜タブラ奏法の強い影響下にあると言えそうだ。 |
|||
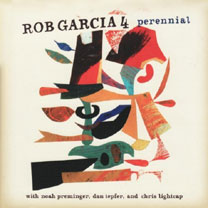 |
5) Rob Garcia 4 : Perennial (BJU Records BJUR 012) Noah Preminger - tenor sax; Dan Tepfer - piano; Chris Lightcap - bass; Rob Garcia - drums. recorded at Benny’s Wash N’ Dry, Brooklyn on August 10-11, 2009. ドラマー繋がり最後は、一転してワン・ホーン・クォーテットによるオーソドックスな4ビート・ジャズ。1曲目の「Joe-Pye
Weed」の心弾むような軽快なメロディに耳が釘付けとなる。ロブ・ガルシアはなかなかのテクニシャンだが、注目すべきはテナーとピアノ。ノア・プレミンガーは2009年にいきなりリーダー作でデビュー。米国の新人賞を総ナメにしたそれは、正直言ってあまり感心できる出来とは言い難いものだったが、ウォーン・マーシュ〜マーク・ターナーに連なるスタイルの持ち主であることは覗えた。一方、ダン・テプファーは、リー・コニッツのお気に入り。パリ生まれのアメリカ人である彼は、パリ音楽院パウル・デュカス校、エディンバラ大学を経て、ボストン、ニュー・イングランド音楽院という一風変わった経歴を持つ。 |
|||
 |
6) Jacob Anderskov : Agnostic Revelations (ILK Music ILK 163 CD) Chris Speed - tenor sax, clarinet; Jacob Anderskov - piano; Michael Formanek - bass; Gerald Cleaver - drums. recorded at Brooklyn Recording, Brooklyn on June 27, 2009. お次は、ワン・ホーン・クォーテット繋がりだが、その肌触りはグッとクール。イルク・ミュージックは、デンマークの18人のミュージシャンによって設立されたレーベル。ジャズに留まらず、エレクトロニカ系も含む幅広い音楽性が特徴。やや食傷気味のノルウェイ勢に比べて、デンマーク勢は一味違った個性があり、ポール・モティアン・バンドに在籍し、NY勢との交流が多いヤコブ・ブロを中心として目下のところ目が離せない存在だ。リーダーのヤコブ・アンデルシュコフのキャリアは全く知らないのだが、NYダウンタウンの重鎮達とのインタープレイに違和感はない。 |
|||
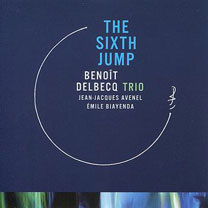 |
7) Benoit Delbecq Trio : The Sixth Jump (Songlines Recordings SGL 1585-2) Benoit Delbecq - piano; Jean-Jacques Avenel - bass; Emile Biayenda - drums, percussion; Steve Arguelles - remix. recorded at La Muse en Circuit, Arfortville, Paris on July 12-13, 2008. 次はヨーロッパのピアニスト繋がり。同時発売のソロ作は未聴。ジャン=ジャック・アヴネルの重心の低いベースとエミール・ビアイェンダ(コンゴ出身)のアフリカン・ビートを軸にしたレイド・バックしたグルーヴに、硬質なピアノとECMサウンドとは一味違うヌメっとした深い残響のコントラスト。盟友、スティーヴ・アーギュエルスによる各メンバーのソロ演奏のリミックスも良いアクセントになっている。 |
|||
 |
8) Hugo Carvalhais : Nebulosa (Clean Feed Records CF 201 CD) Gabriel Pinto - piano, synthesizer; Hugo Carvalhais - bass, electronics; Mario Costa - drums; Tim Berne - alto sax. recorded at Quinta da Musica, Porto on June 10-13, 2009 and Namouche Studio , Lisbon on August 7, 2009. 次はヨーロッパのエレクトロニクス/音響的な要素を含むジャズ繋がり。ここのところ異常なリリース・ペースでその活況ぶりが際立つポルトガルのレーベル、クリーン・フィード。今もNYと並行してスペインのミュージシャンを積極的にリリースしているフレッシュ・サウンド・ニュー・タレント同様、NY勢とほぼ半々の比率でポルトガルのジャズ・シーンを紹介している。だが、情報のほとんどないポルトガル・ジャズになかなか触手が伸びないのも事実。これは、ティム・バーンの参加から聴いてみる気になったが、バーン抜きの演奏も侮れないものだった。 |
|||
 |
9) Ben Monder / Bill McHenry : Bloom (Sunnyside Communications SSC 1247) Bill McHenry - tenor sax; Ben Monder - electric guitar. recorded on February 7, 2000. 次は、エレクトロニクス/音響系つながり。とは言え、ギターとテナー・サックス以外の「楽器」は使われていない。10年前の録音とは俄に信じられないくらい「いま」の空気が収録されている。基本的には気心の知れたコンビによるインティメイトなジャズ的インタープレイなのだが、まるでエレクトロ〜アンビエントのような時間と空間が生み出されていくトラックが圧巻。 |
|||
 |
10) Michael Pisaro : A Wave and Waves (Cathnor Recordings Cath 009) Michael Pisaro - composition; Greg Stuart - percussion. (C)2006/2007 最後は、ジャズとは縁もゆかりもない現代音楽。座間裕子氏のブログにおける熱意溢れる紹介<■>と、実際に対面しての試聴を通じて、その魅力に開眼。座間氏はパーカッション演奏の多重録音とフィールド・レコーディングをクロス・フェードさせた“July Mountain”(Engraved
Glass eg.p05)をベストに挙げたが、私はフィールド・レコーディングを含まないこちらのほうに軍配を上げる。皮膚を多種多様なテクスチュアで触れられ、撫でられ続けるような時間の、瞬間=永遠と思われるような持続。これは果たして音楽なのか? そうだとしたら音楽とは一体何なのか? 人間の、個人の、主体の、あるいは集団の、関係性の、表現なのか? そうではない音楽があってはいけないのか? いけなくないのだとしたら、その音楽は何のために、どのようにしてあるのか? 私にはまだ答えの見出せない問いが次から次へと湧き上がってくるのだが、そんなことより、この音の持続が与えてくれる快楽、至福の時間に身を浸すことに抗する術が見出せなくなっているのも確か。 |