|
|
|
||||
|
||||
 |
1. Farmers by Nature: Out of This World's Distortions (AUM Fidelity 067) Craig Taborn - piano; William
Parker - bass; Gerald Cleaver - drums. 2009年のデビュー作“Farmers by Nature”(AUM Fidelity AUM 053)は The Stone でのライヴ録音だったのだが、サウンド・クォリティの低さと相俟って聴き応えに欠ける内容だった。スタジオ録音の今作はサウンド・クォリティが飛躍的に高まっただけでなく、演奏自体の密度が別次元のものになっている。まるでカヴァー・アートのイメージに沿うかのように、くっきりと屹立する三人の音像。しかし、演奏する場、空間は共有されているにも関わらず、各々の演奏の流れ、時間がピッタリと重ね合わされることはない。同じ空気を吸っていながら、同じ時間、同じストーリーを生きていない、とでも言ったら良いだろうか。そして、それ(=非同期)があるべき演奏の仕方、生き方だと主張しているかのようでもある。特に、セッションの直前に亡くなったフレッド・アンダーソンに献げられた冒頭曲にそれは顕著だ。 カヴァー・アートと音楽の内容を安易に結びつけることは慎むべきだが、水墨画のようなモノクロームの荒涼とした風景は遠景を欠き、遠近感や時間の流れから画面に生じるストーリーを拒絶しているように見える。それは、即興演奏とは即ち自己表現、あるいは自分語り=ストーリーである、という近代的なジャズ観からの決別のようでもある。自分自身が発する音は厳密にコントロールしながら、あるところから先は他者や、その時と場所に委ねているとでも言うような。彼等の集団による表現とは、今、此処で自分たちが共に在る、その「共在」のあり方が如何なるものなのかを示すもののように感じられる。それは決して諦念などではなく、ある種の希望に違いない。「Out of This World’s Distortions Grow Aspens and Other
Beautiful Things」というヴィジョンはそこから生まれてくるものなのだから。いずれにしても、敢えて「同期しないこと」から生じる張り詰めた空気の持続、その強度は群を抜いていると思う。 |
|||
 |
2. Tony Malaby's Novela: Arrangements by Kris Davis (Clean Feed CF 232) Ralph Alessi - trumpet; Ben
Gerstein - trombone; Dan Peck - tuba; Tony Malaby -
soprano & tenor saxes; Michael Attias - alto sax;
Joachim Badenhorst - bass clarinet; Andrew Hadro -
baritone sax; Kris Davis - piano, conduct; John
Hollenbeck - drums, percussion. 上記作にも参加するウィリアム・パーカーとの Tamarindo や、ジョン・ホレンベックを擁する Cello Trio、Apparitions での活動を通じて、所謂ジャズ的な音楽からの逸脱度を増してきたトニー・マラビー。これらの作品での彼のコンポジションはワン・フレーズのみの即興のきっかけ、素材に過ぎないようなものが多く、それを比較的大編成のホーン・アンサンブルにアレンジするというのはかなり無理筋だと思うのだが、クリス・デイヴィスはその難題に見事な回答を与えている。 こちらも一聴して意図的にピッタリとは合わせないラフなアンサンブル。だが、単純に同期していないと言うよりも、フォトショップで異なるテクスチュアの画像をレイヤーで重ねることによって新たな質感や存在感を持つ画像を創り出すことが可能になるように、バラバラな植物が繁茂し、重なり合っていくことで、森という一段上のレイヤーの統一体、別種の生き物が産み出されてくるような印象を受けるサウンドになっている。これもカヴァー・アートとのイメージの連動性が強い。その反面、各人のソロは従来のジャズ的な演奏に留まっているのが残念。 |
|||
 |
3. Steve Coleman and Five Elements: The Mancy of Sound (Pi Recordings PI 38) Jonathan Finlayson - trumpet; Tim
Albright - trombone; Steve Coleman - alto sax; Thomas
Morgan - bass; Tyshawn Sorey - drums; Marcus Gilmore -
drums; Ramon Garcia Perez - percussion, vocals; Jen Shyu
- vocals. 前作“Harvesting Semblances and Affinities”(PI Recordings PI 33)と全く同じメンバーで、同一セッションのものとほぼ1年後の演奏とが収録されている。前作は少し意地の悪い言い方をすると、若手メンバーの複雑極まりないリズム・アプローチに付いて行くことができていないスティーヴ・コールマンの「ドキュメント」になっていたのだが、今作は若手の持つ高度な技量をコールマン自身の音楽を構成するパーツとして使いこなすことに見事に成功した「作品」と言えるだろう。 全体としては4拍子基調なのだが、二人のドラマーは異なるタイミングで変則的なアクセントを置くことで、常に異なるリズム・フィギュアが同時進行するポリリズミックな下部構造を用意する。一方、ジェン・シュウのヴォーカルとホーン・アンサンブルもまた別々のメロディやハーモニーを同時並行で展開させる。聴き方によっては各々がてんでばらばらに演奏しているようでありながら、全体として一つのまとまりを感じさせる音楽。ここにも上記2作とは別の形で「同期/非同期」の問題系がある。それは、まるで別々の機会に別々の構造に基づいて設計された各パートを、サウンドのレイヤーとして重ね合わせるデジタル時代のエレクトロニック・ミュージックのような考え方に則っているように思える。また別の見方をすれば、異なるリズム構造を同時進行させるアフリカ音楽の新たな解釈・再構築のようでもある。 構造的な話に終始してしまいそうだが、00年代前半までは只管暗く抽象的な旋律に傾斜していたのに対し、主にシュウによって歌われるメロディ・ラインがどこのものとも特定できない民俗音楽風(ラモン・ガルシア・ペレスのヴォーカルがはっきりとアフロ=キューバン的なものであることに注意)でありながら、非常にわかりやすく耳に入ってくる上、どこかポップに響くのも新機軸と言えそうだ。いずれにしても、コールマンは只では起きないというか、失敗作の経験を自家薬籠中のものとして、新たな方法論を打ち立ててしまったところは流石である。 |
|||
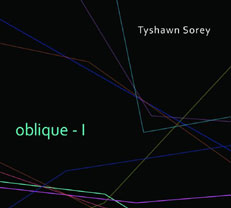 |
4. Tyshawn Sorey: Oblique - I (Pi Recordings PI 40) Loren Stillman - alto sax; John
Escreet - piano, rhodes electric piano, wurlitzer
electric piano; Todd Neufeld -electric & acoustic
guitars; Chris Tordini - bass; Tyshawn Sorey - drums. 上記作のドラマーの一人、タイション・ソーリーの3作目。過去の2作、“That/Not”(Firehouse 12 Records FH12-04-02-005)、“Koan”(482 Music 482-1069)は、如何に音を出さずに、その間合いだけで音楽を構築することが可能かという試みのようだったが(前者には40分以上に及ぶモートン・フェルドマン風のピアノ独奏まである)、今作では一転して最先端ドラマーとしての力量を全開にしている。とは言え、どんなに激しく叩き捲り、吹き捲っても決して従来のフリー・ジャズのように燃焼 → 爆発といった経路を辿ることがない。徹底して低い温度感のまま、インテンポとルバートを交錯させつつ、リズムを複雑に絡ませ合い、互いの出す音を注意深く探索し続ける。その意味では、上記3作で窺えた「同期/非同期」「レイヤー構造」の問題系と重なるものも感じられる。 また、ロレン・スティルマン以外は20代半ばの若手を登用していることもポイント。特にベースのクリス・トルディーニは、2011年になって急激に名前を目にする機会が増えてきており、勝手ながらポスト・トマス・モーガン的な存在と位置づけている逸材。 |
|||
 |
5. Okkyung Lee: Noisy Love Songs [for George Dyer] (Tzadik Oracles TZ 7724) Peter Evans - trumpet; Craig Taborn
- piano; Cornelius Dufallo - violin; Okkyung Lee - cello;
Christopher Tordini - bass; Satoshi Takeishi -
percussion, electronics; Ikue Mori - electronics; John
Hollenbeck - percussion. ジェン・シュウは中国系だったが、こちらのイ・オッキョンは韓国系。近年のNYは、カリブ系やインド=パキスタン系に続いてアジア系の(そして、女性の!)台頭が顕著になってきている。クリス・トルディーニやジョン・ホレンベックを含むダウンタウン・シーンの豪華メンバーが集結しているが、即興演奏よりもコンポジションとサウンド・デザインの比重が高い。 冒頭、蕭条と降りしきる雨音(を模したもの)の中から感情を抑えた短いフレーズを繰り返すチェロが浮かび上がり、ピアノの短音が訥々と呟くように間をおいて散りばめられる。主旋律を奏でるトランペットは、いつしか小鳥の囀りとなり、ヴァイオリンの倍音と融け合っていく。楽器演奏による楽音と、特殊奏法による非楽音、そしてサンプリング・ノイズやフィールド・レコーディングによる自然音の境界が曖昧になり、やがてそうした区別が無意味なものに思えてくる瞬間。モノクロームの幽玄な風景のサウンド・トラックを想起させる、強い映像喚起力を持った音楽でもある。 |
|||
 |
6. The Clarinets: Keep on Going Like This (Skirl Records SKIRL 013) Chris Speed - clarinet; Oscar
Noriega - clarinet, bass clarinet; Anthony Burr - bass
clarinet. 近年のクラリネット復権を象徴する一枚。クリス・スピードが主宰する
Skirl Records の第一弾となった前作“The Clarinets”(SKIRL
001)ではまだ、同種管楽器アンサンブルのバリエーションという位置づけがしっくり来るような「音楽的」な側面が強かった。本作は、カリフォルニア大学サン・ディエゴ校でのライヴで、教室等の比較的エア・ヴォリュームの大きな空間で録音されたことが窺える。クラリネットは、閉管構造によって偶数次倍音をほとんど含まない矩形波を発するため、サックス等のように倍音のコントロールで奏者による個性を出すことが難しい楽器である。ここでは、その「匿名的な」サウンドを互いの肌を触れ合わせるように響き合わせつつ、各々が逐次息遣いを変化させることによって全体の響き方を制御していく。時には強烈なモデュレーションさえ発生する。三人一組で互いに手を取り合ってバランスを取り続ける綱渡りのような演奏。これは制御/非制御の間で揺らぎ続ける演奏であり、同期/非同期のもう一つの問題系であるとも言える。 |
|||
 |
7. Bill McHenry: Ghosts of the Sun (Sunnyside Communications SSC 1422) Bill McHenry - tenor sax; Ben
Monder - electric guitar; Reid Anderson - bass; Paul
Motian - drums. 2011年は、ポール・モティアンというNYジャズの象徴を失ったことでも忘れられない年となった。ペトラ・ヘイデンのヴォーカルをフィーチュアした“The Windmills Of Your Mind”(Winter & Winter 910 182-2)、リー・コニッツ/ブラッド・メルダウ/チャーリー・ヘイデンとの“Live at Birdland”(ECM Records ECM 2162)の2枚のリリースがあったが、それらは2010年の“Lost
In A Dream”(ECM Records ECM
2128)以降続いている、まるで自らの死に際を意識しているかのような抑制された演奏に終始している。本作は彼の逝去を受けてリリースが決定されたもので、2007年リリースの“Roses”(Sunnyside
Records SSC 1167)のセッションの拾遺集なのだが、とてもそうとは思えない素晴らしい内容になっている。演奏の流れを押したり引いたり、浮かしたり沈めたり、止めたり急発進させたりすることで、音楽の表情を大きく変化させるモティアン・メソッドの特質が良く顕れている。いや、それどころか「同期/非同期」「レイヤー構造」の問題系の嚆矢が実はモティアンではなかったか、とすら思わせられる。 |
|||
 |
8. Jeremy Udden's Plainville: If The Past Seems So Bright (Sunnyside Communications SSC 1277) Jeremy Udden - alto & soprano
saxes clarinet; Pete Rende - rhodes electric piano, pump
organ, prophet synthesizer, wurlitzer electric piano;
Brandon Seabrook - banjo, electric guitar, 12-string
guitar; Eivind Opsvik - bass; R.J. Miller - drums; Nathan
Blehar - nylon-string guitar, guitar, voice; Will Graefe
- steel-string acoustic guitar; Justin Keller - voice. 近年のアルト・サックス奏者は、ヒステリックなまでに吹き捲るタイプが多いのだが、ジェレミー・ユーディーンはポール・デズモンドを想起させるような、ふわっとした柔らかな音色と流麗なフレージングが魅力だ。音楽自体は、アメリカーナ〜フォーク・ロックの範疇に納まってしまうものと言ってしまえばその通りなのだが、「バンジョー界のスティーヴ・ヴァイ」と呼ばれるブランドン・シーブルックが持ち込む不穏な空気が、パストラルな心地好さに微妙な綻びを生じさせる。 「ジャズというよりロックに近いよね」と言うインタヴュワーに対し、「このバンドはリハーサルを一切しない、自然発生的に演奏することこそがジャズだと思う」と返していたのが印象的。最早、演奏スタイルだけでジャズ/非ジャズを区別するのは無意味なことが常識になりつつある。 |
|||
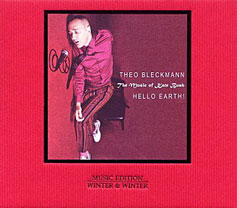 |
9. Theo Bleckmann: Hello Earth! - The Music of Kate Bush (Winter & Winter 910 183-2) Theo Bleckmann - vocals, live
electronic voice processing; Henry Hey - piano, prepared
harpsichord, rhodes electric piano, toy piano, caxixi;
Caleb Burhans - electric five string violin, electric
guitar; Skuli Sverrisson - electric bass; John Hollenbeck
- drums, percussion, crotales, glockenspiel. 個人的にはケイト・ブッシュは然程好きなミュージシャンではないのだが、ケイト・ブッシュ曲集だと意識しなくても十二分に楽しめる作品。演劇的と言って良い程に過度にドラマチックな彼女の歌唱に比べて、ティオ・ブレックマンは抑制の利いたやや中性的な唱法だし、コーラスで加わるメンバーたちは完全に只のおっさんの声だ。個性的なメンバーが揃っているが、胴鳴り感の希薄な非常に乾いた軽いドラム・サウンドと同時演奏する多彩なパーカッションで、楽曲毎の骨組みと色彩感を決定付けるジョン・ホレンベックの存在感が際立つ。また、ジョージ・マイケルのツアー・バンド等、ジャズ以外の領域での活躍が目立つヘンリー・ヘイのセンスも随所で光っている。 |
|||
 |
10. the HIATUS: A World of Pandemonium (Iron Gear Records FLCF-4406) 細美武士 - vocals, electric
& acoustic guitars, electric piano, programming;
masasucks - electric & acoustic guitars; ウエノコウジ
- electric bass, acoustic bass guitar;
柏倉隆史 - drums,
percussion, electric & acoustic guitars, programming;
堀江博久 - piano, rhodes
electric piano, pianorgan, solina, synthesizer,
accordion, vibraphone, glockenspiel, mandolin,
percussion; Jamie Blake - vocals. 最後は、NYジャズとは何の関係もない日本のロック・バンド。これを耳にしたのは12月に入ってからなのだが、すっかり2011年ヘヴィ・ローテイションNo.1 の座に定着してしまった。当初は、取り立てて衝撃的な内容だとか、新しい世界を開拓したとか、そういう類のものではなく、古今東西のロックと、エレクトロニカ等の周辺ジャンルを非常にバランス良くすっきりまとめたものという印象だった。歌詞のほうは、やや抽象的ではあるものの、震災以降のヘヴィでシリアスな認識や感情を吐露するものになっている(細美武士自身は明確に否定しているが、作者の意図はさして重要ではない)にも関わらず、全体としてはポジティヴで明るく軽快なサウンドになっていて、兎に角聴いていて非常に気持ち良い。細美武士のちょっと子供っぽくも感じられる甘い声と、感傷的な節回しにもアゲられるし。それは、00年代の閉塞感、鬱なムードにはもう飽き飽きしていたからかもしれない。 だが、ずっと聴いているうちに、これは単に気持ち良いだけではなく、何かとても画期的な音楽なのではないかと思うようになってきた(そう、Ellegarden “Eleven Fire Crackers”(Dynamord/Zealot ZEDY-2017)とは訳が違うのだ)。非常に多種多様な音楽が、「ミクスチュア」ではなく、「レイヤード」された音楽。完全に混ぜ合わせ、溶け合わされて、元の素材が分離できない状態になっているのではなく、重ね合わされたレイヤーを透かし見れば紛れもない統一体を成しているにも関わらず、一つひとつのレイヤーを分離していくことも可能な状態が保たれているように感じられる。 随所で奇数拍子が導入されているだけでなく、ドラムスは常に変則的な位置にアクセントを置き、メトリック・モデュレーションや、走ったりモタったりしたノリを意識的に持ち込むことで、ロックの定型的なビートとは異質なリズム感覚を与える。一方、ベースは曲想には関係なく、一貫してディストーションを利かせ、まるでクリス・スクワイアのようだったり、パンクのようだったり。それに対して、左右に分かれた2本のアクースティック・ギターは、それぞれ別々のアルペジオを奏で、フレーズを交錯させることは寧ろ少ない。背景では、打ち込みのデジタル・サウンドがギクシャクとしたパターンを刻み、フィードバック・ノイズやドローンが鳴り響く。8曲目の“Shimmer”にはホーン+ストリング・アンサンブルが加えられているのだが、普通のポップスの伴奏的なブラスに対し、激しく飛翔するフルートは伴奏の範疇を逸脱している、といった具合に...。 ここにも「同期/非同期」「レイヤー構造」の問題系の変奏を見出すことが可能である。そして、従来のジャンルで分断された聴取経験の貧しさ、不毛さが痛感される。聴かれるべき音楽と聴きたいリスナーを結びつける、もっと適切で有効な理路が、どこか別に存在するはずなのだ。 |