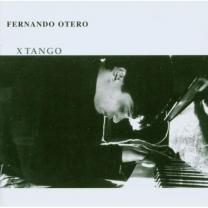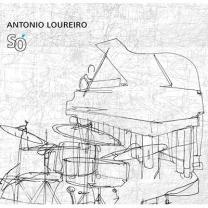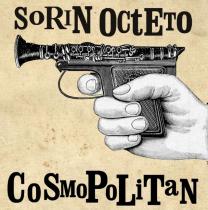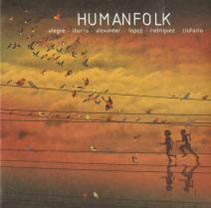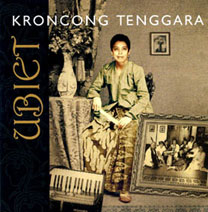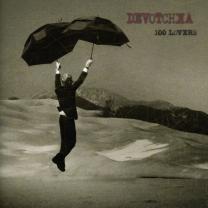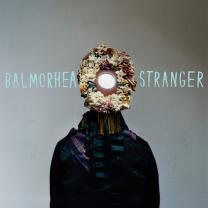| |
|
|
Nifty Serve の音楽系フォーラムのどこかで多田さんと知り合って、かれこれ20年近く経ちます。
この10年余り子育て中心の生活で、コンサートにもイヴェントにも参ずることなく、ネット上で独り
Dig の日々。実世間のほうに思い切り疎くなってしまいました。昨年
Facebook で多田さんに再会して以来、そのズレっぷりを面白がっていただいているのかなぁ…と思いつつ。
|
|
| |
|
|
今回は Facebook の縁ということで、ログを斜め読みしつつ10曲拾い上げてみました。
アルバム単位ではなく、楽曲本意+映像中心のセレクトになっております。便宜的にカヴァー・アートを添付しましたが、当該楽曲が収録されていない場合があります。ご了承下さい。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
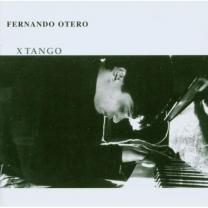 |
|
1. Lombard Twins &
Fernando Otero - Sublevados ■
ブエノス・アイレス生まれ、ブルックリンを拠点に活動する作曲家。
1994年に地元アルゼンチンで発表したデビュー作冒頭を飾った代表曲の、新たな魅力を引き出す意外な共演。かのデビュー作の1997年再発米国盤を見つけたのは、先日閉店を発表した高田馬場駅前のムトウ楽器であったな…。
2012年新作(未入手)のプロモーション映像はこちら。
■
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
2. LASZLO - Bohemian
Groove - Live Studio Performance ■
音のみを聴いていた段階では、この演奏風景(■)はまず思い浮かばない。
なるほど単なるプログラミング音楽だったら、そんなに惹かれなかったかもしれない。むしろ生演奏版のほうがスピード感があるというのが驚きだ。マン→マシーンとマシーン→マンは限りなく接近し、最終的には等価となる。初音ミクと
Purfume の関係にも似ている。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
3. Sasakure.UK -
Jack-the-Ripper ■
初音ミクブームに乗ってブレイクした作者の、ヴォーカロイド以前の作品。
待望の音盤化だったから、いわゆる「同人CD」を扱う店を訪れるのも喜んで(苦笑)。しかしそのすぐ後にリリースされた生演奏版(■/■)
はもうお腹いっぱい。決定的なナニカの欠如は先の
LASZLO と比べるまでもなく、いまだスルーしたままだ。
初音ミクをフィーチャーした代表曲 ■
|
|
| |
|
|
|
|
| |
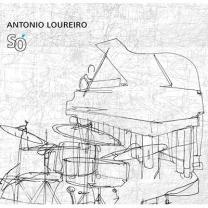 |
|
4. Antonio Loureiro -
Luz da Terra ■
RAMO(■)
のメンバーだとようやく気付いたのが夏頃の話。
ソロ・デビュー作の評判がひととおりネット上を駆け巡った後だから遅すぎだ。反省。出るひとは出るべくして出てくるとはいうけれど、ブラジルは逞しいな。同時代の先端を切り拓きつつ伝統も忘れない。手間暇かけて音を育てる心の豊かさがある。こういう音楽が日本で話題になっているだけでも救いと思いたい。
RAMOからもうひとりハフェエル・マルチニのソロ・デビュー作(■)や、女性ヴォーカルと組んだバンド、qUEbRApEdRA(■)も素晴らしかった。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
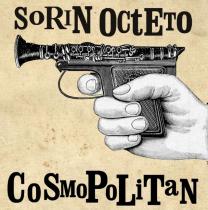 |
|
5. SORIN OCTETO - Otra
(tonta) cancion de amor ■
先のアントニオ・ロウレイロらミナス新世代と共鳴するストイックな音
エレクトロニカ以降とでも言えば良いのか、聴覚の分解能が一段階上がってる感。ニコラス・ソリン(■)の才気はあふれんばかりで、映画音楽のスコアから、4人組ロック・バンドのギター&ヴォーカルまで多種多彩に活躍する。ドラムスはアストル・ピアソラの孫ダニエル・“ピピ”・ピアソラ。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
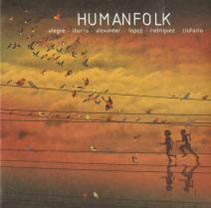 |
|
6. HUMAN FOLK - Para Sa
Tao ■
フィリピンのいわばスーパー・セッション的プロジェクト。
ジャズ+フォーク+プログレ+アヴァン+クラブ系の交配が、これほど優しくおおらかなサウンドに結実しようとは。またメンバーそれぞれの普段の活動とは全く違う側面を知れたのも大きな収穫だった。
Jonny Alegre ■
Cynthia Alexander ■
Abby Clutario ■
Malek Lopez ■
Susie Ibbara ■
Roberto Juan Rodriguez ■
|
|
| |
|
|
|
|
| |
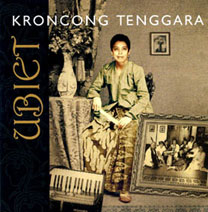 |
|
7. Ubiet - Gambang
Semarang ■
入手したのは一昨年だった気もするが東南アジアの流れでご容赦くだされ。
植民地文化が育んだ混血音楽という特性を活かしつつ、肌触りはあくまでポップに。随所に織り込まれたさりげない仕掛けも刺激的な、幻惑的ノスタルジーに彩られたクロンチョン室内楽。幸福感あふれる音にほっこり。
Ubiet と右端 Dian HP がかつて在籍した SPLASH ■
左端 Riza Arshad 率いる
SIMAKDIALOG ■
|
|
| |
|
|
|
|
| |
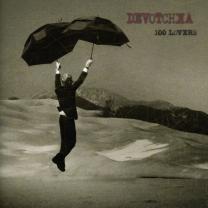 |
|
8. DEVOTCHKA- The
Clockwise Witness ■
どこまでも想像をかき立てられる音たち。
バーレスクのハコバン仕込みという芸達者ぶりに加え、歌声とそのポップ・センスは不思議に英国産バンドのようにも感じる。かつてのライ・クーダーがゆるゆると地表を漂いながら何かを待つ音楽だとするなら、こちらは空を舞ってでも追いかける感じ。しばらく米国音楽界に漂っていた黄昏れた雰囲気は、ここにはもうない。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
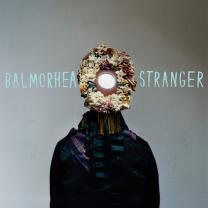 |
|
9. BARMORHEA - Live at
The Modern ■
良い意味で浮世離れした音。
なるほどアメリカ合衆国とは大いなる辺境なのだった。テキサス州のはずれ人口500人にも満たぬ小さな町から現れ、荒野に囲まれたリゾート地バルモレイ(なぜかそう読むそうだ)の名を戴く。本作からエレクトリック・ギターに持ち替え、ヴィブラフォンやスティールパン、シンセなどを大幅に導入し新生面を強く感じさせた。先のディヴォーチカとも共通する、これは光の音楽だ。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
10. The MOMMYHEADS -
Vulnerable Boy ■
美しいメロディに豊かな和音、風変わりなリズム…好物3拍子がすべて詰まっている。
そしてなによりもこの「声」だ。かみさん曰く、歌声の中毒性はモリッシーと共通するそうだ。あちらがずっと上がりっぱなしなら、こちらは下がるところに言いようのない魅力を感じるんだと。なるほど。
零細インディ・レーベルを転々と渡り歩き、晴れてメジャー契約を果たすも束の間。無理解なプロデュースを強いられたり、メンバー間の意見の相違だったりであえなく解散。後に発表された中心人物2人のソロ・アルバムは、どちらも相方の不在が際立つ悲しい仕上りだった。オリジナル・ドラマーの葬儀に参集したことがきっかけで、2007年より約10年ぶりに活動再開。熱心なファンに招かれ北欧ツアーを行うなど根強い支持もあって、解散前よりずっと充実した活動を伺い知ることができる。
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
番外 Nikolai Kapustin -
Toccatina op 40 no 3 piano, drums and bass ■
近年人気のウクライナ生まれの作曲家。その作品を勝手にアレンジしたもの。
日本のバンド MOUSE ON THE
KEYS のヴァージョン(■)は、なんだかもっさりとしたリズムが残念だったけど、こちらはよりストレート。アイディアこそありきたりながら、クラシック畑にはない解釈が新鮮。指先がよく分かるのもミソ。
作曲者本人の演奏は別曲だけどこちら(■)。

|
|
| |
|
|
|
|