|
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
 |
1. V.A. / Wandelweiser und So Weiter (another timbre) Wandelweiser 楽派の音楽と「ポスト・リダクショニスト」インプロヴィゼーションの結びつけという本作における
another timbre レーベルの主催者
Simon Reynell の問題提起は、事態の核心を鮮やかにとらえている。それを「あらかじめ記譜された作曲作品」と即興演奏の融合ととらえては、かえって問題を矮小化してしまうことになる(付属のブックレットに収録された座談会には、ややそうした傾向とこれに起因する防御の構えが見受けられる)。Wandelweiser 楽派の作曲にも見られるテクストによる指定が、音を個別に規定せず、演奏の一定の持続が生み出すべき状態/事態を指し示すならば、演奏者にまず求められるのは絶え間ない現在位置の測定であり、同時に現況(それは楽器・空間・沈黙・他の演奏者等との多様な関係性を内包する)の評価であり、さらには進むべき方向の判断であるだろう。指示に従うとはこの果てしない問い直しのプロセスを生きることであって |
|||
 |
2. Jakob Ullmann / Fremde Zeit - Addendum (Edition RZ) 匂い」は音と異なり、波動により空間を伝播するわけではなく、ミクロな物質粒子が嗅覚粘膜に届かなければ生じることのない、より間接的な体験であるわけだが、それでも匂いを感じた気がして振り返ると、遅れてその思い浮かんだ人物が部屋に入ってきたり、雨が降り出す前に感じる匂いがある。ここに収められているのはそうした音よりも遠い匂いにほかならない。気配の音楽。 |
|||

|
3. V.A. / John Cage Shock vol.1-3 ジョン・ケージ生誕百年かつ初来日五十年記念の発掘リリース。ケージやデヴィッド・チュードアたちによる、この凄まじいばかりの音の強度に身体をさらすことなく、またそうした体験を生々しく受け止めることなく、ただ「4分33秒」や『サイレンス』について、言葉に言葉を接続するだけの講釈を垂れるのはもう終わりにしよう。それともそれは「ショック」を癒すために必要な記憶の書き換え作業なのだろうか。 |
|||
 |
4. Gunter Baby Sommer / Songs for Kommeno (Intakt) 深い想いを噛み締めながら、遠い距離と時間をゆるゆると渡っていくような冒頭曲の演奏から一気に引き込まれる。
Gunter Sommer と Floros Floridis については二人が組んだトリオの演奏もレヴューで採りあげており、充実した活動ぶりが知れる。ギリシャ音楽の豊穣さを再発見できる1枚。すっと線を一本引くだけで、飛行機雲を眺める時の空っぽな哀しさを浮かび上がらせる希代のメロディスト
Floridis の露出が増えたのはうれしい限り。 |
|||
 |
5. Henry Thredgill Zooid / Tomorrow Sunny/The Ravelry.Spp (Pi Recording) ジャズ・フィールドのミュージシャンの中で、長期にわたり眼を離さないで来た数少ない一人。慣用表現として「音楽を編む」という言い方があるが、本作で繰り広げられているのは、まさに「いまここで音楽を編み上げる」ことである。編み手の傍らで編み棒の動きを見詰めていると、その機械的な反復に編み目がつくりだす模様の変化を見失ってしまうが、ここでも各演奏者のサウンドの明滅や移動に視線を合わせると、グループの編み上げているサウンドの模様が見えなくなってしまうところがある。意識のフォーカスをゆるめて、グループのサウンドの推移に向こうに個々のメンバーの動きを透かし見ること。 |
|||
 |
6. Charlotte Hug, Frederic Blondy / Bouquet (Emmanem) 音色や響きを主に取り扱うエレクトロ・アコースティックなインプロヴィゼーションへの傾向が広まる中で、ピアノ奏者たちは
Magda Mayas や Sophie Agnel のようにプリペアドや内部奏法に活路を見出し、あるいは
John Tilbury のように単音を磨き上げ、その深淵を覗き込む。そこで音は速度と鋭敏さを増しながら、加速度的に身体の重みを脱ぎ捨てた薄く脆いものとなっていく。ここで
Frederic Blondy は内部奏法を駆使しながらも、放たれた音がたちまちのうちに響きへと気化してしまうことを許さず、音の身体の厚み/重みを手放そうとしない。そのことはヴィオラの多弦弾きと声を行き違わせる
Charlotte Hug にも当てはまる。John Butcher の変貌とともに新たな予兆が感じられる。 |
|||
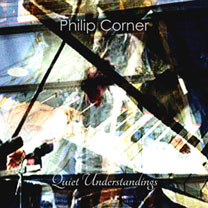 |
7. Philip Corner / Quiet Understanding (Quiet World) 彼はフルクサスの文脈で語られることが多いようだが、パフォーマンス/ハプニング作家ととらえてしまうと、彼の耳の視線の素晴らしい強度を見逃してしまうことになる。ここでもピアノに対する蹂躙ぶりよりも、そこから引き出される苦悶の震えから片時も眼を離すことなく凝視し続ける、冷徹なまでに鋭い眼差しに耳の焦点を当てて聴いてもらいたい。 |
|||
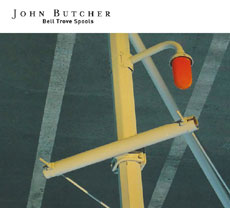 |
8. John Butcher / Bell Trove Spools (Northern Spy) オーヴァートーンやフィードバックを自在に操って、いつもながら精緻なポリフォニーを構築しながら、ここには血の滴るような生身の「肉」がみっちりと詰まっている。以前のワイヤー・モデル/ホログラム的な手を差し伸べると通り抜けてしまうような「希薄さ」(それは決して録音のせいではなく、彼のサウンドの質によるものだ)は少しも感じられない。彼にとっても飛躍を記録した記念すべき作品となるだろう。 |
|||
 |
9. Great Waitress / Lucid (Splitrec) エレクトロ・アコースティックな響きの流動に身を委ねながら、なお、ピアノ、アコーディオン、クラリネットのそれぞれの演奏は、その硬質な輪郭を溶解させてしまうことがない。それゆえにこそどこまでも曇りなく張り詰めた、透明で鋭敏な舞踏のための空間が開ける。距離を置いてゆっくりと微細な動きを続ける三者の間に、幾つもの放電の線が走る。 |
|||
 |
10. Anthea Caddy, Thembi Soddell / Host (room40) 漆黒の空間がねじ曲がり破れ目が走って、そこからまぶしい光が射し込み、それに眼が慣れると逆光の中にチェロのシルエットが浮かび上がる。チェロの一弓が空気を切り裂き、環境音に充満した空間は反転してチェロの響きを押しつぶしにかかる。響きと広がりが一体となってメタモルフォーゼを繰り広げる空間のドラマ。 |
|||
 |
11. 300 Basses / Sei Ritornelli (Potlatch) 3台のアコーディオンが繰り広げる極限的音響劇。空気の流れとリード及びこれに付随する各部の振動を取り扱いながら、管楽器のようには声/息との回路を持たない「手」の楽器に鋭く焦点を絞り込むことにより、サウンドへの意識はさらに深く研ぎ澄まされる。持続音の内部に開ける粒立ち、表面の微細なささくれ、気流の衝突と蛇行。一見平静な息遣いの水面下では乱流が渦を巻き、水草がはためいている。Jonas Kocher、Alfredo
Costa Monteiro の2人は特に要注目。 |
|||
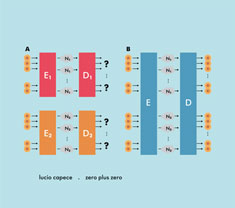 |
12. Lucio Capece / Zero Plus Zero (Potlatch) 顕微鏡下に初めてとらえられるようなミクロな震え、多様な振動の重なり合いが、吹いているサクソフォンの管を弓で弾いたり、ベルに紙筒やオブジェを突っ込むという極端にローテクな方法で生み出されていることは、演奏の様子を撮影した動画をみるまでわからなかった。だがその響きの重層性の美しさは、それを身体の運動に還元/帰着させたとたんきれいさっぱり消え失せてしまう種類のものだ。あるいはデュオにおいても、共演者との間合いや応答関係にたやすく覆い隠されてしまう。彼の本質をえぐり出した
Potlatch レーベルの慧眼と勇気に拍手を。 |
|||
 |
13. 不失者 / まぶしい いたずらな祈り (Heartfast) グループのサウンドを「いまここ」で編み上げていく手つきに
Henry Thredgill との共通性を感じながら、アンサンブルの疎密緩急の幅は不失者の方が絶望的に大きく、さらにヴォーカルの存在が両者を決定的に分かってしまう。絶叫に向かわず、過剰な情感を込めず、声/言葉をぽいと一見無造作に放り出すような歌い方は、語や文章の連なりを残しながら、ふと引き伸ばされる間合いや演奏とのズレを介して曖昧に崩され、宙に吊られる。演劇レヴューで採りあげたARICA『ネエアンタ』の語りのように、始末し難い存在としてただゴロンとそこにある。その点で何よりもヴォーカリスト灰野の作品ととらえたい。 |
|||
 |
14. Satomomagae / Awa (Satomimagae) 自主制作による女性SSWの第1作。基本的にはギターの弾き語りだが、背景にたなびくキーボード、物音やSEの挿入もよく考えられており必要にして充分。何よりも旋律の移ろいが声に落とす陰影の具合が素晴らしい。優れたモノクロ映画を見ているような気分になる。メロディとサウンドそして声の三者が取り結ぶ関係性の魅力を言い当てるのは難しい。以前にレヴューした際には英国フォークの翳りの深さと馨しさを例に引いたのだが、より近い参照項としては『扉の冬』の吉田美奈子だろうか。だが実際に聴き比べるとリズム・セクションの有無の差はあるし、Satomimagae の方がうつむき加減の声の陰影はより濃いのだが。声/うたが心情の運び手に堕してしまわず、自分の足で立っている感じが似ているのだろうか。2012年新人賞は彼女に贈りたい。 |
|||
 |
15. 紫絃会 / 春鶯囀一具 (日本伝統文化振興財団) もともと雅楽については、学校の授業で誰しも聴かされた「越天楽」等以外では、武満徹『秋庭歌一具』しか聴いたことがなく、それさえも「武満の音楽」の一環として接していたに過ぎないことをまずは告白しておこう。それが日本伝統文化振興財団のスタッフ・ブログで熱く紹介されていた本作(1973年録音の2012年再発)を聴いて、遅ればせながら雅楽の魅力に目覚め、他にもCDを聴いたり、コンサートに行ったりした。フィールドレコーディング/サウンドスケープ作品を聴き込んだことが、雅楽を聴く耳を養ったようにも思われる。しかし、やはり本作のスケールの大きさ、響きの豊かさ/強さは別格。油滴天目の茶碗のように、景色が宇宙を映し出す趣がある。 |
|||
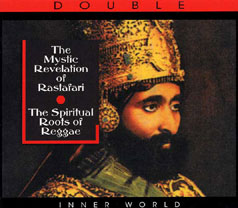 |
16. The Mystic Revelation of Rastafari / The Spiritual Roots of Reggae (Retro) レゲエという音楽ジャンルにはこれまでほとんど関心がなく素通りしてきたのだが、本作はまるで別物。ナイヤビンギというのだそうだが、雅楽にもつながりそうな目の詰まり引き締まった太鼓の音色や朗唱の声の響きをはじめ、古代儀式風の威厳をたたえた格調の高さに打たれる。「プリミティヴ」というややこしく扱いにくい、しかし魅惑的な概念については、改めて考えてみたい。 |
|||
 |
17. Guyun Y Su Grupo / Canta Elisa Portal (Ahora) 「フィーリン」という音楽ジャンルの存在自体、本作で初めて知ったのだが、その熟成した香り高さはポップ・ミュージックとして驚くべきもの。他の名作とされるフィーリン作品と比べても、本作の柔らかな女声と慎ましやかな必要にして充分な演奏の取り合わせは、とりわけ洗練されているように思う。夜更けの底にたゆたうゆったりとした時間。 |
|||
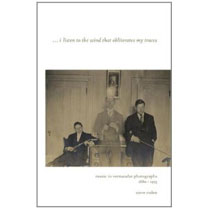 |
18. I Listened to the Wind That Obliterates My Traces (Dust to Digital) 19.や20.のようなSP音源のコンピレーションを聴き始めるきっかけとなった作品。サウンド・アートの作家として知られる
Steve Roden が自身のコレクションから、楽器を携えた人々の古い写真を選び出して写真集とし、これにブルース演奏や風の音のSP盤音源を集めたCD2枚を添付した体裁となっている。針音と不可分にまみれ「いまここ」との隔たりを明らかにしながら、それでいてそれ自体生々しく迫ってくる音の秘密は、いったいどこにあるのだろうか。写真と音楽/音風景の関係については、本作やチェルノブイリ等におけるフィールドレコーディングと現地の写真を収めた
Peter Cusack 『Sounds from Dangerous Places』等を踏まえて考えてみたい(宿題ばかり増えてしまうが)。 |
|||

|
19. To What a Strange Place - The Music of the Ottoman - American Diaspora, 1916 - 1930 vol.1-3 (Mississipi Records) オスマン・トルコを出てはるばるアメリカに渡った移民たちの音楽を、SP盤音源から集めた曲集。その後トルコのポップ・ミュージックがトレード・マークとして身にまとうことになる極端なエコーや極彩色のアラベスクは当然まだなく、素朴なエキゾティシズムが香る。古いポストカードのコレクションを眺めているうちにあり得ない記憶がふとよみがえる‥‥そんな気分になる。 |
|||

|
20. Jamaican Gospel vo.1 & 2 (Social Music Record + Tapes Club) ゴスペルといっても教会での大合唱ではなく、ギター等を奏でながらソロで歌われるもの。声を張る部分はほとんどなくて(ということは恩寵をもたらすべき絶対的な構造も威厳的な崇高性もここには存在しない)、時間が春の雲のようにゆるゆると流れていく。様々な音楽からの影響関係が指摘できようが、そうしたことを斟酌する前に、そのおおらかな豊かさにすっかり武装解除されてしまい、ただただ聴き惚れつつまどろむしかない。 |
|||