|
|
|
||||
 |
1. Henry Threadgill
Zooid Henry Threadgill - alto saxophone,
flute, bass flute; Jose Davila - tuba, trombone;
Christopher Hoffman - cello; Liberty Ellman - guitar;
Stomu Takeishi - acoustic bass guitar; Elliot Humberto
Kavee - drums. 前2作『This Brings Us To Volume 1 & 2』(PI
Recordings)で示されていたのは、未だ試行錯誤の途上にあるような音楽だったが、クリストファー・ホフマンをメンバーに加え、左右にアクースティック・ギターとチェロ、そのやや内側にベース・ギターとチューバ
/ トロンボーン、センターにドラムスとヘンリー・スレッギルという擬似的なシンメトリーの音像を構築した本作において、このバンドが目指していることが明瞭に姿を現したように思える。 |
|||
 |
2. Rafiq Bhatia Rafiq Bhatia - electric &
acoustic guitars, loops, synthesizer, wurlitzer electric
piano; Jeremy Viner - tenor saxophone; Jackson Hill -
double bass; Alex Ritz - drums; Billy Hart - drums; Vijay
Iyer - piano; Peter Evans - trumpet; Corey King -
trombone; Joshua Rubin - clarinet, bass clarinet; Claire
Chase - flute, alto flute; Nina Moffitt - vocals;
Christopher Otto - violin; Caleb Burhans - violin; Victor
Lowrie - viola; Kevin McFarland - cello; Alexander
Overington - processing, synthesizer, wurlitzer electric
piano. まだ、僕自身は生の演奏を耳にしていないし、発表されている音源も少ないので、速断は禁物だが、近年のNYジャズにおける地殻変動が一気に噴出し、相貌を顕わにしたかのような、新しい才能の誕生を感じさせる。どこまでがプロデューサーのアレキサンダー・オヴァリントンの力量によるものなのか測りかねるところだが、本作でエレクトロやヒップホップ、ロックその他の“表現”の模倣ではなく、“態度”を内包した音楽の創造に成功しているのは、彼等「チーム」としての仕事である、ということにこそ本質があると捉えるべきだろう。 |
|||
 |
3. Ryosuke Hashizume
Group 橋爪亮督 - tenor sax, loops; 市野元彦
- electric guitar, effects; 織原良次
- electric fretless bass; 橋本
学 - drums, percussion; 佐藤浩一
piano (2, 3, 8). 日本のジャズ・ミュージシャンで現在進行形の世界水準を体現する者は決して多くない。橋爪亮督グループの成熟を記録した本作は、「日本ならではのジャズ」における一つの達成であると同時に、新たな出発点、参照点ともなっている。「ポップさ」ということでは、ラフィーク・バーティアに一歩譲るが、ジャズ・リスナー以外にこそ届くべき音楽と言える。 |
|||
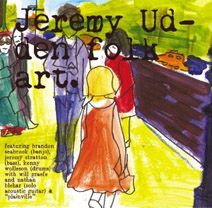 |
4. Jeremy Udden Jeremy Udden - soprano & alto
saxophones; Brandon Seabrook - banjo; Jeremy Stratton -
double bass; Kenny Wolleson - drums; Will Graefe -
steel-string guitar (2); 2012年の10枚にも選んだ Plainville 名義の前作『If The Past Seems So Bright』(Sunnyside Records)と同日録音のトラックも含んでいるが、メインはそれ以前に録音された別編成によるもの。前作より「ポップさ」という面では後退しているものの、「Ensemble Improvisation」としての充実、ブランドン・シーブルックが醸し出す不穏な空気という意味では、一歩進んだ印象を受ける。フォーク的なテイストが色濃いこの音楽も、所謂ジャズ・リスナー以外にこそ聴かれるべきもの。 |
|||
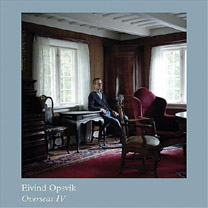 |
5. Eivind Opsvik Tony Malaby - tenor saxophone;
Jacob Sacks - harpsichord, farfisa organ, piano; Brandon
Seabrook - electric guitar, mandolin; Eivind Opsvik -
double bass; Kenny Wollesen - drums, cymbals, timpani,
vibraphone, marching machine. 冒頭のハープシコードとティンパニに驚かされる。「ジャズ」では、まず使わない楽器だろう。全体の印象としても「ジャズ」らしさは皆無に近く、どこかイギリスの劇伴か、映画音楽を思わせるムードに覆われている。かと思えば、トニー・マラビーとブランドン・シーブルックが激しくノイズを撒き散らす場面も。明確な旋律には乏しく、触覚的なサウンド・テクスチュアで織り上げられるアンサンブルの変化を聴く音楽。10年代ダウンタウン〜ブルックリン・シーンのある種の「ポップ化」を示す作品の代表格。 |
|||
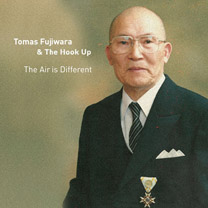 |
6. Tomas Fujiwara &
The Hook Up Jonathan Finlayson - trumpet; Brian
Settles - tenor saxophone; Mary Halvorson - electric
guitar; Trevor Dunn - bass; Tomas Fujiwara - drums. かのダウンビートでも高評価されているメアリー・ハルヴァーソンだが、リーダー作では意外に一本調子な場合が多く、サイドとして本領を発揮するタイプなのだろう。本作では、彼女の空間に揺らぎを与えるような演奏のヴァリエーションを楽しむことができる。 |
|||
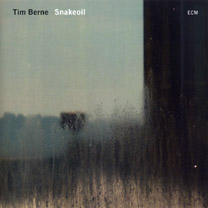 |
7. Tim Berne Tim Berne - alto saxophone; Oscar
Noriega - B♭ & bass
clarinets; Matt Mitchell - piano; Ches Smith - drums,
percussion. クレイグ・テイボーン、トム・レイニーを擁する多彩なバンドで快進撃を続けた00年代前半に比べ、後半は失速したかの印象を抱いていたティム・バーン。しかし、今になって2009年リリースの Buffalo Collision 『Duck』(Screwgun
Records)を聴くと、「Ensemble
Improvisation」的な演奏と、アンビエントな音響処理に本作への布石が感じられる。 |
|||
 |
8. Masabumi Kikuchi
Trio Masabumi Kikuchi - piano; Thomas
Morgan - bass; Paul Motian - drums. 出る出るという噂を耳にしてから幾星霜、ようやくリリースされた本作には、渋る菊地雅章に対して、どうにかしてこの音源を世に問おうとするポール・モティアンの尽力が隠されていた。完全即興にも関わらず、まるで書かれた音楽を演奏するかのように一分の隙も無く同期する「Ensemble Improvisation」。その核を担っているのは間違いなく、バークリー音楽大学在学中から、「必要な音だけを演奏する男」と呼ばれていたというトマス・モーガンだ。 |
|||
 |
9. Colin Stetson Colin Stetson - alto, tenor &
bass saxophones, french horns (4); Laurie Anderson -
spoken vocals (2,6,10,13); Shara Worden - vocals (8,13). ひょんなことから耳にした本作。2011年のリリースながら、これを選ばずに済ませるわけにはいかないだろう。コリン・ステットソンは、ミシガン州アナーバー出身だが、現在はカナダ、モントリオール在住。バス・サックス(!)のソロ演奏とは思えない異形のサウンドで、感情以前のプリミティヴな感覚を多方向から刺激してくる。サックスの反復フレーズに乗せて発するヴォイスが強烈だ。本作においてはジャズ的な即興は皆無だが、彼自身はNYの即興シーンとの関係も深い。13年には、マッツ・グスタフソンとのデュオ作『Stones』(Rune
Grammofon)をリリース。今後の動向から目が離せない。 |
|||
 |
10. Becca Stevens Band Becca Stevens - vocals, guitars,
ukulele, charango; Liam Robinson - accordion, piano,
harmonium, chamberlin, vocals; Chris Tordini - bass,
vocals; Jordan Perlson - drums, percussion; Gretchen
Parlato - vocals (10); Larry Campbell - guitar, cittem
(2, 4-6, 11). こちらもリリースは2011年。当初は、流行りのアメリカーナね、と耳を素通りしていた。ところが、生で聴いたら印象が一変(■)。NYのフォーク〜SSWの系譜に繋がるテイストに、まるでプログレッシヴ・ロックのような変拍子を採り入れた起伏に富んだコンポジションと、それをいとも簡単にこなせる演奏力。ベッカ・スティーヴンスの凛とした佇まいながら、ちょっと甘い声も良い。ゲスト参加しているグレチェン・パラートーに比べると知名度もまだまだといったところだが、端からジャズの枠とは無縁の音楽はポップのフィールドで聴かれるべき。 |
|||
 |
Extra. Bon Iver Justin Vernon - voices, guitars,
banjo, bass, drums, keyboards; Matt McCaughan - drums,
handclapping, programming; CJ “Carm” Camerieri
-trumpet, pedal trumpet, french horn; Colin Stetson -
flute, clarinet, alto, baritone & bass saxes; Michael
Lewis - alto, soprano & tenor saxes; Rob Moose -
violin, viola; Greg Leisz - pedal steel guitar; Sean
Carey - processing, drums, vibraphone, voices; Mikey
Noyce - voices. 実は、2012年のヘヴィ・ローテーションNo.1はこれ。コリン・ステットソン参加ということで聴いたのだが、こっちのほうが大メジャーな存在だった。地味ながら心に沁みてくるメロディを淡々と歌うジャスティン・ヴァーノンのファルセット・ヴォイス。生楽器の演奏に拘った(メロトロン不使用、とまで明記されている)色彩感豊かなアンサンブルが、パストラルなムードと不穏な気配を同時に醸し出す。バッド・プラスのデイヴィッド・キングと
Happy Apple を組むマイケル・ルイス、ビル・フリゼールとの共演で知られるグレグ・リースが参加しているのも胆。 |
|||