|
|
|
||||
|
||||
|
||||
 |
1. ニチエ 『The Two / NE TE』(Long Arms Records CDLA 11084) CD ニチエ(NE TE)はポクロフスキー・アンサンブル出身のセルゲイ・ジルコフ(Sergey Zhirkov; vo, lyre, gusli, kursk pipe,
etc)、エレナ・セルゲエヴァ(Elena Sergeyeva; vo, lyre, handbell, gudok,
etc)のデュエットで、古い民謡を独特のアレンジで演唱する。最初アレクセイ・アイギが率いる4分33秒との共演盤『fall』(Long
Arms, 1997年)でセンセーショナルな話題となり、New world music とか avant-folk
とか称された。その後ニチエ(NE TE)単独名義で Long Arms から発表した『suffering』(2002)ではサックス奏者エドゥアルド・シフコフ、ドラム奏者ミハイル・ユデニッチを迎え、即興演奏を大いに含め、広大なユーラシアを東に西に、北に南に放浪するかのようなアレンジが冴えている。題材を一言で言えばフォークロア、細かく言えば民衆の間に歌い継がれた抒情歌、戯れ歌、婚礼歌、子守歌、巡礼歌、教訓歌、聖歌他ということになるだろう。そうしたマテリアルを、即興演奏を交えて演奏する時、諸々の感情や思想が吹き溜まり渦巻くようなエネルギーをまき散らすところが面白い。そこには猥雑さ諧謔性に満ちた大道芸の類いのフィーリングさえ感じられる。とすると彼らはいにしえの放浪芸人スコモローフを意識しているということになるのだろうか。スコモローフは行く先々のフォークロアで情報を伝え、歌い、踊り、説き、戯れる。そこにはきっと結界というか境界的な破綻が生じたような時間がもたらされたことだろう。各地の土着的フォークロアの内奥に秘めて置かれるべきもろもろがスコモローフ的なひっかきまわし、刺激によってどろどろ流れ出てくるような、あるいはパンドラの箱が開いて飛び散るような様を演じていたのではないか。ニチエ(NE TE)の音楽を聴けば、彼らは各地のフォークロアを現代によみがえらせるというような優等生的な目的で演じているなどとはまったく思えない。そんなわけだから、10年ぶりの Longs
Arms 盤『The Two』(1)には期待で胸が膨らんだ。 |
|||
 |
2. アンドレイ・コトフ 『日々の教訓的な歌 / Andrey Kotov』(Ulitka U 001) 振りかえってみると2011年のこのコラムにもこのCDを挙げている。2012年も2013年もこのCDを聴いていた。コトフは、歌、巡礼歌を主要なレパートリーする合唱団を率いる他、上記したように放浪芸人の歌や古謡や巡礼歌などもハーディーガーディーを手にして弾き語っている人物である。このCDには後者の活動が入っている。人生、死、永遠にまつわるものを主としてとりあげる他、オリジナルも手がけている。ロシア・フォークロア音楽の大家にして、ジャズのアルペリン、シルクロペルと
Moscow Art Trio としても活動しているセルゲイ・スタロスティン(vo、笛)、ジャズ、古楽、フォークロア音楽他、幅広いウラジーミル・ヴォルコフ(bass 他)、カリスマ的なロック・グループ「アウクツィオン」のレオニード・フョードロフ(guitar 他)がゲスト参加している。ヴォルコフとフョードロフはこのところコンビを組んで、ロシア・カルチャーのミッシングリンクを示して現代と架橋してみたり、異能の作曲家ウラジーミル・マルトゥイノフと組んだりしている。このアルバムの誕生には二人の力添えが大きいかもしれない。コトフとかスタロスティンのような一種アルカイックなフォークロア指向は、このところ若いミュージシャンを刺激しているようだ。 |
|||
 |
3. エウゲニー・マスロボエフ、アナスタシア・マスロボエヴァ 『Russian Folksong in the Key of Rhythm / Evgeny Masloboev and Anastasia Masloboeva』(Leo CDLR 517) CD 東シベリアのイルクーツク、バイカル湖から遠くないところで暮らしている父娘、エウゲニー・マスロボエフとアナスタシア・マスロボエヴァの音楽も大好きでよく聴いている。父エウゲニーは1966年生まれ、12歳からドラムを始める。自ら
Arts-cafe を作りブルース、現代音楽、演劇・映画を上演するとともに、ビデオ制作スタジオ、レコーディング・スタジオも手がけ、音楽の先生でもある。子供のための美学センター「小さい翼」、劇団「ド・ミ・ノ」もてがけ、作劇、作曲も行っている。この父娘の音楽は英
BBC2 制作の「ロシア」に使われたこともある。娘アナスタシアは1987年生まれ、10歳から歌とドラム演奏を学び始めた。アナスタシアちゃんが15歳のとき、2008年に出したファースト・アルバム『Russian Folksong in
the Key of Rhythm』(Leo)は印象的であった。コトフの巡礼歌や、ロシア正教というよりはビザンチン聖歌を思わせる調べが耳をかすめ、ニチエ(NE TE)のいわば空想的フォーク音楽にも通じる指向もいくらかうかがわせるし、それだけでなく遊び歌、数え歌といった類の「わらべ歌」も含まれている。アナスタシアちゃんの歌声は、生鮮な湧き水を掬って飲んだときのような気分にしてくれる。エウゲニー父さんはドラムセットや打楽器類だけでなくフォーク系の多数の楽器、台所用品やガラクタなども使い、面白い音を付けている。 |
|||
 |
4. エウゲニー・マスロボエフ、アナスタシア・マスロボエヴァ、アレクセイ・クルグロフ、セルゲイ・スタロスティン、アルカージー・シルクロペル他 『Russian Folksong in the Key of New Jazz / Evgeny Masloboev, Anastasia Masloboeva, Alexey Kruglov, Sergey Starostin, Alkardi Shilkloper, etc 』(Leo Records CDLR 659) エウゲニーとアナスタシア父娘は2012年にモスクワへ呼ばれて文化センター「ドム」に出演した。そのときニュージャズ、フリージャズ系の若手の旗手としてその名が通っている、アレクセイ・クルグロフ(マルチサックス他)、アルカージー・シルクロペル(フレンチホルン、アルプホルン)、セルゲイ・スタロスティン(フォーク・フルート)他がゲスト参加した。この出会いはスタジオで記録され、『Russian Folksong in
the Key of New Jazz』として発売された。即興を楽しんでいる様子が全編から聴き取れる。鳥を歌ったシンプルないわゆる有節歌曲の「Gulbushka」「Kukushecha」なんてとても面白い。前者は快活明朗な曲で、管楽器さんたちはみんな楽しくさえずっている。後者はペーソスのある調べの曲で、なおかつ幻想的なムードも醸し出されている。 |
|||

|
5. ウラジーミル・タラソフ&アレクセイ・クルグロフ 『In Tempo / Vladimir Tarasov & Alexey Kruglov』(Solyd Reocrds SLR 0404) CD 6. 7. ここでアレクセイ・クルグロフのバイオを少し紹介したい。去年12月に出た『JAZZ
PERSPECTIVE VOL.7』誌上でも紹介したのでいくらか重複するのをお許しいただきたい。アレクセイはジャズ・ピアニストの父ウラジーミルの影響もあり小さいときからピアノを勉強し、13歳のときサックスを始めた。セルゲイ・ザルノフスキーの「Class Center」に通った間にジャズをみっちり勉強した。最初のジャズの先生は、なんとレオニード・ウチョーソフのオーケストラのソリストだったエルネスト・バラシヴィリだった。Class Center ではアルカージー・シルクロペル(Moscow Art Trio
他)の「自由な即興」というテーマの授業を受けてさらに進路が定まっていった様子で、その後グネーシン音大のジャズ&ポピュラー音楽科に進み、成長著しく、在学中に多数の受賞を重ね2003年卒業。自己の名前にちなんだグループ「Krugly Band」を結成。クリョーヒンの多ジャンル錯綜マルチメディア無礼講スペクタクル・プロジェクト「ポップメハニカ」や、ウラジーミル・チェカシンの多スタイル折衷かつセンチメンタル・ドラマチック&シアターピース感覚のカルテットなどにインスパイアされたという。クルグロフは詩(自作詩、プーシキン、ヴィソツキー、マヤコフスキー、ヴィクトール・ツォイ他)、映像も交えたり、シアター的な演出をしたレパートリーにも積極的である。そんな一端が聴けるアルバムが『I Love』(Art
Jazz)で、「愛」をテーマとして上記のような経験の統合を試みている。こうした試みというのは、今日を自律的に生きる若いジャズ音楽家ならば誰もが持ち合わせているものだろうが、クルグロフは卒後いきなりそいつでアピールしたのだった。 |
|||
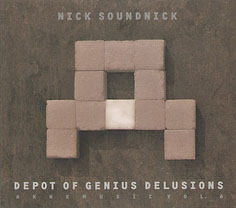 |
8. ニック・スードニク 『Depot of Genius Delusions』(Ultra Records ULTRA CD 27) CD ニック・スードニクはサンクトペテルブルク在住のノイズ〜エクスペリメンタル系パイオニアである。けっこう有名なノイズ・ユニット「ZGA」のリーダーと言ったほうがピンとくるかもしれない。ZGA は1984年にリガで結成されたが、1991年に Pushkinskaya
10 Art Center
のすすめでペテルブルクへ移住し、以来当地で独特の音響をクリエイトしてきた。Pushkinskaya 10 Art Center
は、いわゆるアヴァンギャルド・アートの殿堂である。しかしギャラリーの機能に止まらず、エクスペリメンタルな映像や音楽の場としても著名である。スードニクは今もこのスペースとの強い絆で結ばれている様子だ。オリジナルのノイズ発生機(instruments)による新作『天才の妄想の保管所(Depot of Genius
Delusions)』もここで制作されている。素敵な音楽だ。今度ペテルブルクへ行く機会がきたら
Kuryokhin Modern Art Center
と併せてここも訪ねてみたい。 |
|||

|
9. ウラジーミル・マルトゥイノフ 『Wall-message / Vladimir Martynov』(Long Arms CDLA 11095) CD 10. 今一番モスクワで注目されている作曲家といえば、ウラジーミル・マルトゥイノフかもしれない。米国の著名な弦楽カルテットであるクロノス・カルテットがマルトゥイノフに委嘱して生まれた曲「The Beatitudes(山上の垂訓)」を含むマルトゥイノフ作品集『Music of Vladimir Martynov』(Nonesuch)を発表したおかげで、世界的にもマルトゥイノフに対する注目度は高まっている様子である。 |
|||