|
|
|
||||
  |
|
|||
 |
|
|||
 |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
 |
1. stilllife / 夜のカタログ(Ethnorth Gallery) 繰り返しライヴに通い、レヴューをしたため、ライナーノーツまで書かせてもらって、今更彼らについて何を述べよと言うのか。と言いながら、作品を聴き返すと、周囲の環境音を背景として従えるのではなく、煙幕としてその背後に身を隠すのでもなく、同じ視線の高さから同時生成するように生み出される「演奏」のあり方に、唯一無比なものを感じずにはいられない。誤解があるようなので申し添えれば、彼らの演奏は祭儀的でも宗教的でもない。そもそも祭儀に未来を託し、信心にすがるのは、人智では計り知れない自然の巨大さへの畏れや、眼に見えない将来への不安の故である。だからこそ、人は環境に耳をそばだて、かすかな徴候をとらえようとする。聴覚による触知/探針、すなわち「聴診」は、だから「祈り」のかたちをしている。彼らの演奏もまた。
|
|||
 |
2. stilllife / Color of Winter(No Label) 手前の水音の彼方に広大な空間が開ける視角に、笹島のフィールドレコーディング作品に通じる遠い眼差しを感じる。一方、そこに佇むぽこぽこと丸み/温かみを感じさせる水音や砂利を踏む足音(それは次曲における雪を踏む足音の彷徨へと引き継がれて、旅/移動/漂泊のイマジネーションを鋭く喚起する)は、至るところに記憶の痕跡を見出し、ふと物語を浮かばせる津田の澄まされた耳を思わせる。そうした「自然な調和」を横切っていく交通ノイズを排除することなくそのまましなやかに受け入れ、それでもなおびくともしない竹のような勁さは、いかにも彼ららしい。本作はサウンド・インスタレーションを基本素材とした前作『Indigo』よりはライヴな演奏性へと傾きながら、現在、彼らが展開しているライヴ・パフォーマンスとは、また全く異なる位相を示している。それはCDというパッケージされた録音作品に対する彼らのこだわりのゆえだろう。
|
|||
 |
3. hofli / 12ヶ月のフラジャイル(drop around) 水鳥が鳴き交わす冒頭から、気象情報のアナウンスがはっきりと聴き取れる終曲まで、冬の早朝の冷たく張り詰めた空気みたいに透明できっぱりしている。stilllife のフルレングスCD制作のために、過去の膨大な録音音源を聴き返したことが、後戻りしようもないかたちで彼を「向こう側」へと突き抜けさせたのではないか。あるレコード店主から「ふだん歌ものを中心に聴いているお客様から『よくわからないけどすごく良かった』という感想をもらいました」と聞かされた。一線を踏み越えた浸透力の強さは、ジャンルの壁も突き抜けていく。カレンダーと共に紙箱に封入された美麗装釘。
|
|||
 |
4. 歌女 / 盲声(Blowbass) 本ブログで採りあげたライヴでは、解体したドラム・セットを分有する二人の打楽器奏者が、リズムを迸らせ、自在にスペースをつくりだしながら音楽を組み替え、パーカッシヴなアタックからドローンとしてうねる持続音まで、不定形なサウンドをブリコラージュ的に生み出すチューバと一体となって疾走し、変容し、流動してみせる「歌女」だが、このデビューCDでは、打楽器奏者二人の各々のソロ作品同様、むしろ打楽器演奏の音響的な側面に焦点が当たっており、演奏は重たい静謐さへと傾き、チューバのハウリングやモジュレーションとしか思えない音響にも冷ややかな距離が感じられる。疾走というよりは緩やかな生成。
|
|||
 |
5. 藤巻鉄郎 / 奏像(Blowbass) 「演奏する」というよりは、打撃の際のスティックの感触を確かめる。最初の一打でシンバルが、あるいはドラムのスキンが揺らぎ撓むから、続く一打は自ずと感触が変わる。その差異を味わい楽しみながら、打撃を連ねていく。「鳴り」に指先を浸す感覚。繊細にして克明な「すっとそこにある」感じの録音(レーベル主宰者である高岡大祐による)も素晴らしい。同時にリリースされた、同じくパーカッション・ソロによる石原雄治『打響音集1』も多彩な響きが次から次へと溢れ出す。
|
|||
 |
6. 高岡大祐 / 女木島(Blowbass) ある日突然ひとりになれるところへ行きたいと思って旅立った、香川県高松市沖の女木島における滞在中のフィールドレコーディング。チューバを練習し、音を録音し、食料を手に入れるために釣りをする日々が、そのまままるごと、ここには収められている。チューバの音響にも、島人の話にも、釣りをしている間に過ぎゆく時間にも、フィールドレコーディング特有の冷ややかな視線、機械の聴覚の異質性が向けられている。
|
|||
 |
7. ライブラリ / ライト(Apollo Sounds) おそらくは「ライブラリ」にとって、譜面に書き起こされた指定はほんの始まりに過ぎない。そして彼らは遠くまで見渡せる視覚のガイドで大股に足早に進むのではなく、眼を瞑り手探りで足裏の感触から起伏や傾斜を探り、顔に当たる空気の流れや耳のとらえる響きの違いから空間配置を読み解きながら、少しずつ這い進む。そこには通常のプレイヤーシップとは無縁な、ほとんどシュルレアリスティークな別の感覚世界が開ける(「深夜のトイ・ミュージック」との印象はそこからか)。三角みづ紀による一文節ごと、いや一語ごと、いやいや一音節ごとに移りゆく歌詞と脆い声の手触りもまた。なお、本作で異物性を担っている電子音は、最近のライヴでは排され、そこに秘められた「毒」は、もはや霜降り状に全身に回っていることを付記しておこう。「2014年作品のみ」という原則を破って唯一の2013年作品。
|
|||
 |
8. Rhodri Davies / Pedwar(alt.vinyl) ケルティック・ハープ奏者 Rhodri Davies がこれまで発表してきた3作品と新作をそれぞれLP1枚に収録して収めた4枚組みボックス・セット。『Trem』の抽象的でもっぱら音色に関わるヴォキャブラリー、『Over Shadows』の e-bow により持続的に振動させられた弦、そして限定した本数の弦を張った小型のハープによる『Wound Response』と『An Air Swept Clean of All Distance』。「空虚と充満」、「持続と断片」、「距離と近接」といった対立軸に基づき、奏法やアプローチの制限の下に産み出されたハープの四つの側面。
|
|||
 |
9. The Recedents / Wish You Were Here(Freeform Association) Lol Coxhill, Mike Cooper, Roger Turner の3名によるトリオ The Recedents の30年近くに及ぶ活動から、6回のライヴ録音(いずれも未発表)を5枚のCDに収めたアーカイヴ音源。複数の速度の共存、あちらこちらで起こり続ける出来事、その度に組み替えられていくトリオという構造体……という彼らの柔軟な可塑性の魅力が存分に味わえる必聴作。
|
|||
 |
10. John Edwards, Mark Sanders, John Tilbury / A Field Perpetually at the Edge of Disorder(Fataka) 一聴、ゆるやかな倍音のたゆたいはフェルドマネスクな洗練を予想させるが、すぐに凍てついた打鍵の厳しさ、内部奏法による弦のくぐもった交響がつくりだすぞっとするような虚ろさ、プリペアドによる響きのマテリアルな輝き等に冷水を浴びせかけられ、眼が覚める。ピアノの多面的な力能を自在に操って、多方向へと同時多発的に展開する Tilbury の魔法みたいな手さばきを、他の二人は、天才ドリブラーを迎え撃つディフェンダーのように、距離を詰めすぎず、しかるべきスペースを保ってフォローする。この距離感がここでの演奏を特別なものにしている。「ピアノ・トリオの革命」と言うより別次元か。
|
|||
 |
11. Great Waitress / Flock(Creative Sources) 暗闇に響くかすかな吐息と足音、ねじを巻く音。甲高い耳鳴り、遠く近く響く鐘の音、彼方を通り過ぎるサイレン…とカフカ演劇さながら、アブストラクトにして表現主義的な強い喚起力を持つ音の断片の配置は、舞台が次第に明るさを増すにつれ、情景の広がりとして連なり始める。サウンドはますます優美な洗練を遂げながら、禍々しく生々しい力動そのものと化して、否応なく耳を惹き付け縛り挙げていく。暗がりの湿った匂い、凍てついたピアノの透き通る甘さ、リードのか細い震えが重なり合って照らし出す暗闇の冷ややかさ、希薄な倍音の干渉がつくりだす不定形の広がり。励起され交錯し混濁する五感。素晴らしい。ECM的なアブストラクトなジャケット・デザインを主流とする Creative Sources にあって、このジャケットの禍々しき「乙女力」の解放/暴走ぶりも本当に恐ろしい。
|
|||
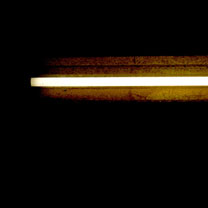 |
12. Hugh Vincent, Yasumune Morishige / Fragment(Improvising Being) 音が二つながら一つになって噴き出してくる。フレーズの投げ交わしによる対話などではなく、エッシャー描くところの互いをペンで素描し合う右手と左手のように、両者は互いを分つべき距離を欠いて、ぴたりと肌を重ね合うところから演奏を始める。ふと漏らしてしまう吐息のようにすべてに一歩先んじる前者と、口ごもり、言いよどみ、乾いた舌が上あごに貼り付いて、痛々しい吃音に至る後者。二人の絡みの相互浸透的な濃密さは、ほとんど器楽演奏の極みに達している。 |
|||
 |
13. Arne Deforce , Mika Vainio / Hephaestus(Editions MEGO) 鋭く空間を切り裂き、響きを圧縮して密度を極限まで高め、溶けた銑鉄の如く迸らせるチェロの強度溢れる演奏を、エレクトロニクスや空間/音響操作がさらに鮮やかに解き放つ。ここでの Vainio による達成は、むしろドロドロの溶解物から張り詰めた形状を自在に引き出すガラス職人の技に近い。重苦しい空虚に満ちた静謐さから、振動が増幅され、破片となって飛び散り、空間を揺るがす苛烈な戦闘状態まで。
|
|||
 |
14. Michel Doneda / Everybody Digs Michel Doneda(Relative Pitch) まっすぐな管に吹き込まれた息は、リードの振動の起動因へと自らの力動のすべてを差し出してしまうことなく、狭い隙間をすり抜け、幾つにも分流し、管のあちこちを震わせながら空間へと射出され、思い思いの速度と軌跡を描いて、空気を揺すり立てる。こうして息音を自在に操る演奏を聴いていると、管楽器のリードが抑圧的な整流化装置であることがよくわかる。野生の「息」の家畜化。水面下で繰り広げられる力動の交錯に、そこで生じる渦や乱流、素早い噴出に身体をどっぷりと浸してみること。
|
|||
 |
15. Hassler-Ullmann-Kupke-Follmi / Hassler(Intakt) ドイツ語圏ミュージシャンの民謡演奏時の没入ぶりは、祭りの記憶や大量のビール/ワイン、あるいは桃や杏のブランデーといったたちの悪い酒のせいなのか、まったくもって鬼気迫るものがある。その切れっぷりは一升瓶抱えた日本のノイズ親父なぞ足元にも及ばない。ここでのスイス勢もやってくれる。室内楽的な緻密なコンポジション/アレンジメントは当然のこととして、俗臭紛々たるメロディを逆手にとった、大衆演芸めいたあざとくも露悪的な構成を随所に織り込みつつ、ソロを交替し、アンサンブルを疾走させ、ついには崖から突き落とす。
|
|||
 |
16. Fred Frith, Michel Doneda / Fred Frith/Michel Doneda(Vand'oeuvre) ちょっとあり得ないほどゆるやかな音の交感が互いの響きを滲ませあい、さらには引き伸ばされた音が弛緩に耐えきれずにほぐれ、内側から響きの遷移が露出してくる。フリスは、ドネダの音の「出」ではなく、立ち上がりの音色の微分的な変化にこそ、自らの響きをぴったりと寄り添わせる。むしろ一歩引いて、管の震えを引き立てるよう裏打ちを施す。「外」に遊び、空間を触知するドネダではなく、完璧に仕組まれたスタジオ・セット(バスビー・バークレイを思わせる…と言おうか)の中のドネダ。それでも聴き応えは充分。異色作。
|
|||
 |
17. Derek Bailey, Simon H.Fell / The Complete 15th August 2001(Confront) 通常のデュオの間合いを明らかに踏み破って、至近距離でベイリーを執拗にチェイスし、我が道を行くことを許さないフェル。弦のブリペアドによりベイリーの音/音色領域を侵犯し、音具を使用して密度を高めたサウンドをぶつけ合わせ、はるか低域へと飛び退いたかと思えば、フレージングやノイズの放出で行く手を先回りしてみせる。その結果として、ベイリーはライン際へと追いつめられ、そこからの脱出に持てるランゲージを総動員させられる。そのようにして運動性が増せば増すほど、両者のサウンドはさらに研ぎ澄まされ、空間は透明度を高め、演奏はくっきりと奥行き深い空間に鋭利な軌跡を彫り刻むものとなる。
|
|||
 |
18. Harry Partch / Plectra and Percussion Dances(Bridge Records) ここでの溌剌としたノリの良いフレッシュな演奏を聴くと、従来の厳かな演奏が歴史博物館の展示物のように思えてくる。もちろんアフリカだったり、中近東〜西アジアだったり、東南アジアだったりする音色のエキゾティシズムは極めて濃密なのだが、自由闊達、めくるめくリズムの噴出/展開ゆえに、そうした濃密さのうちに立ち尽くし窒息してしまうことなく、次々に新たな扉が開け放たれていく。1953年の初演時コンサートの再現という趣向。
|
|||
 |
19. Arnold Dreyblatt / Arnold Dreyblatt, Choice(Choose Records) 持続音のたゆたいのうちにきらめく金属質のかけら。きらきらとした打弦の散乱を、ハーディ・ガーディの持続とベースの弓弾きが生み出す倍音の雲が包み込む。あるいはハーディ・ガーディとベースの弓弾きの重ね合わせが、ほとんど瞑想的な分厚いうねりをつくりだす底の方から、響きの輪がゆったりと巡りながら浮かび上がってくる。ひとつひとつの楽器ではなく、混沌のうちに輪郭を溶解させる中から生じてくる集合的な息づき/脈動。1977年から2007年に至る発掘音源編集盤。
|
|||
 |
20. Populista Presents Ralf Meintz, Karolina Ossowska, Mikolaj Palosz play Giuseppe Tartini La Sonata in Sol Minore Al Terzo Suono(Bolt) 「悪魔のトリル」で知られるイタリアン・バロックの作曲家/ヴァイオリニスト、ジュセッペ・タルティーニの作品を、引き伸ばされた強靭な持続の下、抑揚や装飾音一切無しで弾き切った結果、ほとんど Tony Conrad を思わせるミクロな衝突と軋轢に満ちた世界が姿を現すこととなった。ヴァイオリンの平坦な軌跡は、その鋭く研ぎ澄まされたエッジで空間を切り裂き、チェロはその凝縮された音色の広がりにより床を伝い、埋め尽くして、壁を這い上る。
|
|||
 |
21. Anne Guthrie / Codiaeum Variegatum(Student of Decay) ふくよかな低弦の重層に重ね合わされたフレンチ・ホルンの音色が風にたなびき、陽炎となって揺らぎ、次第に減速しながらゆっくりと輪郭を崩壊させ空間に溶け広がり、いつの間にか小鳥がさえずり、水音が辺りを浸している。至るところ不整合な綻びが生じ、細部は溶けたように曖昧で、輪郭も奥行きもはっきりしない。揺れる音色の不確かな手触りとぐったりとした重さ。視界の曇り/歪みと色彩の混濁。蟻に食い荒らされ、筋だけになった葉が重なりあうオールオーヴァーなジャケットの光景は、ここに収められた響きの特質を象徴している。
|
|||
 |
22. Partial / LL(another timbre) シカゴのヒスパニック地区のリサイクル・ショップで行われた倉庫の在庫(おそらくはガラクタを含む)を音素材とする音響構築。いかにもな楽器音や電子音は登場しない。擦る音、機械仕掛けの作動音、床に落とした金属パイプ、がさがさと騒々しくかさばった物音、どすっという落下音、弾かれたピン、重苦しく湿った沈黙、床下から響く排水管の共鳴、風に吹かれたガラス窓の震え等々の多彩な音素材がループ処理等を含め緊密に組み立てられ、ときには古めかしいミュージック・マシーンと聴き紛う音を立てる。この危うい連なりを築き支えている Noe Cuellar と Joseph Clayton Mills の研ぎ澄まされた耳の強度に驚かされる(なお前者は Coppice の、後者は Haptic のメンバー)。
|
|||
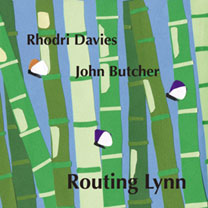 |
23. Rhodri Davies, John Butcher / Routing Lynn(Ftarri) Chris Watson があらかじめ録音した二人のデュオ演奏や環境音をプレイバックしながら、再び二人で行ったデュオ・インプロヴィゼーションのライヴ録音。強風が唸り、潮騒が轟き、激しい雨が大地を叩く環境音の絶え間ない流動変転がもたらすサウンド・スペクタクルと拮抗して、重ね合わされたデュオが切り裂き、張り詰め、ほとばしる。硬い絵筆やパレット・ナイフの跡が生々しく刻み込まれ、あちこちに絵の具の塊が荒々しくへばりついたサウンド・キャンヴァス。
|
|||
 |
24. Antoine Beuger / Tschirner Tunings for Twelve(another timbre) 一音ずつ、すっと力みなく立ち上がり、身体の力を抜いて水に浮かぶように水平にたなびく。そのたなびきながら引き伸ばされる一音の中に、倍音の揺らぎや弦の掠れ/軋み、息のもつれ/震え、その他もろもろの僅かな音色スペクトルの変化が映し出される。それは不思議なことに、時間変化というより、視線を巡らせ、景色を眺め回した時に現れる変化に似ている。複数の楽器の音が重ねられた場合においても、和音が提示されたと言うより、複数の色合いが浮かび上がり、あるものは透かし見るように溶け合い、あるものは隣り合って互いを際立たせ、さらには水面のさざめきと、樹々のざわめきと、雲の揺らめきが視界の中で響き合う。
|
|||
 |
25. Ilia Belorukov, Pedro Chambel, Bruno Duplant, Kurt Liedwart / Quiet Place Recomposed(Theme Park) 息音の短い噴出の間を置いた繰り返しが響きの広がりをふと変えると、電子音の低い唸りが床を這い、金属の擦れる音が繰り返し繰り返し静かに響く。最小限に切り詰められたアクションは、それゆえに僅かな差異に聴き手の耳をそばだてさせる。サンプリングされた断片のループでは生み出し得ない揺らぎが、事態を絶え間なく更新していく。思わず身を乗り出して、暗い深淵を覗き込んでいる自分に気づく。耳はいつも聴こえている音の向こう側を探っている。
|
|||
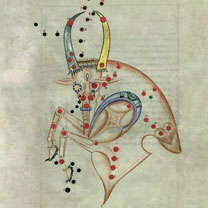 |
26. Chris Strickland / Animal Expert(Caduc) フィールドレコーディング素材とエレクトロニクスによる、繊細極まりない手つきで織り上げられた音絵巻。ループやジャンプカットを安易に用いず、またモンタージュによる直列のつなぎだけでなく、ひとつのパースペクティヴの中での重ね合わせも駆使しながら、声や音風景のような対象の音、移動や変容を支持する音、環境音、電子音や電子的に変容された環境音や音楽の断片による「サウンドトラック」等、フレーム内外の音を巧みに使い分けながら、サウンドをデザインし、視覚的イメージを強烈に喚起しながら、アリアドネによる導きの糸を一瞬たりとも手放すことなく、強靭に持続をつむいでいく。
|
|||
 |
27. David Michael, Slavek Kwi / Mmabolela(Gruenrekorder) この耳の視界に飛び込み、突き刺さる音響の鋭さ/鮮やかさは一体何なのだろう。奥行きのパースペクティヴをしっかりと保って、どこまでも見通せる透明性を持ちながら、なおかつ音は痛いほど皮膚に食い込んでくる。見知らぬ音に惹きつけられ耳がそばだてられ、音源を耳元にたぐり寄せるように聴覚がブーストされる、あのプロセスが随所で生じているのだろうか。まったくただごとではない。
|
|||
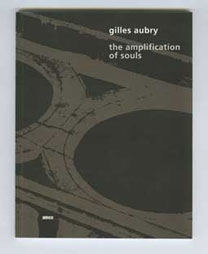 |
28. Gilles Aubry / The Amplification of Souls(Adocs Publishing) コンゴの首都キンシャサの市街、及び市内のペンテコステ派教会における集会のフィールドレコーディング。B6版78ページの冊子が付属(むしろこちらがメインで、CDの方が付属資料)。キンシャサにおいて電気増幅による歪みやハウリングは、もはやサウンドの欠かせない、そして活き活きとした一部となっている(その点で Christina Kubisch による昨年の傑作『Mosaique Mosaic』と似ている)。特に市街各所で収録された音源のコラージュとなっている1曲目において、マイク・テストから始まる電気増幅された声やギターの音は、手前を横切る人々の声や自動車の交通騒音と明らかに異なる手触りを有しており、パースペクティヴの凄まじいばかりの混乱にもかかわらず、くっきりと浮かび上がる。対して教会に集う群衆の間に入り込んだ2曲目においては、電気増幅された説教(というかアジテーションというか)に熱狂した人々が口々に叫び、さらにはそうした人々もまたマイクを向けられて、混沌としたやりとりが増幅放射され、恐るべきカオスをつくりだしている(ゴスペルを一斉に唱和するような「調和」などどこにも存在しない)。Aubry は人々の間を泳ぎ回りながら、あちこちにマイクを向ける。その様は『神聖騎士』でヴードゥー儀式のトランスをキャメラで撮影したマヤ・デーレンにも似て、人々の興奮に自らを溶け込ましているようだ。
|
|||
 |
29. Frederic Nogray / Merua(Unfathomless) 船のエンジン音が止むと、聴き手は辺りを包み天へとたちのぼる虫の音の充満のうちに、ぽつんとひとり取り残される。微かな水音や足音。別の水の流れが次第に大きくなり、耳の視界の中央を占める。とたんに機内で聴くジェット機のエンジン音を数倍にした轟音が辺りを包む。ジャケットには「この夢のようなコンポジションは、Merua(ホンジュラスの北岸)が遺した印象と数年前にペルーのアマゾン熱帯雨林で得たシャーマニックな体験の印象を元に編曲したものである」と記されている。
|
|||
 |
30. Phillip Sulidae / History of Violence(Unfathomless) かつて連続殺人の舞台となった森林は不自然なほどに静まり返り、耳慣れた鳥や虫の声も、せせらぎも雨音も葉擦れも聴こえない。耳鳴りにも似た甲高い響きが、森の奥を見詰めるこちらを見返している。真っ白なキャンヴァス=抽象空間をグラフィックに埋め尽くしていく代わりに、採集した土壌を水に溶かし、ふるいにかけて骨のかけらや特徴的な植物の種子を探すように、顕微鏡的な視線による走査がこの森に潜む地の精霊を音響的特質としてあぶり出していく。
|
|||
 |
31. Banks Bailey / A Listening of Stones(Fungal Records) 霧の立ちこめた深い森の響きと、仏具を思わせる残響の長い打楽器の演奏が重ね合わされる。音色と響きを確かめるような間を置いた打撃。彼方で響く切れ切れのガムラン。虫の声。暗がりで静かに明滅する各種打楽器。辺りに立ちこめ視界を奪う電子音。夢の中から響いてくるせせらぎと潮騒、遠くの歓声。風が運んでくるマリンバの共鳴と鳥の声。輪郭が滲んでもはや出所も形状も定かではない音響の集積。ここで世界はすべて、テーブルに置き忘れられた南国の果実を思わせる甘ったるい腐臭を放っている(それは沈黙にすら沁み込んでいる)。
|
|||
 |
32. Edu Comelles / A Country Falling Apart(audiotalaia) 大学の教室で引き回される椅子と床の軋みにしろ、放置された狐の死骸にたかる無数の蠅の羽音にしろ、急カーヴを曲がるトラムの車両と線路の軋轢にしろ、そこにたなびく音響は安定した輪郭あるいはパースペクティヴに収まることなく、解け流れ出て拡散し、空間の呼吸へと沁み込んでいく。その時に立ち現れてくるのは、その空間に特有のアコースティックな本質が、長い年月をかけて積み重ねられた古い地層のように感じられる。
|
|||
 |
33. Arturas Bumsteinas / Different Trains(Bolt) 列車の走行音とリズミックな線路の響きに交錯するヴォイスが重ねられ、進行をナレーションに委ねながら、穏やかな、しかし静かに張り詰めた響きを緻密に織り成していく30分近くに及ぶ「ラジオフォニック・ドラマ」たる1曲目。チャーチ・オルガンの瞑想的な即興演奏が、子どもたちの合唱やよりしめやかな朗唱、泡立つ水音等と重ね合わされる白昼夢的な2曲目。1936年にベルリンで録音されたヘブライの祈祷からサンプリングされたハーモニウムの古色蒼然たる響きに掠れたヴァイオリンやダルシマーのきらめきを加えた3曲目。
|
|||
 |
34. Carrie Olivia Adams, Joseph Clayton Mills, Deanna Varagona / Huntress(Suppendaneum) 封筒に入った詩編と写真や図版を収めた50ページに及ぶ縦長の冊子にCD-Rが付属する体裁。雨が降りしきり、雷が轟く嵐の夜に突然に鳴り出すピアノ。誰もいないはずの夜更けの大広間から響いてくるチェロ。その旋律は亡霊に拠るものであることを証し立てるように古風で濃密なロマンティシズムに染め上げられている。
|
|||
 |
35. Gianluca Becuzzi / (b)haunted(Silentes Minimal Editions) 出口のない悪夢を思わせる暗黒音響絵巻が展開される。ソナーにも似た甲高い響きの探索、どこまでも空気を揺るがせて波紋を広げていくバスドラムの鳴り、突如として出現する民族打楽器群の連打、下腹部にのしかかる低音から耳を傷つける高音まで全ての音域に渡って重層する金属的軋み……。広大な空間をゆるやかに渡って足元に忍び寄り、あるいはゴシック聖堂にも似た崇高な垂直的空間を照らし出す重厚な響きが、常に細部をことごとく明らかにする凝視の相のもとに展開される。この彫啄された「遅さ」に映える壮大な空間こそが、人間の精神を縛り上げ打ちのめす恐怖の源泉なのだと、彼は知り尽くしている。
|
|||
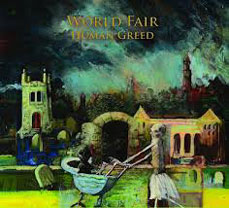 |
36. Human Greed / World Fair(Omnepathy) 「悪夢のカーニヴァル」といった形容が、これほどまでに似つかわしい音響はこの世にあるまい。甘苦く舌に残り、重苦しく胸にのしかかる重層化した響きは、パースペクティヴを混濁させたまま当てもなくさまよい、灰燼となって風に散り飛ばされる。ナレーションに導かれる場面は闇に溶け、ずぶずぶと足元のぬかるみに沈み込んでいく。彼らはあくまでもブラッドベリ的な悪夢、古風なサーカスの舞台裏、幼年時代の夢想のホルマリン漬けの並ぶ埃だらけの地下室に留まろうとする。
|
|||
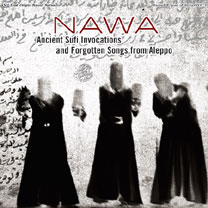 |
37. Nawa / Ancient Sufi Invocations and Forgotten Songs from Aleppo(Electric Cowbell Records) 「シリアの聖なる声」と題されたシリーズの初作。冒頭に収められた声だけによる演奏、とりわけ第1曲に完膚なきまでに打ちのめされる。声は虚空に震え揺らぎながら立ち現れ、大地から立ち上る気の起伏、その微細な凹凸を舐め進むことにより、その這い回る軌跡が美しいヴィブラートを描く。あるいは盲いて行く手を阻む壁を撫で探る指先の動き。かつて降神の儀式を吹き浄めるシャマン金石出(キム・ソクチュル)のホジョクのうねりに、そうした軌跡を認めたことがあった。だが沸騰し泡立つホジョクの叫びに比して、彼らの声は石造りのモスクの床の冷ややかな堅牢さを保ちながら、暗がりに溶けていく。斉唱もまた、ぞっとするほどに深い底の知れない奥行きをたたえる。2本の川の色の異なる水が溶け合うように、組成の異なる揺らぎが不整合なまま混じり合う様に陶然としてしまう。
|
|||
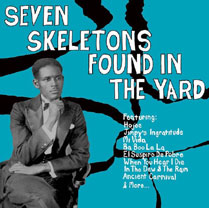 |
38. Various Artists / Seven Skeletons Found in the Yard Trinidad Calypsos 1928 - 1947(Mississippi Records) トリニダードのカリプソ音源のSP盤からの発掘編集盤。田園的優雅さをたたえたストリングスやヒューモアいっぱいのソプラノ・ソロが耳に飛び込んでくる「カワイイ」感覚の比類ない横溢の一方で、舌足らずで寸詰まりなクレオール的英語によるヴォーカルのラップ的なリズムの弾み方や、バックのブラス・サウンドの、サンプリングしてディレイをかけてずらしながら積層化したとしか思えない、ぶっ飛んだアレンジメントの「進み具合」にまた驚かされる。
|
|||
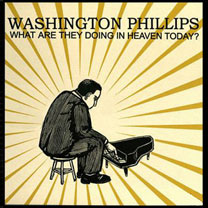 |
39. Washington Phillips / What Are They Doing in Heaven Today ? (Mississippi Records) 伝道師によるゴスペル録音。彼が伴奏に用いたトイ・ピアノのような外見をした楽器ドルセオーラのオルゴールに似た天使的音色が、彼の演奏に不思議な彩りを与えているのは確かだ。録音状態とも相俟って、声も音も放たれるそばから空気に溶けてしまい、熱も重さもない目映い光の微粒子と化して改めて遍く降り注ぐような「恩寵」的感触がある。遠い記憶の中から響いてくるというか、ずっと以前、まだ言語的記憶が備わっていない頃に聴き親しんだ響きがフラッシュバックして、様々な感情とともに一気に込み上げてくるというか。
|
|||
 |
40. Benedicte Maurseth, Asne Valland Nordli / Over Tones(ECM) ふうわりと舞い降りた細い細い天蚕糸が、仰ぎ見るなか空間を横切り、ぴんと張り詰め縦横に張り巡らされていく。そこに粉雪が降り積もるように降り立つ声もまた、ふうわりと重みを感じさせない柔らかさのうちに、ぴんと揺るぎなく張り詰めた芯を持っている。遥か高みから、いや肩を並べていてさえ、地の果てまで透かし見る声の遠い眼差し。重なり合う樹々の黒い裸の枝を射通し突き抜けて、彼方へと渡っていく声の響き。広大な空間のこことあそこに立って音を放つ二人のちっぽけな姿とは別に、たちのぼる響きは香るように広がって、空気を透き通った色合いに染め上げていく。
|
|||
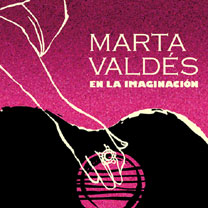 |
41. Marta Valdes / En La Imaginacion(Disco Caramba) 「フィーリンの第2世代を代表するアーティスト」であり、もっぱら作曲家として活躍した彼女の自作自演アルバム。フィーリンの馨しさに魅せられながらも、時として混じる「ナイトクラブ臭」が苦手な私にとっては夢のような理想的作品。曲は以前にベスト選にも挙げた
Guyun Y Su Grupo 『Canta Elisa Portal』並みに素晴らしく、歌唱はいささか生硬だが、それも私にとってはむしろ好ましい。1991年の録音。キューバ国内でカセット・テープのみ流通していた音源の復刻再発とのこと。(■) |
|||
 |
42. Reet / Eesti Rahvalaule(Nature Bliss) エストニア生まれの女性フォーク歌手
Reet Hendrikson による1969年のアルバムの復刻再発。口承により伝承されたエストニアのトラッド曲がギター弾き語りにより披露される。時にいかにも民謡調の垢抜けない曲調も混じるのだが、彼女の控えめなギターと冷ややかで硬質な声は、伝承曲に込められた、行き場のない悲しみや張り詰めた暗さに見事に寄り添っている(幾つかの声音の使い分けも神話的というか、妖精的イメージを醸し出している)。現代北欧トラッドの透明感にも通じる感触。遥か遠くを見詰めるような冒頭曲が特に素晴らしい。(■) |
|||
 |
43. Itasca / Unmoored by the Wind(New Images) アコースティック・ギター弾き語りのフィメール・フォーク。荒れ果てた世界を、澱んだ時間を、水面を揺らすことなく、ゆっくりとかき分けて歩む希薄で虚ろなやさしさに満ちた声。彼女の眼差しは部屋の隅の暗がりをじっと見詰めているようだ。ギターは時折、神々しいばかりの聖なるきらめきを見せる。Christina Carter ほど極端ではないが共通点はある。ジャケットそのままに、昼間の暗がりに溶けていくサイケデリア。(■) |
|||
 |
44. Rachael Dadd / We Resonate(Sweet Dream Press) プリペアド・ピアノ、タイプライター、ウクレレ、タップ・ダンスに至るまで、楽器・非楽器を総動員してつくりあげたミニマルなリズム格子に対し、ゆったりと軽やかにステップを踏む声の足取り。かつての
Meredith Monk 『Do You Be』のようなヴォイス・ダンス・カンパニーの鍛え上げられた超絶技巧ではなく、うきうきした気分が軽やかにする身体の動きでクリアできる自然体な感覚がうれしい。こちらの身体も「共鳴」させられ、思わず弾んでくる。(■) |
|||
 |
45. Zitten / Diaspora(Pastel Music) 今回唯一の K-POP 作品は、私にしては珍しく男性ヴォーカル。彼には
Patel Music のコンピレーションで出会って以来、たまたま
youtube で見つけたアニメーション(■)の素晴らしさ(絶対泣くぞっ)もあって、ずっとその叙情性に惹かれ続けている。その後、だんだんとしなやかな強さを増して、ジョン・レノンのカヴァー(■)も楽しく聴いた。ここでは内なる重苦しさと向かい合い、さらにゆったりとした息遣いを聴かせる。本作は5曲入りと短いのだが、これまでの蓄積に免じて選んだ次第。(■) |
|||
 |
46. Lutine / White Flowers(Front&Follow) 女性2人による自作自演集(一部トラッド曲を含む)。素人っぽい歌唱や拙さの残る演奏にもかかわらず本作を挙げざるを得ないのは、聴いた瞬間から声に魅入られてしまったからにほかならない。抱きしめた子鹿のようなどきどきする声の震え。それは
Sally Oldfield が第1作『Water Bearer』で垣間見せて、すぐに無くしてしまったものだ。音盤に封じ込められた束の間の奇跡。(■) |
|||
 |
47. Damien Rice / My Favourite Faded Fantasy(Atlantic) 何でこんなメジャーな人を…と不審に思われるかも。前作『9』をソウルで友人に薦められて買って良かったんで、新作もソウルで見つけて「おおっ」と購入(日本じゃ人気あるのかな)。前作が時折垣間見せたぞっとするような冷ややかさが薄れた分、「うた」や「演奏」の背後の空間が奇妙にざわついている。何か別の存在の気配が濃密に漂っているというか。それ自体、奇妙に息づいているというか。その点、Mark Hollis 的。声やメロディやオーケストラだけじゃなくて、そうした「通り過ぎて行く眼に見えないもの」もぜひ聴いてほしい。(■) |
|||
 |
48. Minha Dolores / Nina Becker Canta Dolores Duran(Joia Moderna) MPBってブラジル産のコーヒー豆と同じで「バランスよく豊かな味わいなんだけど、透明感や突き抜ける香り高さに欠ける」感じがして、試聴だと良くても盤1枚通して聴くと……ということが多いのだが(あくまでも個人的な嗜好の問題です)、ここまで上手くて心配り細やかでは文句の言いようが無い。たびたび後ろを振り返りつつ歩むような、声の繊細な運びを彩る吐息の滲み。高音域を受け持つギターの香るように優雅な抑揚と低音域を受け持つギターの腹に沁みるさわり。それらは空気をはらみながら、ゆるやかに絡みあい、編み糸の異なる色目をかわるがわる映し出していく。(■) |
|||
 |
49. Yann Fanch Kemener, Aldo Ripoche, Damien Cotty / Les Chants De La Passion(Buda Musique) スパイシーに倍音の香るチェロの響き、張り詰めた喉や頬から放たれる声の震えの這い進む強度。空間に拡散し、希薄に広がるのではなく、ごつごつと彫り刻むが如き無骨な逞しさ。「土着」と言うにふさわしく、まさに固い大地を踏みしめ、大きく四肢を伸ばし、「土に足が着いた」音だ。圧倒的。(■) |
|||
 |
50. Jürg Frey / 24 Worter(Edition Wandelweiser Records) それぞれの曲題を二度繰り返すだけのミニマルな歌詞。ソプラノによる語の発声、微かに震え息づく「生きている彫像」のように耳の視界に現れ、ヴァイオリンとピアノの音数も抑揚も限られた平坦で希薄な響きにゆっくりと照らし出されていく。光の筋が通り過ぎるたびに陰影の模様が変化する。「Wandelweiser楽派の作品」と構えずに、部屋の空気に混じらせ、そのふうわりとあてもなく漂う様に耳を浮かべてみること。それゆえポップ・ミュージックの「歌もの」の枠に配した次第。(■) |
|||