|
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
 |
1. Tyshawn Sorey: Inner
Spectrum of Variables (Pi Recordings PI 65) |
|||
| タイション・ソーリーの5作目は、CD 2枚組、2時間に及ぶ大作となった。それは、これまでの活動の集大成という位置付けを超え、新たなディメンションへの突入を宣言するものとなっている。 彼が「ダブル・トリオ」と称する特異な編成(ピアノ・トリオ+ストリング・トリオとのことだが、変則弦楽四重奏にピアノとドラムをオーギュメント、と言われたほうがしっくりくる)と相俟って、「ジャズ・ドラマーの作曲した現代音楽作品」と安直に認識され、その結果として敬遠されているのだとしたら勿体ないとしか言いようがない。 そうした先入観を外して虚心坦懐に耳を傾けてみる。冒頭のピアノ・ソロにはキース・ジャレットを想起させる美メロが散りばめられているのだから、つかみはOK。チェロ独奏から弦のアンサンブルへと続く流れに少し身構えてしまうが、まずはその量感豊かな音色と各奏者のヴァーチュオーゾぶりに集中すると次第に視界が拓けてくる。 作曲/即興、アンサンブル/ソロ、同期/非同期、変拍子やポリリズム、レイヤードされた音像やタイム、触覚的な質感と立体的な空間構成、エスニックな語法の導入、等々といった現代ジャズを巡る多様な問題系に多彩な角度から光を当てる、目眩く音楽絵巻の様相。特に、ディスク2の冒頭に配されたゴング独奏は、光沢のない鈍い金属音を一つ一つ確かめながら配置していく、空間に張り巡らされた感覚の集中度から耳を逸らすことができない。やがて、弦楽器がそれぞれに弓奏やピチカートのさざ波を打ち寄せるが、その感覚の繊細さ、鋭敏さはアンサンブル全体に伝播し、細部に至るまで行き渡っている。 ピアノのコーリー・スマイスを始め、現代音楽系の奏者が集められてはいるのだが、所謂ジャズと現代音楽のコラボレーションのようなものとしては捉え切れない。この音楽にはタイション・ソーリーの幅の広い耳の来歴が刻み込まれており、それは各メンバーにおいても同様である。ジャズとコンテンポラリー・クラシカルとの相互浸透も「New Chapter」の論点の一つだが、言及されることの多いポスト・クラシカルやインディー・クラシカルがクラシックのポップス化やプロダクションの洗練化(エレクトロニクスの導入がメルクマールの一つ)の流れだとするなら、ここで起こっていることはローカルなミュージシャンのコミュニティにおけるグラス・ルーツ的な交流に根差したものだと言えるだろう。
|
||||
 |
2. Flin van Hemmen:
Drums of Days (Neither/Nor Records N/N 005) |
|||
| 1982年、オランダ生まれのドラマー、フリン・ヴァン・へメンの初リーダー作。サイド・マンとしての録音すらほとんどないので、日本では全く無名の存在と言って良いだろう。 彼の生演奏にはNYで触れたことがあるが、ヴァーサタイルなドラマーという印象の域を出るものではなかった。まず、アルバムの大半でドラムではなく、ピアノを演奏していることに驚かされる。同時に彼はジャズ・ミュージシャンには珍しく、アイヴィン・オプスヴィーク等と並んで録音物としてのプロダクションに極めて意識的でもあることに気づく。ローファイな音像、多重録音やフィールド・レコーディングの使用等、1曲毎に異なるコンセプトに合わせたきめ細かなサウンド構築。ミニマルで静謐な室内楽、サックスとギターによるメランコリックなメロディ、ジャズ的なコレクティヴ・インプロヴィゼーションに音響的なフリー・インプロヴィゼーション、フィールド・レコーディングの中から立ち上がるドローン、多重録音されたポエトリー・リーディング、ロック的にパワフルなリフレイン…… ここから所謂「現代ジャズ」に共通するクールな洗練を聴き取ることは難しい。一方、現代音楽系の奏者は参加していないものの、ミニマルな楽曲構成や楽器の響かせ方にその影響を聴き取ることは難しくないだろう。それにも増して全体から漂ってくるもの、聴き手を侵犯してくるものは、どこか懐かしい気配、たゆたうような気怠るさ、もの憂く弛緩しつつも集中力を失わない宙づりの感覚。ここには先ほど指摘した緻密な構成感覚とは一見相反するようなリアルな身体性が露呈している。 音楽を作り物のように感じさせてしまうか、それとも生命の息づくものとして感じさせるか、その違いは微妙だが、決定的でもある。やはり只者ではない。
|
||||
 |
3. Raphael Malfliet:
Noumenon (Ruweh Records 003) |
|||
| 1990年、ベルギー生まれのベーシスト、ラファエル・マルフリートの初リーダー作。これはクリティカルな録音だ。音像型のオーディオで鳴らすと、各奏者が譜面やキューに基づいて様々な音響を次々に発していくだけの無味乾燥な演奏に聞こえてしまいかねない。一方、音場型のオーディオでなら、各奏者が発する音響が相互に浸透しながらアメーバのように姿を変え、時間が伸縮していくような様相を聴き取ることができるだろう。そして、後者が喚起する視覚的なイメージは、驚くほどカヴァー・アートとの親近性を持っている。 アルバム・タイトルの「noumenon」とは、ギリシャ語で「phenomenon=現象」の対になる概念で、プラトンの「イデア」、カントの「物自体」に相当する。人間には直接経験することのできない本質といったところだろうか。聴き手がこの音楽を「認識」しようとすることなく、「音自体」を感じて欲しいという意図によるものだという。 ヴァン・へメンと同様に現代音楽系の奏者は不参加だが、現代音楽的な響きに満ちてもいる。しかし、現代音楽とジャズの融合を目指したものなどではない。彼はモートン・フェルドマンからの影響を含めて、五線譜と図形楽譜をつなぎ合わせて作曲を行なっており、それは五線譜では記述できないフィーリングを生かしつつ、作品として再現できることを重視したためだという。しかし、聴感上はサウンド・アート的なフリー・インプロヴィゼーションの印象が強い。互いの発する響きに敏感に反応し合いながら、自在に行先を変え、表情を変え、形を変えていく。 それは、若干26歳の彼が時間をかけてジャズの語法を習得した上で到達したアプローチではない。NYダウンタウン〜ブルックリンの猛者たちとの交流を通じて感覚的に体得したものだ。彼が最初にジャズに見出した自由というものが、この先どのような形に展開されていくのか、追いかけてみたい存在だ。
|
||||
 |
4. David Virelles:
Antenna (ECM Records ECM 3901/5710440) |
|||
| 2014年の『Mbókò』では、キューバの呪術に根ざした音楽で強烈な印象を残したダヴィ・ヴィレジェス(1983年生まれ)。ところが、引き続きECMからお目見えした本作は、およそECMらしくないカヴァー・デザインが施され、アナログの、それも10インチのみのリリース。プロデュース:アレキサンダー・オヴァリントン、マスタリング:ヴァルゲイル・シグルズソン、ギター:ラフィーク・バーティアという布陣は、ラフィーク・バーティア『Yes It Will』(Rest
Assured)のプロダクション・チームそのものではあるものの、ヘンリー・スレッギル、マーカス・ギルモアの参加によって内容は全く予測不能。 『Yes It Will』では、まだ辛うじて留められていたジャズの形式が、ここでは完全に雲散霧消してしまった。ハード・ディスクの上だけに構築された録音芸術。最初と最後に配されたアフリカっぽいプリミティヴなパーカッション・アンサンブルは生演奏ではなく、ヴィレジェスが音源制作、プログラミングを担当したもの。 輪郭のはっきりしないスレッギルのアルト・ソロは分厚い電子音の波間を漂い、ギルモアのフリーなドラミングに導かれてアンビエントなシンセ、チェロの強奏、ヴォイス、ミニマルなギターが姿を現しては消えていく。一転、ギルモアが操るMPCの訛るビートにウーリッツァのリフが絡むとキューバン・ヒップホップの激しいラップが繰り出され、ゆったりしたコード進行に乗せてピアノの強烈な打鍵が刻まれていく…… まるで一貫性のないサウンド・コラージュのようでありながら、統一感のあるサウンド・デザインを実現している。ポスト・クラシカルのプロダクション・チームによるジャズとキューバ音楽とエレクトロニック・ミュージックとヒップホップのミクスチュア。わずか20分とやや物足りないが、既にフル・サイズの続編が予定されているとのこと。ついでながら、ラフィーク・バーティアの次作にも嫌が応にも期待が高まる。 |
||||
 |
5. Jim Black Trio: The
Constant (Intakt Records Intakt CD 268) |
|||
| 俺が悪かった、許してくれ、ジム。ジム・ブラックは1967年生まれだから既にアラウンド・フィフティで、流石にマンネリの陥穽から逃れられなくなったのだと断じていたのだが、本作リリース前の2016年6月にNYで聴いたギグがあまりに素晴らしくて考えを改めざるを得なくなった。 活動の止まったアラス・ノー・アクシズに取って代わるように2010年頃に誕生したピアノ・トリオは、若干19歳のピアニスト、エリアス・ステメセダー、ベースには天才トマス・モーガンという新鮮なメンバーを擁しながら、新たな耳の扉を開くような魅力を感じさせるものではなかった。彼は一体何をやりたいのだろうか? 当時、スタンダード・オンリーのギグを聴いたこともあって、歳をとったせいでジャズ回帰路線でも目指し始めたのかと考えていた。 しかし、こいつは全然違う。プリペアドを交えた多彩なサウンド・パレットをサンプリングのように駆使し、強靭な打鍵で鍵盤上を自在に動き回るピアノに、人力ディレイ的フレージングを挿入するベース、そしてジャストなビートと縒れたビートを往来し、音の伸びないシンバルと胴鳴りの少ないデッドな革物でマシン・ライクなサウンドを叩き出すドラム。テーマ‐ソロ‐テーマという構成を排し、まるでDJが流れるようにトラックを繋いでいくように場面転換していく長尺の楽曲。 それは完全アクースティックのピアノ・トリオでエレクロニックなフィーリングを演奏する音楽。ここ数年、「アクースティックな生演奏でエレクトロニックなサウンドを再現している」と形容されるものは少なくないが、概ね定型的なリズム・フィギュアに終始し、ジャズ的な自由度の高い即興からは縁遠い。しかし、このトリオはエレクトロニックなフィーリングを持ちながら、即興演奏の局面に突入したときの自由度と振幅が半端なく広い。 教え子筋のマーク・ジュリアナの人気に対抗して発奮したのだろうと言ったら穿ち過ぎだろうか? ともあれ、筆者にとってはメリアナやビート・ミュージックよりも遙かに刺激的な存在となっている。 |
||||
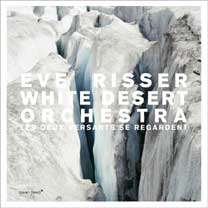 |
6. Eve Risser White
Desert Orchestra: Les Deux Versants Se Regardent (Clean
Feed Records CF 399 CD) |
|||
| イヴ・リッサーは1982年フランス生まれのピアニスト。クリスティアン・ヴァルムレー・アンサンブルの一員で、頻繁に来日しているトランペット奏者、アイヴィン・レニングの参加で辿り着いた。ソロ、トリオに留まらず多彩なアンサンブルに参加しており、録音も多い。フランス国営ジャズ・オーケストラのメンバーでもあり、ジョン・ホレンベック曲集『Shut Up And Dance』(BEE JAZZ)には彼女のために書かれた曲が収録されていて、本アルバムで再演している。 しかし、本作は、フランス国営ジャズ・オーケストラを含むマリア・シュナイダー以降のモダン・アンサンブルの潮流とも、ヨーロッパ伝来のフリー・ジャズ・オーケストラの系譜とも異なるものだ。 プリペアド・ピアノやマルチフォニック、エレクトロニクスも導入した多彩なサウンドを用いる10人編成のラージ・アンサンブルは、フィールド・レコーディングのようなサウンドスケープから、音響的即興、エレクトロニカ、ノイズ、繊細に編み上げられたホーン・アレンジメント、M-BASE的なリズム、ジャズ的なソロ、ロック・フィーリングを発揮するギターやベース等々と実に幅広い楽想を展開している。これもコンテンポラリー・クラシカルとの共振を感じさせる動きの一つと言えるだろう。 |
||||
 |
7. Sara Serpa &
André Matos: All The Dreams (Sunnyside Records SSC
4028) |
|||
| ポルトガル出身の夫婦デュオの2作目。サラ・セルパは1979年リスボン生まれ、2005年に初リーダー作『Quintet』を録音後、バークリー音楽大学に入学。同じくボストンでニュー・イングランド音楽院を卒業したアンドレ・マトス(同名のブラジル人ヘヴィ・メタル歌手がいる)とともに2008年にNYへ進出。以降、セルパは既にソロ名義で2枚(ヴァルダン・オヴセピアンやクリス・デイヴィスと共演)、ラン・ブレイクとのデュオで3枚のアルバムを出している。 深い残響が音像全体の輪郭を滲ませ曖昧なものにし、時に楽器のピッチが大きく揺れ続けることで、何か白昼夢でも見ているような朦朧とした気分に誘われる。そういえば、シンセとミックスを担当するピート・レンディは、RJミラーの2013年作『Ronald's Rhythm』(Loyal Label)でも同様の作風を示していなかったか? そして、このある種の酩酊感はヨゼフ・デュムランにも通底している。 歌手のセルパが器楽的な跳躍の激しい旋律を描き、マトスのほうが歌物らしく優しいメロディを作っているのが意外かつ対照的で面白い。 |
||||
 |
8. Lilly Joel: What
Lies in the Sea (Sub Rosa SR 416) |
|||
| リリー・ジョエルというふざけた名前のユニットの音源は、実は2015年にリリースされていたのだが、入手しそびれているうちに2016年になってしまった。しかし、これを紹介しないままでは名が廃るというもの。 リン・カシエは1984年ベルギー、アントワープ生まれ。ジャズ〜即興シーンで活動し、参加作も多い。高岡大祐とも共演歴があるらしい。フェンダー・ローズの魔術師ことヨゼフ・デュムランとはLidlboj名義の『Trees Are Always Right』(BEE JAZZ)で共演済み。 エフェクターで変調された音像は上記作以上に輪郭が滲んで暈けていて、まるでチューニングの合わないラジオから聞こえてくる何処か知らない遠い国の放送のようだ。はっきり歌物と認識できるものもあれば、歌と伴奏らしきサウンドが一致していないもの、アンビエントな音響だけのもの、グリッチのように壊れた反復、等々が入れ替わり立ち替わり。かと思えば、妙にリアルな物音やチューニングの狂った楽器音がくっきりとした音像で飛び出してくる。白昼夢というより、夜中に寝惚けて朦朧としているときのような意識が判然としない何か遠い感覚。カヴァー写真は劣化してザラついたモノクロームの夜景。 |
||||
 |
9. Jeff Parker: The New
Breed (International Anthem IARC 0009) |
|||
| ジェフ・パーカーといえば、言わずと知れたトータスの一員で、ロブ・マズレクのシカゴ・アンダーグラウンドに長く関わり、ブライアン・ブレイド・フェロウシップの創立メンバーでもあり、バークリー音楽大学在学中のカート・ローゼンウィンケルのルームメイトとか等々……
奥さん都合で長年過ごしたシカゴを離れ、現在LA在住。 その成果が本作で、ジャマイア・ウィリアムズ、ジョシュ・ジョンソン、二人の若手を抜擢する一方、白人のヴェテラン・ロック・プロデューサー/セッション・ベーシスト、ポール・ブライアンを共同プロデューサーに迎えている。 冒頭、チューニングもリズムも縒れた緩いストリングスのサンプリング・ループに、太く重心の低いベース・ラインが微妙にズレたタイミングで入ってくると、思い切り腰砕けになりそうなグルーヴに一発でヤラレてしまう。続くアルト・サックスとギターのハーモニーも合っているんだかいないんだか良くわからない微妙なズレがあり、2曲目の70年代ジャマイカン・レゲェ風オルガン、5曲目で繰り返される女性コーラス・サンプリング等々、どこか調子のタガが外れた、徐々に気が遠のいていくような非現実感と、強い身体性を伴った酩酊感が横溢している。 どこかに書いたことがあるのだが、パーカーの音楽からは常に、失われた記憶やありえない思い出を呼び起こすノスタルジア、あるいは遠い過去に想像された未来像への追憶、とでもいうような、とても懐かしい雰囲気を漂わせながらも、それは過去のどの時代にも実際には存在したことのない、と同時にどこかSFチックな未来感も併せ持つ、非道く矛盾した性質を内包している。 |
||||
 |
10. Marcus Strickland's
Twi-Life: Nihil Novi (Blue Note Records/Revive Music
B002468402) |
|||
| いつまでも若手サックス奏者のイメージだったマーカス・ストリックランドも、1979年生まれだからすっかりヴェテランの域に達している。従来はストレート・アヘッドなジャズに拘泥した地味な作風が続いていたが、本作ではミシェル・ンデゲオチェロをプロデューサーに迎え、R&Bやヒップホップとの繋がりを強調した方向性に大きく舵を切ってきた。 まずは、やたらと生々しい録音に耳を奪われる。タイトに引き締まったドラムと低域の量感溢れるベース。ヒップホップ〜R&B畑では有名らしいチャールズ・ヘインズとカイル・マイルズのコンビネーションが心地好い。特に3曲目の冒頭、メトリック・モデュレーションを駆使したフィルでドラムがインしてくる瞬間が最高。サックス・ソロは控え目で、メロディとアンサンブル、そしてサウンド構築に注力しているところにも好感が持てる。センスの良いキーボード・ワークを聴かせるのは若手のミッチ・ヘンリー。 フロリダ生まれの彼の音楽からは、最近話題のヒューストンやフィラデルフィアのような教会や高校でのバック・グラウンドは感じ難い。古き良きソウルやジャズの伝統、アフリカへの敬意に満ちた眼差しと刷新への意志。ロバート・グラスパーやLAのブレインフィーダー一派にはどうにも乗れなかったという方にこそ聴いていただきたい。 |
||||
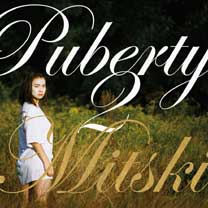 |
extra. Mitski: Puberty 2
(Dead Oceans DOC 123) |
|||
| ミツキ・ミヤワキは1990年、日本生まれの日米ハーフで、コンゴ、マレーシア、中国、トルコ等を転々とした後にNYへ。NY以前はオルタナティヴ・ロックやインディー・ロックには触れず、父親所有のスミソニアンの民俗音楽アーカイヴ(Smithsonian Folkways Recordings)と、母親所有の中島みゆき、荒井由実、山口百恵といった歌謡曲〜ニューミュージックを聴いて育ったという。 年末に聴いてみて以来、そのアルト・ヴォイスがすっかり耳から離れなくなってしまった。声域は狭く、メロディの起伏に乏しく、サウンドにも特に目立った特徴や新規性は見当たらないのだが。寧ろアウト・オヴ・デイトで、一般的にアトラクティヴな要素が希薄なところが良かったのかもしれない。前述の彼女の聴取経験が、このどこか垢抜けない感じやうっすらとした怨念めいた雰囲気に繋がっているに違いない。何処かで聴いたことのある雰囲気に似ていると思って、ようやく思い出したのはLily Chou-Chou『呼吸』だった。 「第二思春期」と題されたアルバムに社会性は希薄で、普遍的な実存をテーマにしているようだ。一方、「Your Best American Girl」ではアメリカにおけるエスニック・マイノリティの女性ならではの苦悩をさり気なく吐露しており、そうした観点に立つとビヨンセやソランジェ、リアーナ等と並べて聴くのが適切なのかもしれない。
|
||||