| オデッサ への 手紙 005 |
増補版 ボヤンZとバルカン・ジャズの展開 |
岡島豊樹 Toyoki Okajima (東欧〜スラヴ音楽リサーチセンター) |
||||||
BOJAN A TO Z: Guide to the Balkan Jazz by Bojan Zulfikarpasic Biography and selected discography text by Toyoki Okajima |
||||||||
| 00 | 序:「バルカン・ジャズ」とは |
|||||||
| ボヤンZことボヤン・ズルフィカルパシッチは、旧ユーゴスラヴィア連邦共和国のセルビア出身のジャズ・ピアニストである。ボヤンZのジャズは「バルカン・ジャズ」と形容されることが多い。 | ||||||||
| バルカンとは、北は旧ユーゴスラヴィア諸国(セルビア、スロヴェニア、クロアチア、ボスニア=ヘルツェゴビナ、マケドニア、モンテネグロ)、東はルーマニア、ブルガリア、西はアルバニア、南にはアルバニア、ギリシアが含まれ、バルカン半島と呼称されてきた一帯である。民族の分布も文化や音楽の特徴も多彩である。ジプシーも数多く暮している。 | ||||||||
| バルカン音楽と言えば、ジプシー音楽がすぐさま連想されるが、ボヤンZのバルカン・ジャズは、コブシ、奇数系の拍子、ジプシー調の哀愁モードなどに安易に依存するものではない。彼の場合、セルビア、ボスニア、マケドニア、ブルガリア他の伝承曲を題材としたジャズ演奏や、さらにバルカン諸国へかつて大きな音楽的影響を与えた近隣のトルコの音楽からもインスピレーションを得たジャズ演奏を積極的にアピールして評価を高めてきた。 | ||||||||
| エスニック音楽とジャズが融合した音楽を演奏する人は今では珍しくない。それには大きく分けて2つのタイプがある。 | ||||||||
| 1つは、ジャズ・ミュージシャンであって自分の出自に関わる伝統的な民族音楽の要素を取り入れている人、もう1つは伝統音楽の熟練ミュージシャンであってジャズの要素を取り入れている人、である。ボヤンZの場合は前者である。 | ||||||||
| 東欧やロシアには、日本と同じ位長いジャズの歴史がある。近年は毎年恒例のように来日している旧ユーゴ出身のドゥシュコ・ゴイコヴィッチ(DUSKO GOJKOVIC, トランペット/1931年生れ)にうかがったことがあるが、彼がジャズを演奏しはじめた50年代には優れたビーバップ・プレイヤーがいたそうだ。しかしバルカンの伝承的音楽の性格もあわせもったジャズということでは、ゴイコヴィッチ自身が1960年代に作った『SWINGING MACEDONIA』の中の5拍子でスイングしバルカンの香りを放っている「MACEDONIA(マケドニア)」他が本格的なバルカン・ジャズ演奏の創始と言えるだろう。他にもこのような人物は過去散見されるが、ボヤンZのような内容を意欲的かつ体系的に継続した例は多くない。 | ||||||||
| ボヤンZのバルカン・ジャズが花開くのは、1988年(21歳)にパリのジャズ・スクール(CIM)に留学するために渡仏してからのことである。以来18年、若いミュージシャンとだけではなくフランス・ジャズ界を代表する先輩ミュージシャンの多くとも共演を果たした。なかでも指折りの巨匠たち、アンリ・テクシエ(HENRI TEXIER, ベース)、ミッシェル・ポルタル(MICHEL PORTAL, クラリネット、サックス)のグループをかけもちするという大役をつとめるために初来日し(1998年)、鮮烈な演奏を聴かせてくれた。翌年ソロ・ピアノで再来日、飛んで2005年フランス生活の最初期からの親友ジュリアン・ルロ(JULIEN LOURAU, サックス)のグループのキーボードを担当して3度目の来日をし、2006年ふたたびソロ・ピアノでやってきた。 | ||||||||
| リーダー・アルバムは6作あり、すべてフランスの名門レーベル「ラベル・ブリュー(LABEL BLEU)」から発表されている。 | ||||||||
|
||||||||
| 華々しい受賞歴もある。今ではフランスのトップ・ジャズ・アーティストに数えられている。フランスに来てからの年月は栄光と充足の日々であったかにみえる。しかし、その間、旧ユーゴは解体・内戦という事態になったあげく、両親が暮らしていた郷里のセルビアがNATO(北大西洋条約機構)の爆撃に見舞われてもいる。そんな苦渋のなかでバルカン・ジャズを大きく花開かせたのだった。 | ||||||||
| 筆者は数度、音楽的足跡についてボヤンZに直接質問する幸運に恵まれた。そのときの談話や、公式文書(自身のホームページにおける略歴:■)などを取り混ぜてボヤンZの足跡をまとめたい。 | ||||||||
| 01 | 少年期の音楽環境 |
|||||||
| ボヤンZは1968年2月2日セルビア共和国の首都ベオグラードに生まれた。両親とも大の音楽ファンであることから、ズルフィカルパシッチ家には両親の友人達が頻繁に集まり、深夜まで音楽を楽しんでいた。ユーゴスラヴィアのフォークソングも盛んに歌われ、ボヤンZはそれを子守唄代りに眠りにつくこともたびたびだったと両親から後に聞かされた。こうした環境もあって、幼少時から楽器に触れることになり、5歳のときピアノのレッスンを受け始めて以来、長らくクラシック音楽をさらった。バッハ、次いでラヴェル、ドビュッシーを発見したが、友人の影響でビートルズの『リヴォルヴァー』を発見し、ギター、ドラムもかじり、ロックに興じる一方、父の影響でブラジル音楽にも惚れた。音楽学校(STEVAN MOKRANJAC)時代はピアノ以外にコントラバスを学び、学生オーケストラのメンバーでもあった。 | ||||||||
| 「ずっとクラシック音楽の教育を受けてきたけど、クラシックの演奏家になりきれなかった。というのは、楽譜に忠実に演奏することに飽きたらなくて、自分なりに付け加えたいという気持ちがすごく強くてね。少年時代に仲間とロックバンドをやったのは、自分でつくり出せる音楽だから。ブルースにもはまったなぁ」 | ||||||||
| 02 | ベオグラード・ジャズ・デイズ |
|||||||
| 自分でつくる音楽がしたいボヤンZがジャズに向かうのは当然の成りゆきで、1980年代に入りジャズにも関心を抱き始めた。急速にジャズ演奏の能力を高め、15歳のときには LADONJA JAZZ BAND という名のグループでジャズ・ミュージシャンとして演奏開始し、ギグ(仕事)もやっている。1984年クロアチアのグローズニャンで開催された夏期ジャズ研修に参加し、ジャズ・ミュージシャンを目指す多くの若者と出会い意見を交わした結果、心は大きくジャズへ傾いた。当時ベオグラードで主流的なジャズといえばアメリカン・スタイルのスイング、ビーバップだったが、ボヤンZはそれ一色に染まらず、広範な時期のジャズを聴いた。特に熱心に聴いたのはハービー・ハンコック(HERBIE HANCOCK, ピアノ)、ビル・エヴァンス(BILL EVANS, ピアノ)だった。 | ||||||||
| 「あの人たちみたいになりたくてコピーしまくったよ。他にもいろんなピアニストをコピーすることで育ったみたいなものだ。今でも(1998年の時点)アメリカのジャズを聴くよ。20年代、30年代のものもよく聴く。けっこう過去の音楽にもさかのぼるんだ」 | ||||||||
| そうして音楽学校在学中は、練習室かベオグラードのジャズ・クラブにたむろする生活が始まった。当時ベオグラードに毎夜ジャズ・ライヴのあるクラブが1軒あり、そこで彼は旧ユーゴのトップ・ミュージシャンの大半、一例をあげればストエプコ・グート(STJEPKO GUT, トランペット)、ララ・コヴァチェフ(LALA KOVACEV, ドラム)、ヴォイン・ドラスコシ(VOJIN DRASKOCI, ベース/後にボヤンZのアルバム『KORENI』参加)他と出会い共演するようになっていった。1986年、18歳のとき音楽学校を卒業。奨学金を得て米国でクレア・フィッシャー(CLARE FISCHER, ピアノ)に3ヵ月師事(ミシガン州のブルー・レイク芸術キャンプ)して帰国し、兵役義務を果たした後、すぐにパリにあるジャズ・スクールCIMへ留学した。ジャズだというのにニューヨークやニューオリンズではなくパリを選んだのには、グローズニャンで出会った恋人への思いが強かったからだと、ほがらかに明かす、ピアノ演奏と同様歯切れのいいナイスガイがボヤンZである。 | ||||||||
| 03 | オリジンへの目覚め |
|||||||
| ボヤンZを自分のグループに迎え入れて長い間活動を共にしたアンリ・テクシエ(HENRI TEXIER)に、ボヤンZに対する評価を求めたことがある。 | ||||||||
| 「きわめてアイディアのひき出しが豊かで、いつもフレッシュな音楽が出てくる。繰り返しがない。驚きだよ」 | ||||||||
| 人一倍多くのものを聴いてきたボヤンZとはいえ、単に多くのものを聴き、覚え、消化するだけで、そのような演奏が常にできるようになるとは限らない。 | ||||||||
| 「何か表現するということは、例えば自分が何かにすごく感動した場合に、それを他人に伝えたいというような気持ちが出発点だと思う。ミュージシャンなら音楽という手段で伝えたいと願う。過去に聴いて感動したものをそのまま再現したのではダメで、自分というフィルターを通して作り直して聴き手に伝える形になると思う。僕の演奏には繰り返しがないといってくれるのは嬉しいけど、それでも、やはり過去に聴いてきたものの蓄積からそうなっているんでしょうね。システマティックに同じようなフレーズが出てくるということになると、もう聴き飽きたと思われてしまう。偉大な即興演奏者はそんなことはなくて、システマティックに聴こえない素晴らしい演奏ができるものだ。緊張の部分、緩む部分などを自分なりにどういう風に取り混ぜるかということからして、いろいろ研究しています」 | ||||||||
| 自分の人生で経験する思いを自分らしい音楽ヴォキャブラリーで表現することを指針として活動しているアーティストがボヤンZである。自分らしいヴォキャブラリーとは、彼の場合、バルカン的ないしユーゴ的音楽の表出をともなった表現法ということである。「ジャズを通じて自己のバルカン・オリジンをきちんと呈示できたらいい」とも彼は公言し、実践してきた。 | ||||||||
| 「ベオグラードで暮していた頃、バルカン音楽の中にジャズ的なものがあると感じた。逆に、ジャズの中にバルカン的なものがあると言ってもいいかもしれない、とも感じた。つまり、リズムの重要性、そしてインプロヴィゼーションの重要性は両者に共通するんだなということを感じたとき、ジャズへの関心がさらに深まったことをはっきり覚えている」 | ||||||||
| そうした認識が自分の音楽活動のエネルギー供給源となるのは、パリに行ってからのことだった。 | ||||||||
| 04 | パリ若手ジャズメン群像 |
|||||||
| 1988年にパリに来てスクールに籍を置きながら、ジャズ・ミュージシャンとして演奏活動も始めた。たとえば、CIMで同窓のノエル・アクショテ(NOEL AKCHOTE, ギター)。アクショテはマルチなベクトルで音楽的な才能を発揮している若手の注目株で、アヴァンギャルドな性癖もありジャンルを超越して即興演奏の新しい文脈を探っていた。ボヤンZはそんなアクショテとデュオ、カルテット他、様々な編成でライヴをしまくった。その中の重要な1つに、今も親密な付き合いの続くサックス奏者ジュリアン・ルロ(JULIEN LOURAU)も含むグループ「トラッシュ・コーポレイション(TRASH CORPORATION)」があった。こんな音楽を指向したグループだった。 | ||||||||
| 「オーネット・コールマン(ORNETTE COLEMAN)的な音楽をはじめとして、フリージャズ的な音楽、フォーク的な音楽、ファンク、その他なんでもあり。面白いものは片っ端やっちゃおう。メンバーみんな、てんでに興味のあるものをもってきて、ミックスしてやっちゃおうって感じ」 | ||||||||
| 当時はジョン・ゾーン(JOHN ZORN)のネイキッド・シティ(NAKED CITY)的なアプローチに興味があったという。ボヤンZはシンセサイザー、ヴォーカルもやったとか。しかし4年で解散した。その間、マルク・ビュロンフォッス(MARC BUROFOSSE, ベース)らとのカルテットで参加したコンクール・ドゥ・ラ・デファンスではベスト・ソロイスト賞をもらった(1990年)。さらにマルク、ジュリアン、そして後にルイ・スクラヴィス(LOUIS SCLAVIS, クラリネット、サックス)のレギュラー・ドラマーを務めることになるフランソワ・メルヴィル(FRANCOIS MERVILLE)とのカルテットで活動していた頃の1992年に上記コンクールに出演したときには、作曲賞を獲得した。ちなみにこのグループでデモ・テープ録音をしているとき、マルクの友人で巨匠アンリ・テクシエの子息であるセバスティアン・テクシエ(SEBASTIEN TEXIER, サックス&クラリネット)が覗きにきていた。セバスティアンを通じてボヤンZのその時の演奏が巨匠の耳に入ったのがきっかけとなって、後に巨匠は自分のグループへ誘うことになる。 | ||||||||
| 巨匠テクシエがボヤンZを含む新グループ「AZURE(アズール)」を始動したのは1991年のことだった。アズール名義の最初のアルバム『AN INDIAN'S WEEK』(LABEL BLUE LBLC 6558)では、ゲスト参加した巨匠ポルタルや俊英スクラヴィスと知己を得て、その後も共演している。さらに、欧米屈指のジャズメン多数との共演も経験することになった。 | ||||||||
| ちなみに、テクシエのアルバム『MAD NOMAD(S)』(LABEL BLEU LBLC 6568)*1 は、ボヤンZ、アクショテ、ルロ、セバスティアン、さらにフランソワ・コルネルー(FRANCOIS CORNELOUP, バリトンサックス)といった若者が結集している。今やフランス・ジャズの歴史的1枚と言える。 (*=文末にデータ掲載) |
||||||||
| 05 | バルカン・ジャズ実践の環境 |
|||||||
| 「フランスで僕に興味をもってくれる人が増え、いろいろ共演が増えていくにつれて、自分独自のものは何かと強く考えるようになった。ベオグラードにいた頃からアメリカン・スタンダードも好きでフランスに来てからもずっと演奏してきたけど、何か違ったものを出せないのかと自問した。スタンダードが嫌いというわけでは決してないんだ。思い至ったのが、ユーゴ的、バルカン的なものを素材にすることだった。リズム、メロディ、即興演奏の展開、インタープレイにおいて、バルカン音楽的な要素は有効だと再認識した。実際にジャズのアーティストと共演する形で演奏したかったが、それにはオープンな精神をもっている人たちが必要だった。その点、僕はとてもラッキーだった。ずっとフランスのジャズ界は自分をよく迎えてくれたという思いが強い。フランス・ジャズ界には非常にオープンなエスプリがあって、出会いを受け入れていこうという姿勢があるから、素敵な出会いがたくさんある。そうして混ぜて新しいものを作っていくよね」 | ||||||||
| バルカン・ジャズの実践と発展という点から大きな支えとなったのは、アンリ・テクシエとジュリアン・ルロの存在だった。 | ||||||||
| 「アンリ・テクシエさんは、自分がもって生まれたブルターニュ的なもの、フランスの様々な音楽と、知的後天的な影響、つまりインドやマグレブの音楽他を自分の中で非常によく咀嚼して合体させてジャズとして表現できる素晴らしいアーティストだと思う。初めて一緒に演奏したときから、ウマが合うと感じた。君が行きたい方向に行っていいんだよというふうに非常に勇気付けてもらった。テクシエさんやそのカルテットの人たちは僕の曲を乗って演奏してくれて、その感触から結構いけるのではないかという思いを強めたんだ。 ジュリアンとは一緒に音楽を作った。彼とは同世代で共通言語があり、なおかつ彼なりに非常に多彩なバックグラウンドを混ぜて素晴らしい音楽を作る才能に恵まれている。ジュリアンはバルカンの音楽にもとても興味をもっていた。マイルス・デイヴィス(MILES DAVIS)の60年代のグループをみればわかるように、同じ世代の共通言語とバックグラウンドをもっている若者が一緒に演奏していく中で暗黙の了解みたいにして相手を理解し、刺激しあって成長していった。ああいう関係で僕とジュリアンも15年ほど一緒にやってきたと自分では思っている」 |
||||||||
| 06 | MASHALA登場 |
|||||||
 |
HENRI TEXIER / AN INDIAN'S WEEK
(LABEL BLEU LBLC 6558) - HENRI TEXIER (bass), GLENN FERRIS (trombone), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), TONY RABESON (drums) + guests: MICHEL PORTAL (bandoneon), LOUIS SCLAVIS (clarinettes, soprano sax) - 1. LUNDI, 2. LAGUA VENETA, 3. MARDI, 4. STANISLAS, 5. MERCREDI, 6. CYCLOSIS, 7. JEUDI, 8. INDIANS / DESAPARECIDO, 9. SIMONE SIGNORET, 10. VENDREDI, 11. AMAZONE BLUES, 12. SAMEDI, 13. TZIGANE, 14. MASHALA (Bojan's composition), 15. SAMEDI SOIR, 16. THE BRIDGE, 17. DIMANCHE, 18. DON'T BUY IVORY, ANYMORE, 19. DIMANCHE SOIR, 20. LAGUA LAITA, 21. LUNDI - recorded on January 11-13, 1993 |
1993 | ||||||
| ボヤンZのオリジンを色濃く反映したジャズがCDに刻印されて広まった最初は、テクシエが率いるアズールの第1作『AN INDIAN'S WEEK』(1993年発表)に収録されている「MASHALA(マーシャラ)」だった。このボヤンZのオリジナル曲はピアノ、ベース、ドラムスのトリオ編成で演奏されている。バルカンの民族音楽や、トルコ音楽、アラブ音楽などを想起させるコブシと哀感があいまって一種独特の情調を生み出している。 | ||||||||
| 「マーシャラはトルコ語で、神のおかげという意味だ。とても満足したときとか、道行く女の子がすごくキレイだったりしてイイねぇなんて思ったときに発する言葉なんだ。この曲は僕のルーツに根ざしたユーゴの民謡/民衆音楽的なアレンジをしている。ユーゴの民謡/民衆音楽はベオグラードで生まれてからずっと僕の周りにあって、むこうにいた頃はむしろ聴き飽きてゲンナリなくらいだったけど、今は自分のルーツを辿りながら音楽を探究していきたいと思っている」 | ||||||||
| ここでボヤンZのルーツに立ち入ろう。 | ||||||||
| 彼の両親はともにボスニア出身とのことである。2人はベオグラードで勉学に励む間に出会い、結ばれ、ボヤンZの誕生となる。家系をかなりさかのぼるとペルシャ(現在のイラン)、さらにトルコに行き着くという。この後発表していくことになる自身のリーダー・アルバムにも、バルカン音楽とともに多かれ少なかれトルコ、中東調のフレーズやリズム感覚も例外なく聴かれる要因のいくらかはここにあると考えていいだろう。ただし、彼自身は自分の民族的アイデンティティとして何人と特定して自分の音楽と結び付けて語ろうとしない。彼の場合、言ってみれば、複合的なアイデンティティ認識をオリジンとしていることがリーダー・アルバム群から感じられる。 | ||||||||
| 07 | 初リーダー・アルバム |
|||||||
 |
BOJAN Z QUARTET (LBLC 6565)
- BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), JULIEN LOURAU (soprano & tenor saxes), MARC BURONFOSSE (bass), FRANCOIS MERVILLE (drums) - 1. NO NAME VALSE
(BZ), 2. PLAY BALL (Steve Swallow), 3. ZILBRA (BZ) - BZ= Bojan Zulfikarpasic's composition - recorded on December 19 & 20, 1993 |
1993 | ||||||
| ボヤンZは初めてのリーダー・アルバム『BOJAN Z QUARTET』(LBLC 6565/1994年発表)にボスニア、セルビアの伝承音楽をアレンジして含めた。そのことは、両親や自分のルーツだからということだけなく、当時ボスニアがセルビア人、クロアチア人、ムスリムの3勢力による内戦状態に陥っていたことと切り離して考えるわけにはいかない。ボスニアの伝承曲「GRANA OD BORA」のアレンジ版は、リズムもメロディもバルカン色濃厚、ボヤンZもルロも徹底的にリリカルでメロディアスなソロを繰り広げる。慈愛に満ちた世界であるが、ときどき哀愁味がよぎる。セルビアの伝承曲「NISHKA BANIA」のアレンジ版は祝祭的な舞踊光景を活写したような、徹底的にブリリアントな音楽である。トラッド2曲を、暗い心持ちが表立たず、むしろ安らかな曲調に仕上げたのは、祈り・願いの現れではないかと考えられる。 | ||||||||
| ボヤンZ作曲とクレジットされた曲は4曲ある。まず、冒頭に据えたワルツ曲「NO NAME VALSE」。この味わいは複雑な仕込みから生まれたものだろう。ラテン風味というべきか地中海的味わいといっていいのか、そこに淡くバルカンの風味を添えている。3曲目「ZILBRA」。鮮明にバルカン的舞踊曲を連想させる曲想で、1曲目のときとは逆に、ラテン/地中海風味を淡くまぶしてある。ボヤンZのソロにおけるフレーズはバルカン/ビザンチン的と呼んでいいようなモード感がある。4曲目のテクシエ・グループにおける録音のある「マーシャラ(MASHALA)」。ジュリアン・ルロがうまくコブシを回してオリエンタル・ムードとジャズの融和感を出している。9曲目 「SPIRITO」、これは名残りを惜しむように終わっていく、ややメランコリックな曲で、特にバルカン色は出してないようだ。 | ||||||||
| 「マーシャラ」に限らず、ルロのバルカン調のコブシが実に板に付いた演奏が光っている。ルロのバルカン調フレーズ回しには本場の人たちもうなったとか。 | ||||||||
| 「ジュリアンと一緒にベオグラードで、バルカン伝承曲を演奏したとき、この生粋のフランス人がとても上手にバルカン的メロディを演奏したので土地の人はビックリしていたよ。ジャズってそういう面白さがあるよね」 | ||||||||
| 『BOJAN Z QUARTET』にはルロのオリジナルも1曲、「GINGER PICKLES」がある。ルロはテナー・サックスでもソプラノ・サックスでも、ジョン・コルトレーンの遺伝子を受け継いだような吹奏も時折みせるが、メロディックなアプローチが本領だろう。それでいてこじんまりしない、スケールの大きさがある。ボヤンZはバルカン音楽的的表出という視点を脇において評価しても高水準のポイントを得るような魅力的な演奏を、この曲のほか随所で披露している。スティーヴ・スワロウ作曲の「PLAY BALL」では重量級のスイングが面白い。メルヴィルのオリジナル「LES INSTANTS SENS DESSUS DESSOUS」はリズム、構造ともテクニカリーな仕立てになっている。アナーキーな部分も込めてあるところはトラッシュ・コーポレーション的なアプローチと言えるかもしれない。ボヤンZの演奏は嬉々として活発に聴こえる。 | ||||||||
| 08 | サラエヴォ・ブルース |
|||||||
 |
『SARAJEVO (SUITE)』(L'Empriente Digitale / Collection deux z) (ED 13039) - HENRI TEXIER (bass), SEBASTIEN TEXIER (alto sax), NOEL AKCHOTE (guitar), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), TONY RABESON (drums) - track 5: SARAJEVO BLUES (composed by Henri Texier) |
1994 | ||||||
| しかし、この時期の彼は内心まったく嬉々とはしていなかったことだろう。CD『SARAJEVO (SUITE)』(L'Empreinte Digitale / Collection deux z)に収録された「サラエヴォ・ブルース(SARAJEVO BLUES)」の彼の演奏がそのことを示唆していないだろうか。これはアンリ・テクシエのグループの一員としての演奏である。このCDはボスニア内戦解決の見通しの暗い状況の中、終結への働きかけというメッセージを含んで、ジャズ系ミュージシャンを主として多数の賛同者によって制作されたコンピレーション・ディスクである(1994年発表)。このテクシエ作の曲でボヤンZは先発ソリストを担当し、コブシ回しもバウンスのフィーリングも特徴的な演奏を聴かせる。いつもよりやや重い、と言うべきか内省的な傾向の演奏と言うべきか。ただし、決して悪く無い演奏である。続くノエル・アクショテ、セバスティアン・テクシエのソロはホットかつエモーショナルで、ボヤンZを激励しているようでもある。 | ||||||||
| 09 | オリジン・リサーチの進展 |
|||||||
 |
BOJAN Z QUARTET / YOPLA!(LBLC 6590) - BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), JULIEN LOURAU (soprano & tenor saxes), MARC BURONFOSSE (bass), FRANCOIS MERVILLE (drums) + special guest: KUDSI ERGUNER (nay, on 2 &9) - 1. YOPLA! (BZ), 2. BEYOND THE FRAME (BZ), 3. UN DEMI-PORC ET DEUX CAISSES DE BIERE (Lourau), 4. ZAJDI, ZAJDI (Macedonian traiditional, arr. by BZ), 5. NIGHT THING (BZ), 6. MULTI DON KULTI (BZ), 7. INGENUITY (Buronfosse), 8. POST IT (Merville), 9.DUGUN EVINDE (Huseyin Saadeddin-Arel, arr. by Kudsi Erguner), 10. SHE-DANCE (BZ) - BZ= Bojan Zulfikarpasic's composition - recorded on December 18-21, 1995 |
1995 | ||||||
| ボヤンZにおいてオリジンを表出することの意識は、折しものワールド・ミュージック隆盛の音楽業界を射程に入れただけのものではないことは、どのアルバムでもきっぱりと演奏で断言されている。2作目のリーダー作『YOPLA!』(LBLC 6590/1995年発表)では、第1作のメンバーに加えて、2曲でトルコ出身の著名なネイ(葦笛)奏者であるクツィ・エルグネル(KUDSI EGUNER)をゲストに迎えた。ピーター・ゲイブリエルの Real World からリリースされたコンピレーション・アルバムでエルグネルの演奏を聴いてネイの音、トルコ音楽に深く興味を覚えて、エルグネルのディスクをいろいろ聴き込み、コンサートにも行き、アルバムへの参加を求めた結果である。 | ||||||||
| 「ネイは葦をくり抜いただけの、リードもないシンプルきわまりない管楽器だ。しかし、その音にはヨーロッパの音楽の全てが詰まっているとさえ感じる。オスマントルコが制覇していた時代に、セルビア、ボスニア、マケドニア、ブルガリアといったバルカンの諸地域だけでなく、ヨーロッパ全域にオスマントルコの音楽の影響が及んでいる。モロッコ、アルジェリア他、北アフリカにもね。ブルガリアにはネイに似たカヴァルという管楽器もあって、この音も好きだ」 | ||||||||
| ネイは尺八のような瞑想的な吹奏を特徴とし、イスラム教神秘派教団スーフィーと切っても切り離せない楽器である。このアルバムに収録されている「BEYOND THE FRAME」「DUGUN EVINDE」におけるエルグネルの吹奏もその連想を促すものだ。ブルガリアのカヴァルも同系のメカニズム/演奏法の管楽器である。ボヤンZはネイ、カヴァルの息の表現が好きでたまらないと語る。ブルガリアで演奏されているカヴァルのレパートリーには快速演奏をアピールする曲も多い。2006年の最新アルバム『XENOPHONIA』ではカヴァル奏者をゲストに迎えて緩急両タイプの演奏を入れることになる。 | ||||||||
| エルグネルの参加は、ボヤンZのオリジン・リサーチの必然的帰着と言えると思う。 | ||||||||
| バルカン伝承曲の借用という面では今回マケドニアの「ZAJDI, ZAJDI(ザイジ、ザイジ)」がある。エルグネルがアレンジした古典曲「DUGUN EVIND(ドゥグン・エグンデ)」も広義で該当する。「ZAJDI, ZAJDI」のメロディの美しさ、抒情性、そしてエレジー性は筆舌尽しがたい。ボヤンZは1音1音を珠玉の音色で慈しみ深く弾き綴る。哀愁美旋律の多いことで名高いマケドニア民謡の中でも屈指の「JANO, MORI(ヤノ、モリ)」に似た旋律も聴こえてくる。 | ||||||||
| エルグネルのアレンジによる「DUGUN EVIND」は瞑想系ではなくミディアム・テンポで、活気のある曲である。エルグネルのソロ・パートでは格調高いオリエンタル調であるが、ボヤンZのソロになると珠玉のバルカン・リリカル・メロディに変容する。ここは彼の歴史観の実験的ショウケースであると思う。 | ||||||||
| バルカン伝承曲のジャズ・アレンジのみを彼のバルカン・ジャズの実践と呼ぶのは早計で、ボヤンZ名が記されたオリジナル曲にもバルカン風味が漂っている。 | ||||||||
| 「このメロディはどこかで聴いたことはないですか? といろんな人に尋ねる。そうして前に誰も書かなかったと確信が持てる場合だけ自分の名前をサインすることにしている」 | ||||||||
| この発言は、彼がオリジン由来の演奏行為・作曲行為にいかに積極的であるかを物語ると同時に、できるかぎり出所を明らかにしたいというリサーチ精神の現れであろう。このアルバムは、すでにそのリサーチがかなり進み、バルカン音楽の中の重要な、いわば優性遺伝子のようなものを生かして作曲あるいは大胆に編曲するという手法がとられていると言える。オリジナル曲をみよう。 | ||||||||
| 「YOPLA!」は軽快なステップのバルカン舞踊の躍動感とブギウギのバウンス感やノリとの近似を示すという狙いが下地にあるかもしれない。 | ||||||||
| 「BEYOND THE FRAME」は東洋音楽、西洋音楽、アフリカ音楽が融和した興味深い曲想である。エルグネルの瞑想的なソロにルロが重なり、やがてルロはアフリカン・アメリカン・スタイルとバルカン調を折衷したソロを展開する。 | ||||||||
| イベリア+マグレブ+地中海=「NIGHT THING」という式が成り立つかどうか? このオリジナル曲は、ボヤンZのオリジン・リサーチが広範な視野から行われていることを示している。そして、どう聴いてもジャズという音楽に収斂している。 | ||||||||
| そうした思考の展開に、実は大きなインスピレーションをくれた人がいたことを示すのが「MULTI DON KULTI(ムルティ・ドン・クルティ)」である。これは故ドン・チェリー(DON CHERRY, 米国のトランペット奏者)への捧げものだ。 | ||||||||
| 「ドン・チェリーのことは昔から大好きだった。ワールド・ミュージックと呼ばれる音楽があるけど、その最初のクリエーターの1人がドン・チェリーと言えるんじゃないかな。彼は60年代にギリシアやブルガリアの音楽にも接し、自分の音楽の肥やしにしたし、アフリカ音楽の影響も強い。特にカメルーンの音楽のね。彼はトランペット以外にいろいろな楽器も演奏したけど、どの演奏を聴いても彼らしさが伝わってくる」 | ||||||||
| ということで、アフリカ音楽、カリブ音楽、ジャズ、そして最もダイレクトなオリジンであるバルカン音楽とのハイブリッド音楽としてチェリーに献呈した。 | ||||||||
| その延長で、アフリカ系かカリブ系か判別出来ないまでに溶け合って、ユーモラスにフィナーレを飾るのが「SHE-DANCE」である。 | ||||||||
| メロディもリズムもバルカン色濃厚な「UN DEMI-PORC ET DEUX CAISSES BIERREU」がルロの作曲とは驚きを禁じ得ない。しかもバルカン・ジプシー調とラテン調がミックスしたようないかしたリズム設定を、バルカン・ルンバ・ジャズと呼んでいいかもしれない。細かいコブシ、バウンス感、ちょっと誇張気味の哀愁モードが溶け合っている。ルロはブルガリアのパパソフ(IVO PAPASSOV)あたりのジプシー・サックスを念頭に置いているかも知れない。ボヤンZがソロで聴かせるツィムバロム的なグリッサンドを合わせて考えれば、中〜東欧ジプシー音絵巻みたいなノリもあるかもしれない。実に面白い。 | ||||||||
| 収録曲は他にビュロンフォッス作のシリアス・タッチのバラード「INGENUITY」、メルヴィル作の凝った構成とリズムによる「POST IT」もある。ボヤンZは研ぎ澄まされた音、幻想的ハーモニー、切れ味などで貢献している。 | ||||||||
| 10 | バルカン・ジャズ第1章結論 |
|||||||
 |
BOJAN ZULFIKARPASIC / KORENI(LBLC 6614) - BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), VOJIN DRASKOCI (double bass), KUDSI ERGUNER (ney), JULIEN LOURAU (saxophones), VINCENT MASCART(saxophone), TONY RABESON (drums), PREDRAG REVISIN (double bass), VLATKO STEFANOVSKI (guitar), KARIM ZIAD (percussion) - 1. LA PETITE GITANE (Cigancica) (traditional, arr. BZ), 2. RADIO BO (Tony Rabeson), 3. KORENI (BZ), 4. CECEN KIZI (Tanburi Djemil Bey, arr. BZ), 5. GRADINO KOLO (BZ), 6. SVETI BOZE (Dear Lord), 7. THE JOKER (BZ), 8. ZULFIKAR-PACHA (BZ), 9. CD-ROM (BZ), 10. SRTCHA (On ferme) (BZ) - BZ= Bojan Zulfikarpasic's composition - recorded on November and December, 1998 |
1998 | ||||||
| この書き手は今でも、『KORENI(コレニ)』(LBLC 6614/1999年発表)の演奏を聴き、メンバーの名前や曲名を眺めていると目にも胸にも熱いものが込み上げてくる。 | ||||||||
| なんと勇気のある人だろう。博愛や民族主義の超越などを唱える文化人や音楽家は珍しくないが、ボヤンZを凌ぐ実行力の持ち主はどれほどいるのだろうか。理想主義を独白することは誰にでもできるが、このアルバムの制作には大変込み入った手続きと、信頼と、決断が必要だったはずである。 | ||||||||
| メンバーを紹介すると、ベオグラードで活動するジャズ・ミュージシャン2人、ヴォイン・ドラスコシ(VOJIN DRASKOCI)、プレドラグ・レヴィシン(PREDRAG REVISIN)というベース奏者たち。マケドニアのスコピエ在住のカリスマ的ギター奏者ヴラトコ・ステファノスキー(VLATKO STEFANOVSKI)。その他はパリ在住のミュージシャンだが、出自はバラバラだ。『YOPLA!』に参加したトルコのクツィ・エルグネル(KUDSI ERGUNER, ネイ)、アルジェリア人のカリム・ジアード(KARIM ZIAD, 打楽器)、テクシエのアズール・グループの同僚でマダガスカル出身のトニー・ラベソン(TONY RABESON, ドラム)、そして親友ジュリアン・ルロ(JULIEN LOURAU, サックス)、新鋭ヴァンサン・マスカール(VINCENT MASCART, サックス)という2人のフランス人。 | ||||||||
| 「もちろんメンバーの選出は意識的に行った。ベオグラードから来たヴォインは、スロヴァキアとロシアの血が混じっているかもしれない。プレドラグは名前からするとマケドニアとセルビアの混血かなとも思うけど、たぶん先祖の代にもっと複雑な血の混交があったかもしれないと思う。何人と規定するのは非常に難しいんだ。規定する必要もないと思う。何より大事な大前提は、非常に高い即興演奏の能力をもったアーティストを選ぶことだった。音楽的には、それまで自分がめざしてきたもの、即興演奏、ジャズ、バルカン音楽の要素の融合をさらに高いレベルにまでもっていきたかった」 | ||||||||
| 『KORENI』は彼のバルカン・ジャズの発想を考える上できわめて重要な演奏の宝庫であり、彼の最初のピークを記録したとも言える内容だ。各曲のバックグラウンドを質問したので紹介したい。 | ||||||||
| 1曲目「LA PETITE GITANE(ジプシーの少女)」はジプシー音楽的というよりも汎バルカン的旋律の伝承曲で、旧ユーゴ時代にララ・コヴァチェフ(LALA KOVACEV, ドラム)ら当地のミュージシャン(ヴォイン・ドラスコシもその1人)によってジャズ・アレンジされて録音されたものが残っている。ボヤンZたちは勇壮かつビジーなリズム・アピールを設定し、まずエルグネルによる詠唱的とも鎮魂的とも解釈できる吹奏、ジュリアン・ルロのアグレッシヴなブロウ、ボヤンZの躍動するプレイ、ヴラトコ・ステファノフスキーの鬼気迫るロング・ソロなどの冴えた即興演奏が連なる約9分である。 | ||||||||
| 2曲目「RADIO BO」。ボヤンZはジャズ博士といっていいほど様々なジャズを知っている。しかも自分で再現的な演奏もできる。そのことが浮き彫りになった演奏の1つがこのトラックである。米国50年代の黒人達のジャズに親しんでいる人が聴けば、もしかしてソニー・クラーク(SONNY CLARK)の蘇りか? とさえ思うのではないだろうか。哀愁のハードバップ/ファンキー・フレーズが実によく板に付いている。ここではバルカンは抜きだ。 | ||||||||
| 3曲目「KORENI(コレニ)」。根っ子の意味。アル・アンダルース音楽やセファルディの音楽に関心のある人はもとより、地中海音楽に興味のある聴き手なら、ステファノフスキーのギターにハッとするに違いない。続くエルグネルのソロも含め、ほぼ即興演奏で構成されている。 | ||||||||
| 4曲目「CECEN KIZI(チェチェン・キジ)」は「トルコのモーツァルト」の異名のある歴史的な作曲家/タンブーリ演奏家のタンブーリ・ジェミル・ベイ(TANBURI DJEMIL BEY)の著名な録音から採取しアレンジしたものである。トルコ色濃厚のテーマから、バルカン・タフ・テナー調でアグレッシヴにブロウするルロのイマジネーションは素晴らしい。それを受けて、おれはこうだとメロディックな展開を繰り広げるボヤンZの遊び心。 | ||||||||
| 5曲目「GRADINO KORO(グラディーノ・コロ)」はセルビアの古典舞踊曲で、親戚のおじさんグラーダから教わった曲を2ビートでセルビア風のスイング・ナンバーにアレンジしたもの。ストライド・ピアノ奏法もとりまぜ、さらに小粋なモダン・リリカル・スイングにまで展開する。するりと変容する様はマジックを見ているみたいだ。この辺の小技にも注意していると、ボヤンZの1曲の演奏は何度聴いても発見がある。 | ||||||||
| 6曲目「SVETI BOZE(スヴェティ・ボージェ)」は「主よ」の意味。この曲は14世紀セルビア正教の僧侶が修道院の詠唱用に作ったものとのこと。ボヤンZいわく、 | ||||||||
| 「厳しい戒律があって楽器で演奏してはいけないけど、僕らは信仰心が欠けてるからやってしまった。ヴォインの勧めでとり上げた」。 | ||||||||
| ルロの激しいグロウルを効かせた即興演奏も不謹慎(!?)だが、スーフィーとかかわりの深いエルグネルがこの曲で即興するというのもすごい状況である。 | ||||||||
| 「実は、この曲をCDに入れる入れないで、プロデューサーともめたんだ。プロデューサーは入れたくなかった。僕は、本当に生きた混血(メティス)文化が欲しいのなら、まさにこれじゃないか、と懸命に力説した。なんとか納得してもらえて本当によかった。このCDで一番重要な意味をもつ曲がこれだから。音楽は国境や宗教やイデオロギーさえも超えることができることの証明の1つだと自分では思っている。音楽は閉じたままではありえない。いちど歌い奏でたものは、もはや誰か特定の所有物でもない。どこの誰が歌い奏でたものでも、誰にでも届く可能性があるということでもある」 | ||||||||
| 7曲目「THE JOKER」はテナーサックス・バトル。親友ルロが自分のグループ活動で忙しいとき、見込んで代役でギグに起用していたのがヴァンサンである。オリエンタル、しいていえば「チェチェン・キジ」に通じるトルコ調で、推進力のあるハードドライヴィングな掛け合いを両立させるという趣向を成功させている。 | ||||||||
| 8曲目「ZULFICAR-PACHA(ズルフィカル・パシャ)」はZ家のご先祖に捧げた曲目だが、曲自体はマケドニア調が濃い「テシュコロ・オロ」、ヘヴィー・ダンスの意味、とのこと。タパンという太鼓をスティックで叩きながら踊るのがオリジナルである(8分の7拍子)。新作『XENOPHONIA』の「ZEVEN」でこの曲の継承的な演奏が聴かれる。 | ||||||||
| 9曲目「CD-ROM」。タイトルは言葉遊びである。ベオグラードにはロマ(ROMA)によって海賊版CDのブラックマーケットが張り巡らされており、路上屋台でCDを売るロマをベオグラードではCD-ROMと呼ぶそうだ。自分のCDも売られていて、嬉しいやら腹立たしいやら、とか。曲自体はルーマニアの舞踊曲の一種でセルビアの東地方にもあるリズム・パターンをニューオリンズ・スタイルと合体させたもの。 | ||||||||
| 「僕はバルカン伝承フォーク音楽にとてもスイングを感じる。アメリカのジャズを知っていく中で、いろんな時代のスイングのありかたも知った。どちらのスイングのありかたも好きだから、両方をパラレルにあしらってみたわけなんだ」 | ||||||||
| 10曲目「SRTCHA(スルチャ)」。 | ||||||||
| 「午前3時から4時頃のベオグラードの酒場のムードを出したかったんだ。むこうで暮していたときはしょっちゅうその中で過ごした。スルチャは割れたグラスのこと。飲んでご機嫌になって議論して、グラスを割ってまた飲んで、音楽が始まって、というのがベオグラードの習慣なんだよね。だから明け方になると床中割れたグラスだらけ(笑)。この曲の頭と最後にくるテーマはすごくノスタルジックなものにして、中間部はがやがや騒いでる。マイ・ジューリアンネーなんて歌っているのは、戦場へ行く男を送りだす古いフォークソングで向こうではお馴染みの『マイ・ミラネ』(いざ行かん)なんだ。サックス吹きながら、ガラス瓶割って騒がしい音を出しているジュリアンに、いざ行かん、ジュリアーネ! てなもんでね(笑)。ジュリアンはそのへんよく知っているから、頼んでもいないのにワインを買いに行って瓶を用意してたね(笑)」 | ||||||||
| このCDアルバムは、1999年3月24日にリリースされた。その前日の23日に行われたリリース・パーティ・コンサートに録音メンバーが全員揃った。その前日の22日にはコソボ紛争の政治的解決が成果を見ないまま打ち切りになり、アメリカ合衆国が中心になったNATO軍がユーゴ空爆を開始したばかりだった。 | ||||||||
| 「旧ユーゴのアーティストたちはフランスでライヴをするという名目があってヴィザの問題は解決していたとはいえ、かろうじて出国できた。皆、奥さん、ご家族を連れてきた。コンサートは話題になってTV局が取材にきて、インタビューが行われた。折も折りで、反ミロシェヴィッチ発言みたいなことを言わせたかったんだろう。僕の両親がベオグラードにいたので、そんなことを言ったが最後、両親に何が起きるかわからないので、多くのことは言えず、引き裂かれるような思いをした。しかし、ステージには、アルバム・ブックレットの中程にある写真を掲げて出身地を記し、ここには政治家には難しいことが実現されているということを示した。音楽ではそれが可能なのだと」 | ||||||||
| 空爆下のベオグラードへ帰るヴォイン・ドラスコシに『KORENI』のCDを託し、当地の両親や知人たちが聴き喜んだ。特に「スルチャ」が大いに受けたという。 | ||||||||
| 「空爆はあたりをぶちこわして人の心を縮めるけど、スルチャは笑い死にするくらい気持ちを大きくさせた。音楽は空爆の10倍以上の効果があるんだね。このとき以上にミュージシャンでよかったなと感じたことはないよ」 | ||||||||
| 11 | 戦争について |
|||||||
| 「戦争(旧ユーゴ解体、内戦、コソヴォ紛争と続いた10年間)は非常に辛い思い出として、自分の中に残っている。僕はアンチ軍隊、アンチ戦争だ。しかし、セルビアにいたときは徴兵制度があって応召しなければならなかった。軍隊経験のあるジャズ・アーティストはそうはいないよね、きっと。そんな経験もしているから、はっきり言えるんだが、軍服、軍隊、戦争に関連することすべてに対して嫌悪感を覚える。あのときユーゴで起きたことだけではなく今世界でも起きている戦争に対し怒りを感じるし、愚の骨頂であるとしか言えない。自分の人生において探しているものの対極にあるのが戦争であり軍隊だ。そこからインスピレーションを受けて音楽を作ることはなかったが、10年間もつづいた戦争によって、沢山の悲しみ、憂鬱、憎しみ、心配、不安、いろんな感情が起こった。それをポジティヴな方向に変えていこうと、当然思ったりした。戦時下では人間は寛大さを失うと思う。自分もより攻撃的になったりしたことがある。愚かだった。現在、旧ユーゴの構成国を統治している人間達が、前から権力をもっていた人たちと変わりがないので、一体なんなのだと思わざるを得ないというのが正直な気持ちだ。自分は発言力のある有名人ではないが、メディアで発言することもあるので、違うと思ったことははっきりノーと発言することにしている」 | ||||||||
| 12 | バルカン・ジャズ第2章突入 |
|||||||
 |
BOJAN ZULFIKARPASIC / SOLOBSESSION (LABEL
BLEU LBLC 6624) - BOJAN ZULFIKARPASIC (piano) - 1. FINGERING
(BZ), 2. WHO'S BOB (BZ), 3. MULTI DON KULTI (BZ), 4.
SOLOBSESSION (BZ), 5. DON'T BUY IVORY, ANYMORE (Henri
Texier), 6. TOUT NEUF (BZ), 7. ZULFIKAR-PACHA (BZ), 8.
VALSE HOT (Sonny Rollins), 9. MOTHERS OF THE VEIL
(Ornette Coleman), 10. UCI ME MAJKO, KARAJ ME - BZ= Bojan Zulfikarpasic's composition -recorded on November and December, 1998 |
1998 | ||||||
| ボヤンZは自分のグループでコンサートも続けながら、巨匠アンリ・テクシエのアズール・グループにとって欠くことのできないピアニストとしても活躍を続けてきた。アズールでのアルバムは『AN INDIAN'S WEEKA』の他、『MOSAIC MAN』(LABEL BLEU LBLC 6608)*2、『STRINGS' SPIRIT』(同
LBLC 6648/49)*3 もある。その他、巨匠ミッシェル・ポルタルの『DOCKINGS』(同 LBLC 6604)*4 における演奏も大きな話題となった。 (*=文末にデータ掲載) |
||||||||
| また、1995年アミアン・ジャズ・フェスティヴァで初めてソロ・ピアノを経験して以来、ソロのステージが増えていった。ソロの場数を重ねた成果は、『SOLOBSESSION(ソロブセッション)』(同 LBLC6624)で披露された(2001年発表)。 | ||||||||
| ボヤンZがバルカン・ジャズという文脈で素晴らしい成果を挙げることが出来た理由の1つとして、並外れたリズム・センスを含む特上の演奏能力、豊かなハーモニー・センスも特記しないではすまされない。また、オリジン・リサーチの成果という見地を離れて、ジャズ語法は如何ほどかという見方をしたとき、豊富な蓄積があり、それもジャズ博士と呼びたいほどのレヴェルにあることは既に述べたが、『SOLOBSESSION』によって改めて明白な了解事項になったと言える。 | ||||||||
| 「バルカンの要素は自分の中に根源としてあるものだから、出そうとしなくても自然に出てきてしまう。特にソロ・ピアノの場合には、共演者のいる場合よりも無意識かつ強く出てきてしまう。しかし、バルカン音楽の専門家といったレッテルを貼られてしまうのも嬉しくないから、あえて、バルカン音楽の要素ばかりが前面に出ることがないような音楽を作ろうとした。今では、バルカン音楽だけではなくて、モーリタニアのフォーク音楽などのアフリカ音楽、アルジェリアなどの北アフリカの音楽も重要な要素として自分の中に組み込まれている。そういった全てを対等に出していきたくて出来たのが『ソロブセッション』なんだ」 | ||||||||
| 『SOLOBSESSION』にはジャズのクラシックス、モダンジャズ、カリブ音楽、アフリカ音楽、スパニッシュ音楽、アラブ中東音楽、現代音楽、そしてもちろんバルカン音楽が去来する。しかも、気宇壮大なヴィジョンも感じさせる。 | ||||||||
| 冒頭の「FINGERING」では、ピアノの内部の弦にタッチしながら演奏開始し、サワリの効いた音と断片的な感じのリズムがうごめいている。その中から汎調的な不思議なハーモニーが生まれる。これはアルバムの序章的意味だけではなく、強い欲求に基づいたものだったようだ。胎動といえるトラックである。 | ||||||||
| 2曲目「WHO'S BOB」でようやくメロディとなって結実し、リズムとシンプルな和声を伴い、ボヤンZ色が浮かび上がってくる。以降、多彩な趣向が現れる。様々なリズムやメロディや和声を生成しながら、カレイドスコープを覗き見るような鮮やかさを印象づけるが、奇を衒ったという印象はなく、むしろ、古今ジャズと称された演奏の中で聴いたことがあるようなデジャヴュ感を覚える。その象徴的な曲がアルバム表題曲「SOLOBSESSION」と言えるだろう。セロニアス・モンク(THELONIOUS MONK)とバド・パウエル(BUD POWELL)の曲がブレンドしたような始まりから、カリブ風、アフロ風、スパニッシュ風、アラブ音楽風、ドビュッシー風、バルカン風、初期ジャズ・ピアノ・スタイル等が違和感なく連結されている。言ってみれば、ジャズの染色体構造を示したような演奏だと思う。 | ||||||||
| 鎮魂歌のように聴こえる「TOUT NEUF」の哀しさはどうしたことだろう。響きは誠に優美だが、愁いが深い。 | ||||||||
| 「ZULFICAR-PACHA」は再録音である。マケドニア色が地色の曲だが、今回はアラベスクとも言えそうなアレンジである。 | ||||||||
| 再録となった「MULTI DON KULTI」はドン・チェリーへの捧げもの。 | ||||||||
| 「MOTHERS OF THE VEIL」は、北アフリカのモロッコのジュジューカの音楽家たちに共感したフリージャズの巨匠オーネット・コールマン(ORNETTE COLEMAN)の曲だが、この上なくソウルフルでブルージーに、なおかつリリカルにアレンジしたもの。 | ||||||||
| 愛らしいメロディの「VALSE HOT」はモダンジャズの巨匠ソニー・ロリンズ(SONNY ROLLINS)の曲。この仕込みはなかなかわからない。 | ||||||||
| 「ワルツというと3拍子だけど、それを4拍子に変えて、シャハビーというモロッコの音楽の中ではポピュラーなリズムを思わせるようにアレンジにしてみたけど、どう? テーマは変わらないけど、ちょっと違ったスイング感になってないかな」 | ||||||||
| ボヤンZのやることは、すべてこの調子である。みんなでBZネタ研究会を作ってわいわいできたらどんなに楽しいだろう。 | ||||||||
| 「DON'T BUY IVORY, ANYMORE(象牙は買わないで、もうこれ以上!)」はアンリ・テクシエ作。ボヤンZは『AN INDIAN'S WEEK』でこの抒情的なワルツ曲を初録音した。今回は目を見張るほどの美しい響きを導きだし、前以上にリリカルな解釈をして名曲をさらに忘れがたいものにした。 | ||||||||
| アルバムの最後は、哀切な美旋律のマケドニア民謡「UCI ME MAIKO, KARAJ ME(ウチメ・マイコ・カーライメ)」。曲名の意味するごとく「母さん、人生とは何か教えてください」と凛々しく訴えるようなこの演奏に、この書き手は胸が張り裂けそうになるほど鮮烈な美的情調を感じる。 | ||||||||
| かくして、ジャズのクラシックス、モダンジャズ、カリブ音楽、アフリカ音楽、スパニッシュ音楽、アラブ中東音楽、現代音楽、そしてもちろんバルカン音楽が去来する画期的なジャズ・ピアノ・ソロ・アルバムの誕生をみた。 | ||||||||
| 13 | 評価/受賞 |
|||||||
| エスニックなオリジンとジャズを融合したジャズ作品は今や世界中で珍しくない。スラヴ系ないし東欧、旧ソ連/ロシアのジャズ・ピアニストでは、ブルガリア出身のミルチョ・レヴィエフ(MILCHO LEVIEV)やアントニイ・ドンチェフ(ANTONY DONCHEV)、ルーマニア出身のミルセア・ティベリアン(MIRCEA TIBERIAN)、ウクライナ出身のミシャ・アルペリン(MISHA ALPERIN)、アルメニア出身のアルタシェス・カルタリヤン(ARTASHES KARTALIJAN)、アゼルバイジャン出身のヴァギフ・ムスタファ=ザデ(VAGIF MUSTAFA-ZADE, 故人)、その娘さんのアジザ・ムスタファ=ザデ(AZIZA MUSTAFA-ZADE)といった魅力的なジャズ・ピアニストが思い出される。しかし、ボヤンZのように複合的なオリジン解釈を真摯に示唆し、良い意味で波紋を招くケースは珍しいと思う。ボヤンZの他には、セファルディ音楽/スパニッシュ音楽、ジェリー・ロール・モートン、セロニアス・モンクなどを併置し、独特の洞察によりリンクさえ浮かび上がらせた米国のアンソニー・コールマン(ANTHONY COLEMAN)のトリオ・ユニット「セファルディック・ティンジ(SEPHARDIC TINGE)」の諸作など少々しか思い当たらない。ボヤンZの『KORENI』はそれらと共に、いつしかジャズの歴史的重要作/名盤として繰り返し振り返られることになるのではないかという気がする。また、『SOLOBSESSION』は特上の演奏と独特の着想によってソロ・ピアノ表現に新しい地平を拓いたアルバムとして歴史に残るだろう。フランスは、2002年ボヤンZにシュヴァリエ芸術文学勲章を授賞している。ジャズ界も毎年恒例のジャズ・アカデミー賞のジャンゴ・ラインハルト賞に選出し表敬した。最近では、オーストリアの権威あるジャズ賞であるハンス・コラー賞を2005年に受賞した。 | ||||||||
| 14 | 初めてのピアノ・トリオ作アルバム |
|||||||
 |
BOJAN Z TRIO / TRANSPACIFIK(LABEL BLEU LBLC 6654) - BOJAN ZULFIKARPASIC (piano, Fender Rhodes), SCOTT COLLEY (bass), NASHEET WAITS (drums) - 1. SET IT UP (BZ), 2. THE JOKER (BZ), 3. FLASHBACK (BZ), 4. RUN RUNE, RUN! (BZ), 5. BULGARSKA (Based on “Tche da ti kupim bela seitsa”, Bulgarian trad.), 6. Z-RAYS (BZ), 7. GROZNJAN BLUE (BZ), 8. SEPIA SULFUREUX (BZ), 9. NINER (BZ), 10. PURPLE GAZELLE (ANGELICA) (Duke Ellington) - BZ= Bojan Zulfikarpasic's composition -recorded on June 13, 15 & 16, 2003 |
2003 | ||||||
| 5作目のリーダー作『TRANSPACIFIK(トランスパシフィック)』(LABEL BLEU LBLC 6654/2003年発表)は初めて米国のジャズ・ミュージシャンと一緒に録音したアルバムであり、初めてのピアノ・トリオ・アルバムである。スコット・コーリー(SCOTT COLLEY, ベース)、ナシート・ウェイツ(NASHEET WAITS, ドラムス)とのトリオ編成による。今回、ブルガリアの伝承曲1曲とエデューク・エリントン(DUKE ELLINGTON)の1曲以外は全てオリジナルである。 | ||||||||
| 1曲目「SET IT UP」はとてもリラックしたリズムの、いわばニューオリンズ・タッチの曲想で、フェンダーローズと生ピアノの両刀使いの演奏である。フェンダーによるソロはとてもファンキーかつグルーヴィ。 | ||||||||
| 2曲目「THE JOKER」は『KORENI』が初出の曲。トルコ=バルカンの色合いの勇壮なテーマを力強い打鍵で呈示するときドラムスが多彩なリズムのヴァリエーションで絡む。このリズム的な面白さが維持される中で、緩急をつけてスピード性、リリカル性の両方を織りまぜるという趣向である。この曲をはじめとしてウェイツにもコーリーにも積極的なインタープレイを求めたと推量される演奏がこのアルバムに多い。 | ||||||||
| 愁いの勝ったバルカン調メロディの3曲目「FLASHBACK」。 | ||||||||
| 4曲目「RUN RUNE, RUN!(ラン・ルネ・ラン)」は、言ってみれば急速バルカン・ビーバップ&クールジャズ・アンド・ビヨンド(本人もその形容に同意してくれた)。ウェイツのドラミングは自在で、スコット・コーリーの低音はツボを押さえつつ積極性もある。コーリーはきわめて売れっ子で、スタジオ入りする前日に初めて顔を合わせたというが、そんなことはまったくわからない充実の演奏になっている。しかも1テークで済んだ曲が多く、この「RUN RUNE, RUN!」もその1曲とのこと。 | ||||||||
| このあとボヤンZの詩情の豊かさ、抒情性の深さを再度深く認識できる演奏が続く。 | ||||||||
| まず「BULGARSKA(ブルガルスカ)」は、「Tche Da Ti Kupim Bela Seitsa(チェ・ダ・ディ・クピン・べラ・セイツァ)」(「絹にシミをつけました」の意味)というブルガリアの伝承曲を下地にしたバラード演奏。素朴な哀愁表現であるが、味わいは深い。 | ||||||||
| 「Z-RAYS」の演奏中、この男はバルカンを南下し地中海へ出てイベリアを訪ねモロッコ、アルジェリアへも飛ぶ、というように空想上の周遊をしていたのではないか。その当否はともかく、なんて心を打つメロディを書ける男なんだ。しかもファンタジックな和音を、これみよがしに聴かせるのではなく、そっと差し出すのである。 | ||||||||
| しみじみしていると、さらに押し寄せる波。形容しがたいほどの美しさをもつ「GROZNJAN BLUE(グローズニャン・ブルー)」である。これにはきっと深い思いが込められている違いないと、本人に探りを入れた。 | ||||||||
| 「グローズニャンは、イタリアとの国境にあるクロアチアの村の名前だ。自然に満ちた素敵なところで、かつて80年代にここでジャズのサマーセミナーが行われていたことがある。僕が初めて参加したジャズの研修はここでのものだった(1984年)。ジャズについて学び始めたスタート地点と言えるんだ。その後、戦争があったりしてクロアチアにはめっきり足が遠のいていた。1996年久しぶりに夏に訪ねてみたら、むかしの面影はまったく無くなっていた。といっても、村の素敵な自然はそのままなんだ。しかし、むかしならアーティストたちが村中にあふれていた。アーティスト同士のエネルギー、アイディアの交流があった。歩きながら哀しみが湧いた」 | ||||||||
| 収録曲は他に、愁いと期待が相半ばする心情を描いたようなバラードの「SEPIA SULFUREUX」、リズムの変則的な面白さと軽快スイングを両立させた「NINER」そして、最後に独特のゴージャスなハーモニーとソフィスティケーディッド・メロディをパワフルな鍵盤タッチで飾ってデューク・エリントンへ捧げた「PURPLE GAZELLE (ANGELICA)」。 | ||||||||
| 15 | バルカン・ジャズ第3章突入 |
|||||||
 |
BOJAN Z / XENOPHONIA (LABEL
BLUE LBLC 6684) - BOJAN ZULFIKARPASIC (piano, Feder Rhodes, Xenophone), REMI VIGNOLO (bass), ARI HOENIG (drums on 2,3,4,8 & 10), BEN PEROWSKY (drums on 1,5,6,7 & 9), KRASSEN LUTZKANOV (kaval on 1 & 9) - 1. ULAZ (BZ), 2. ZEVEN (BZ), 3. WHEELS (Bojan Z-R.M.Tocak), 4. BIGGUS D (BZ), 5. ASHES TO ASHES (David Bowie), 6. PENDANT CE TEMPS, CHEZ LE GENERAL...(Bojan Z-Remi Vignolo-Ben Perowsky), 7. XENOS BLUES (BZ), 8. THE MOHICAN AND THE GREAT SPIRIT (Horace Silver), 9. CD-ROM (BZ), 10. IZLAZ (BZ-Ari Hoenig) - BZ= Bojan Zulfikarpasic's composition -recorded on December 2004 (1, 5, 6, 7 &9), and July 2005 (2, 3, 4, 8 &10) |
2004/5 | ||||||
| 2006年、不思議なタイトルの『XENOPHONIA』(LABEL BLEU LBLC 6684)発売。ドラマーには米国の売れっ子のベン・ペロウスキ(BEN PEROWSKY)またはアリ・ホーニク(ARI HOENIG)、ベースにはイタリア出身でフランスで活躍しているレミ・ヴィニョーロ(REMI VIGNOLO)。彼らとのトリオ編成を基本に、2曲にブルガリア出身でパリ在住のカヴァル奏者クラッセン・ルツカーノフ(KRASSEN LUTZKANOV)が参加している。カヴァルはすでに紹介したようにトルコの伝統管楽器ネイと同系のメカニズムの楽器である。今回はフェンダーローズが積極的に使われ、それもかなり変化に富んだ音を出している。また Xenophone という楽器もクレジットされている。これはアルバム・タイトル、ひいてはアルバム・コンセプトと連動しているようだ。 | ||||||||
| アルバム・タイトル XENOPHONIA(ゼノフォニア、フランス読みではグゼノフォニア)は医学用語で「声変わり」のことを指す。実際にCDでフェンダーローズの変わった音色を聴けば、なるほどとすぐピンとくるだろう。「別の」を意味する Xeno に、phone、phonogenic などの音を連想させる phonia がくっついているのですね? | ||||||||
| 「まあね。今回フェンダーローズは2種類使った。1つは通常のモデルで、もう1つは、まだ開発途上だけど自分用に調整したフェンダーで、それをグゼノフォン(xenophone)と呼んでいる。通常と違う調律の鍵盤楽器があったらなあと、長年思ってきたんだ。しかし生ピアノでは無理がある。偶然も手伝って良い感じで変わった音が出せるようになったんだ。イーヴンではない音が出せているでしょう」 | ||||||||
| 「WHEELS」と「XENOS BLUES」で弾いているフェンダーローズはこの xenophone だけとのことである。なるほど、フェンダーローズが変声期を迎えたような変わった音がする楽器である。 | ||||||||
| しかし、アルバム・タイトルは、声変わりとか変わった音のことだけを言っているのではない様子だ。 | ||||||||
| 「ふふふ。このタイトルには少なくとも3つの意味を込めているつもり」 | ||||||||
| と、ニヤリとするボヤンZ。全曲を辿りながら考えてみよう。 | ||||||||
| 今回のレパートリーにはバルカン方面の伝承曲こそないが、カヴァル奏者を起用したことから、今回もオリジン表出の意欲が依然続いていることを表明しているも同然であるし、実際、各曲の演奏の中にオリジンの表出を随所にみることができる。 | ||||||||
| 1曲目「ULAZ(ウラズ)」。曲名(「入り口」の意味)の通り、しばしばコンサートのオープニングに使う曲で、チューニングも兼ねてリラックスして入っていくための曲とのことである。どこかのアフリカのローカル・リズムにも聴こえるようなパターンの向こうにカヴァルの音の淡いベールがミステリアスに浮遊する中から、凛とした生ピアノが立ち上がるが、やがて内部弦に触れることでアフリカ楽器のようにも、さらにオリエンタル楽器のようにも変容する。メロディはもう、どこそこ的と指摘するのはナンセンスという感じだ。 | ||||||||
| 2曲目「ZEVEN」。オランダ語の「7」は、この曲のリズムを指している。このゴキゲンなリズム・パターンのルーツは? | ||||||||
| 「これはアルバニアのジプシー・シンガー、キタ(Qita)のレコードを聴いていてインスパイアされて出てきたリズム・パターン。そしたら自然にメロディとハーモニーが湧いてきた」 | ||||||||
| かつて録音した「ZULFICAR-PACHA」「NINER」のように、フォービートにはまらないが軽快にスイングするというリズムのプレゼンテーションの曲である。このタイプの曲は、バルカンの伝統的な舞踊曲に親しんだ者なら普通に出てくる発想であろう。バルカン・ジャズということではボヤンZの先輩格と呼べるブルガリア出身のミルチョ・レヴィエフ(MILCHO LEVIEV, ピアノ)の例を思い出す。かつてレヴィエフが米国へ移住して間もない頃に所属していたドン・エリス・オーケストラでは、レヴィエフのフィーチュアリング・ナンバーとして33拍子の曲をウルトラ級の快速でしかもダイナミックにスイングしながら演奏していた。そのあまりにも軽快で朝飯前な感じは肉体感を伴っており、踊りのステップと不可分のものがあると想像される。幼少時からユーゴの民族/民俗音楽を浴びていたボヤンZもそういう派手な演奏もできないことはないのだろうと、この7拍子で軽快にスイングする曲を聴きながら思う。 | ||||||||
| 3曲目はグゼノフォン大活躍の「WHEELS」。アフリカ+スラヴ+オリエンタル風味ファンクといった曲趣だが、ここにはセルビアのロック・バンド「シュマク(SMAK)」のリーダーでギタリストのラドミール・ミハイロヴィッチ・トチャク(RADOMIR MIHAILOVIC-TOCAK)への表敬挨拶が込められているとのこと。 | ||||||||
| 「子供のときしょっちゅう聴いた曲を思い出してインスパイアされた。『ZASTO NE VOLIM SNEG』というアルバムに入っている曲『MAHT-PUSTINJA』でね。彼はストラトキャスターでクレイジーに弾いていたよ」 | ||||||||
| 4曲目「BIGGUS D」というタイトルは、去年ずっと観ていたモンティ・パイソンの映画『THE LIFE OF BRIAN』にちなんでいるという。破天荒な先行きのわからない感じが遊戯的で偶然的にも聴こえるが、その実、リズムから何から手が込んでいて高度な演奏である。 | ||||||||
| 5曲目「ASHES TO ASHES」はデイヴィッド・ボウイ(DAVID BOWIE)の往年のヒット曲である。珍しい選曲例である。クール、ヒップ、それでいて暖かいのがボヤンZの音楽である。 | ||||||||
| 「むかし愛聴した曲というわけではないけど、なぜか心に残っていて思い出した。これは亡くなった父への捧げものなんだ。去年6月、父の遺灰(ash)をアドリア海へまいたよ」 | ||||||||
| 6曲目「PENDENT CE TEMPS, CHEZ GENERAL…」は閃きとシャープな反応が楽しめる即興演奏。下準備ゼロ。こうした高性能の感度、機敏な展開能力がなければ、フランスの巨匠連には器用されなかったはずである。 | ||||||||
| 7曲目「XENOS BLUES」もグゼノフォンがフィーチュアされた曲。 | ||||||||
| 「グゼノフォンのサウンドから必然的にブールスを演るという考えが生まれた」 | ||||||||
| これはミシシッピ・デルタへの賛歌といえる演奏で、ダウンホームかつグルーヴィ。こんなにディープに踏み込んだブルースタッチの演奏はボヤンZの録音物の中では例外的だ。しかし、ベオグラード時代にはブルースにどっぷりハマった時期がある。彼の愛聴盤『黒人の刑務所ブルース&歌唱集』(著名な音楽学者アラン・ローマックス編)からサンプルした歌声も入れている。 | ||||||||
| 8曲目「THE MOHICAN AND THE GREAT SPIRIT」は「ファンキー・ジャズ」の代名詞のようなジャズ・ピアニストのホレス・シルヴァー(HORACE SILVER)による、アフロ・カリビアンなテイストのジャズ・ナンバーである。 | ||||||||
| 「ホレス・シルヴァーの曲はどれも大好きだ。特にこの曲だね。8分の9拍子の良い感じ。簡潔にして、なんて美しいメロディなんだろう!」 | ||||||||
| 9曲目「CD-ROM」は『KORENI』が初出の、バルカンのリズム・スタイルをニューオリンズ・スタイルと合体させて生まれたオリジナル。 | ||||||||
| 「今回は、ベン・ペロスキの軽快なドラムのシャッフルはゴキゲンでしょう!」 | ||||||||
| その通りだが、カヴァルのクラッセン・ルツカーノフの超絶的なテクニックにはくらくらする。 | ||||||||
| 「クラッセンのブロウは空高く舞いあがってるよね! 大好きだ。彼の人間性も大好きなんだ」 | ||||||||
| カヴァルの超絶技巧といえば、ブルガリアの国民的ヒーローのテドシイ・スパソフ(THEODOSII SPASSOV)の名人芸が名高いが、このボヤンZのアルバムを通じてルツカーノフの名前も広まるだろう。彼は主に伝統音楽のフィールドで活動しているが、音楽的素養は幅広いという。そして何よりも即興演奏が上手いところを高く評価しているという。 | ||||||||
| 10曲目「IZLAZ(イズラズ)」(出口の意味)。愛くるしさと気紛れが交錯する演奏だ。子供がおとぎ話の絵本にわくわくするうちに夢の世界へ入っていった、みたいかな。そんなプリティな曲想だが、これも下準備なしの即興演奏の中の一部とのこと。 | ||||||||
| 最新作『XENOPNONIA』もまた、ボヤンZの豊かな洞察力と、それを音楽化してしまえる能力があいまった作品と言うことができると思う。バルカン(スラヴ、オリエンタル、地中海他の混交という意味で)音楽とジャズには共通点が多く、ジャズにはアフリカ黒人の歴史(アフリカ、カリブ、ラテン・アメリカ、ニューオリンズ他の混交という意味で)が反映されているという発想の連鎖・循環が今も機能しているようだ。今回ボヤンZは、バルカン・オリジンの表出にあたっては、どこそこの伝承曲の旋律を借用したり、誰かの録音ヴァージョンを参照したりということがない。そういう方法をとらないでも、バルカン性は出せるもの/出てくるものであることを、納得できる演奏である。 | ||||||||
| 経験と思考の蓄積が増えることを人間は成長と称する。男の子が変声期を迎えるのは思春期の頃、つまり子供から大人への成長期と言えるかも知れない時期である。XENOPHONIA というタイトルは、まさに言い得て妙だと思う。これが2つ目の意味ではないか。つまり、また新たな指向、いわば第3次バルカン・ジャズの成長記録のようなもの、と呼んでいいアルバムではないかと考える。この書き手は当の本人にそう伝えた。 | ||||||||
| 「ふふふ。まあ、なんというか、XENOPHONIA という言葉は最初ジョークみたいに使っていたものなんだ。ストレンジ・サウンド(strange sounds)とかストレンジャーズ・サウンド(stranger's sounds)とかって意味で。しかしいつしか自分の人生と関連している言葉かなと思うようになった。僕はフランスにきてもう長い。フランスに来てから、音楽活動の面でも、生活面でもいろいろ岐路があった。フランスはよく僕を受け入れてくれたと思う。エンターテイナーとしてではなくアーティストとして扱ってくれた。フランスは、外国/外国人とのコミュニケーションの容易さという点でとても優れている国ではないかと思う。しかし、自分は100パーセントフランス人なんて思ったことがない。郷里のベオグラードへ戻ったときでも同じで、100パーセントセルビア人と思ったことはない」 | ||||||||
| どっちにいてもストレンジャーということか。 | ||||||||
| 「しかし、どうだろう、どこにいたって、自分を保っていれば、気が楽じゃないかな」 | ||||||||
| XENOPHONIA は、「外国人嫌い」を意味する言葉 xeonophobia(ゼノフォビア)を連想させもする。そこはいくらか意識的であることが上記の発言からうかがわれる。しかしその字句通りの意味で取るのはヘマである。 | ||||||||
| 「今、僕は中間地点に来ていると思う。新しい出会いがあって再婚し、3人目の子供の父親になった。妻はオランダ人だ。子供達はオランダとユーゴスラヴィアのハーフ、フランス人の前妻とユーゴのハーフ。こんな家族がフランスの家の中で暮らし、いくつもの言葉が飛び交っている。マルチカルチャーな、ヨーロッパを象徴するような家庭ではないかな(笑)」 | ||||||||
| マルチカルチャーこそボヤンZのバルカン・ジャズの性格を示すものだ。人間の出自を説明するものの1つに国籍がある。現在の国籍というものは、陸続きのヨーロッパにおいては現代の国家体制間の約束事であるとも言える。大切なのは帰属意識ではないとこの音楽家は言いたいのだろう。音楽/ジャズ、その表面を誰がどんな言葉で仕分けても、根っ子では多かれ少なかれつながっている。ボヤンZのバルカン・ジャズ、その中でもアルバム『KORENI』がその明解な見本である。彼のバルカン・ジャズの推進は自分のオリジン・リサーチでもあったが、それは結果的に複数の xeno な自分との出会いでもあった、ということをこのタイトルから感じないではいられない。これが3つ目の意味だろうか。 | ||||||||
Additional recording data: |
||||||||
| * 1:
|
HENRI TEXIER / MAD NOMAD(S) (LABEL
BLEU LBLC 6568) - HENERI TEXIER (bass, oud, percussions, voice), JULIEN LOURAU (tenor and soprano saxes), FRANCOIS CORNELOUP (bariton and alto saxes), SEBASTIEN TEXIER (alto sax, clarinet), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano, synthesizer), NOEL AKCHOTE (guitar), JACQUES MAHIEUX (drums, percussions), TONY RABESON (drums, percussions) - 1. S.O.S. TIBET, 2. MAD NOMAD, 3. S.O.S. FANANTENAMA, 4. DEZARWA (FOR A.T.), 5. GO!, 6. S.O.S. DOUR, 7. ENTRAVE, 8. S.O.S. TAMASHEQ, 9. HAPPY HAOUSE, 10. RADIO BO, 11. BLASTED RATS, 12. S.O.S. HOZHO, 13.THE BAND OVER THE CLOUDS, 14.S.O.S. MIR - recorded in September and October, 1995 |
1995 | ||||||
| * 2:
|
HENRI TEXIER / MOSAIC MAN(LABEL BLEU LBLC 6608) - HENRI TEXIER (bass), SEBASTIEN TEXIER (alto sax, clarinet), GLENN FERRIS (trombone), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), TONY RABESON (drums) - 1. MOSAIC MAN, 2. THE LOST KIDS OF NAIROBI, 3. MR. FREEMAN, 4. FERTILE DANSE, 5. TWIGA AND PUNTAMILIA, 6. APE, DOG AND TIGER, 7. OUT OF THE LIGHTS (composed by Bojan Zulficalpasic), 8. CAP ESPERANCE, 9. HAPPY DAZE, 10. AWA, 11. RUSS AND JIM, 12. TOGO - recorded in September, 1998 |
1998 | ||||||
| * 3:
|
HENRI TEXIER / STRINGS' SPIRIT(LABEL BLEU LBLC 6648/49) - HENRI TEXIER (bass), SEBASTIEN TEXIER (alto sax, clarinet), GLENN FERRIS (trombone), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), TONY RABESON (drums) + ENSEMBLE DE CORDES DE L'ORCHESTRE DE BRETAGNE, STEFAN SANDERLING (conductor), CLAUDE BARTHELEMY (string arrangement) - disc-1: 1.
ARMOIRE DOG, 2. TONIC TONY, 3. SERIOUS SEB, 4. GLENN THE
SPACE, 5. DEZARWA (FOR A.T.), B.Z. THE BEE / - recorded on 8-12, April, 2002 |
2002 | ||||||
| * 4:
|
MICHEL PORTAL AZUR QUINTET /
DOCKINGS(LABEL BLEU LBLC 6604) - MICHEL PORTAL (B-flat clarinet, bass clarinet, alto sax, bandoneon), MARCUS STOCKHAUSEN (trumpet), BOJAN ZULFICALPASIC (piano), STEVE SWALLOW (el-bass), BRUNO CHEVILLON (bass), JOEY BARON (drums) - 1. BAROUF, 2. DOLPHY, 3. LION'S DREAM, 4. MUTINERIE, 5. NEXT, 6. SOLITUDES, 7. EMBROUILLE, 8.K.O., 9.TOURNIOLE, 10. IDA LUPINO, 11. ILLUSION IN BFLAT - recorded in June 1997 |
1997 | ||||||
 |
SYLVAIN BEUF QUARTET / IMPRO PRIMO
(MELODIE DK 016 40067.2) - SYLVAIN BEUF (tenor and soprano saxes), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), CHRISTOPHE WALLEMME (bass), STEPHANE HUCHARD (drums) - 1. LIKE SOMEONE IN LOVE, 2. PEDRO, 3. A TRAVERS LA FENETRE, 4. IMPRO PRIMO, 5. DELTA, 6. HONEY MOON, 7. BALLADE POUR ISA, 8. BLUES FOR FRIENDS, 9. STABLEMATES, 10. WALTZ FOR CLAUDE - recorded on May 10 & 11, 1993 |
1993 | ||||||
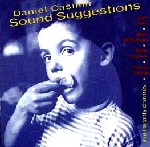 |
DANIEL CASIMIR / SOUND SUGGESTIONS
(CHARLOTTE RECORDS CR 172) - DANIEL CASIMIR (tenor sax), JULIEN LOURAU (soprano sax), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), HELENE KLABARRIER (bass), FRANCOIS MERVILLE (drums) - 1. PREACH ME, 2. REGENTAG DUNKELBUNT, 3. LES SATELLITES, 4. 2 A.M .JAMAICA, 5. CAPTAIN' KIRK - recorded live at the Instants Chavires, on April 13, 1993 |
1993 | ||||||
 |
JULIEN LOURAU / FIRE & FORGET
(LABEL BLEU LBLC 6670) - JULIEN LOURAU (tenor and soprano saxes), BOJAN ZULFIKARPASIC (Rhodes , CX3), ERIC LOHRER (guitar), VINCENT ARTAUD (bass), DANIEL GARCIA-BRUNO (drums), JOHN GREAVES (vocal on 2 &3), MALIK MEZZADRI (vocal on 2, 9 & 10), ALLONYMOUS (vocal on 4), MINA AGOSSI (vocal on 6), SEBASTIEN QUEZADA (vocal on 8 & 9) - 1. FIRE AND FORGET, 2. A STITCH IN TIME, 3. DON'T SAVE ME, 4. SOMETIME, 5. I'D RATHER NOT, 6. LA BOUCLE, 7. LISA ET FLAVIO, 8. RELAXIN', 9.GUANTANAMO, 10. MESSIEURS LES ANGLAIS, TIREZ LES PRENMIER! - recorded in June and October, 2004 |
2004 | ||||||
 |
JULIEN LOURAU / FORGET
(LABEL BLEU LBLC 6680/81) - JULIEN LOURAU (tenor and soprano saxes), BOJAN ZULFIKARPASIC (Rhodes , CX3), ERIC LOHRER (guitar), VINCENT ARTAUD (bass), DANIEL GARCIA-BRUNO (drums) - 1. LIZA ET FLAVIO, 2. DIASPORA, 3. I'D RATHER NOT, 4. COCHON CREOLE (SWING), 5. COLLARETAL DAMMAGE, 6. BIGGER THAN LIFE, 7. COCHON CREOLE (SWING), 8.HOPE, 9. COCHON CREAOLE (SWING), 10. COCHON CREAOLE (DUB), 11. VE-VOR - recorded in June and October, 2004 |
2004 | ||||||
 |
NGUYEN LE / MAGREB & FRIENDS
(ACT 9261-2) - NGUYEN LE (guitar), KARIM ZIAD (vocal, drums, percussions, gumbri), MICHEL ALIBO (el-bass), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), ALAN DEBIOSSAT (soprano sax), JEAN-JACQUES AVENEL (bass), MOHAMED MENNI (bendir), PAOLO FRESU (trumpet), WOLFGANG PUSCHNIG alto sax), STEFFANO DI BATTISTA (alto and soprano sax), HUOUNG THANN (vietnamese vocal), HAO NHIEN (vietnamese flute), and many others - 1. IFRIKYIA, 2. CONSTANTINE, 3.LOUANGES, 4. YHADIK ALLAH, 5. NORA, 6. FUNKRAI, 7. L'ARKHA LI JEYA, 8. GUINIA, 9. NESRAF - recorded during 1997-98 |
1997/98 | ||||||
 |
KARIM ZIAD / IFRIKYA (ACT
9282-2) - KARIM ZIAD (vocal, drums, percussions, gumbri, guitar, mandola), ABDELKBIR MERCHANE (vocal), MENNI MOHAMED (percussion), KHLIFF MIZIALLAOUA (guitar), NGUYEN LE (guitar), BOJAN ZULFIKARPASIC (piano), VINCENT MASCART (tenor sax), MICHEL ALIBO (bass), JEAN-PHILIPPE RYKIEL (synthesizer) and othersANN (vietnamese vocal), HAO NHIEN (vietnamese flute), and many others - 1. AIT OUMRAR, 2. YA RIJAL, 3. AWRA, 4. LEBNIA, 5. ALOUHID, 6. SANDIYA, 7. AMALIYA, 8. GWARIR, 9. THE JOKER (composed by BOJAN Zulfikarpasic), 10. NESRAFET - recorded in June and July, 2000 |
2000 | ||||||
| 註記 | 本稿は、最新アルバム『XENOPHONIA』の日本版(ビオデオアーツミュージック
VACB 1006)付録のブックレットのために着手されました。 ブックレットではページの都合でこの 2/3 程が掲載されています。 また、当ブックレットには、飯竹恒一著「ズルフィカルパシッチ 二重国籍者の貌」、天城桜路著「プリティ・フレンドよ、また会う日まで ベオグラード追想」、拙著「バルカン・ジャズを知るためのディスクガイド」も掲載されています。 数年越しの取材に優しく応じてくださったボヤン氏、長文を掲載してくださったビデオアーツミュージック(宮野川真氏)に心から感謝申し上げます。 |
|||||||
BOJAN A TO Z: Guide to the Balkan Jazz by Bojan Zulfikarpasic Biography and selected discography text by Toyoki Okajima |
||||||||



