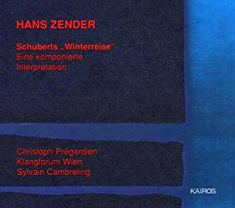| |
ハンス・ツェンダーの音楽「シューベルトの『冬の旅』」について

|
|
|
 |
ハンス・ツェンダーはこれまで日本ではあまり知られてこなかったが、ドイツを中心としてヨーロッパの音楽界では重要な役割を担っている指揮者/作曲家である。 |
|
| |
1936年の生まれで、フランクフルトとフライブルグの音楽大学で学んだあと、ボンとキールの州立歌劇場の主席指揮者・音楽監督、ハンブルク歌劇場の音楽総監督をつとめ、その後、フランクフルト音楽大学の作曲家の教授をつとめるとともに、ザルツブルク音楽祭、バイロイト音楽祭、ワルシャワの秋音楽祭、ウィーン現代音楽祭、ベルリン音楽祭などにたびたび招かれ、クラシックと現代音楽の双方の分野で信頼と名声を得ている。
|
|
| |
古典作品の演奏では、ハイドン、モーツァルトをはじめ、特にシューベルト、シューマン、マーラー、ドビュッシーなどを得意とする一方、バイロイト音楽祭ではワーグナーの『パルジファル』を振り、ベルリン・フィルでは尹伊桑ユン・イサンなどの現代作品の初演を手がけ、アンサンブル・モデルンなど現代音楽専門アンサンブルではツィンマーマンやフェルドマン、ジャチント・シェルシなど最尖端の現代音楽を演奏するというきわめて幅広い活動を行っている。 |
|
| |
作曲家としては、この『シューベルトの「冬の旅」』が話題になったほかは日本ではほとんど知られていないが、72年にミュンヘン・フィルハーモニーの日本公演に指揮者として同行して以来、日本や東洋の伝統文化に深い関心をもち、その影響のもとに書かれた『無字の経』や『オーケストラのためのカリグラフィ』などが知られている。前者は78年にNHK交響楽団で、90年には東京都交響楽団で自身の指揮により演奏されている。
ほかに『ヘルダーリンの詩(詩の朗読と弦楽四重奏)』やオペラ『ドン・キホーテ』などが知られている。 |
|
| |
さて、それではハンス・ツェンダーによる「シューベルト『冬の旅』」とはどういう音楽なのだろうか。 |
|
| |
この作品は1993年にフランクフルトで初演されているが、おそらくシューベルトの原曲を聴き慣れた人びとには相当の衝撃を与えたにちがいない。詩のことばも歌の旋律もほとんど変わっていないけれど音楽の様相がまったく変わっていたからである。 |
|
| |
2002年の「東京の夏音楽祭」で日本初演されたときの新聞評には、「不協和な音響が到るところ加味される。『冬の旅』に善良な市民の心の安寧を求めようとする聴き手を嘲笑うように。」という表現があった。だが、ツェンダーは『冬の旅』を難解なものにしたり解体したりしようとしているわけではない。この作品の副題が
"A Composed Interpretation"とされているように、これは単なるオーケストラ編曲という以上に(日本盤CDでは「創造的編曲」と訳されている)、シューベルトを深く愛していると自ら語るツェンダーの『冬の旅』についての解釈を作曲というかたちで表現したものなのである。では、その解釈とはどういうものなのか。 |
|
| |
シューベルトの歌曲「野ばら」や「菩提樹」「セレナーデ」、あるいは「辻音楽師」なども、昔から日本でも教科書に載せられ広く親しまれている。遙かなものへの憧れ、優しく美しい夢を描いたロマン主義の作曲家――、シューベルトは多くの人からそのようなイメージで捉えられてきたはずだ。しかし、その「菩提樹」や「辻音楽師」を含む『冬の旅』をよく聴いてみよう。なんという寒々とした音楽なのだろうか。ウィルヘルム・ミュラーの24編の詩につけられたこの連作歌曲集は、結婚の約束までした恋人に裏切られ、さすらいの旅に出た青年の失意の物語というかたちをとっているが、実は人生そのものに対するシューベルトの深い絶望、死への憧れの物語なのだ。冒頭の第1曲ですでに恋の物語は終わっている。残りの23 曲はすべて内面に抱えた悲哀、あてどのない孤独、生きることの痛み、疎外感、そうした心象風景を延々とうたっていくのである。 |
|
| |
『冬の旅』はシューベルト(1797-1828)の死ぬ1年前に作曲された。彼はすでに梅毒という不治の病の不安を抱えていたが、『冬の旅』はそれ故に生まれただけではない。 |
|
| |
時代は産業社会の発展の戸口に立っていた。ウィーンは都市化の速度を増し、成功した市民が中産階級を形成していく。裕福になった市民層はナポレオン戦争収拾のあとの宰相メッテルニッヒの警察監視体制のなかで政治的発言を封じられ、心の内側への亡命を強いられた。それが後にビーダーマイヤーといわれる、洗練されてはいるが極めて個人主義的で、ささやかな安穏と美食を求めるような生活スタイルを生んでいた。シューベルトはこうした社会の雰囲気の中で暮らしてはいたものの、彼はいつも貧乏で金に困っていたし、常にさすらい人、アウトサイダーであった。そうした社会に対する鬱屈を内面に感じていたことは彼自身が書き残した詩や手紙の中にしばしば顔を表している。それは古典的ロマン主義者といわれるシューベルトの影の、隠れた部分なのである。 |
|
| |
シューベルトのこの時代は、どうだろう、今日の私たちの時代に似てはいないだろうか。 |
|
| |
「古典クラシック」となった作品はいったん額縁に入れられると、作品の意味や聴き方が固定されてしまう危険がある。そうしたものが、『冬の旅』の初演された当時の衝撃を見えなくしているのだ。『冬の旅』はまさに「心の安寧を求めようとする善良な市民」をこのように震撼させたのではないか、とツェンダーは考えたのである。 |
|
| |
「創造的編曲」の実際について詳しく触れるスペースがなくなったが、ツェンダーは原曲の歌の旋律を基本的に変えず、ピアノの伴奏部分をオーケストレーションし、特に前奏と間奏部分に工夫を凝らしている。しかしその基本的なアイデアはシューベルトが各曲の伴奏で暗示的に用いている音型やフレーズ
[例えば第1曲の歩行のリズム(ツェンダーは冒頭からそれを延々とくり返し歩き続けるが、これは「風」の暗示とともに『冬の旅』の基本をなしている)、第2曲以降、風の吹きすさぶ音、氷を踏む音、カラスの飛行、犬のうなり声、郵便馬車のラッパや馬の駆ける様子、落ち葉、嵐など]
をもとにし、現代音楽で開発されたさまざまな技法、楽器の特殊奏法をつかって多様な音色を作り、原作をさらに視覚的なものにしながら、彷徨う若者の心象風景を拡大して見せるのである。 |
|
| |
終曲の「辻音楽師」の最後、音楽のかたちはしだいに崩れていき、今日の何かの崩壊を暗示するように、アモルフな轟音とともに消えていく。
|
|
| |
[初出] 2005年1月−2月、ジョン・ノイマイヤー/ハンブルグ・バレエ団
日本公演プログラム・ブック。本稿は、著者の確認・承諾を得て掲載するものです。(2006.10.26.
musicircus) |
|
| |
2002年 第18回<東京の夏>音楽祭 「音楽と文学」■ ハンス・ツェンダーの“創造的翻案による”《冬の旅》
公演案内
■ 公演レポート 「《冬の旅》──現代の孤独を問いかけるツェンダー」
(2002年 7月 18日
大田区民ホールアプリコ)
 |
シューベルト:冬の旅
〜ハンス・ツェンダーによる創造的編曲の試み
ハンス・ペーター・ブロホヴィッツ(T)
アンサンブル・モデルン
指揮:ハンス・ツェンダー
録音:1994年8月
国内盤CD:BVCC-8863/8864
|
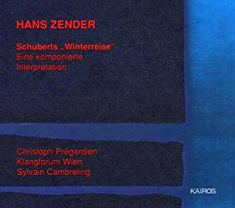 |
Winterreise
von Hans Zender / Franz Schubert
Christoph Prégardien, tenor
Klangforum Wien, Sylvain Cambreling
Kairos 0012002KAI
|
註記=この2つの録音はまったく違った雰囲気をもっている。作曲者自身の指揮による
BMG(RCA) 盤は凍てついた風景が地の果てまで続く灰色の気分に満たされているが、いっぽうカンブルラン(指揮)と<東京の夏>音楽祭でも独唱を務めたプレガルディエンによる
Kairos 盤では、より主人公の内面をドラマティックに造形する表現に焦点を当てている。以前、1995年のザルツブルグ音楽祭で実際に同作品に接した方から聞いた話では(作曲者指揮のアンサンブル・モデルン)、演奏中に各奏者が舞台上を移動するなど、視覚的な効果も計算されていたとのことだった。本作品は、その劇的な性格ゆえに、CDよりも舞台や実際の演奏で接したほうが刺激的であるといえそうだ。映像作品としての可能性もあるだろう。(堀内宏公)
|
|