ヨーロッパの精霊四人組としてのヤン・ガルバレク・グループ(きっと水木しげるもびっくり)
多田雅範



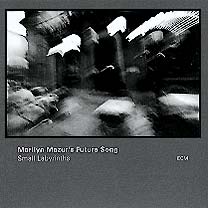

女の子のような透き通った声をしていた。
手が大きくて肉厚でマシュマロのように柔らかかった。

多田雅範
Masanori Tada
![]()
ECM DIVISION |
homeへ戻る ECM DIVISIONのtopへ戻る Album cover reproduced by courtesy of ECM Records, Munich ●ジャケット写真はECM Recordsの許諾のもと、掲載しております。(musicircus) |
ヤン・ガルバレク・グループ 2004. 2. 25(水)来日公演リポート
|
||
| ヤン・ガルバレク・グループの来日公演があった。ものすごく楽しかった。 |
||
| ベースのエバーハルト・ウェーバーが、音を重ねて描く彼らしい音響の世界、そこに、竹笛のヤン・ガルバレクが旋律を乗せる。そこかな、いちばん良かったのは。意識が飛んだ。まだようやく人が住み始めた頃のヨーロッパの原風景に訪れたような気がした。 |
||
 |
コンサート会場は、すみだトリフォニーホール。JR錦糸町北口沿いに駅前再開発されたビルの並びにあるホール。単日公演なので、この日に全国のECMファンが集まる。5年ぶり、8年ぶり、20年ぶりの顔がある。ホールに入ると《Solstice》(ECM
1060)がかかっている。〈Oceanus〉がかかっていて、それだけでECMファンにはお祭り気分だった。 |
|
 |
電気ベースのエバーハルト・ウェーバー。ガルバレクのグループに参加する以外は、すっかり隠遁してしまっている。まるでその引き篭りをサウンドにしたような多重録音ソロ作《Endless Days》(ECM
1748)──たしかに“終わり無き日々”ではあるだろう──が最新作。かつては、自らのグループ“カラーズ”を率いていたり、ライル・メイズが参加したりする《Later That Evening》(ECM 1231)を録音したり、ケイト・ブッシュの録音にその強烈なサウンドの刻印を残したりしているという鬼才だ。 |
|
 |
キーボード/ピアノのライナー・ブリューニングハウス。とにかく聴き手の精神を浮遊させるピアニズムは《Freigeweht》(ECM
1187)、《Continuum》(ECM 1266)などのリーダー作で個性を放っているものだが、今日のライヴでは、風呂に浸かりながらすさまじい屁をしているのにずっと何事もなかったかのような、ヌボーっとした顔のまま、ピアノの指が走る走る。そんなに弾けるんならECMで新しいリーダー作出しなよー。ねえー。 |
|
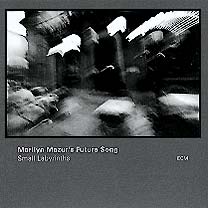 |
パーカッションのマリリン・マズール(■/■)。ギル・エヴァンスやウエイン・ショーターでも演っていた経歴の持ち主。現在彼女が率いるバンド“フューチャー・ソング”の圧倒的な人気とサウンド構築力は、ヨーロッパではガルバレク以上の集客力がある。たしか昨年、ヨーロッパ・ジャズ・シーンのグラミー賞みたいのを獲得している。今日のステージでは、ホールの床が音鳴りしていて、風呂桶を叩いているような軽さも感じられて、彼女のCDに聴かれる世界観は味わいにくかったものの、このグループにおける存在感は充分に示した。 |
|
| 四人がステージで演奏している姿は、ムーミンの世界、の、にょろにょろとか、スナフキンや、ミーや、ヘムレンさん、のように、素敵でした。 |
||
| ガルバレクはノルウェー、マズールはデンマーク、ウェーバーとブリューニングハウスはドイツ、です。 |
||
| やっている音楽は、ジャンルの壁を越えた「ガルバレクの音楽」、としか言いようがないものです。パット・メセニー・グループのコンサートとほぼ同じ構成感覚を覚えましたし、東儀秀樹のコンサートとも大差ないものです。この場合、ジャズかジャズでないかなど問題にならない音楽であるという点で共通している。コンサートを聴きながら、「あー、うちのむすめはこんなふうに東儀秀樹のコンサートを聴いてきたんだろうなー」と、思った。わたしの耳はまたしてもひとかわむけた。 |
||
| あれ。 |
||
| “単騎ECMファン”だったころ、ジャズ・ファンに「ECMはジャズじゃない」と、インプロ・ファンには「ECMは即興ではない」と、断ぜられ、「ECMが何かである必要があるんだろうか」と思いつつも、ジャズを、即興を、わかろうと、必死にひとりジャズ修行僧になって過ごすこと幾年月、ようやく彼らの言うところの感覚を会得して、今日はヤン・ガルバレクを聴きに来た。 |
||
 |
ヤン・ガルバレクが自らのカルテットにビル・コナーズ、ビル・フリーゼル、デヴィッド・トーン──いずれもギタリストだ──を迎えて録音していた時期、は、ガルバレクは自分の音楽とジャズをアマルガムして彷徨っていた。たしかに彷徨っていた。そして、彷徨うこと、は、ジャズだ。 |
|
| 今日のヤン・ガルバレク・グループを聴いて、「ジャズじゃないじゃん」と、野暮を言うのはやめよう。音楽に耳を澄まそう。 |
||
| 公演後の楽屋で、ヤン・ガルバレクと話をして、握手をした。 女の子のような透き通った声をしていた。 手が大きくて肉厚でマシュマロのように柔らかかった。 |
||
 |
ガルバレク・グループの現在のところの最新作は2枚組《Rites》(ECM
1685)で、その制作のコアにあったのは、ヤンスク・カヒーゼの歌声だった、と、私は確信する(▼)。カヒーゼさんはその後2002年に亡くなっている(■)。ガルバレクに彼との思い出をきいてみた。身振り手振りを交えて、オーケストラを前にしたカヒーゼさんの指揮者としての専横ぶりをガルバレクは嬉しそうに語った。「でもぼくには、事前に、練習ではそういう厳しい態度を取るけど気にするなよって伝えてくれてね。」あたかもガルバレクにとって、カヒーゼさんは死んではいないことを語っているようだった。 |
|
| ぼくはガルバレクの透き通った声をききながら、音楽はそのようなものだと思った。 |
||
|
||