私がそもそも音楽に特別な興味を抱くようになったきっかけは、アントン・ウェーベルンの作品をラジオで聴いたことにあった。個人の内面的な投影を超越した、それ自体が自然の事物のように組成した音楽が実在することに感動したのだ。それは、自然それ自体のなかにカミの存在を観想する、神道的な世界観を背景にもつ日本人の感性ゆえのことだったのか。いずれにせよ、音楽を通じて、ある古典的な秩序と前衛的な手法が交差した地点に生まれる、時空を超えた精神の交感の可能性を知ったことが、そのときの体験の核心だった。

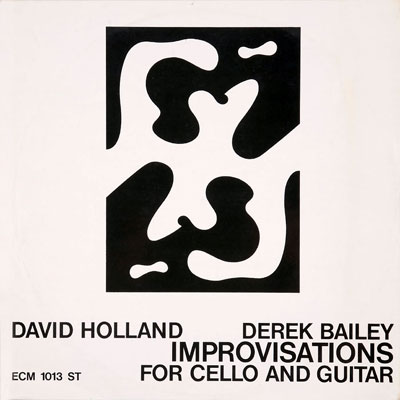








堀内宏公
Hiromasa Horiuchi
![]()