July 15, 2011
|
| 今週の批評から Reviews
of the Week
|
|
|
 |
メレディス・モンク
Meredith Monk の《ソングズ・オブ・アセンション
Songs of Ascension》(ECM New Series 2154)が、スイスの新チューリッヒ新聞
Neue Zürcher Zeitung で大絶賛されています。レヴュー筆者はクリストフ・ワーグナー
Christoph Wagner です。
|
|
| |
本作が湛える清浄な雰囲気は、ほとんど聖なるものと称されてよい特質を備えている。モンクは、聖フランシス
St Francis [註:アッシジの聖フランチェスコ(Francesco d'Assisi)]のように、彼女のアンサンブルと共に“太陽の歌
sun songs”を詠唱することを通じて、ついに鳥や動物たちと神秘的な言語を使った会話を交わしうる境地に到達したように思われる。モンクの音楽は一貫して独特な澄み切った特色を持っているとはいえ、40年以上に及ぶ活動のなかで、その時々に新鮮な発想(アイディア)が探究されたり、また時には新しい構成要素が編入されたりして、その性格は少しずつ変容を重ねてきた。そのことは、この最新録音においても同様で、本作ではトッド・レイノルズ弦楽四重奏団
Todd Reynolds Quartet がモンクの音楽に新たな変化を与えており、作品の最後のクレッシェンドでは劇的な効果を担っている大勢の声からなる聖歌隊とほぼ同等な役割を演じている。
|
|
| |
|
|
 |
ダウンビート誌 DownBeat の8月号では批評家たちが名を連ねて、リー・コニッツ
Lee Konitz、ブラッド・メルダウ[メルドー]
Brad Mehldau、チャーリー・ヘイデン
Charlie Haden、ポール・モーシャン[モーション/モチアン]
Paul Motian による《ライヴ・アット・バードランド
Live At Birdland》(ECM 2162)について記事を書いています。
|
|
| |
メルダウ[メルドー]はどのトラックでも一貫して誇大妄想的なまでに華々しい。彼は煽動者となってコニッツが新しいラインを吹くように常に後ろから背中を押していて、そうかと思うと、今度は支える側に回り、「ラヴァー・マン
Lover Man」では、サックス奏者の驚異的な捧げ物に色彩感を与えている。まさしく彼は音楽につねに変化を提供し続け、途絶えることなく湧き続ける聖なる泉であり、こうした特質は「バードランドの子守唄
Lullaby of Birdland」の演奏で存分に発揮されている。 ジョン・コルベット
John Corbett
ダウンビート誌 DownBeat
|
|
| |
コニッツ、メルダウ、ヘイデンの三者はお互いの和音を優しく魔術的な仕方でつなぎ合わせていく。メルダウの内声部のヴォイシング(和声付け)とコード・チェンジの時の鐘が鳴り響くような音は、じつに喜びに溢れている。コニッツはいつにも増して一段と活気に満ちた演奏を聴かせ、ヘイデンとモーシャン[モーション/モチアン]は美しい色彩空間を彫琢している。 ポール・デ・バロス
Paul de Barros
ダウンビート誌 DownBeat
|
|
| |
コニッツは均衡を欠く生来の気性そのままに暖かい光を放っている。メルダウはじつに多くの対処の仕方を身につけていて、コニッツの音の周囲にかぼそいシングル・ノートのラインを地味に巻き付けること以上のことをやってのけ、しかもリスナーに歓迎されるというピアニストはこの人物の外に存在しないだろう。ヘイデンは全体の水面下で濃厚で感傷的な引き波を発生させつつ、ソロを展開している。 ジョン・マクドノー
John McDonough
ダウンビート誌 DownBeat
|
|
| |
|
|
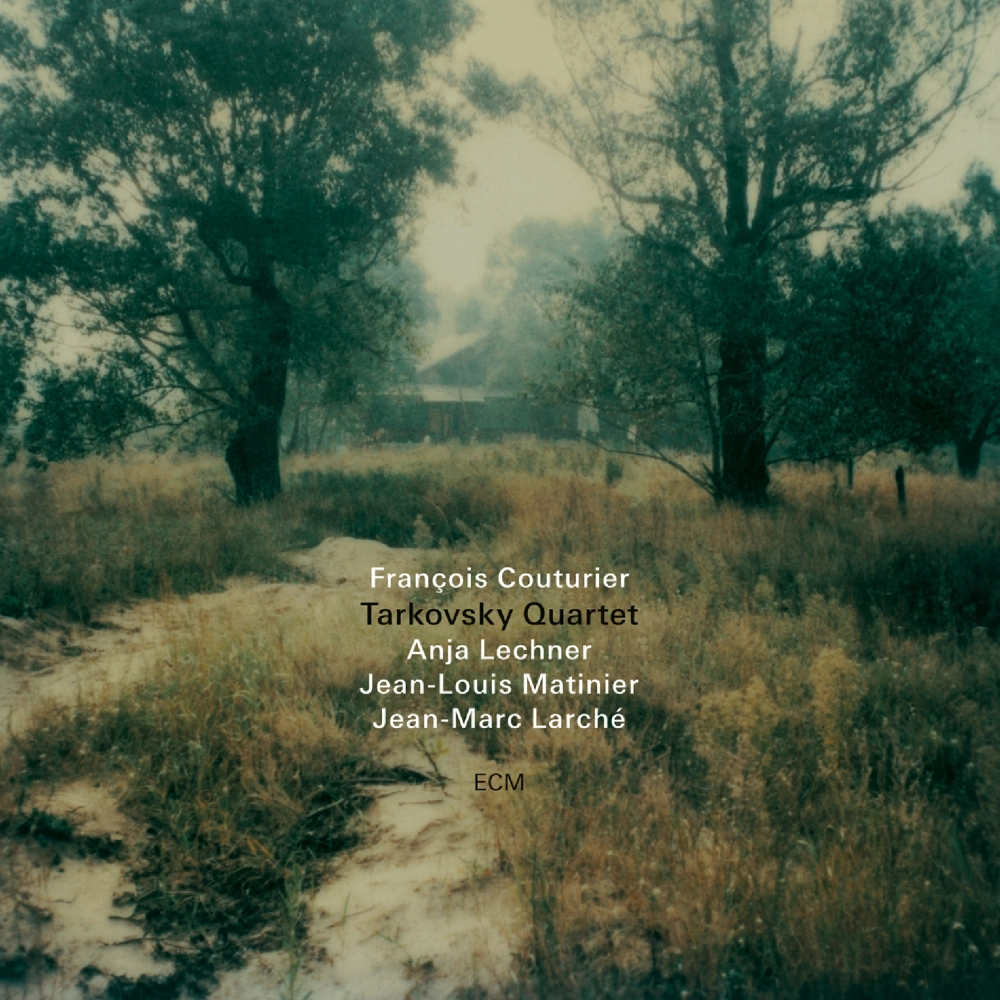 |
タルコフスキー・クァルテット
Tarkovsky Quartet (フランソワ・クチュリエ
François Couturier、アニヤ・レヒナー
Anja Lechner、ジャン=ルイ・マティニエ Jean-Lous Matinier、ジャン=マルク・ラルシェ Jean-Marc Larché)の新作《タルコフスキー・クァルテット
Tarkovsky Quartet》(ECM 2159)に対し、先週、オーストリア
Austria とニュージーランド
New Zealand という遠く離れた地域で、ポジティブな注目を表明する記事が同時に掲載されました。以下はニュージーランド・ヘラルド紙
New Zealand Herald のウィリアム・ダート
William Dart のレヴューです。
|
|
| |
ECMの新譜《タルコフスキー・クァルテット
Tarkovsky Quartet》は、メンバーのフランス出身のピアニスト、フランソワ・クチュリエが、アンドレイ・タルコフスキー
Andrei Tarkovsky の映画との間に生じた音楽的恋愛関係の第三回目の分割支払分を携え、再び戻ってきたという脈絡をもつ作品である。タルコフスキーが自作の映画音楽を任せるに際して寵愛したのはエドゥアルド・アルテミエフ
Eduard Artemyev という作曲家だったが、アルテミエフはしばしば音楽文化の驚くようなクロスオーバーに夢中になって、東と西の響きを融合させようと試みた。そしてまたタルコフスキー監督も、たとえば1972年の『惑星ソラリス Solaris』でバッハの音楽が中心的な力を担っていたように、クラシックの巨匠たちの作品を上手く利用することを好んでいた。こうしたことは全てクチュリエの作り出す響きの風景にも反映しており、このアルバムは、彼が弾くピアノに、チェロとアコーディオンとソプラノ・サックスが加わったクァルテットの演奏で進行していく。この四人は音楽家としてまさしく比類ない存在であり、しかもそこに5つ星が付くプロデューサーであるマンフレート・アイヒャーが寄り添い、この作品全体を取り巻く大変快適で心地好い環境を供給している。このアルバムには古い時代の音楽の反響が立ち籠めている。それはたしかにノスタルジアではあるが、ただし、清々しい気分を伴うものとなっている。
|
|
| |
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.

|
|
| |
※本記事は、ECM が発信する最新情報を ECM Records の許諾を得て翻訳掲載するものです。(musicircus) |
|


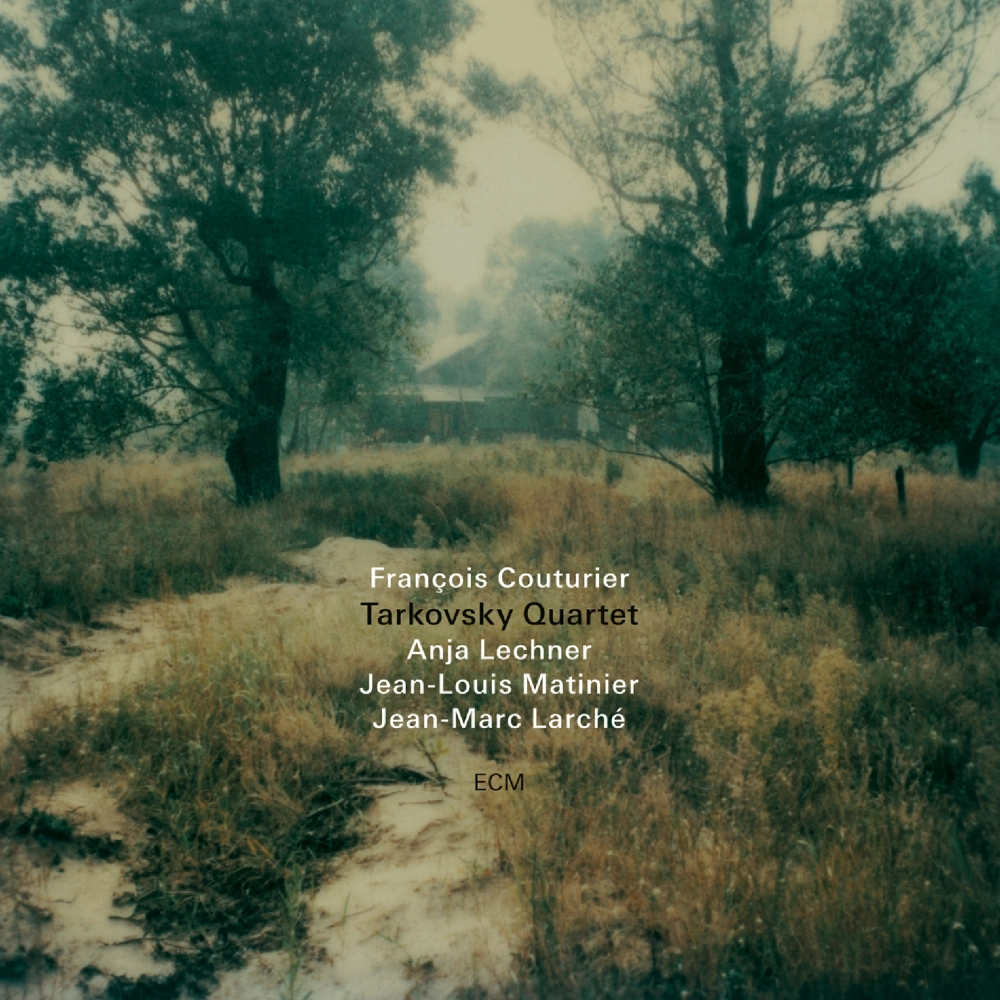
![]()