July 25, 2011
| 今週の批評から Reviews of the Week |
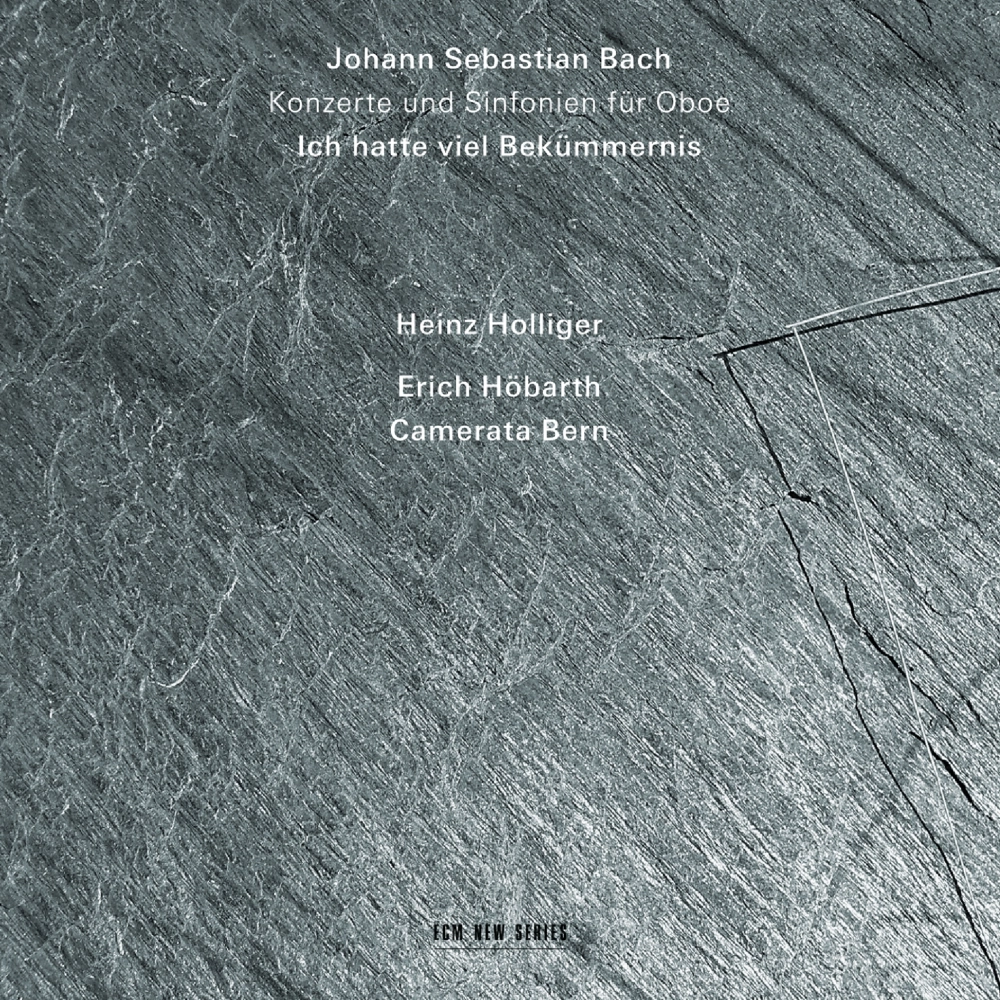
ラジオ番組でこう語りかけたのは、アメリカ合衆国の公共ラジオ局「ナショナル・パブリック・ラジオ(National Public Radio、略称NPR)」の番組“NPRクラシカル NPR
Classical”を担当するトム・ハイゼンガ
Tom Huizenga です。彼は続けて次のように述べました。
このECMの新譜から、こうした特別な感動が呼び起こされる理由というのは、やはりひとつにはなんといってもスイス出身のこのオーボエ奏者ならではの絢爛(けんらん)たる楽器の響きそれ自体にあると言えますが、ホリガーは、この清潔で特色に満ちた音色を、じつに50年以上に亙って今でも維持しているわけです。
そしてもうひとつの理由、つまり鍵となる要素が、おそらくJ.S.バッハの作品そのものにあるのだと思います。まさしく、今回のホリガーのCDではバッハの音楽に焦点が当てられているからです。
バッハは、声楽曲であれ器楽曲であれ、しばしば最も魅惑的で最も魂の内部へ分け入った独奏旋律をオーボエのパートに与えています。このアルバムの幕開けとなる作品は、このCDのタイトルともなっている、カンタータ第21番 BWV 21 の冒頭の曲、死の別れの悲痛な心に満ちた「わがうちに憂いは満ちぬ Ich hatte viel Bekümmernis」ですが、バッハはこの曲を書いたとき、若くして亡くなった彼の最愛の弟子のひとりの面影が心の中に鮮やかに残っていたと言います。この曲は、ホリガーにとってもバッハと似たような精神の浄化作用があったようで、彼はこのアルバムを、レコーディング・セッションの終了する少し前に相次いで世を去った自分の兄と友人に捧げています。
このアルバムの演奏からは、そうしたホリガーの心の痛みが、息の長い苦悶に溢れたオーボエの嘆きの歌となって展開されていくのを、おそらく、お聴き取りいただけるだろうかと思います。蛇のように曲がりくねったオーボエの旋律がエーリヒ・ヘーバルト Erich Höbarth の独奏ヴァイオリンと絡み合いますが(ヘーバルトはこの充ち足りたアンサンブルであるカメラータ・ベルン Camerata Bern の指揮者でもあります)、しかしホリガーとヘーバルトは両者共に深い嘆きの淵に沈んだ歌い手たちのごとく、いささかも乱れのない心臓の鼓動のリズムを保って、どこまでも一心に演奏を続けています。
ホリガーは、バッハのカンタータや管弦楽曲におけるオーボエのソロ・パートを“奇跡的な富”だと称していますが、じつはこれらの作品以外にも、バッハがオーボエのために書いた“失われた”協奏曲がいくつか存在しています。これらの作品はバッハが最初に作曲したオリジナルのかたちのまま現存しているわけではないのですが、というのも、当時は作曲家が前に書いた曲を、たとえばハープシコード協奏曲のように、違った編成の作品に再利用することが普通に行なわれていたからです。
ですからそうした形を変えて残った作品を手がかりとして、音楽学者たちは、そこから作品の元の姿を丹念に探って、信頼に足る再構成を行なうことができたわけです。
こうした復元作品の内で最も有名なものが、BWV 1060 のオーボエとヴァイオリンのための二重協奏曲です。このアルバムでは、第2楽章のアダージョで、ホリガーとヘーバルトによる、それぞれの見事な演奏による旋律がお互い同士絡みつくようにして進んでいく部分が大きな聴き所です。
また本盤には、これ以外のオーボエ協奏曲も収録されていて、そのひとつはオーボエ・ダモーレのための大変威勢のよい協奏曲、そしてもう一曲が埋葬の情景を思わせる遅い第2楽章をもつアレッサンドロ・マルチェッロ Alessandro Marcello 作曲のオーボエ協奏曲です(バッハはこの曲をハープシコード独奏用の協奏曲に編曲しています)。
ホリガーのファンの方であれば、これらの協奏曲が彼にとっては二回目の録音であることや、前にも録音が存在していることは既にご存知だろうと思います。しかし、このオーボエ奏者、指揮者、作曲家にとっては、72歳という年齢は大変有利に働いているように思います。人生を通じて味わった喜びと悲しみの経験の全てを、ホリガーはこの崇高な音楽の中に注ぎ込んでいるからです。
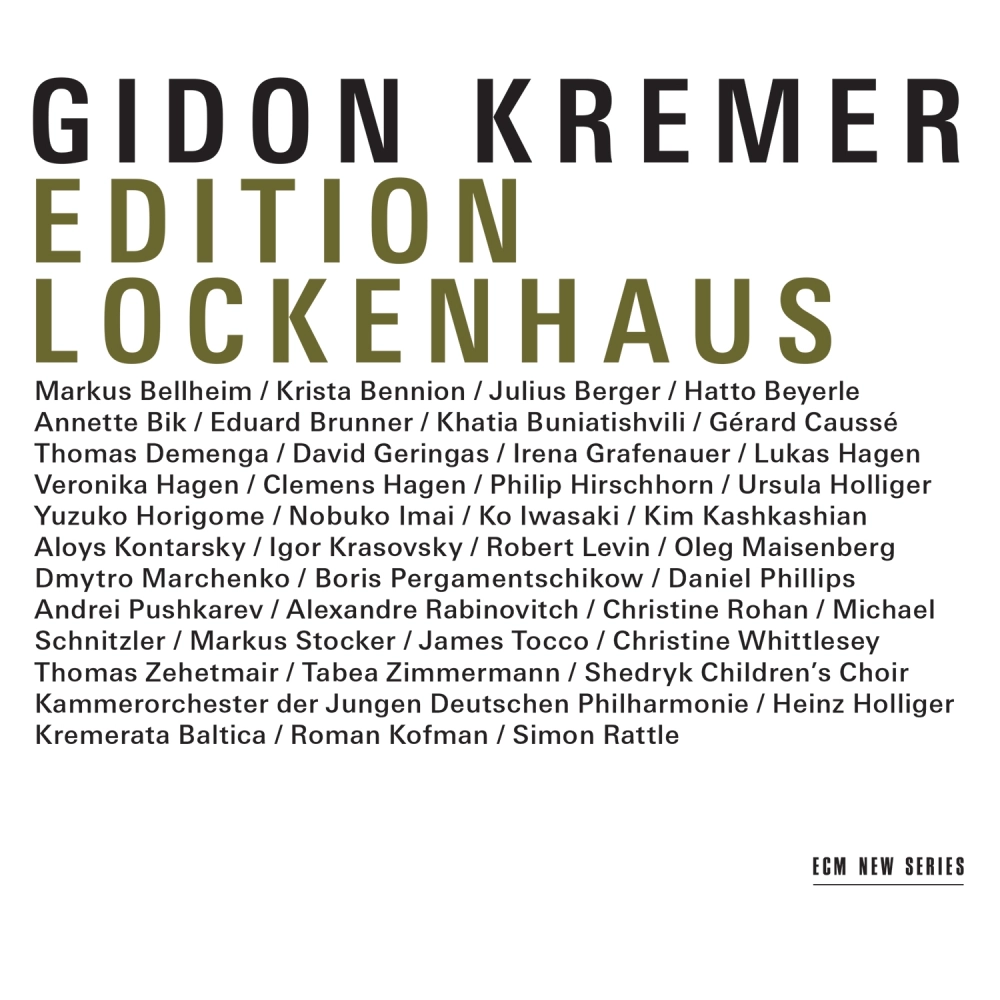
すなわち、「この音楽祭は幾多の若い音楽家を熱狂的な聴衆の前に引き出すのに功績があったばかりでなく、他では見られない音楽的な創造性と自発性に関わる雰囲気を生み出した点においてこそ特筆されるべきものだったのです」。
記事の筆者フォルカー・ハゲドーン Volker Hagedorn は、ロッケンハウスが「瞬く間に有名になった」のは、「数々のレコードの存在も大きく与っていたが、このたび、その内ECMの録音が5枚のCDアンソロジーとして集成されることになった」と、このECMの新作ボックスCD《Edition
Lockenhaus》(ECM New Series
2190-94)にも言及しています。

[訳註:このサイトは、ドイツ人が政治・社会・文化各分野の記事や論説・批評を英語で投稿していて、欧州全域の世論形成への影響力が注目を集めている。]
ヴィラロボス:「ECMとそのサウンド・クォリティに没頭してそれらを習得していたから、だからこうやっていざ実際にECMを相手に何かをする機会が訪れてみると、これまでに聴いてきたECMの全アルバムから得たあらゆる情報が、このプロダクションの中へ自然に流れ込んでいったというわけだ」。
ローダーバウアーとヴィラロボスがそれほどまでECMのサウンドに熱中していた理由は、ECMのサウンドが幅広い周波数の範囲、三次元的な深さ、ダイナミックな音色などを有していた点にあった。こうしたオーディオ愛好家らしい関心の持ち方には、きまってある種の道徳律がつきものになる。すなわち、ヴィラロボスにとっては、サウンドの細部に注意を払うことによってのみ、異文化の響きに開放性を確保することができるのだ。
ヴィラロボスとローダーバウアーは、ECMのサウンドをループにして、その内部に聴き手の心に動揺を与える電子的な音をいくつも差し挟んでいる。たとえば、クリスティアン・ヴァルムルー・アンサンブル Christian Wallumrød Ensemble の魔法にかけられたような美を湛えるハープの音色が、ここでは奇妙な楕円形の中でしつこく繰り返されるシークェンスに包まれて、鏡に映し出されるように反射している。
すなわち、ヴィラロボスとローダーバウアーはフリージャズと同じ態度によって、《Re: ECM》の中で独特なパターン(型)をいくつものサウンドへと分類・分解しているのである。
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.
![]()