July 7, 2011
| 今週の批評から Reviews of the Week |
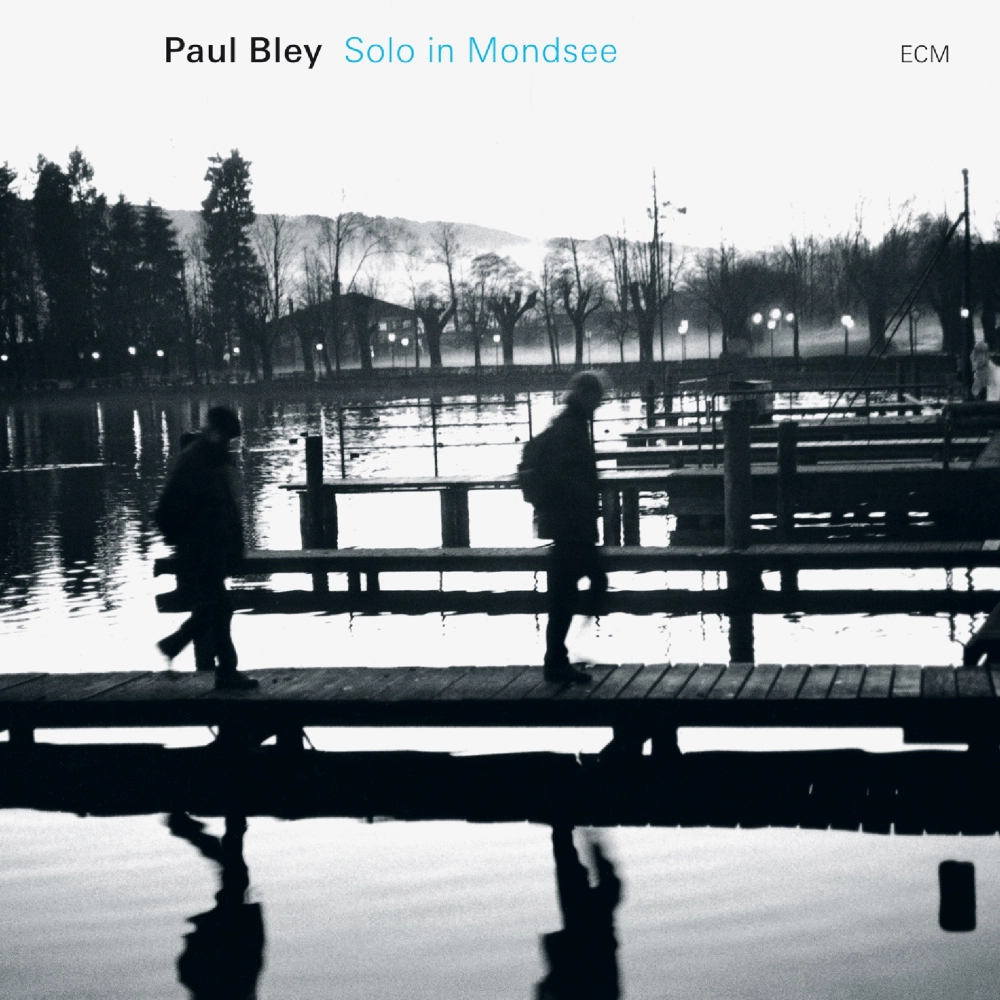
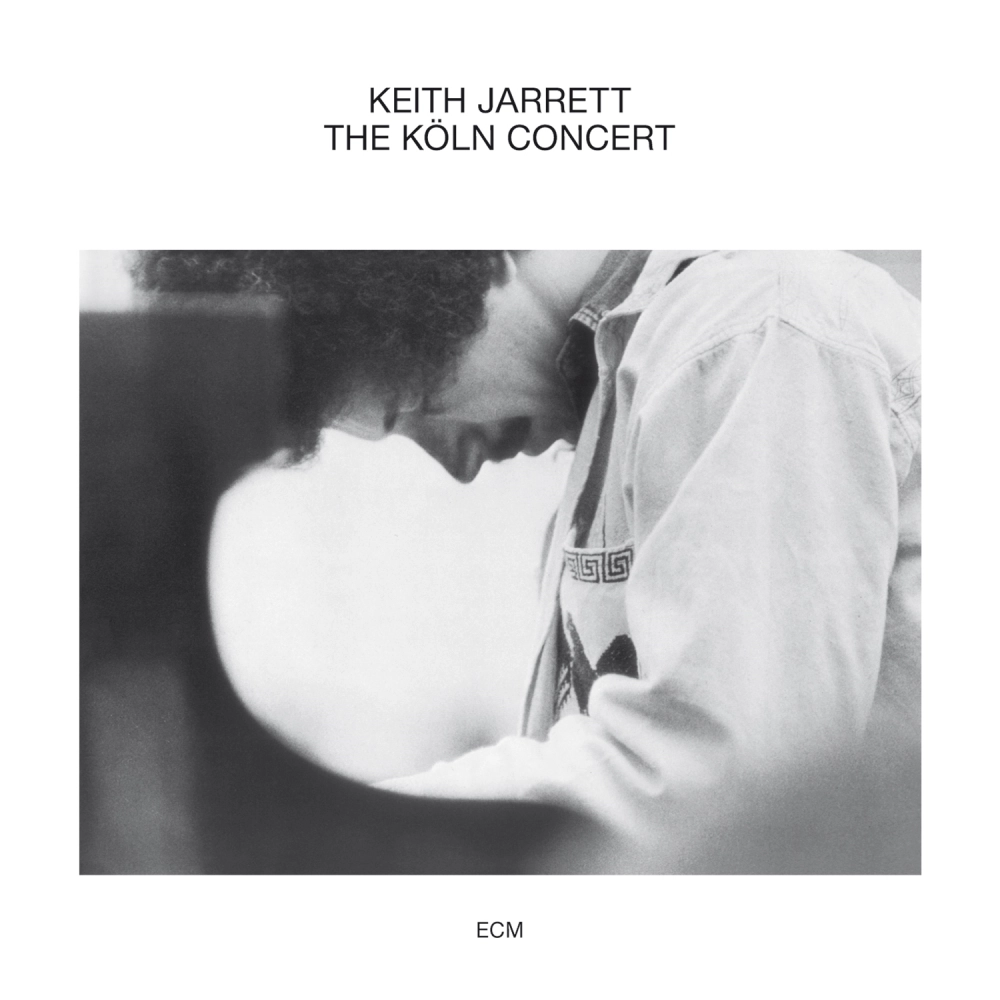

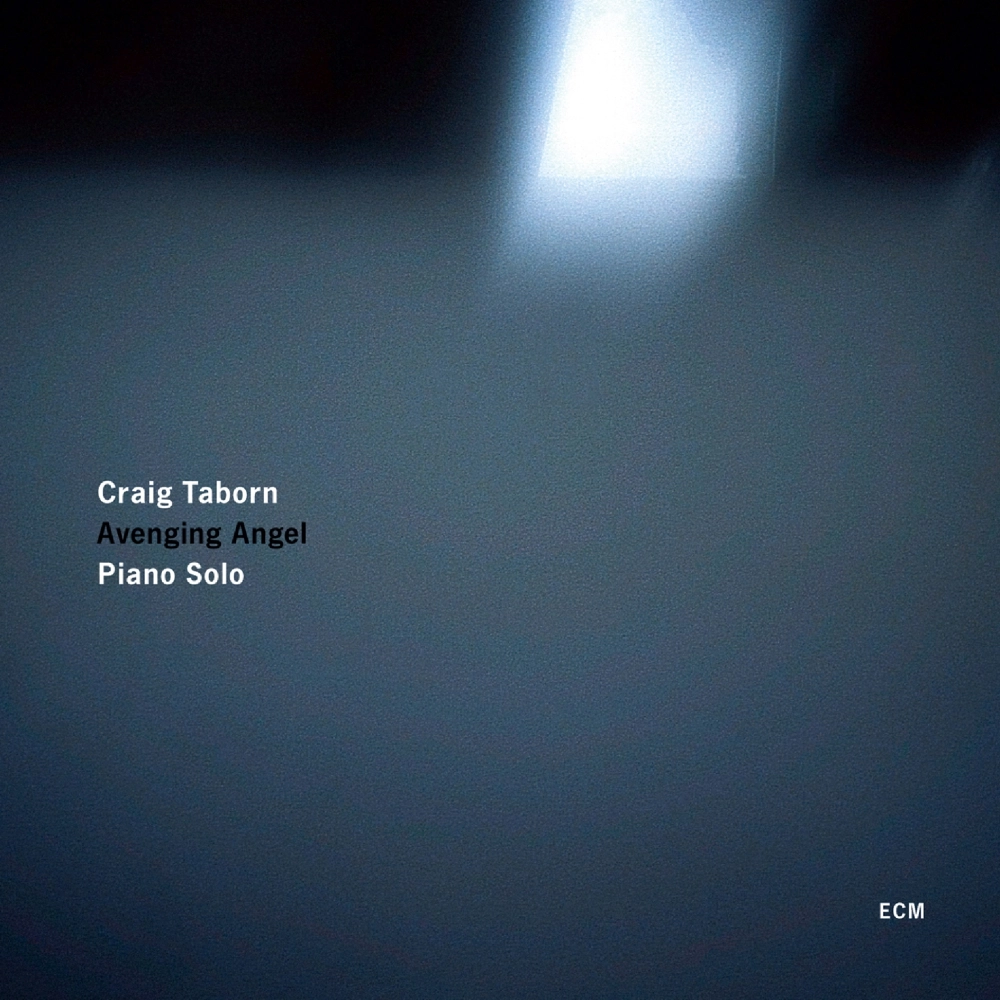


──というレヴューの見出しがワシントン・ポスト紙
Washington Post に踊りました。筆者はアン・ミジェット
Anne Midgette です。


(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.
![]()
homeへ戻る
ECM NEWS のtopへ戻る
2011年度分のニュース のtopへ戻る
| ECM NEWS/ECM情報 | Album cover
reproduced by courtesy of ECM Records, Munich |