November 11, 2011
|
| 今週の批評から Reviews
of the Week
|
|
|
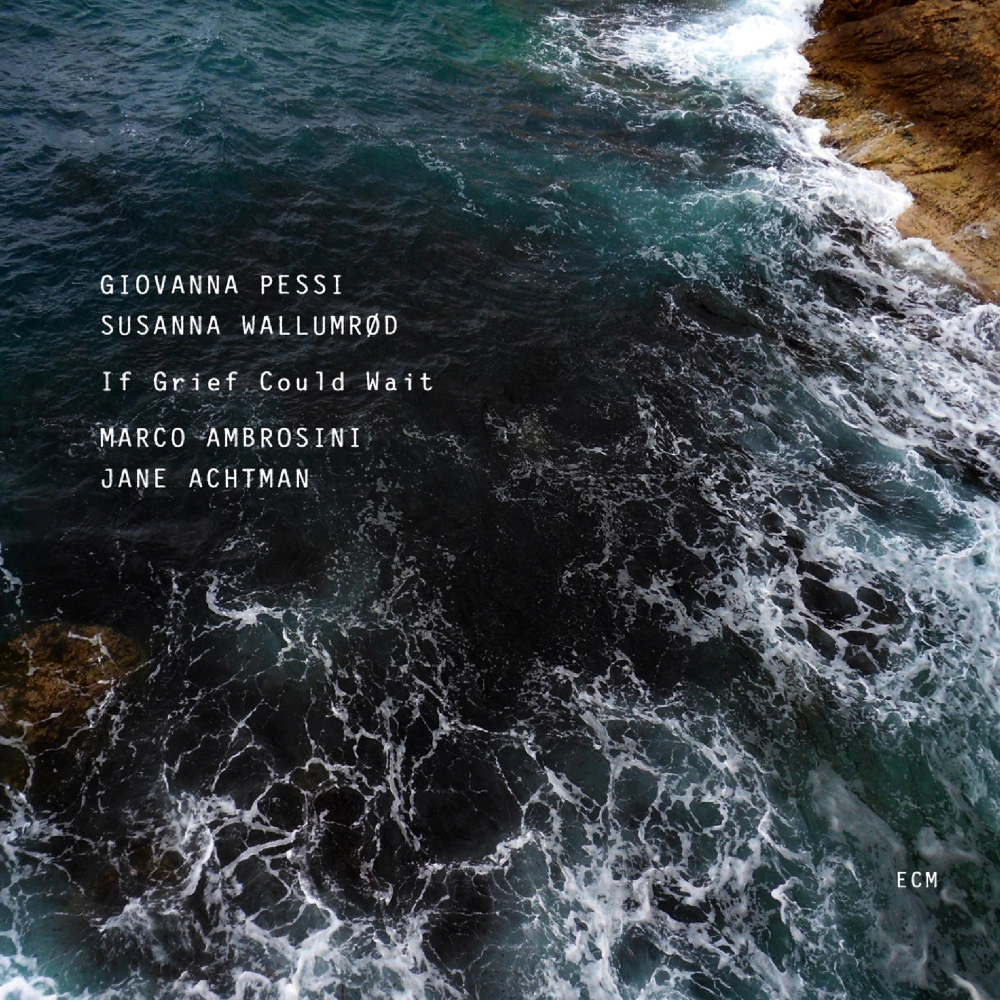 |
ジョヴァンナ・ペッシ
Giovanna Pessi とスサンナ・K・ヴァルムルー Susanna K. Wallumrød が録音した《イフ・グリーフ・クッド・ウェイト
If Grief Could Wait》(ECM 2226)に賛辞を寄せたジョン・フォーダム
John Fordham の批評(■)が英国ガーディアン紙
The Guardian に掲載されました。
|
|
| |
これは全くジャズのアルバムではない。声とハープ、そしてピリオド楽器の弦楽器が奏でる極上の美しい響きがスサンナ・K・ヴァルムルー Susanna K. Wallumrod の軽いタッチの歌声と結び合わされ、いにしえの時代を織り交ぜ喚起力のある魅力的な旋律と威厳のある曲調を有するヘンリー・パーセル
Henry Purcell が作曲した17世紀の教会と劇場のための音楽や、ヴァルムルーのオリジナル作品、レナード・コーエン
Leonard Cohen の歌、そしてニック・ドレイク
Nick Drake の「ホイッチ・ウィル
Which Will」などの曲が次々と演奏されていく。
本作は、思いがけない組み合わせで成功したクロス・ジャンル作品への参加歴のあるバロック・ハープ奏者ジョヴァンナ・ペッシ
Giovanna Pessi との、じつにユニークで大胆不敵なコラボレーション作品である。レナード・コーエンの曲「フー・バイ・ファイアー
Who by Fire」における──「バルビツール剤(鎮静剤・催眠剤)で死ぬ者、愛に包まれて死ぬ者
Who by barbiturate/ Who in these
realms of love /次は誰を呼ぼう? Who shall I say is calling」──といった現代的な歌詞や、あるいは同じくコーエンの曲「ユー・ノウ・フー・アイ・アム
You Know Who I Am」におけるコーエンならではの身に染みるような宿命を感じさせるメロディ・ラインなど、こうした箇所を解釈する際に見せるスサンナ・K・ヴァルムルーの繊細な歌い回しは、ペッシの奏でるハープや、マルコ・アンブロジーニ
Marco Ambrosini が奏でる鍵盤付きヴァイオリンであるニッケルハルパ
nyckelharpa、ヤーネ・アクトマン
Jane Achtman の奏でるヴィオラ・ダ・ガンバ
viola de gamba などが間断なく展開する響きに見事なまでに対置され、聴き手に驚くようなインパクトを与えるものとなっている。
ヴィオラ・ダ・ガンバは時にチェロのような深い共鳴を響かせ、またハープはギターの響きを醸し出し、そして古楽(アーリー・ミュージック)の形式的構造の内部に棲むスサンナ・K・ヴァルムルーの人間性の静かなる力は、催眠術にかけたように聴き手を魅了する。
|
|
| |
|
|
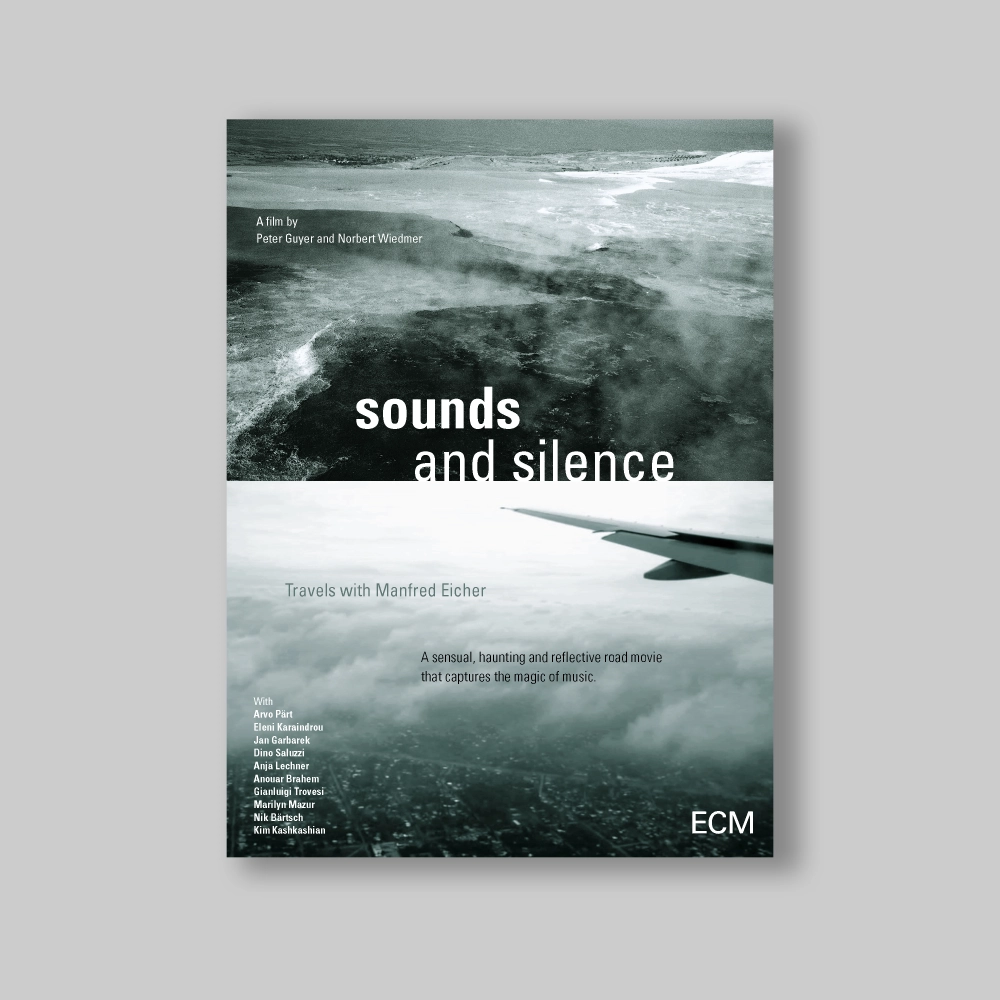 |
ドキュメンタリー映画「サウンズ・アンド・サイレンス
Sounds And Silence」(ECM Cinema)に対し、傑出した評価を綴ったレヴューが引きも切らず続いています。ジェフ・アンドルー
Geoff Andrew がサイト・アンド・サウンド誌
Sight And Sound に執筆した批評をご紹介します。
|
|
| |
この映画は、アイヒャーが音楽の属性を区分する様々な“境界線”の限界の受け入れを拒否していることを明示するとともに証明してみせているが、それだけに留まるものではない。音楽家と共震する想像力豊かなプロデューサーが、録音や演奏会の場に何をもたらし得ているのかを提示したじつに意義深い研究報告ともなっている。エレニ・カラインドルー
Eleni Karaindrou はこの映画のなかで次のように語っている。「アイヒャーの情熱は、いつでも与えられた時間の許す限り、そのとき一緒に働いているアーティストに対して100%の力を捧げることをつねに保証している」。そしてまたこの映画には、アイヒャーがニック・ベルチュ
Nik Bärtsch の“禅ファンク
zen-funk”バンド〈ローニン(浪人)
Ronin〉と、あるトラックの制作を行なっている瞬間を切り取ったスタジオ内での素晴らしい映像も収録されている。
ペーター・グイヤー Peter
Guyer とノルベルト・ヴィードメル Norbert Wiedmer によって独特な慎み深さと印象主義的な方法論(ロード・ムービーの場面では、時折ECM特有のカヴァー・アートを彷彿させる映像が流れる)によって美しく巧妙に編集製作された本作品は、音楽創造のプロセスを目に見えるかたちで顕在化させ、そして音楽それ自体のあらゆる多様性の中で新たに生ずるであろう未知の奇蹟に向けて変わらぬ情熱を漲らせる一人の男の肖像を描き出したという点で、極めて印象深い作品となっている。ゴダールが過去20年間に亙ってアイヒャーとの協同作業を続け、アイヒャーの音の趣味に深い信頼を置いてきたというのも、本作を見れば少しも不思議なことではないと納得できる。
|
|
| |
|
|
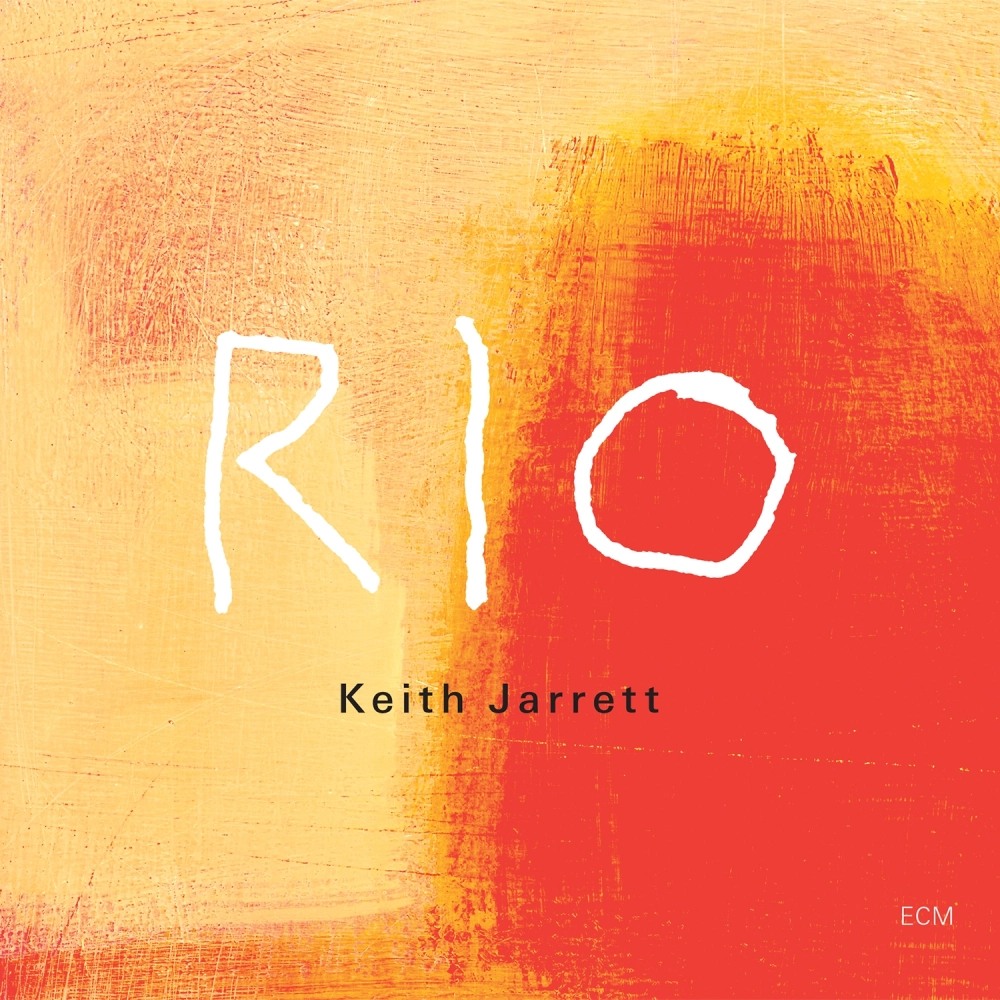 |
英国インディペンデント・オン・サンデイ紙
Independent on Sunday に、キース・ジャレット
Keith Jarrett の新譜《リオ
Rio》(ECM
2198/99)を称賛するフィル・ジョンソン
Phil Johnson のレヴューが掲載されました。
|
|
| |
この2枚組の作品の内の2枚目は、即興演奏の過程で長距離を走りながら描き出されていく厳(きび)しいドラマと感情的なカタルシスという点において、《ケルン・コンサート
Köln Concert》にも匹敵する抒情性の凱旋となっている。
|
|
| |
英国フィナンシャル・タイムズ
Financial Times のマイク・ホバート
Mike Hobart は、《リオ Rio》について次のようなレヴューを書いています。
|
|
| |
キース・ジャレット
Keith Jarrett が今年の前半にリオ・デ・ジャネイロ
Rio de Janeiro で行なったコンサートをライヴ録音しそれを2枚組のディスクに収めた本作は、温かな感情と的確な論理性、非の打ち所のない技術による、全15曲のソロ・ピアノ・インプロヴィゼーションで構成されている。騒々しく、幾分ものものしい感じでのオープニングから、クラシック風のロマンスの波紋で形作られた最後の曲の演奏に至るまで、ジャレットは彼特有の驚くべき語り口でドライブを続けている。その中間には、バラードがあり、沈思する時間があり、燃え滾(たぎ)る劫火(ごうか)があり、心暖まるダンスがあり……、さらに、楽天的なワルツがあり、穏やかなボレロがあり、物思いに耽ったブギがある。そしてそうしたどの一曲を取ってみても、ジャレットの演奏はそれぞれの曲が含み持つ物語に応じて異なった実体を提示しているのである。
|
|
| |
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.

|
|
| |
※本記事は、ECM が発信する最新情報を ECM Records の許諾を得て翻訳掲載するものです。(musicircus) |
|
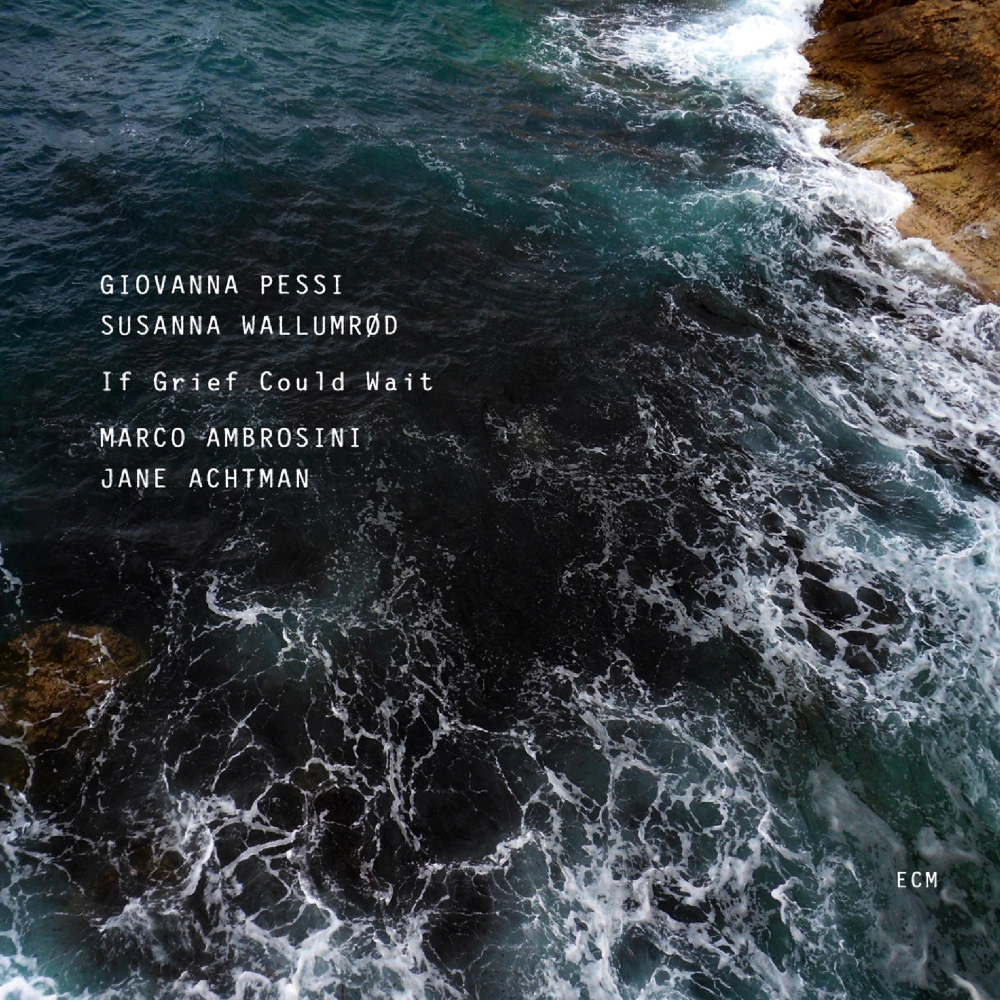
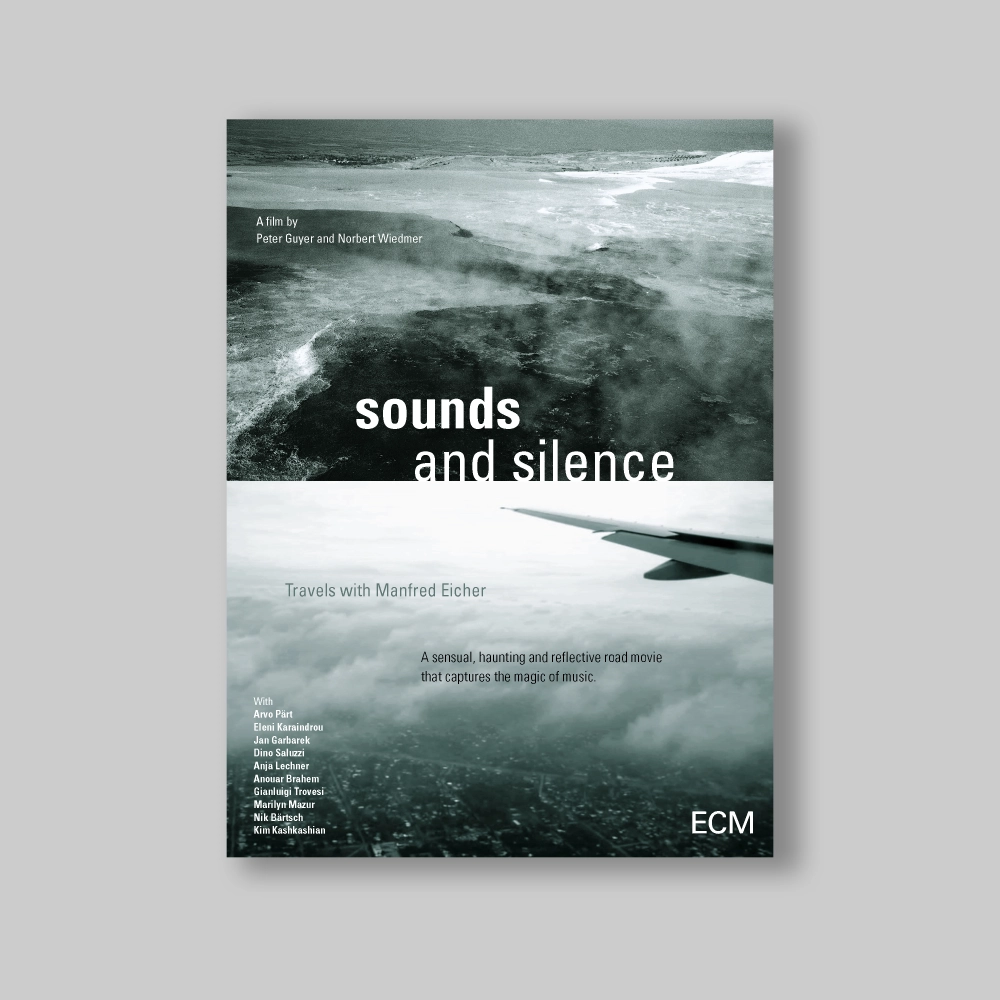
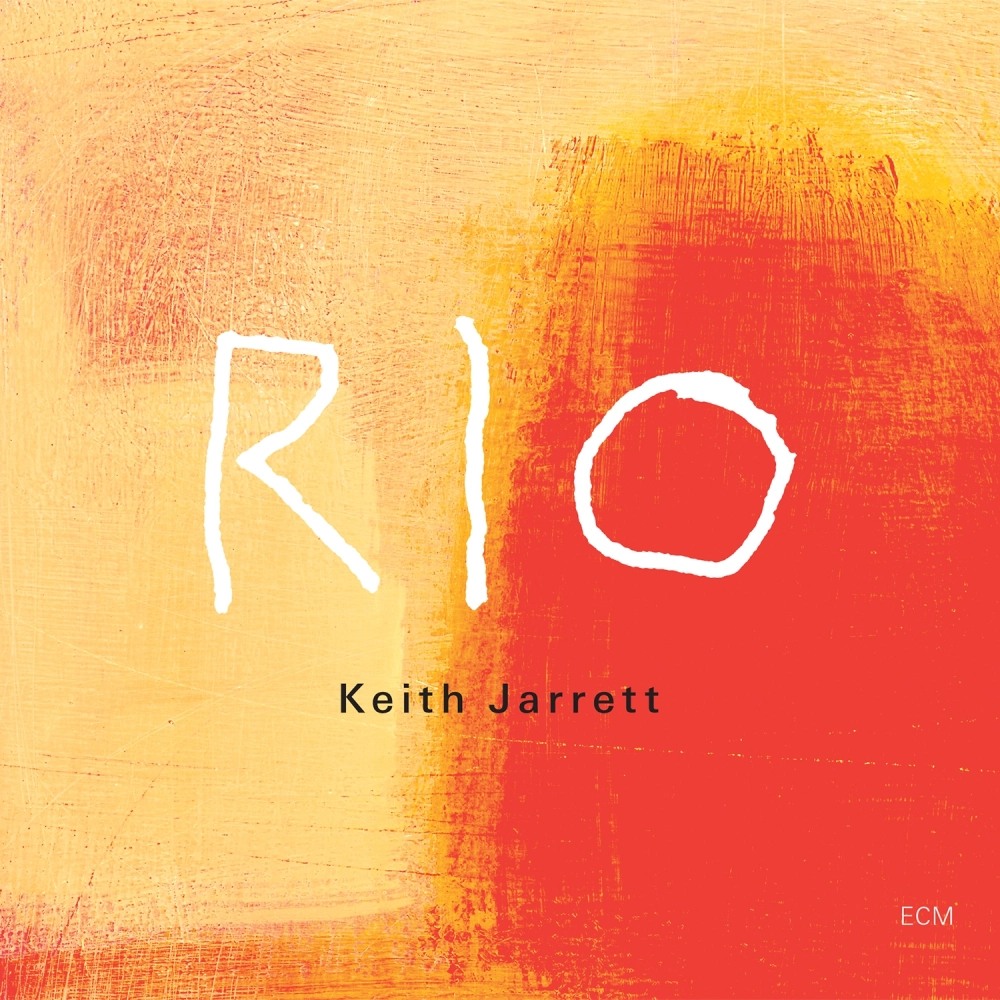
![]()