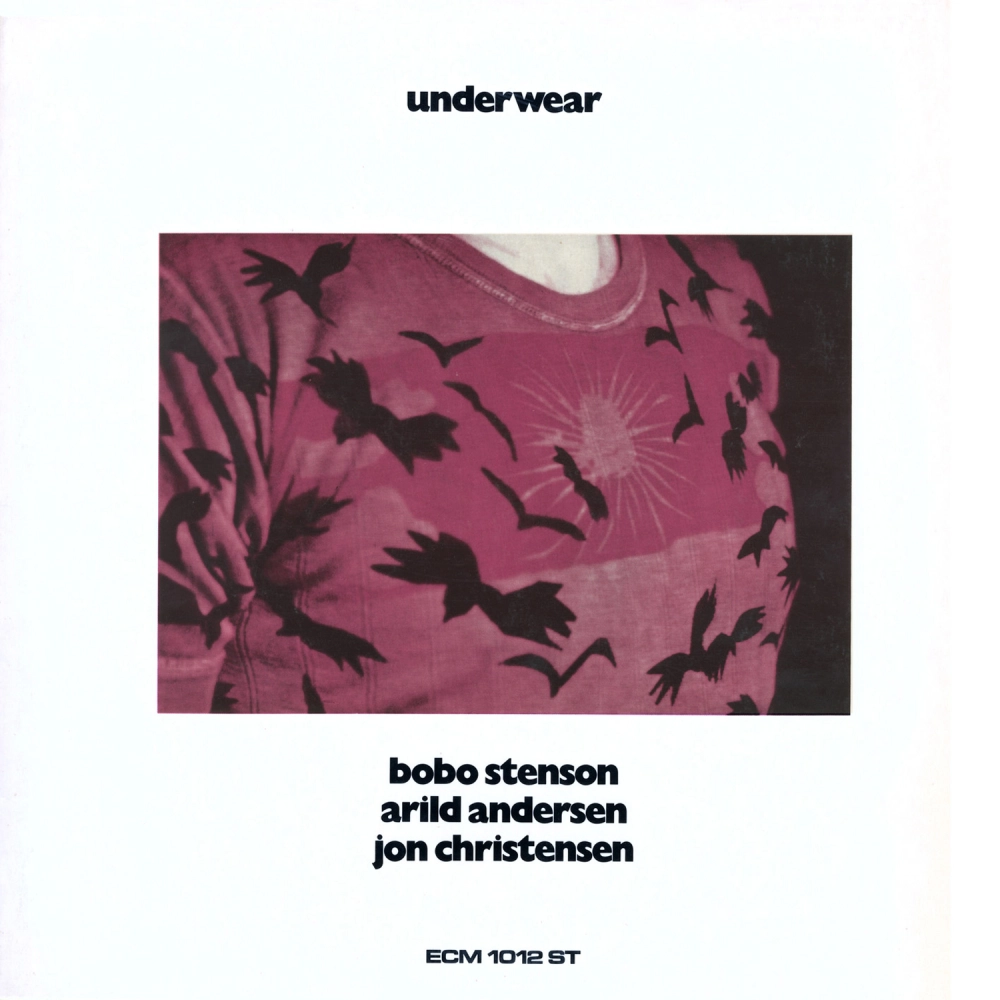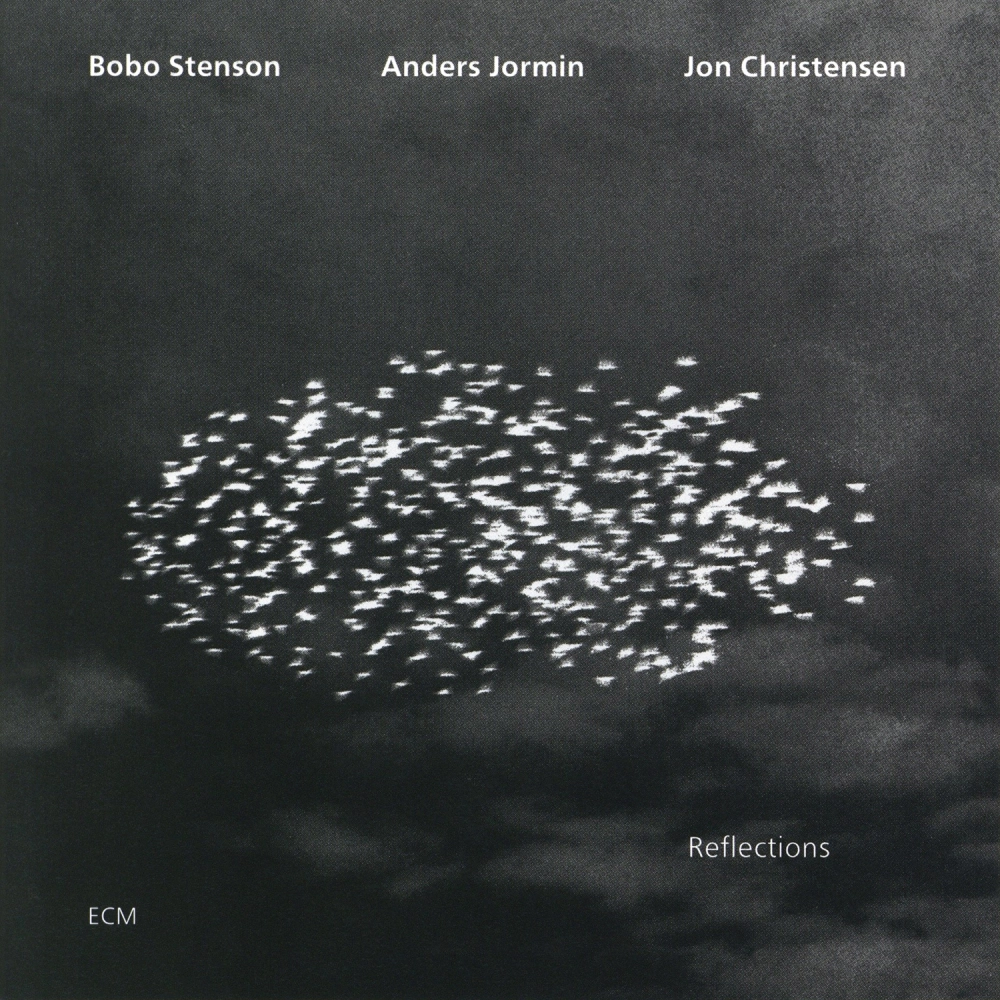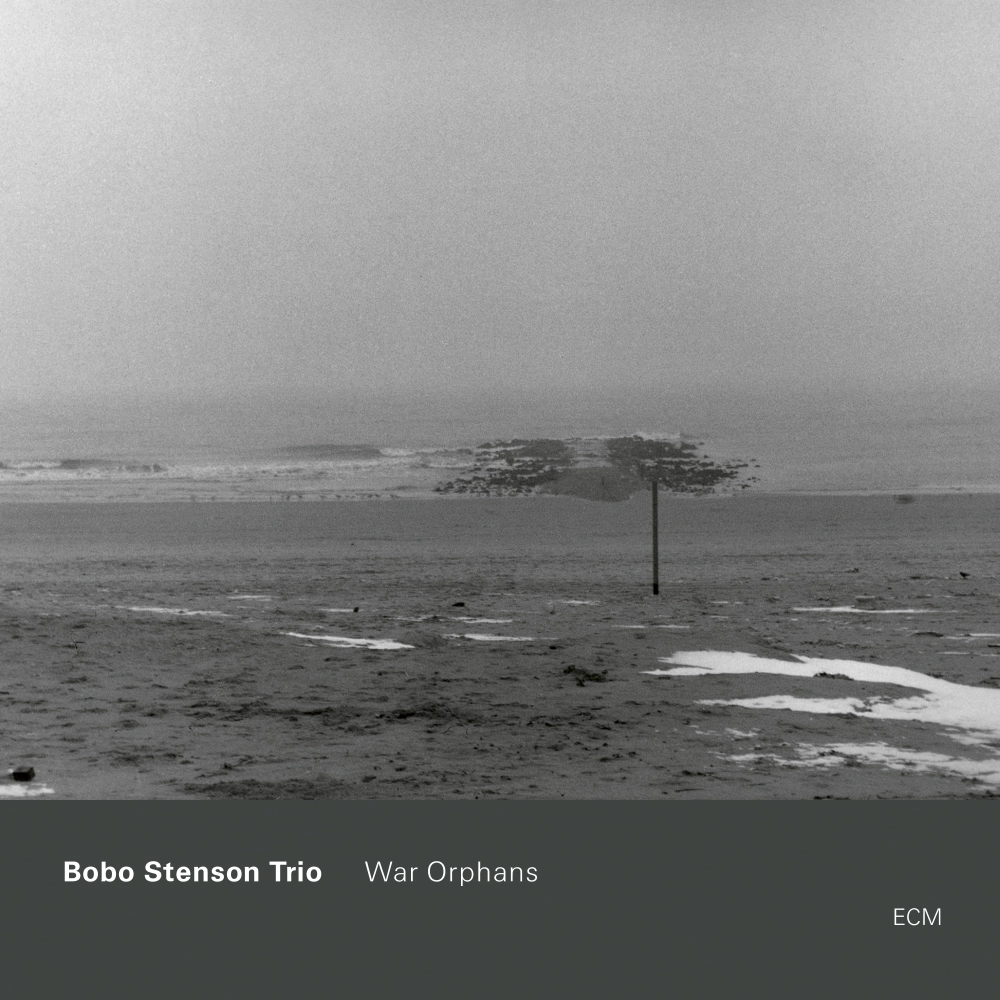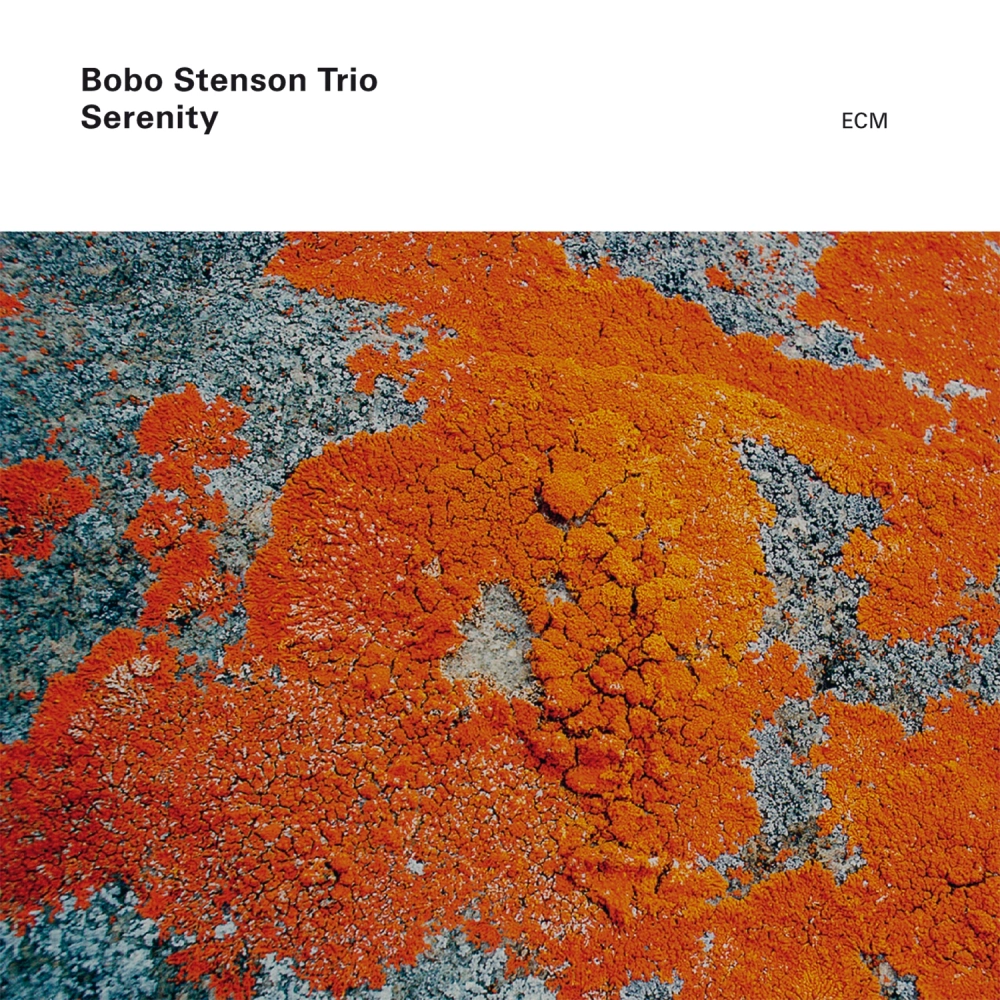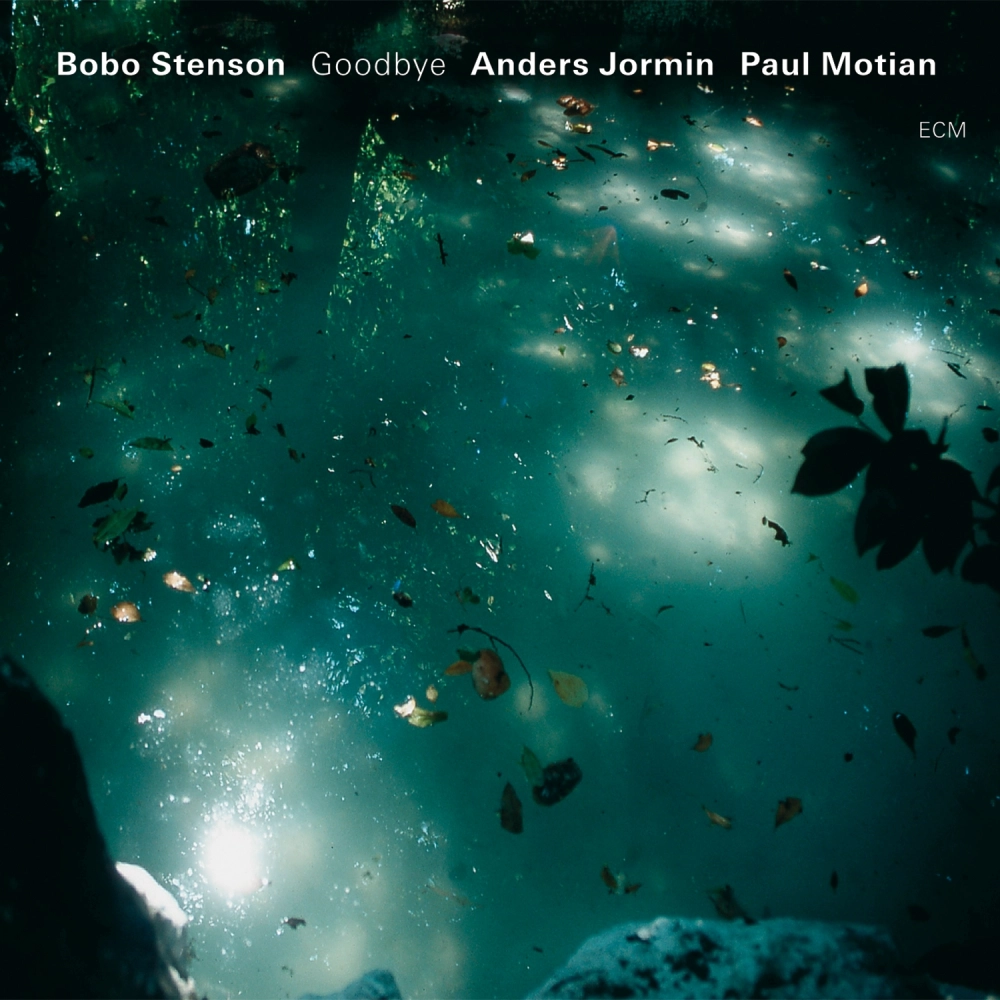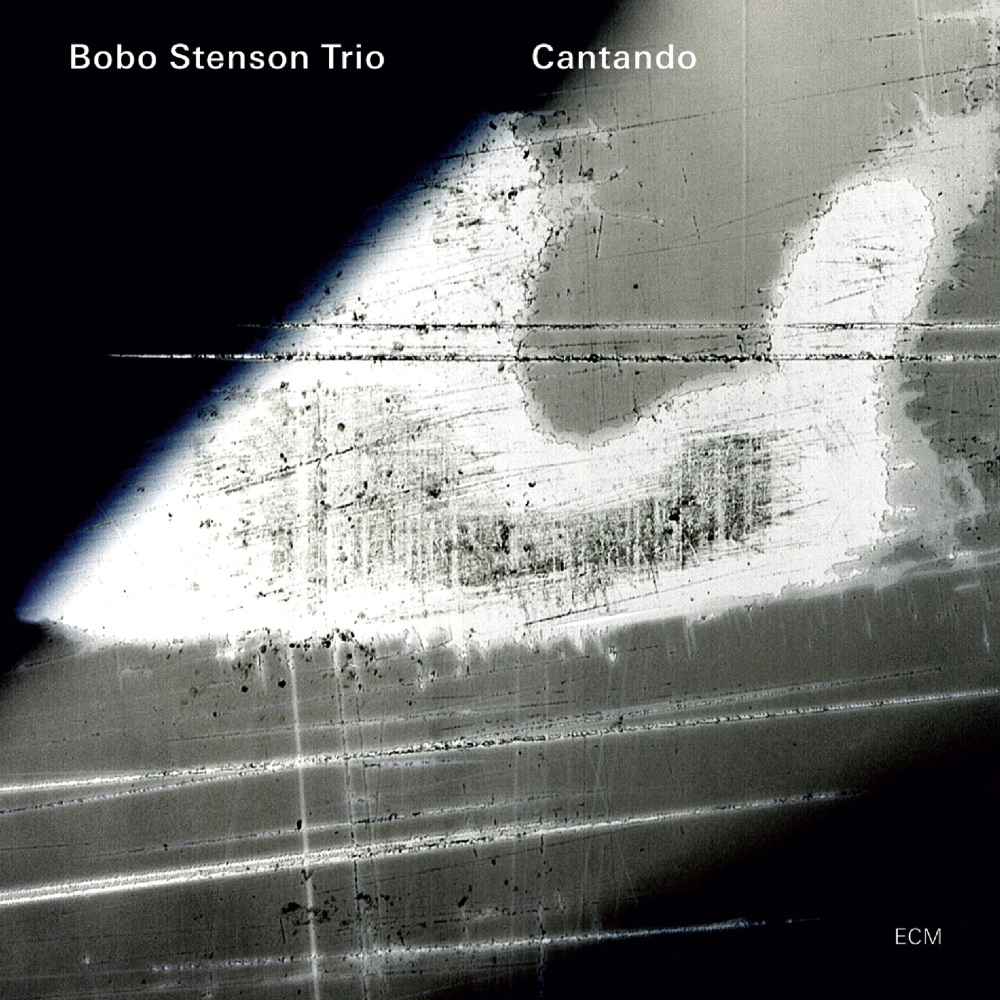October 26, 2012
|
| 今週の批評から Reviews
of the Week
|
|
|
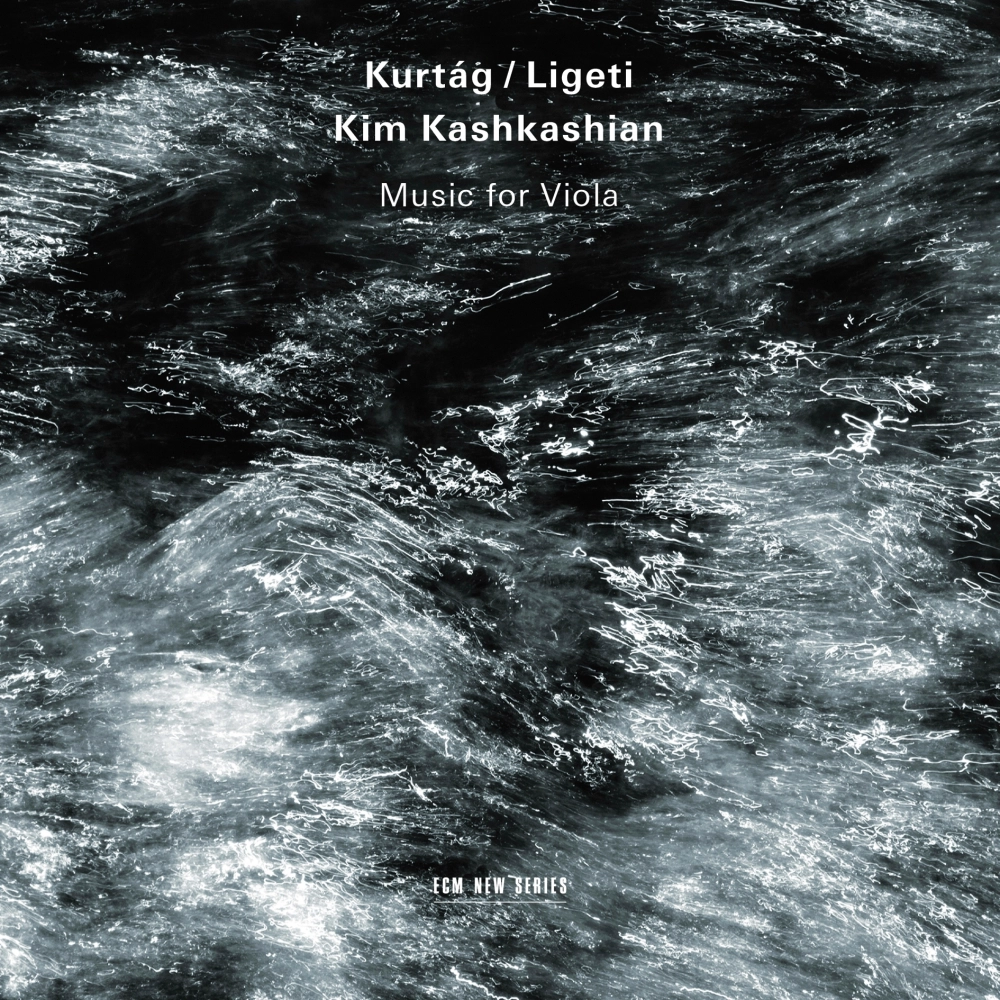 |
キム・カシュカシャン
Kim Kashkashian による新しい録音、ジェルジ・クルターグ
György Kurtág とジェルジ・リゲティ
György Ligeti というハンガリー出身の二人の作曲家の作品を取り上げた《クルターグとリゲティ;ヴィオラのための音楽
Kurtág / Ligeti, Music for
Viola》(ECM New Series 2240)について、「タイム・アウト・シカゴ」に掲載されたレヴューです。
|
|
| |
現代音楽においては、新しく開拓された作曲語法を聴衆に正しく届けるために、それを流暢な音楽的言語として体現して伝えることのできる優れた演奏者の存在が必要とされる。世界各地のコンサートホールでソロのヴィオラ奏者としての活躍を続けているキム・カシュカシャンは、このアルバムを通じて卓越した桂冠詩人ばりの溢れ出る弁術を駆使して、クルターグとリゲティの音楽を見事に“物語って”いる。《ヴィオラのための音楽
Music for Viola》と題された本作はカシュカシャンの最新盤に当たり、収録されているジェルジ・リゲティの過激な音楽語彙とジェルジ・クルターグの簡潔極まる音の断片が、このアルメニア系アメリカ人の手により極めて精巧なかたちで演奏されている。今年一年を通じて発売されたアルバムの中でも、最も優れた一枚である。(中略) しかしながら聴き手の中には、本作で表現されている種類の美しさを受け付けないという人もいるかもしれない。だが、唯一つ確かなこととして言えるのは、現代音楽を好むと好まざるとに関わらず、音楽芸術を愛好する者であるならば、いつの日にか必ずやこのハ音記号の譜面[訳註:ヴィオラのスコアは通常ハ音記号で記譜される]を弾きこなす優れた対話者の存在と直面する時がやって来るということだ。それはもはや避けようがない運命である。
ドイル・アルムブラスト Doyle
Armbrust
タイム・アウト・シカゴ Time
Out Chicago
|
|
| |
|
|
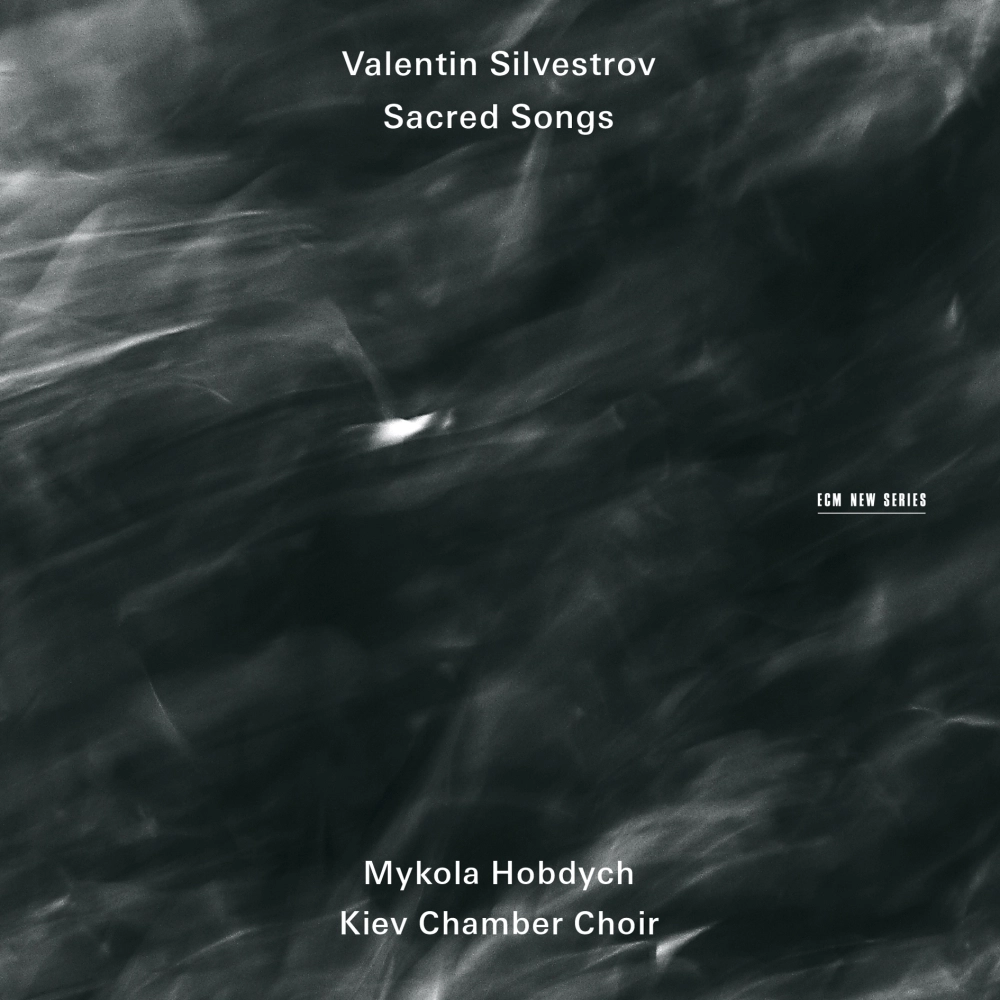 |
ヴァレンティン・シルヴェストロフ
Valentin Silvestrov の《セイクレッド・ソングズ(神聖な歌)
Sacred Songs》(ECM New Series 2279)が、classicalmodernmusic.com で紹介されています。
|
|
| |
音楽は内在的論理によって展開するものではあるが、それだけでなく、ある種の情熱を伴う聖なる雰囲気の探究という側面も持っている。それゆえに作曲家が音を使って聴き手の心に直接働きかけようと望んだ場合、現代的な旋律や和声の可能性を鮮烈な手法で駆使しているつもりが、ふと気がつくと、伝統的価値の存在に同意を示していたりすることが起こり得るわけである。シルヴェストロフは、いにしえの時代に実践されていた作曲様式への回帰を企図したアルヴォ・ペルト
Arvo Pärt のような技法的観点から古楽を参照することはしていない。そうではなく、紛(まご)うことなきシルヴェストロフ自身の独創的かつ人々の心を深く惹きつける音楽的プロセスを歩みながら、今もなお創作を続けているのである。
グレッグ・アップルゲイト・エドワーズ Greg Applegate Edwards
ClassicalModernMusic.com
|
|
| |
|
|
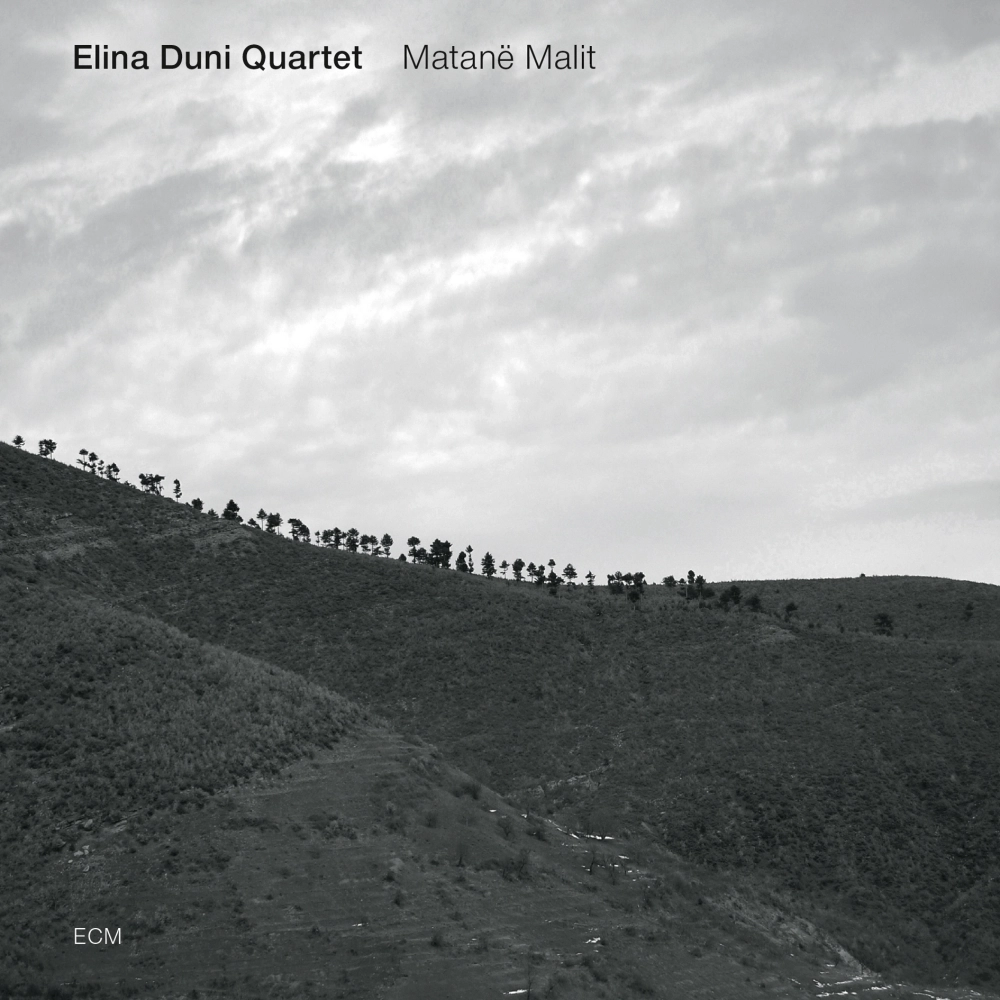 |
エリーナ・ドゥニ・クァルテット
Elina Duni Quartet 《マタン・マーリツ
Matanë Malit》(ECM 2277)が、米国と英国のプレスで絶讃されています。
|
|
| |
今年一年間に世界中のジャズ・シーンに多くの新人歌手が登場したが、この《マタン・マーリツ
Matanë Malit》[註:このタイトルはアルバニア語で、英語に訳すと“Beyond the mountain(あの山の向こう)”]と題されたアルバムで聴くことができるのは、そのなかでも最も魅惑的な声の持ち主の一人であると断言できる。エリーナ・ドゥニ
Elina Duni はアルバニア Albania 出身のジャズ・シンガーであり、またクラシックの声楽を学んだ歌手でもある。本作では素朴で清らかな天賦の声を駆使して、バルカン半島のフォーク・ミュージック(民謡)を自らのサウンドの中に見事に取り込んで聴かせてくれる。(中略) 《マタン・マーリツ
Matanë Malit》はじつに美しく彫琢されたアルバムだ。アルバニア民謡が優雅な雰囲気を纏ったジャズへと見事な変容を遂げている。
アンヘル・ロメロ Angel Romero
ワールド・ミュージック・セントラル World Music Central
|
|
| |
本盤では民謡という伝統的な枠組みの上に、鮮やかな彩りを纏ったセンシティヴな新しい焦点が与えられている。それを実現させたのはなんといってもエリーナ・ドゥニ
Elina Duni による民謡唱法に由来する繊細な仕方でピッチ(音高)を揺らす即興的な性質や傾向に拠るところが大だとしても、それ以外にも、彼女の歌唱を支えているスイス出身のピアニスト、コリン・ヴァロン
Colin Vallon と彼が率いる音楽仲間たちが展開する聴き手の心に働きかけて注意を促す陰翳に富んだ響きの色合いを醸し出した演奏や、さらにはエリーナ・ドゥニ自身のブルーズ風味のヴォーカリーズなど、他にも本作を支える重要な要素が指摘できるように思う。もっと正確に言えば、本盤ではサポート(伴奏)という言葉遣いは誤りであって、歌と楽器はそれぞれ継ぎ目のない滑らかな繋がり方によって完全に一体化しており、本作に参加している全ての音楽家達は、祖先から継承されてきた歌(民謡)と現代の歌を縒(よ)り合わせてひとつの詩学を拵(こしら)えることに等しく貢献している。(中略) また厳然たる事実として、本作の大部分は黙想的な雰囲気で占められているわけだが、しかしこの音楽はどこまでも“上昇”を続けながら、本当の意味で彼方へ飛び立つことを実現している。本作は強力な推薦盤である。
マイケル・タッカー Michael
Tucker
ジャズ・ジャーナル誌 Jazz
Journal
|
|
| |
|
|
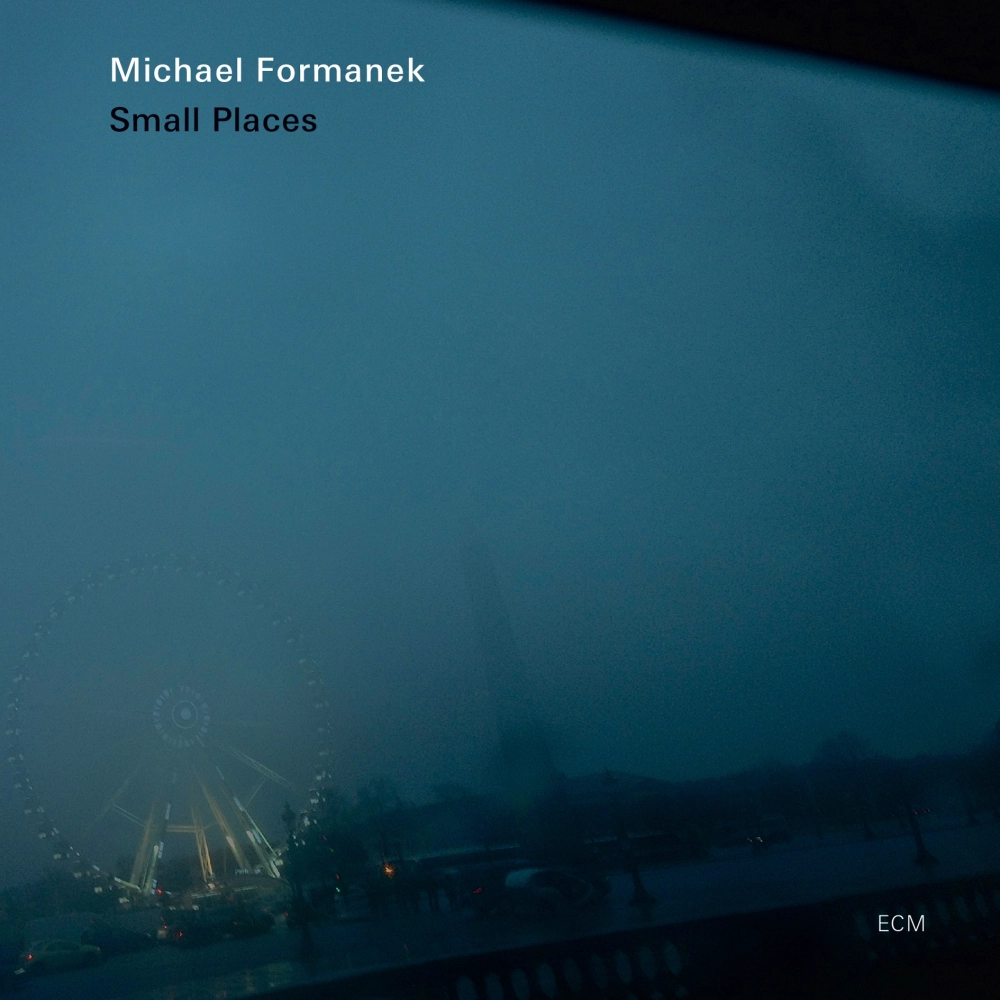 |
マイケル・フォーマネク[フォーマネック]
Michael Formanek の新作《スモール・プレイセズ
Small Places》(ECM 2267)を取り上げたレヴューが、米国の専門誌ジャズ・タイムズ
Jazz Times に掲載されました。「聴いていると、徐々に心地好い気分になってくる」という好意的な批評から、その一部をご紹介します。
|
|
| |
《スモール・プレイセズ(小さな場所)
Small Places》というアルバム・タイトルは、フォーマネクが作曲する作品の構造自体を描写しており、じつに言い得て妙である。各曲はそれぞれ沢山の小さなセクションを内包していて、音楽的な探究を実践する用意の整った演奏者であれば、誰でもがそこで提供されている何らかの素材を使って創造的な音を奏でていくことができる仕組みとなっている。またサウンド面において相当に切り詰められて静寂に近づく場面であってさえ、常にそこには緊張感が持続しており、決して弛緩することがない点も本作の特徴となっている。
マイク・シャンリー Mike
Shanley
ジャズ・タイムズ Jazz Times
|
|
| |
|
|
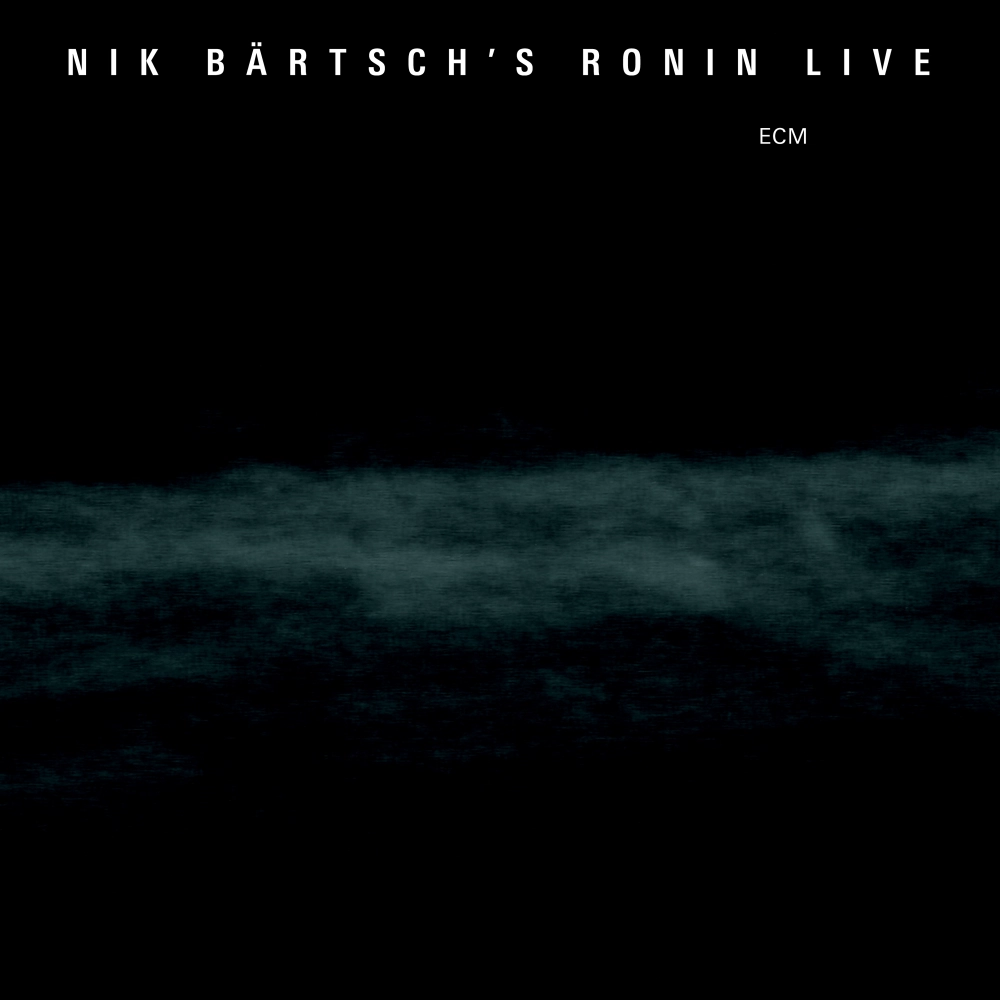 |
スイスのバンド、ニック・ベルチュ
ローニン Nik Bärtsch's Ronin の2枚組新作ライヴ・アルバム《Live》(ECM
2302/03)が、米国西海岸で強い印象を与えているようです。
|
|
|
リズム・セクションに囲繞(いにょう)されたつねに生成進化する反覆パターンの上下に、せわしなく動き続けるベルチュのピアノが複数の層を形作る。そのことによって、このグループの音楽はロックやファンク、あるいは多くの場合コズミック(宇宙的)と形容されるある種の音楽、さらには知識の裏付けを伴った一部のジャズの動向とも峻別されるスティーヴ・ライヒ
Steve Reich の音楽[ミニマル・ミュージック]等との間で、つねに戯れを演じている。ベーシストのビョルン・マイヤー[メイエル]
Bjorn Meyer とドラマーのカスパー・ラスト
Kaspar Rast が奏でるサウンドがお互いに十分に浸透し始めてきた頃合いを見て、ニック・ベルチュ
Nik Bärtsch が音楽的推進力を備えた新しい型(パターン)を奏でる。こうしたローニンの音楽は、ある局面だけを部分的に取り出して見た場合、個々の音の姿は必ずしもスイングしているとは限らない。だが、彼らの繰り出す音楽は絶えず姿を変えて動き続けており、また少しずつ展開し、膨張し、前進する姿勢を止めることがない…。
クリストファー・バートン Christopher
Barton
ロスアンゼルス・タイムズ LA
Times
|
|
| |
|
|
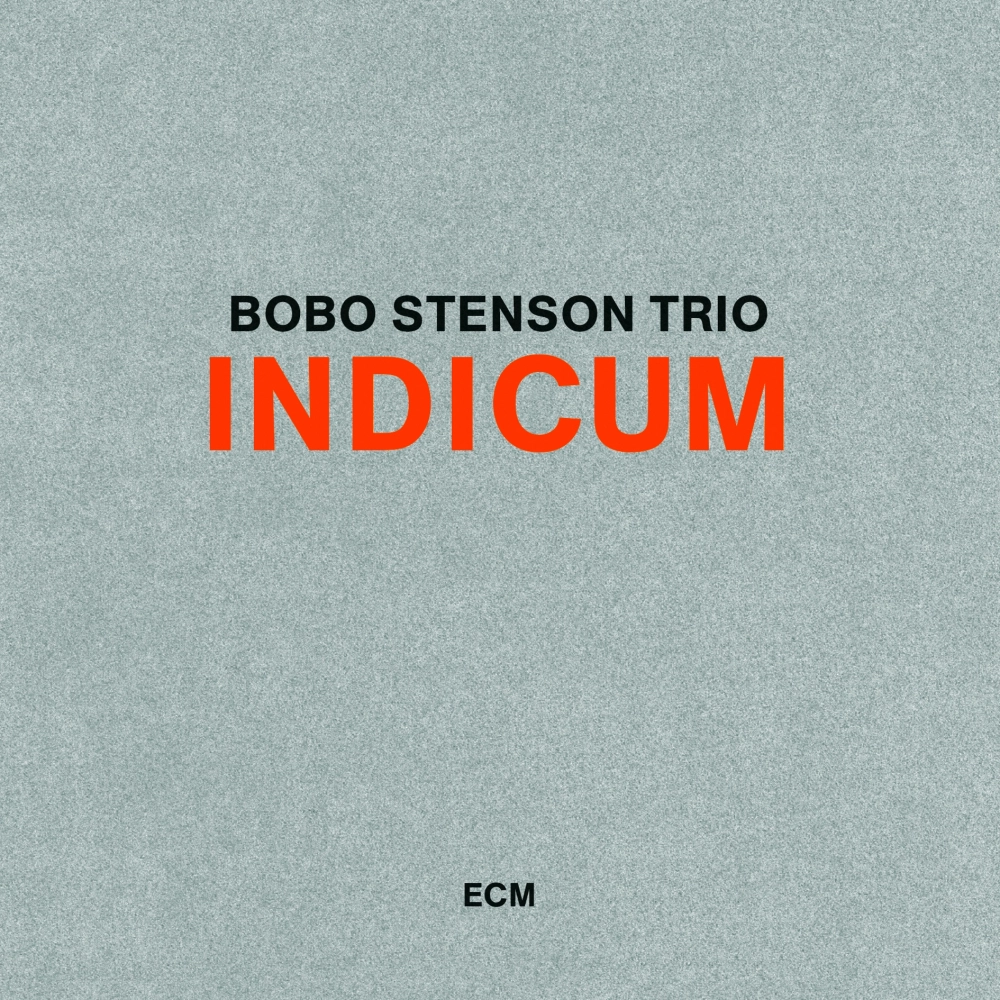 |
ボボ・ステンソン Bobo Stenson の新作《インディクム
Indicum》(ECM
2233)に対する、米国ジャズ専門誌「ジャズ・タイムズ」のレヴュー。
|
|
| |
“偉大な”という形容詞が当て嵌まる同時代のピアノ・トリオは極めて少数に限られるが、ボボ・ステンソン
Bobo Stenson がベース奏者アンダーシュ・ヤーミーン[アンデシュ・ヨルミン]
Anders Jommin とドラムのヨン・フェルト
Jon Fält と組んでいるこのトリオは、その僅かなリストに名を連ねて然るべき存在と言えよう。しかし、その隣に名前が並んでいるライヴァルのトリオ達、すなわちキース・ジャレット
Keith Jarrett、ブラッド・メルドー
Brad Mehldau、ステーファノ・ボッラーニ
Stefano Bollani、ジェイソン・モラン
Jason Moran などが率いるトリオと比べると、ボボ・ステンソン・トリオの録音数はかなり少な目である。リリースから録音までの期間が長く空いた《リフレクションズ
Reflections》(ECM 1516)を別として(1993年録音、1996年リリース)、1998年リリースの《ウォー・オーファンズ
War Orphans》(ECM 1604)から数えたとしても、本作《インディクム
Indicum》はようやく5作目という寡作ぶりである。従って今回のステンソン・トリオの新作アルバムの登場は、それだけでもう十分注目に値する出来事だと言える。ところで、ステンソンのアルバムには、有機的統一体とも呼び得る[音楽制作のプロセスに関わる]側面がある。すなわちステンソンはアルバムを制作する際に、まず最初に全面的に取り組む作業として、音楽作りの様々な起点となる素材の収集から始める。そして次の段階では、そうして集めた個々の要素を吟味し探究しながら、それらがステンソン自身の詩的かつ質素な審美的世界の内側に自由に注ぎ込まれて行くままにしておく。そして最後の段階において、それらは[実際の演奏として]熟成の時を迎えるのである。(中略) 彼が最も自分と近しく感じているピアニストはビル・エヴァンス
Bill Evans とのことだが、ステンソンの演奏が与える印象は、そのエヴァンスにも似て、孤独のまま音楽に耳を傾ける孤独な聴き手の存在を事前に思い描いている面が多くを占めている。リリシズム(抒情)を通じて表出され、孤独な他者と共に味わう悲しみは、もはや単なる悲しみとは別の何かであると言ったほうが相応しいのかもしれない。
トーマス・コンラッド Thomas
Conrad
ジャズ・タイムズ誌 Jazz Times
|
|
| |
◆補遺;
ボボ・ステンソン・トリオのECMでの録音リスト
|
|
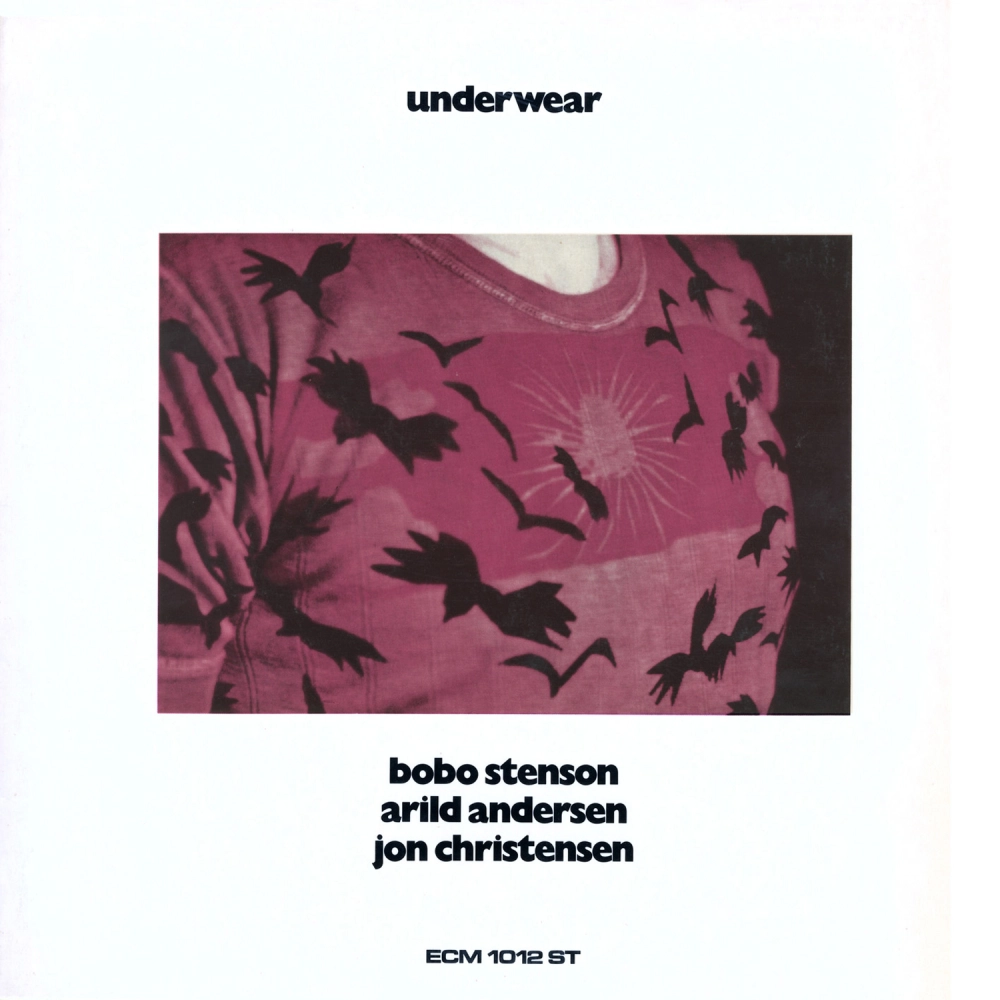
|
[1971年]
《アンダーウェア Underwear》(ECM 1012)
with Arild Andersen on bass and Jon
Christensen on drums
|
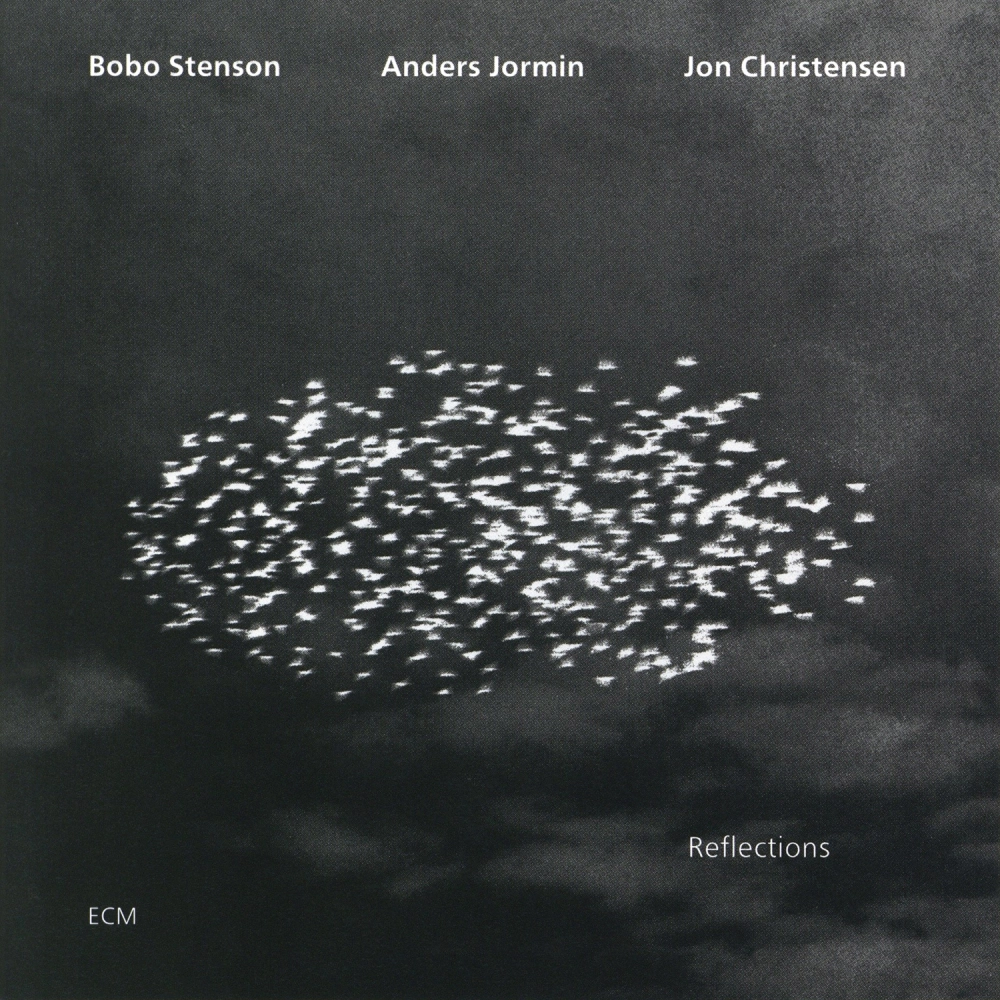
|
[1996年]
《リフレクションズ Reflections》(ECM 1516)
with Anders Jormin on bass and Jon
Christensen on drums
※スウェーデン・グラミー賞及びゴールデン・レコード賞を受賞。
|
|
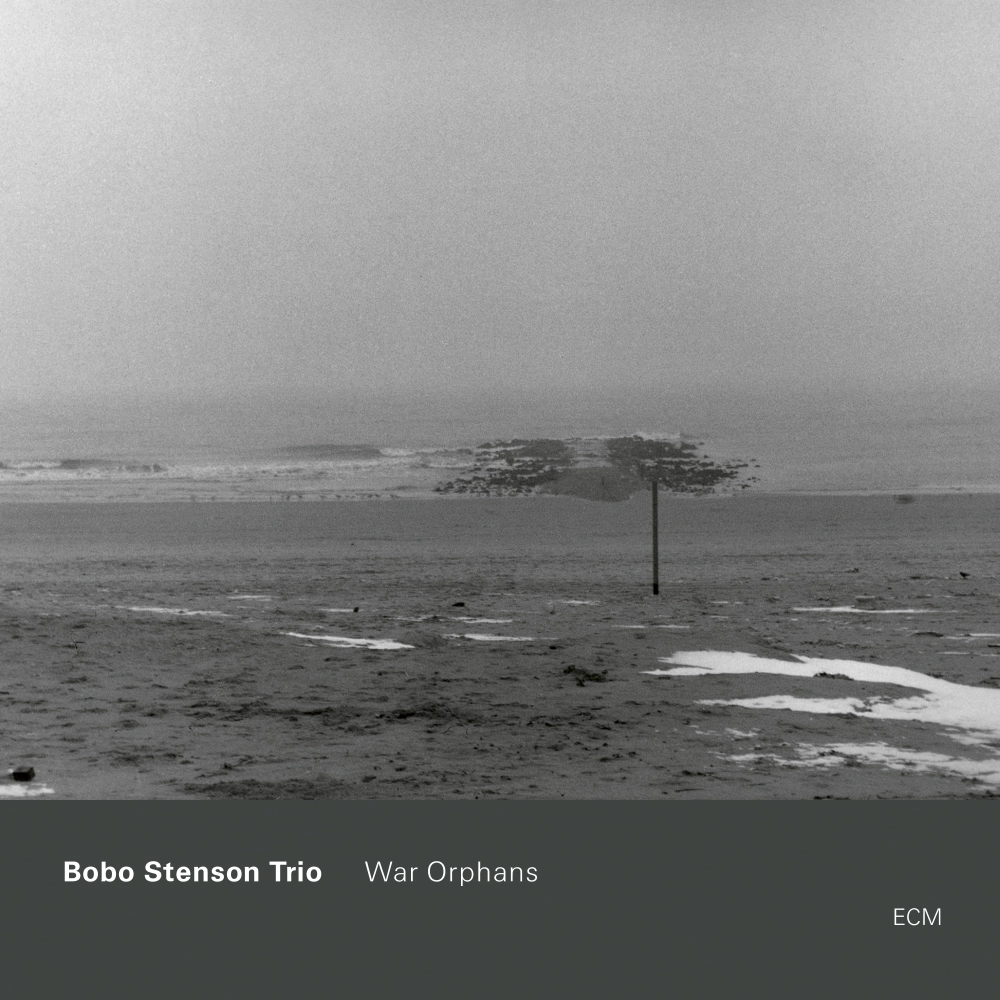
|
[1998年]
《ウォー・オーファンズ War
Orphans》(ECM 1604)
with Anders Jormin on bass and Jon
Christensen on drums
|
|
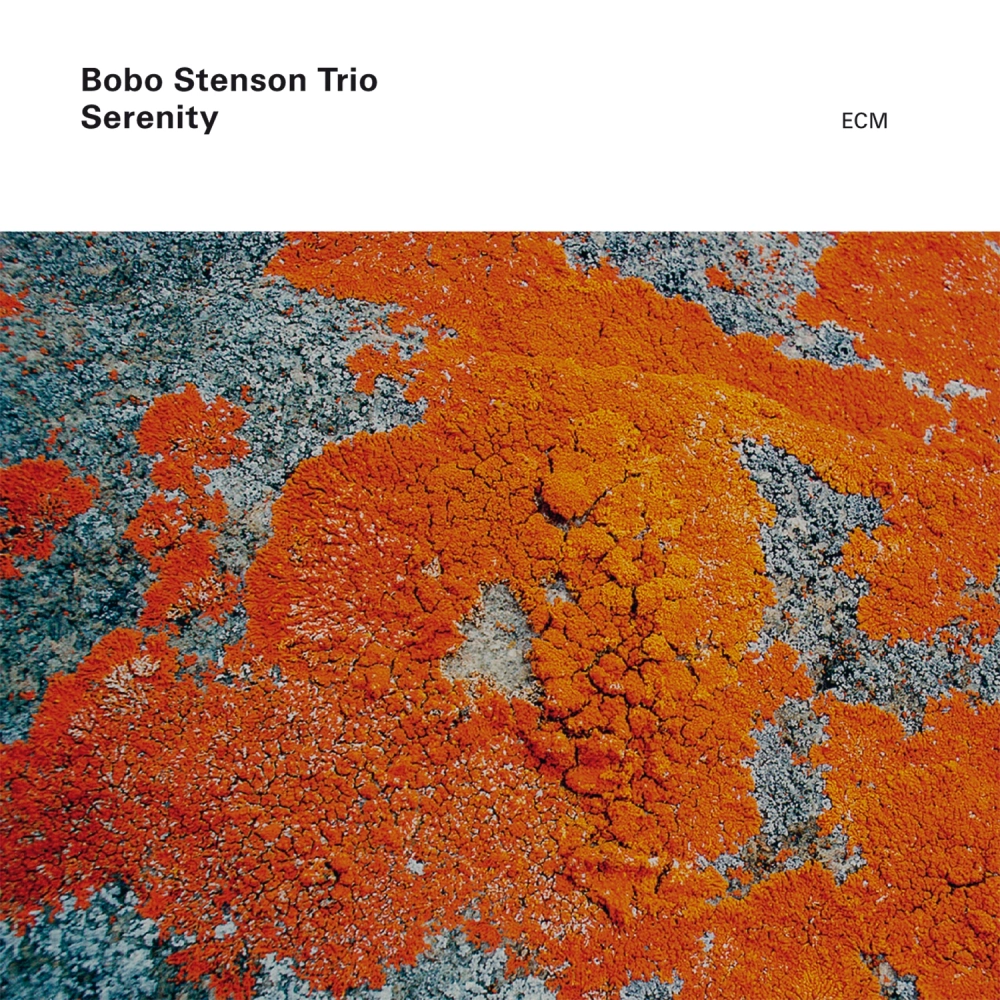
|
[2000]
《セレニティ Serenity》(ECM 1740) *2
disc-set
with Anders Jormin on bass and Jon
Christensen on drums
|
|
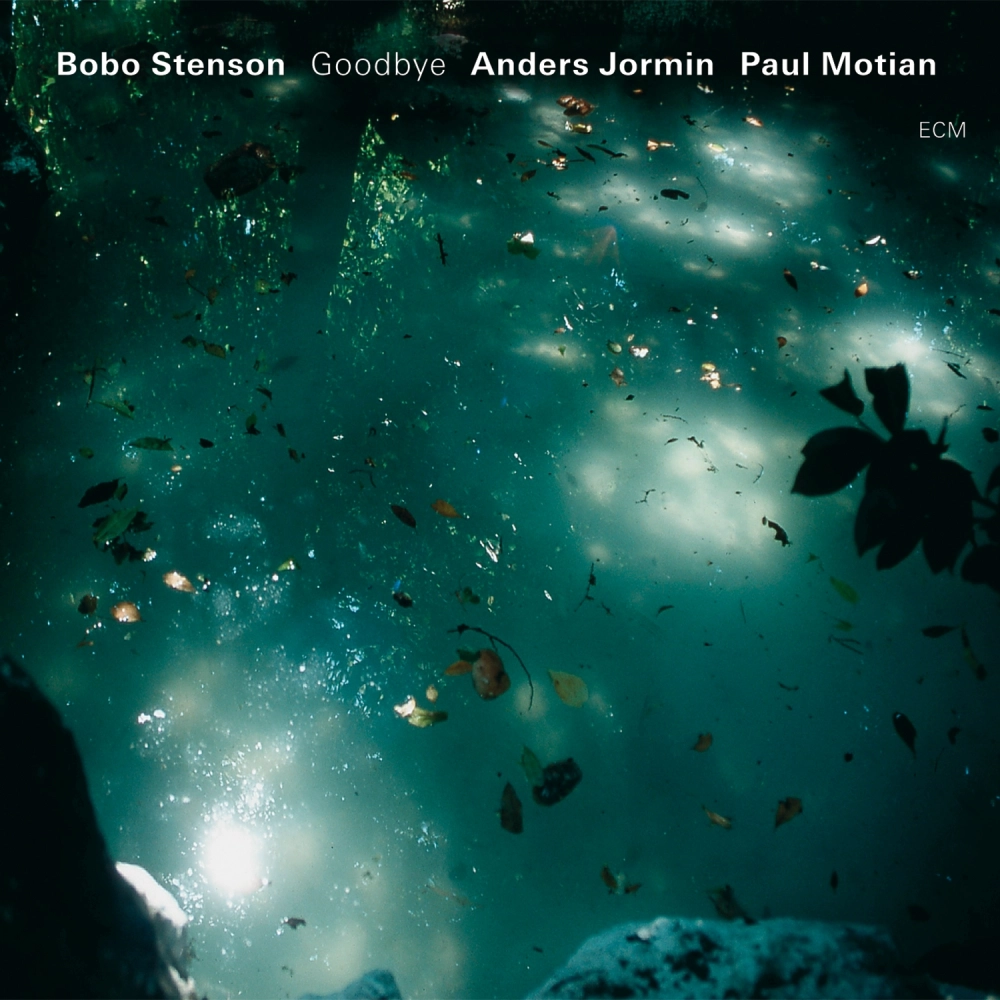
|
[2005年]
《グッドバイ Goodbye》(ECM 1904)
with Anders Jormin on bass and Paul
Motian on drums
※同年、ボボ・ステンソンにスウェーデン国王より文化功労章メダル(Litteris et Artibus)授与。その翌年にはヨーロピアン・ジャズ賞(Musician of the Year)を受賞
ECM NEWS/ECM情報;
December 7 , 2006 ▼
|
|
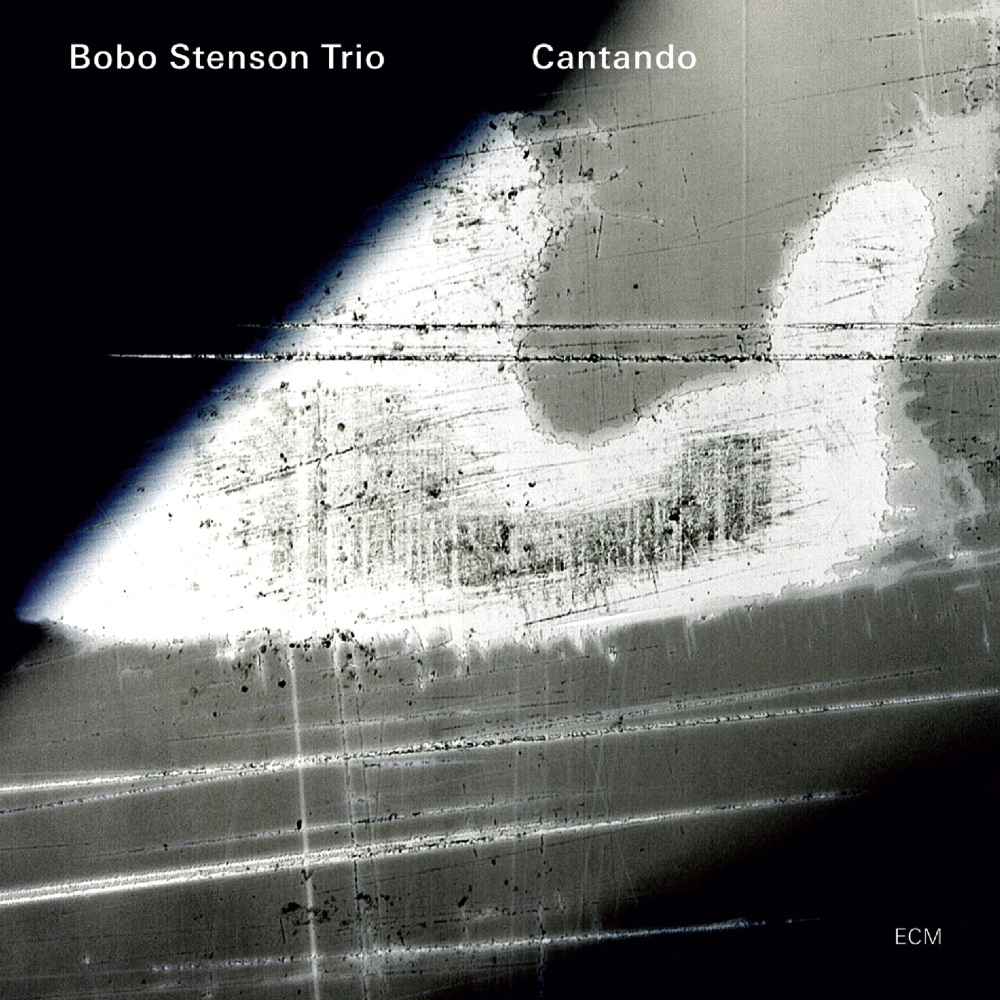
|
[2008年]
《カンタンド Cantando》(ECM 2023)
with Anders Jormin on bass and Jon Fält
on drums
※リリースの翌年、2009年度スウェーデン賞(ベスト・ジャズ・ミュージック)を受賞。
|
|
| |
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.

|
|
| |
※本記事は、ECM が発信する最新情報を ECM Records の許諾を得て翻訳掲載するものです。(musicircus) |
|
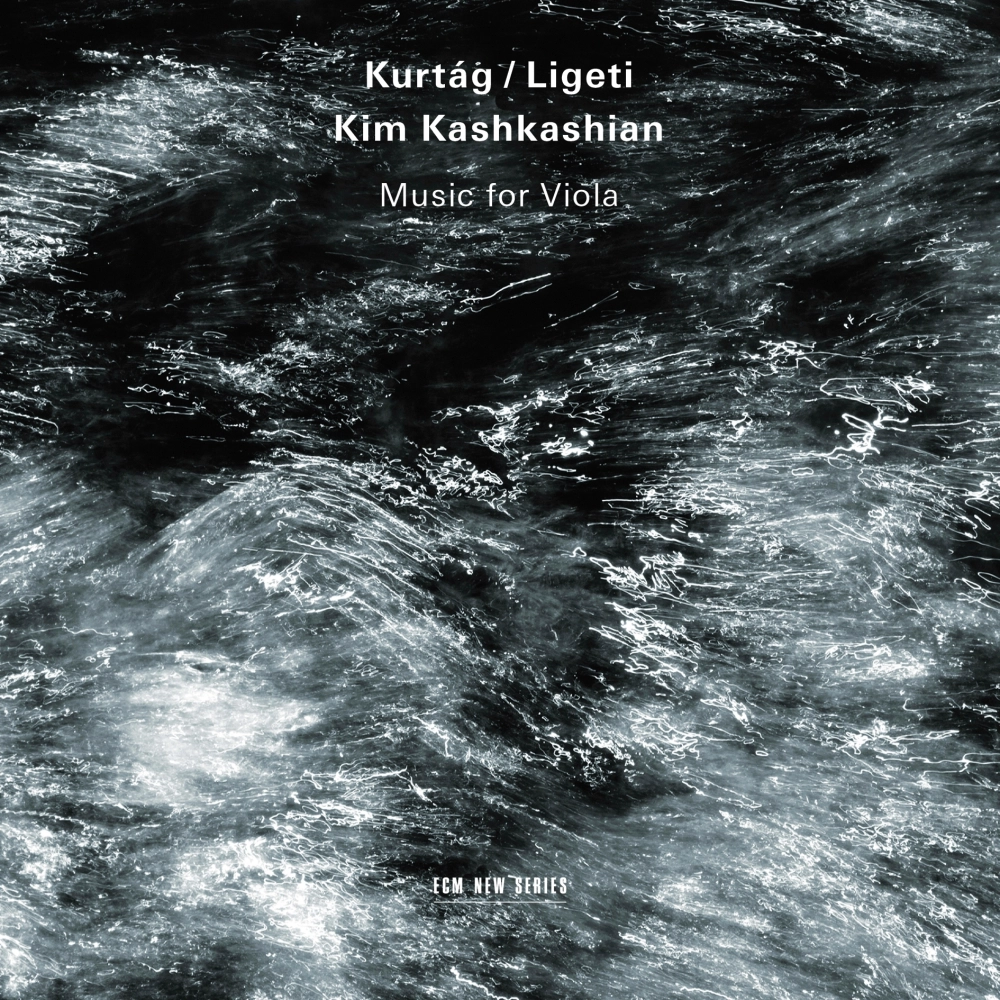
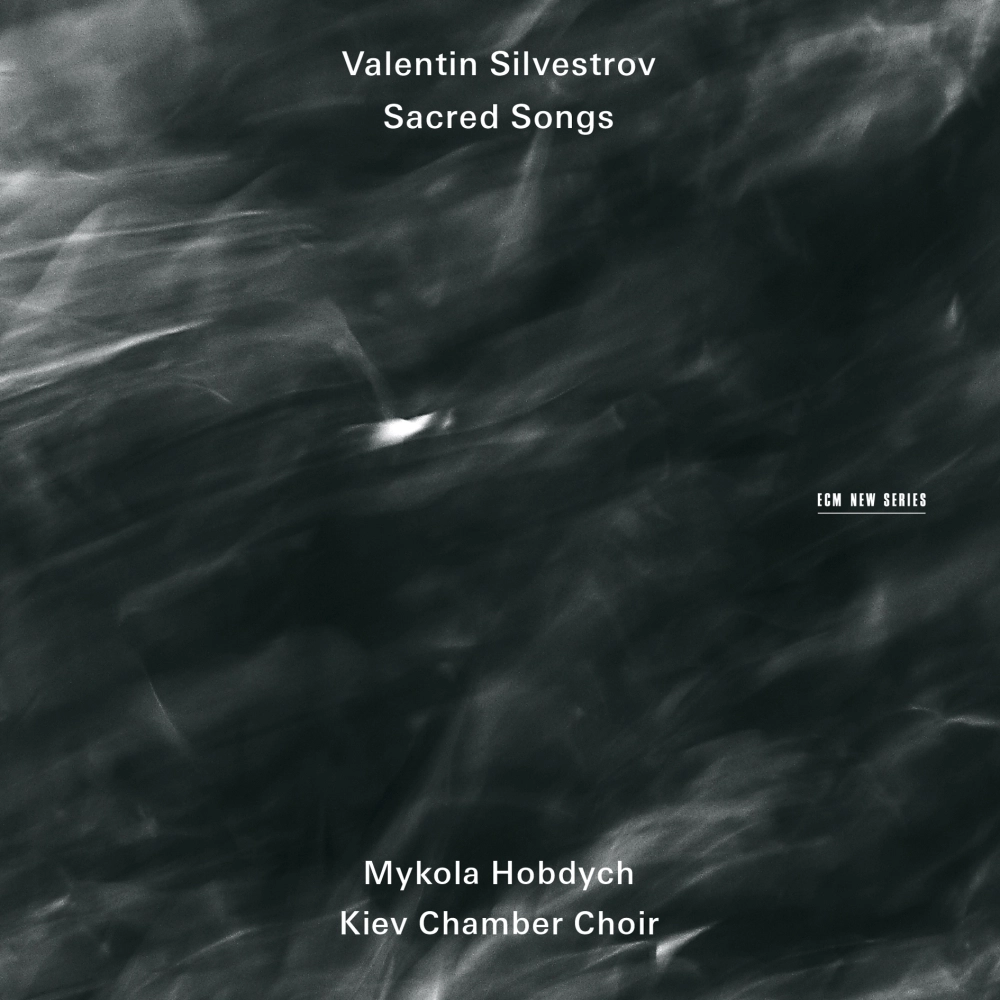
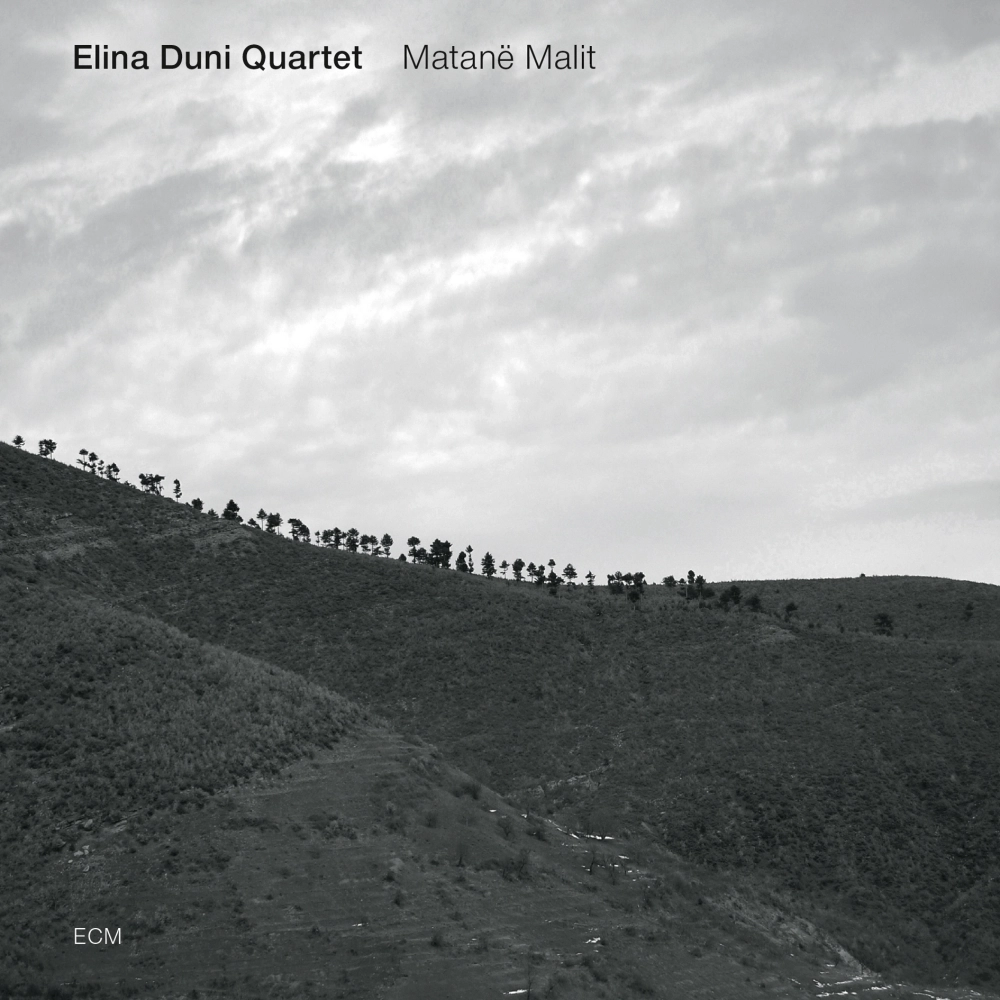
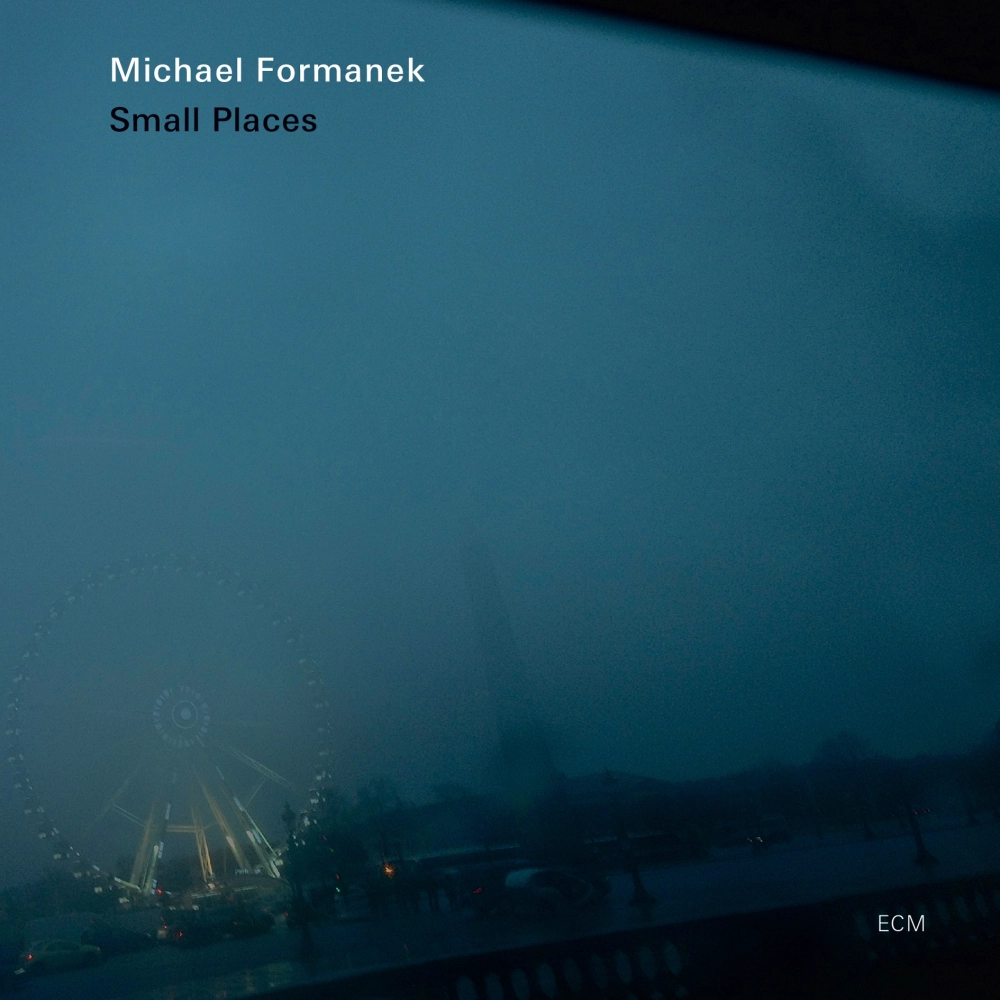
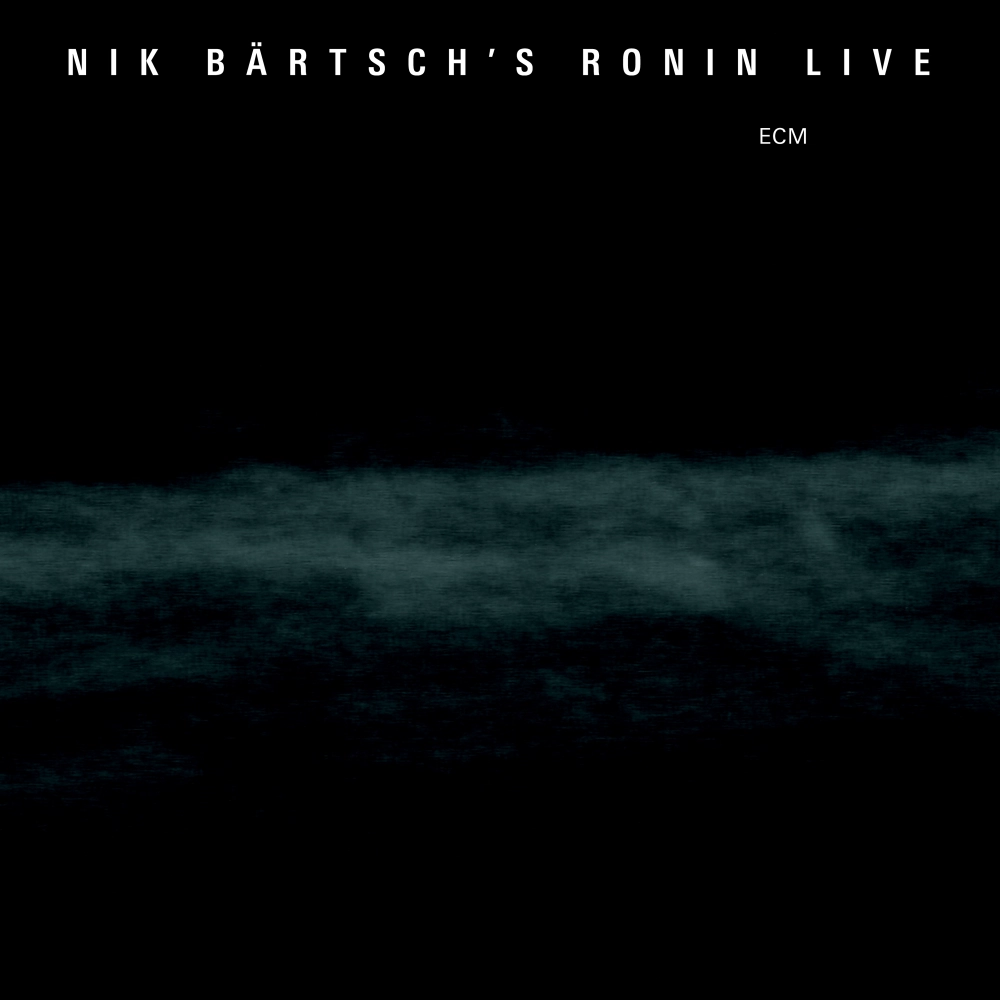
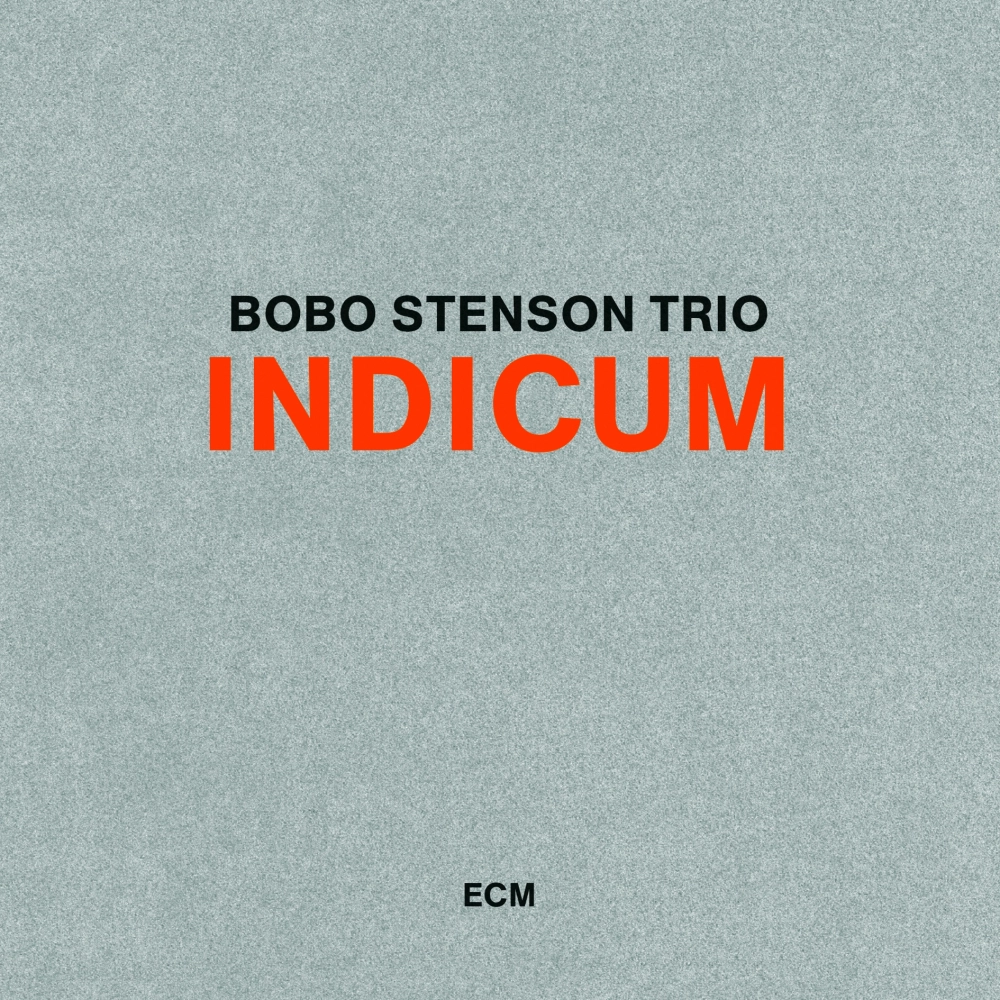
![]()