September 9, 2011
|
| 今週の批評から Reviews
of the Week
|
|
|
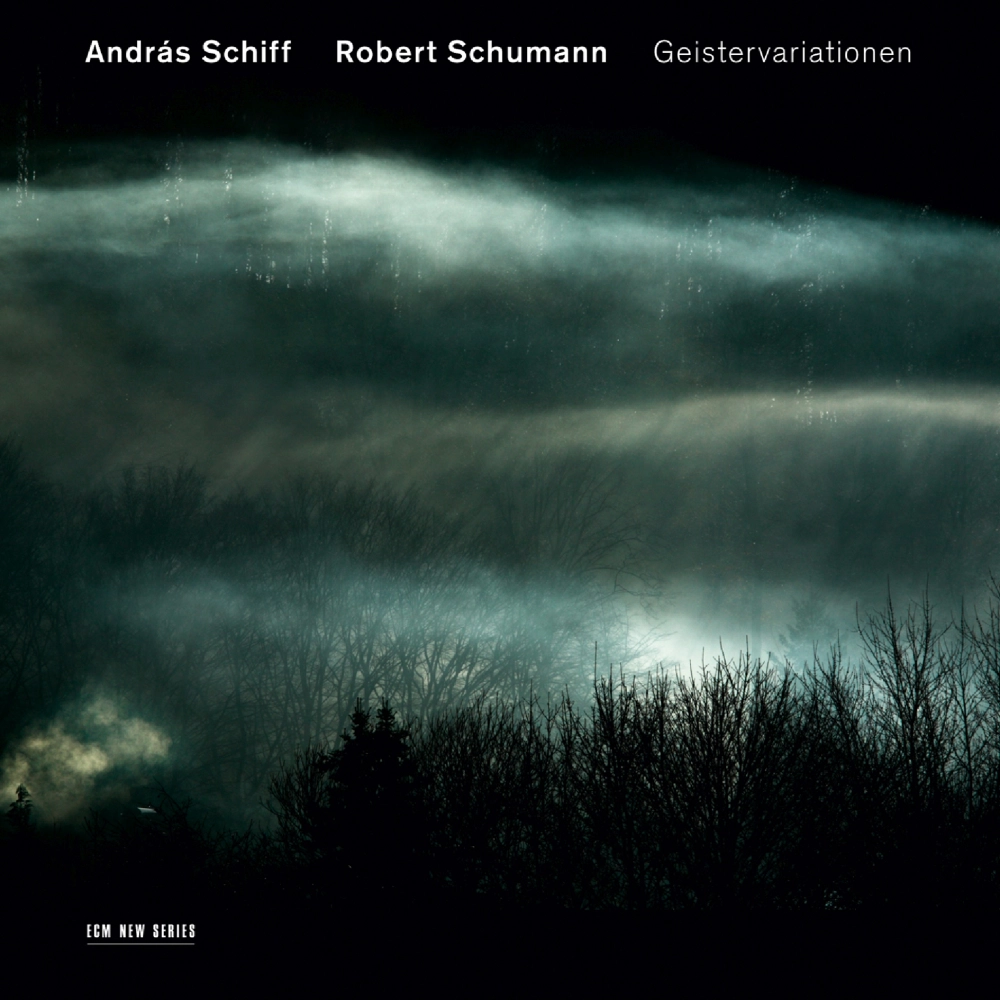 |
ピアニスト、アンドラーシュ・シフ
András Schiff
の新譜《幽霊変奏曲 Geistervariationen》(ECM New Series 2122/23)へのレヴューが英国オブザーバー紙に掲載されました。
|
|
| |
アンドラーシュ・シフは演奏家としての生涯をシューマン
Schumann
の代弁者であることに捧げてきたが、今回のリサイタル・アルバムにおいては、改めてシューマンのマニュスクリプト(自筆譜)へと立ち返っている。初期の「パピヨン(蝶々)
Papillons Op.2」と「ピアノ・ソナタ第1番 嬰ヘ短調 Op.11」から、シューマンが作曲途中で自殺を図った「幽霊変奏曲
Geistervariationen(Ghost Variations)」までの、シューマンの創作の全期間を含んだ作品を収録した内容となっている。「幽霊変奏曲」はシューマンが完成させた最後のピアノ曲で、タイトルが示唆するようなほの暗く謎めいた雰囲気をもった作品である。冒頭の主題を、シフはあたかも呼吸が停止したかのような趣で静かに弾いている。また「幻想曲
ハ長調 Fantasy Op.17」では現行の出版譜による演奏に加えて、シフはこれとは違う予期せぬ別の終結部をもつ版の演奏を追加収録しているが、これは長年にわたってブダペスト市内の図書館に秘蔵されていたシューマンの初稿譜に基づくものである。本作は、シフの極めて鋭敏で名状し難い説得力に満ちたピアニズムばかりでなく、こうしたシューマンの音楽を味わうための深い探究の試みも聴き所となっている。 フィオナ・マドックス
Fiona Maddocks
オブザーバー紙 The
Observer
|
|
| |
|
|
 |
チャールズ・ロイド
Charles Lloyd ならびに
マリア・ファランドゥーリ[ファラントゥーリ]
Maria Farantouri のライヴ録音盤《アテネ・コンサート
Athens Concert》(ECM 2205/06)。
|
|
| |
二つの異なる音楽文化がたとえ何世紀もの隔たりを有していても、さらには、その両者の文化の背景となる起源が数千マイル以上離れた土地にあるのだとしても、そこに何らかの共通の地平を見出すことが可能だという事実が、おそらくは本作《アテネ・コンサート》の偉大な成功の要因と言えるのかもしれない。ロイド
Lloyd とファランドゥーリ
Farantouri はお互いの音楽の伝統との相互浸透を果たすべく少なからぬ準備期間を費やしたが、その間つねに開かれた心を失うことなく、このサックス奏者が率いるクァルテットに所属するとびきりの個性を有した音楽家達と今回のプロジェクトに特別参加したギリシア出身の二名の音楽家達との間で徐々にお互いの理解を深めてこの87分間に及ぶコンサートを見事に演じ切るまでに至った。本アルバムのどの一瞬を切り取ってみても、二つの文化の音楽家たちの長い音楽人生における全ての仕事の文脈と重なり合うものとなっている。アーティストによる表面上は共通点の見られない別々の伝統文化を融合する試みは何ら珍しいことではないが、しかしそれがこれほど高いレベルで成功しているのはじつに稀少なことである。この《アテネ・コンサート》におけるふたつの音楽文化の継ぎ目のない滑らかな合一は、もしかするとこの両文化の間には当初から何か共通する観点が潜んでいて、まさに本作で発見されるのを待っていたのではなかったかという空想を引き寄せずにはおかない。 ジョン・ケルマン
John Kelman
オール・アバウト・ジャズ All about jazz
|
|
| |
ロイドは70歳代を迎え復活を満喫している魂のこもったサックス奏者である。ファランドゥーリは崇敬を集めるギリシアの歌手だ。この二人の音楽家は、もうかれこれ十年間に及ぶ友人同士であり、昨年(2010年)アテネでジョイント・コンサートを開催し、その記録が二枚組のCDとしてリリースされた。これは心の奥から揺さぶられる事件である。(中略)
ファランドゥーリの朗々としたコントラルトの周りにロイドのサクソフォンが渦巻くように纏(まと)わり付き、深い精神的な美に満ち溢れた音楽を産み出している。 ジョン・バンゲイ
John Bungey
英国「タイムズ」 The
Times
|
|
| |
|
|
 |
ディノ・サルーシ Dino Saluzzi、アニヤ・レヒナー
Anja Lechner、フェリックス・サルーシ
Felix Saluzzi のトリオによる新作《ナビダッ・デ・ロス・アンデス(アンデスのクリスマス)
Navidad de los Andes》(ECM 2204)へのレヴューが英国のガーディアン紙
The Guardian に掲載されました。
|
|
| |
《ナビダッ・デ・ロス・アンデス》は、薄暗い闇に包まれた山岳風景から村人たちの民俗舞踊に至るまで、アンデス地方のすべてのイメージを呼び起こしてやまないじつに魅惑的な力に溢れた作品である。ここでは、囁くような高音が低い残響音へと劇的に潜り込むチェロの儚い響きと、バンドネオンの和音による悲しげな短い音の身振りの下で、いくつもの変奏曲が波のように満ち引きを繰り返している。尤(もっと)も、なかには激しいアクセントをつけた小品が描き出す短時間の心情の爆発が姿を見せる場面もあるが、各楽器はそこでもあくまで優雅な身振りでお互いに追いかけ合い、そして即興で演奏された部分と予め作曲された部分の区別がほとんどできないまでに一体化した対位法的なパッセージを編み合わせていく。トラック5の〈Requerdos
de Bohemia〉では、フェリックス・サルーシ
Felix Saluzzi のテナー・サックスが深夜に煙で目を瞬(しばたた)かせるような味わいを醸し出して驚かせるが、こうした憂鬱な上品さが音楽の気分を一新する雰囲気を与えているという面もある。 ジョン・フォーダム
John Fordham
英国ガーディアン紙 The
Guardian
|
|
| |
(c) ECM Records, Munich. Used by
permission.

|
|
| |
※本記事は、ECM が発信する最新情報を ECM Records の許諾を得て翻訳掲載するものです。(musicircus) |
|
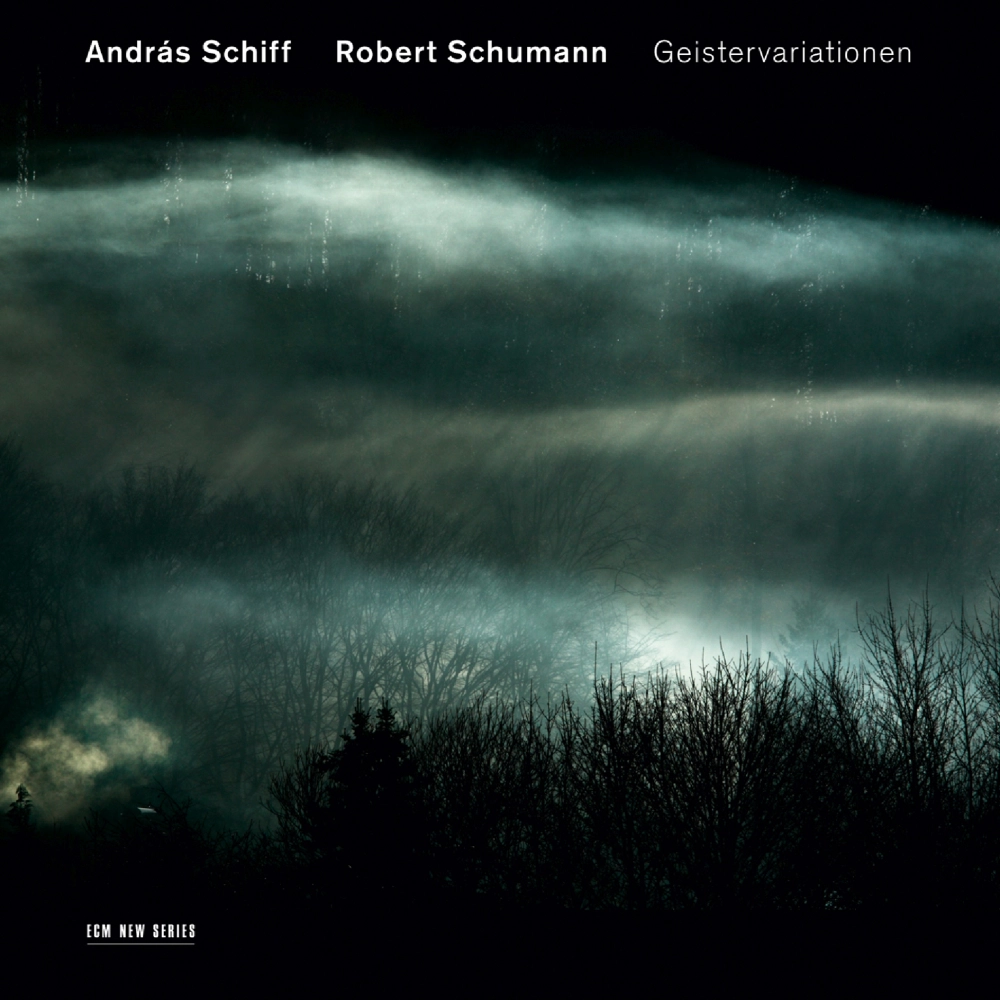


![]()