|
|
新旧取り混ぜて、この一年に聴いて印象深かった音楽・映像作品について。下記では取り上げていないが、ニック・ベルチュ「ローニン(浪人)」の《ストア》も繰り返しよく聴いたアルバムだった。──ベルチュは来日公演もあり素晴らしい演奏に接することができた(▼)。 ジム・オルークが武満徹の図形楽譜作品『ピアニストのためのコロナ Corona for Pianist(s)』(1962)を多重録音で演奏したアルバム《コロナ - 東京リアリゼーション》は、2006年度の芸術祭優秀賞を受賞した。本作はライナーノーツを書かせてもらったこともあり、その執筆準備のため上野毛の多摩美術大学の瀧口修造文庫に行って武満徹が瀧口修造に贈った「コロナ」のスコアをじっくり拝見し、レコーディング現場にも立ち会わせていただいた。 |
||||
 |
Jim O'Rourke "Corona: Tokyo Realization" Corona for Pianist(s) Written by Toru Takemitsu Columbia Music Entertainment COCB 53573 (Japan) (CD) Released in November 2006 ■ ジム・オルーク/コロナ-東京リアリゼーション 武満徹 《ピアニストのためのコロナ》(1962) コメント:ジム・オルーク、解説:堀内宏公 Congratulations ! セタビ Podcasting Vol.5 ジム・オルーク
インタヴュー ■ |
|||
|
||||
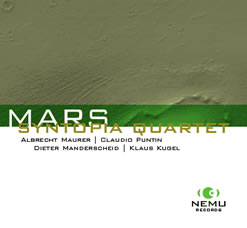 |
Mars / Syntopia
Quartet Nemu Records - NEMU 001 Albrecht Maurer - violine, gothic fiddel Claudio Puntin - clarinet, Bassclarinet Dieter Manderscheid - bass Klaus Kugel - percussion, soundobjects 1. Goodby Earth 2. Chryse Planitia 3. Tempe Terra 4. Elysium Planita 5. Valles Marineris 6. Olympus Mons 7. Newton Basin 8. Chasma Boreale 9. Back To Earth Recorded & mixed by Albrecht Maurer,
August 2003. ドイツ出身の二人の音楽家、アルブレヒト・マウラー(vn)と、クラウス・クーゲル(perc)が新たに設立したインプロヴァイズド・ミュージックのレーベル“nemu records”から至高の輝きを放つアルバムが登場。アコースティックな編成によるフリー・ミュージックで、さまざまな民族音楽の要素も反映させた野心的な内容だ。 |
|||
 |
『瞽女』(LP) 盲目の旅芸人、瞽女(ごぜ)。何十年・何百年と人々が生きて積み重ねた歴史の地層。瑞々しい歌声と峻烈な三味線のバチ捌きを聴いていると、胸がいっぱいになってきて苦しい。感動という言葉すらここではあまりに軽すぎて、歌はもっと遠い魂の住処へと連なって弾け、散り、咲き、巡る。注がれる光の帯。瞽女さんは神だ。津軽三味線をはじめ、各地の有名な民謡で瞽女唄から影響を受けて派生したものも多い。 2005年4月25日、最後の瞽女小林ハルさんが105歳で亡くなった。小林さんの96歳時の演奏を記録したCDも貴重だが、ここに掲げたのは、高田瞽女(杉本キクエ、五十嵐シズ、難波コトミ)と、長岡瞽女(中静ミサ、金子セキ、加藤イサ)の演奏を両面に収録したLPレコード(CBSソニー:SODL-25/監修・解説=斎藤真一/制作=渡部幸世/録音=半田健一)。録音は、1973年(昭和48年)3月7日~9日(高田)、10日~11日(長岡)。同社からは3枚組LP『越後の瞽女唄』(SODZ 1-3)も出ているが、ボックス盤には収録されていない本盤が初出の曲もあるようだ。昭和48年3月の録音テープの完全なかたちでの一刻も早いCD化を切に願う。 2005年には、映画『はなれ瞽女おりん』(1977)[監督=篠田正浩/原作=水上勉/音楽=武満徹/主演=岩下志麻]がようやくDVDになった。 |
|||
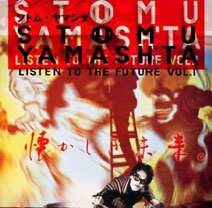 ※このアルバムは、通常CD(SSCL-2)とSACD盤(SSGL-5003)の二種が発売されている。 |
『ツトム・ヤマシタ/Listen to
the Future Vol.1 懐かしき未来』 1350万年前の火山溶岩から生まれた、音を発する石「サヌカイト」。なんという澄んだ響きだろうか。濁りのない、透明な音。真っ直ぐに伸びていく勁(つよ)さと同時に、軽く押すとそれを跳ね返す柔らかい弾力も併せ持つ。冷たくて暖かい、不思議な膜面で包み込まれているような心地のなか、遊び疲れた子供たちが家路についた後、夕陽のなかで回り続ける風車の情景がふと浮かぶ。この音楽を聴いていると、シュティフターを思い出す。 アーダルベルト・シュティフター Adalbert Stifter の小説『石さまざま Bunte Steine』。全6作品の内、「水晶」、「みかげ石」、「石灰石」、「石乳」の四篇を二分冊で収録した岩波文庫版を愛読していたが、今年2006年、「電気石」と「白雲母」を加えた新訳の完訳本が松籟社から出版された(■)。シュティフターの物語は、自然の名状し難い神秘と苛酷な猛威を丹念に描きつつ、困難な事態との直面に際してもなお清澄な眼差しを失わない子供たちと、その周辺で起こる出来事とを、救済への揺るぎない信念と共に、抑えた筆致でひそやかに綴っていくというもの。 ツトム・ヤマシタがスペシャル・プロジェクト「Go」を解散して日本に戻り、京都の寺に籠もって「音の心」と向き合うなかで創造した連作が《いろは》だった。それは、レコードの一面が、ザァーと降り続ける雨音の向こうに読経の声が小さく延々と続くだけといった部分に象徴されるように、無常と平安を行き交う魂の遍路行であった。そして、禅でいう「身心脱落(しんじんだつらく)」の境地で楽器を打つようになったとき、まるでそれを待っていたかのようにサヌカイトが現れる。こういうことはもはや偶然ではない。 現在は、世界各地の聖地で音による祈り「供音式(くおんしき)」を行なっているが、一昨年、妙心寺山内霊雲院の主催で、霊雲派祖大寂常照禅師五百年遠諱記念の供音式「音禅」が執り行なわれた際には、その様子の一部がテレビでも放映されて大きな反響を呼んだ。 そしてついに新しいレコーディング作品が出来上がり、アイスランドでリリースされた。収録されているのは、2005年の愛知万博でも演奏された(あのときのライヴは会場にも聴きに行ったが本当に素晴らしかった)、歌手ラッガ、詩人ショーンとのコラボレーションによる作品『エコー』。少女たちの合唱、キーボードも加わった壮大な音の叙事詩。サヌカイトの悠久の響きが、子供たちの祈り、苦痛と絶望の告白、世界への問いかけと呼応する。なんと優しく、気高く、美しい音楽であることか。 |
|||
 |
Ragnhildur Gísladóttir
- Stomu Yamash'ta - Sjón bergmál - echo ツトム・ヤマシタ/ラグンヒルドゥル・ギスラドッティル(ラッガ)/ショーン 『bergmal / echo / こだま』 Smekkleysa / SM 138 Music: Ragnhildur Gisladottir and Stomu Yamash'ta Poems and lyrics: Sjon Skolakor Karsness (カウルスネス学校少年合唱団) Stoma Yamash'ta (ツトム・ヤマシタ) Ragnhildur Gisladottir (ラグンヒルドゥル・ギスラドッティル) Sigtryggur Baldurssan (シグトリギュール・バルドゥールソン) David Thor Jonsson (デヴィッズ・ソール・ヨンソン) 1. fate / 2. an oracle / 3. angels i / 4. angels ii / 5. angels iii / 6. angelic children / 7. the grown ups talk / 8. children / 9. the children ask / 10. answers / 11. fortune / 12. lullaby / 13. dawn i / 14. dawn ii / 15. echoes Bergmal (Echo) is the collaboration of Ragnhildur Gisladottir (ex-Grylurnar, Studmenn, etc), Japanese percussionist and keyboardist Stomu Yamashta and prize winning poet Sjon. Bergmal is the conversation of the young soul of the children and the old japanese stone. The unique sound of each stone seems to have traveled through dizzying gap of thirteen and half million years of time and matter to bring us news. The music on this album is performed by the school choir of Karsnes, Stomu Yamashta, Ragnhildur Gisladottir, Sigtryggur Baldursson and David Thor Jonsson. Total time is 59:55. アイスランドでは最大の知名度と人気を誇るスツーズメンの歌姫ラッガ(通称)と、ビョークとのコラボレーションでも知られ北欧文学賞も授与された詩人ショーンが、日本が誇る世界的打楽器奏者ツトム・ヤマシタと共に創り上げた壮大な音の叙事詩。子供たちの合唱の清冽な歌声が、みせかけの安定と秩序で糊塗された世界に閉じ込められた魂に問いかける。その、底無しの「なぜ?」が聴き手の心を射貫く。 アイスランドの教会で初演され、2005年の愛知万博アイスランド・ナショナル・デイでも演奏されて大きな感動を呼んだ『ベルグマル(エコー/こだま)』が、遂にCDになった。本作はアイスランドのレーベルからのリリースということもあって流通が限定される。深く心を揺さぶる透明な悲しみと美しさに溢れた純粋な音楽だ。 この作品は組曲形式になっていて、夢や希望を抱いて生まれた子供たちが、やがて大人社会の欲望の犠牲になって無残な状況に陥っていく様子が描かれ、この現実への子供たちの問いかけの声に対し、古代の石サヌカイトの響きがエコーを返し応答するというもの。1350万年前の地球が生み出した溶岩石の響きを、人間社会への警鐘として聴くか、それとも心の傷への慈しみの響きとして聴くのかは、聴き手ひとりひとりが自らの内面に問いかけ、決めることでもある。 アルバムはサヌカイトの神秘的な演奏で開始され、そして合唱、詩の朗読、ロック・オペラ的な展開も挟みながら、約1時間にわたって壮大な時空を旅していく。これは21世紀版「Go」プロジェクトと言ってよいかもしれないが、かつての祝祭的な輪廻のエネルギーは数滴の雫にまで蒸溜圧縮され、作品全体を包み込むのは神話的な風景の拡がりと、預言者の静謐なまなざしである。 同様のテーマで創作された忘れ得ぬ音楽として、三善晃作曲の児童合唱とピアノのための『オデコのこいつ』(1972)がある。ビアフラの戦争で餓死した黒人の男の子が、戦争とは無関係な日常を生きる日本人の少年の頭に入り込み、やがて少年が他者の死を自らの責任として自覚する、という作品。『ベルグマル(エコー/こだま)』とは語法も音像も大きく異なるとはいえ、語りかける音楽の力が、酷たらしい現実を潜り抜けて魂の実在へと転化するとき、現実は、もはや新しい意味を担われてそこにある。それこそが、音楽を演奏し聴くという人間の行為がかろうじて果たし得る「責任」のかたちであり、同時に守るべき「可能性」でもある。 |
|||
 |
『トマシュ・スタンコ・クァルテット/ロンターノ』 "lontano" とは、イタリア語で「遠い、遙かな、遠方の、離れた」(形容詞)、「遠くに、遠方に」(副詞)という意味。前作《サスペンデッド・ナイト》がスラヴ的憂愁に彩られた旋律が前面に出た明快なものだったのに対し、新作はアブストラクトな展開が多くなり、インタープレイというよりも自在なコレスポンダンス(照応)やカンヴァセーション(対話)というほうが相応しい音の世界が展開されている。熟成を重ねた芳醇な香りと味わいは格別。いわば、深山に位置する奥社の趣だ。その悠然たる存在感は、峻厳かつ優美な霊峰富士の姿を思わせる。 四人の奏者が交わし合う気配の綾取り。神経が繊細に波打つ震えまでが透視されてくる響きの姿態の向こう側に、微視的でありながらその場で起こっているすべてを俯瞰する研ぎ澄まされた感性と知性が潜んでいる。縁語や掛詞を思わせる重層化されたニュアンスの波が交差する佇まいに浸されていると、突飛な空想ではあるが、万葉の歌人たちの耳にすり替わっていくような心地になる。 |
|||
 |
『ひまわりの海~セヴラック・ピアノ作品集/舘野
泉』 舘野泉が演奏生活40周年を記念して、若い頃から憧憬の対象だったセヴラックの音楽を2001年に録音した2枚組CD。南仏の農村に暮らし、自然と人々の生活から沸き起こる感興を淡々とピアノに託した孤高の作曲家デオダ・ド・セヴラック(1872-1921)は、分厚い音楽史のページの片隅にようやく名前が見つかる程度の控えめな存在でありながら、昔も今も、その音楽をどうしたきっかけなのか見つけ出して深く愛する人が増えもしないけれど減りもしない。一般に「印象派」と称されるドビュッシーやラヴェルが、じつは象徴派の詩人の深い影響下にあったことを思うと、むしろセヴラックこそがその呼び名に最も相応しい作曲家とも思える。大地と太陽のきらめきを音符に移しかえた類稀な詩情。人々の日常生活における心情の機微を捉えるデリカシーに富んだ視線。空間を包み込む豊饒な静けさ、沈黙、郷愁、瞑想。謙虚でごくありふれた日々の生活を積み重ねた温かみが、彼の音楽からは響いてくる。 舘野泉さんは2002年1月、コンサートの最中に脳溢血で倒れて以後、右半身の自由を失った。このニュースは日本、そしてとりわけ第二の母国フィンランドの音楽ファンを悲嘆の淵に沈み込ませた。しかし、舘野さんは2年半のリハビリを経て、2004年に左手だけのピアニストとして再起する。その姿は人々の心を熱く打った。 |
|||
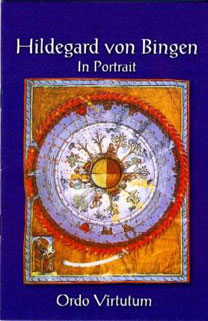 |
『ヒルデガルト・フォン・ビンゲンのポートレート』(DVD) バーバラ・ソーントン Barbara Thornton(歌唱)とベンジャミン・バグビー Benjamin Bagby(中世楽器[オルガン、プサルテリウム、ハーディ・ガーディ、他])を中心に設立された中世音楽アンサンブル「セクエンツィア Sequentia」は、イベリア半島や欧州各地に残された写本を解読し、綿密な学問的精査と創造的なリアリゼーションによって、1980年代から90年代にかけて中世音楽の復興を世界的にリードした。ドイツ・ハルモニア・ムンディ・レーベルから数多くの優れた録音を発表したが、天から射し込む光のような純粋で美しい歌声を聴かせていたソーントンは、1998年、48歳の若さで死去。彼らが特に熱心に取り組んだ中世の預言者にして超人的女性ヒルデガルト・フォン・ビンゲン(1098-1179)が残した音楽作品を取り上げた何枚ものCD録音は、欧州ではクラシックの常識を覆す記録的な売り上げとなり社会現象にもなった。日本でも、欧州とは比較にならないが、それでも《Hildegard von Bingen: Symphoniae》の国内盤(《ヒルデガルト・フォン・ビンゲン:シンフォニア──宗教歌曲集》)は、再発盤を含めて、トータルで1万枚以上売れたという。 彼らがヒルデガルトを演奏したディスクのなかに、2枚組CD《宗教的音楽劇「オルド・ヴィルトゥトゥム」》がある(国内盤は以前東芝EMIとBMGビクターから出ていたが、現在は廃盤)。これは現存する最古の音楽劇とも言われる、16の徳を主人公とした道徳劇で、ヒルデガルトが自身の修道院において教育目的で演じさせるために創作したもの。登場する歌手の役名も、幸せな魂、不幸せな魂、謙遜、神の英知、信仰、慈悲、貞潔、堅慮、畏敬、俗世軽蔑、愛、規律、無罪、従順、羞恥、勝利、希望、対神愛、忍耐、悪魔、といったものだが、このうち悪魔だけは男性が演じる。 その《オルド・ヴィルトゥトゥム Ordo Virtutum》をイギリスの演奏者たちが実際に演じた音楽映像作品がこのDVDだ。日本語の字幕もついている。正直、音だけで聴くなら、長年親しんだセクエンツィア版のほうが好みだけれど、映像と一緒に伝わってくる力はやはり大きい。ヒルデガルト研究者マシュー・フォックス Matthew Fox 教授のコメントも、分り易い的確なガイダンスとなっており価値あるもの。2枚のDVDに収録されたコンテンツはトータルで4時間を超えるが、時空を超えて中世の世界に浸れる一時は日常の時間感覚を失わせる。内容詳細はHMVのサイトにて。■ セクエンツィアは、現在もベンジャミン・バグビーを核に活動を続けている。ソーントンを記念した財団も設立されているようだ(■)。また、現在セクエンツィアで活動している中世のフルートおよびハープ奏者ノルベルト・ローデンキルヒェン
Norbert Rodenkirchen は、ジントピア・クァルテット
Syntopia Quartet の一員でもあるゴシック期のフィドルを奏でるアルブレヒト・マウラー
Albrecht Maurer と組んで、2006年に nemu
records から《Hidden Fresco》をリリースしている。これは全編恐るべき質の高さで、物凄いことになっている。古楽器による、中世と微分音とインプロ。 |
|||
 |
Hidden Fresco /
Albrecht Maurer, Norbert Rodenkirchen Nemu Records - NEMU 004 Norbert Rodenkirchen - midieval transverse flutes, harp Albrecht Maurer - gothic fiddle 1. Hidden Fresco 2. ... a deu 3. Tempera 4. Fadenspiel 5. Erosion 6. Melancholia 7. Aura 8. Nibbio 9. Calindra 10. Sfumato 11. Craquele 12. Behind Recorded & mixed at Christuskirche Mulheim / Ruhr, May 2005 by Albrecht Maurer Mastered by Reinhard Kobialka, Topaz Studio Cologne Grafic Design by Christiane Resch Produced by Albrecht Maurer ドイツの新しいレーベルNEMUの4枚目の作品。ジントピア・カルテットの一員でありケント・カーターとのプロジェクトも組んでいるアルブレヒト・マウラー(Albrecht Maurer)のバロック・ヴァイオリンと、有名な中世音楽アンサンブル「セクエンツィア」のメンバーとしても活躍しているノルベルト・ローデンキルヒェン(Norbert Rodenkirchen)が奏でる中世のフルートとハープとのデュオによるニュー・ミュージック/ジャズである。二人の演奏家とも、ジャズ、クラシック、中世音楽の演奏を追求して多彩な活動を行なっている。こうした音楽的背景を持つミュージシャンはヨーロッパならではともいえる。彼等にとって、「ジャズ」とは、エンタテインメントであると同時に(あるいはそれ以上に)、革新的な表現語法のひとつとして捉えられており、それは必ずしも黒人音楽やブルースへの帰属を重視しない。ジャズは未知の地平にかざす創造の灯火であり、音の内容を示唆する補助線は欧州の文化的歴史全体の反照として意識されている。したがって、本作が示す中世とジャズというラインは、決して、奇を衒ったものではない。むしろ逆に、じつに自然なサウンドが綴られている。音の語法は完全に現代的なものが用いられており(作曲された部分が基礎を構成しているのは一聴して分かる)、中世音楽をそのまま引用するようなことはしていない。しかし、聴いていると、つい先月ECMからリリースされたクリスティアン・ヴァルムルー・アンサンブルの新譜(部分的に古楽の引用も含むが、こちらもまた大傑作だ!)と同じ雰囲気が感じられるし、アルファ・レーベルがリリースする古楽作品群とも共通する意識の地平が広がってくる。尤も、ジャズ、クラシック、古楽等の外面的な形式に焦点を合わせてしまうと、こういう連想はまったく理解不能なことになる。 アルバム・タイトルは「隠されたフレスコ画」で、収録曲のタイトルも絵画にちなむものが多い。「テンペラ」=にかわやのりで顔料を練った絵の具。「エロージョン」=腐食・浸食。「メランコリア」=これは有名なデューラーの作品だろうか。「スフマート」=輪郭や色をぼかして描く技法。「クラックレ」=絵の具、絵画の表面(ニス)のひび割れ。しかし、音を聴いていると、こうしたタイトルがほのめかし、暗示する世界が、ダイレクトに、豊かに立ち上がってくる。描く行為。描き方(技法)。描かれた表面(画面)。表面と空気との接触、そこに徐々に生じる浸食。時間と空間。見るものの意識、そのコンテキスト。こうした「見えるもの(感覚)」の背後にある「見えないもの(物質・理路)」の存在と介在が、響きの世界を通じて、意識のなかに、震動と色彩のかたちを取って伝わってくる。これこそ、音楽の歓びと醍醐味のひとつといえるだろう。私は、最近眼を患って以来、音楽を聴くときも眼を閉じることが益々多くなってきたのだが、このアルバムを聴いていると、なんだか楽しくなってきて、思わぬところで驚かされて、えっと思って聴き返してみたり、とにかく、「絵を見ている」ように、近づいたり、離れたり、つまりは、見ている自分と見られている絵との色々な意味での隔たりを確認することにまったく飽きないのだ。 昨年度のJAZZTOKYO年間ベストとして挙げた、ジントピア・カルテット(Syntopia Quartet)の『マーズ[火星](Mars)』がNemu Recordsの第一回リリースだった。NEMUは、記譜された音楽と即興演奏のあわいを探求することを旨とした、真に意欲的なレーベルの筆頭格である。どの作品も驚くべき質の高さを持ち、音楽を聴くことを通じて、未知の新しい意識の地平に開かれていく体験を約束してくれる。今のところハズレは一切なし。ただし、NEMUの音楽はどれも「ながら聴き」を許してくれない。とにかく内容が非常に濃い。別の言葉でいえば、聴き手が音楽に能動的に関わることで、「聴き取る」「発見する」ポイントが、その魅力の核心となっているともいえる。刹那に潜む、息をのむ間合い、複数の中心が同時に存在する仕方、かすかなニュアンスの変化が生む絶大な効果。こうした得も言われぬ魅力をたっぷりと味わうためには、読書や運転、PC画面を眺めながら等々、注意を分散させながら聴くことは望ましくない。楽器の、音の、多彩な表情。演奏者の意識の変化。それらに耳をすまし、心を寄り添わせて、かたちを探ること。音楽を「与えられて楽しむ」ものだと思っていたら、こういう種類の音楽を聴く楽しみは、最初から、出会う(気付く)ことが奪われているともいえる。とはいえ、NEMUの音楽は、決して難解だったり硬派なフリー・ジャズだったりというわけではない。暖かな気配と、しなやかな自由に溢れているNEMUの音楽は、今一番おもしろい音楽のひとつであることは間違いない。 |
|||
 ※ライナーノーツが発売元のサイトで公開されている。■ |
『Percussion
Songs / Christian Wolff / Robyn Schulkowsky』 クリスチャン・ウォルフの音楽を聴くと、いつも表裏がない印象を受ける。それは真率であるという以上に、さりげなさを基盤として成立しているという意味において。すべての音が明るい光のもとで、眼前に晒されているように響く。1950年代に、ジョン・ケージ、モートン・フェルドマン、アール・ブラウン、クリスチャン・ウォルフは、当時世界を席捲していた抽象表現主義の画家たちに倣って、音楽面での「ニューヨーク・スクール」と称された──当時の先鋭的な芸術家たちはジャンルの違いを越えて相互に交流を持っており、なかでもフェルドマンはマーク・ロスコ、ウィレム・デ・クーニング、フィリップ・ガストンとの精神的紐帯を強く意識していたが、「不確定性の音楽」として括られるこのグループ全体の美学的側面においては、その後のポップ・アート/ネオ・ダダを担ったジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグとの関係のほうが深かった。これらの芸術家のなかでも、ウォルフは皆から一目置かれていた存在。いくつか出版された楽譜を見たり、本人が書いた文章も読んでみたが、その種の知識が本質的な意味で聴取を助けることが殆どないというのも、この作曲家の特徴だろうか。音の醸し出す印象や雰囲気で「近いかな」と思うのは高橋悠治の作曲作品。自転車やスノーボードと同じで、身体が覚えてしまえば考えずに反応できるようになるわけだけれども、それまではちょっと苦労するというか。 本アルバム収録作品は、ロビン・シュルコフスキーという演奏家の存在、その感性と知性を前提に書かれている。作曲者と演奏者が共に個人性を滅却し、押しつけやナルシズムを注意深く排除した無為の心を開いた場所に、僥倖として、巡礼の道が姿を顕している。それは、美しく、可憐に花開いたアノニマスな世界の庭だ。 |
|||
 |
『岡島さんがくりかえし聴いているロシアの女性歌手の歌声をあつめた自選
CD-R』 岡島豊樹さんのお手製編集 CD-R、これがもう本当に素晴らしい。ドストエフスキーとトリスタン・ツァラが同じ部屋にいて、そこをたまたま通り掛かったイサドラ・ダンカン(詩人エセーニンとの結婚前という設定)が即興のダンスを舞って見せた、というような興奮状態。 底なしの哀愁、絶対への接吻、正四角形の抒情、祈りのタペストリー、きらめく希望。これらの歌が湛える深々とした情感は、ロシア文化の避け難い宿命ともいえる「神」および「自由」との徹底的対決の余韻を漂わせ、聴き手の魂の芯にダイレクトに響いてくる。かつての鉄のカーテンの向こう側、そして今のロシアに、こんな素敵な歌声があったなんて知らなかった。それにしてもジャンナ・ビチェーフスカヤの「声」はなんという深さだろう。一気にファンになりました。ロシア民謡をアレンジして新たな生命を吹き込んだ彼女の他の作品群もぜひ聴いてみたい。7曲目は『ホテル・コスト hôtel costes』でステファン・ポンポニャック Stephane Pompougnac がリミックスしてもおかしくない位のオシャレ度満点のラウンジ・フレイヴァーで耳をくすぐる。 収録曲── 01. ズィキナ:私のモスクワ/02. ザイチェヴァ:ああ霧が/03. ゲルマン:庭が花咲く頃/04. ビチェフスカヤ:われらロシア人/05. ビチェフスカヤ:霊性にみちた巡礼者/06. ビチェフスカヤ:ロシア人に/07. エピファノーヴァ:汝の黒い瞳/08. ズリヤ:Leaving/09. リコヴァ:指輪/10. ドゥドゥキナ:かつての新年/11. カプーラ:春/12. カプーラ:夏 以下は岡島さんによるコメント。 |
|||
[01]と[02]は第2次世界大戦時の愛国ソング。ズィキナの声は永遠のおっかさん。 [03]は60年代の映画主題歌。 かつてのソ連フォーク・ムーヴメントのディーヴァ、ビチェフスカヤはこのところ敬虔な正教徒らしくて、[04][05][06]はそのメッセージか。正教はともかくとしてビチェフスカヤの声が大好きなのでビデオ買いましたよ。 [05]の霊性にみちた巡礼者というのはラスプーチンのこと? [07]はナツメロの現代カヴァー。 [08]のズリヤは最近のシンガー=ソングライター。 現代ロマンス調の[09]のリコヴァの素性はよくわかりません。 [10]のドゥドゥキナも最近の人気シンガー=ソングライターですが、この曲は「ネズミ捕り」という旧アングラ系のグループのカヴァー。 [11]と[12]はクリョーヒンのアルバム「雀オラトリオ(Sparrow Oratorium)」の中の2曲で、カプーラはクリョーヒンの造語歌詞(解読不可)を一体どんな気持ちで歌っているのでしょうかね……。 |
||||
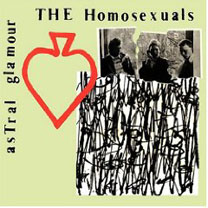 |
『The
Homosexuals / Astral Glamour』、『The Work /
Live in Japan』 マニエリスティックな音響操作とストレートなロック・スピリッツの融合が、ミシンと蝙蝠傘の解剖台での出会いを祝福している。パンク、プログレ、サイケ、スペース・ロック、アフリカン、レゲエ、ディスコ、ダブ、これらすべてをラフに取り込み、明るいんだか暗いんだか分からない歪曲したメロディを楽しげにハモり、ギターが掻き鳴らされ、ドラムはバタバタと叩きまくる。どの曲もメロディやリズム面で何かしらユニークな実験が織り込まれて、飛び交う断片的フレーズ、突然止まっては動き始めるビートなど、コラージュ漫画然とした素っ頓狂な構成で、健康かつ愛らしくも奇妙な2分間程度の短いポップ・チューンが、次から次へ手品のように登場してくる。さしずめロック界のチャールズ・アイヴズといったところだ。夢と欲望を宙吊りにして、種々の変形と加工を施す魔術的リアリズム。自由と反骨に根ざした上質なユーモアと批評精神。 当時、彼らはインタヴューを一切行なわず、録音と音盤制作と流通のすべてを自らの手でまかなう完全手工業製を貫徹していたこともあって、その活動はつねに謎めいて映り、色々な推測と妄想を掻き立てた。「変態系」と揶揄されることもあって、実際、1985年頃の活動停止以降も、彼らへの評価は「狂気」を主調音に定着していた。そのうち、伝説化・神格化もチラホラと。ところが、最近になって、バンド設立時からの中心メンバー、ブルーノ・ウィザード Bruno Wizard がそうした声に異を唱えた。「おれは気違いでもなければ、伝説や名声を狙って沈黙しているわけでもない」。そして過去の音源の発掘が始まったのだが、メンバーの手許には未発表テープのほかは、既出のレコードやカセットの現物が満足に残っておらず、そのため熱心なコレクターたちが手分けして持ち寄った音源を元に制作されたのが、この3枚組のCD。 附属のブックレットに掲載された、ブルーノ他の関係者の証言に基づくバンドの詳細なバック・ストーリーは、彼らの謎めいた活動の日々を初めて活写するものだ。元は「Rejects」というバンド名だったこと。NMEによるギグのレビューで完膚無きまでに酷評され、半ば公的なブレイクを放棄して反社会的なバンド名に変えたこと。一見パンク的とも見える新しいバンド名が英国では受け入れられず、知り合いのミニコミ音楽誌で一度取り上げられた以外、英国のプレスは彼らを完全に黙視したこと。曲作りと練習、録音は、ポリスのレコーディング・スタジオの空き時間を使って(最新の編集機器!)、夜中や早朝、何日または何週間かおきに熱心に続けられたこと。「L. Voag」と「Amos & Sara」がジム・ウェルトン Jim Welton の、「George Harrasment」がアントン・ハイマン Anton Hayman の各々ソロ・プロジェクトだったこと。イスラエルから留学していた英語も覚束ないアート専攻の女性スージー・ヴィダ Suzy Vida が、このバンドの方向性やジャケットを含むヴィジュアル面でのアイディア、戦略の核だったこと。 一度はメジャーでの成功を目指したが、ある時を境にそれとは全く別の道、つまり表現のすべてを自分たちの手で行なう自由を選び(たぶんそこを見て当時レコメンデッド・レコーズが彼らの作品を全世界にディストリビュートしたのだろう)、結果として奔放な想像力が羽ばたいた稀有な音楽が生み出された。彼らがパンクから学んだ「何でも自由にやっていい」という精神が、レコード会社やファンの意見、流行に左右されることを一切拒否した時点で、音楽そのものの革新へと方向付けられた、という意味では、フランク・ザッパを想起させるところもある。 2006年、ザ・ワークの《ライヴ・イン・ジャパン》(1982)が初CD化された。カセット録音だがそんなことはまったく気にならない程に内容は凄い。知性と情動、覚醒と蒙昧、抵抗と隷属、それらが極限でせめぎあう。現在はシベリアのシャーマニズムとインプロヴィゼーションとの関係を機軸として独自の極北的音楽を構築するティム・ホジキンソン Tim Hodgkinson のシャウトするヴォーカルは鬼気迫るもの。ドラムスは“御神体”クリス・カトラー。ベースを弾いているのがエイモス、すなわちホモセクシュアルズのジム・ウェルトン。2作品紹介してしまったけれど、メインはホモセクシュアルズということで。 90年代以降のホジキンソンの音楽はロックから離脱して、ミュージック・コンクレート/音響構成、インプロヴィゼーション、宗教的儀式音楽、厳密なスコアに基づくアンサンブル、これらを統括した、きわめて異彩を放つ音の秘境域を着々と形成している。もっと注目されてもよいのでは。最新作は
mode records からの《Sketch of Now》。 ■ |
|||
 |
『冥途の飛脚』(VHS) 近松門左衛門原作の文楽を主題に、マーティ・グロス Marty Gross が監督・製作・編集・脚本を務めた1980年の映画作品『冥途の飛脚 The Lover's Exile』(撮影は1979年の夏)。この東芝EMIから発売されたビデオ(SK080-1030H・現在廃盤)を今年初めて見て、すっかり心を奪われてしまった。 かつての、そして、現在の人間国宝である名人たちが演じた、表現の臨界点に沿って進む濃密な劇空間。死へと溢れ出るまでに激しく燃えさかる生の欲望。哀しい恋の道行。その避け難い宿命を、多重の箱に丁寧に詰め合わせる心理面の演出を通じて、破滅を前に、そこからけっして目を逸らさない冴えた覚悟に貫かれた主人公たちへの優しい憐憫を、劇中空間、それを演じている舞台(現実)空間、さらにはそれを観ている者の心理空間、それぞれの間で相互に行き交わせ、物語の奥行きを一段と深めている。 音響・音楽監修は武満徹。作曲ではなく、義太夫の演奏のつながりの確認や数ヶ所での擬音の録り直しが主だが、武満自身のコメントによれば、トロントで行なわれたその作業は、「何れも、私にとっては、さほど苦労の要らぬことばかりだったのだが、それが意外に、緊張を強いられる一週間だった。早朝から深夜に及ぶ作業が続いた」とのこと。映画作家マーティ・グロスとの出会いについては、こう記している。「その時間感覚や空間に対する繊細な思慮が、私が音楽で意図しているものと余りにも酷似していたために、直ぐ、彼に、特別な親近感を覚えたからである。ふたりが理解し合うために、多くの言葉は必要なかった。」 本作は、2006年9月に海外でDVD化されたが、VHSビデオのマスターがそのまま使われているので画質と音質はビデオと同じ(■)。 ◆追記 |
|||
■キャスト 淡路町の段 大夫=五世 竹本織大夫(たけもと・おりたゆう)[後・九世 竹本綱大夫(たけもと・つなたゆう)、九世 竹本源大夫(たけもと・げんだゆう)] 三味線=五世 鶴澤燕三(つるざわ・えんざ) 封印切の段 大夫=四世 竹本越路大夫(たけもと・こしじだゆう) 三味線=鶴澤清治(つるざわ・せいじ) 「恋飛脚大和往来」より 新口村の段 大夫=九世 竹本文字大夫(たけもと・もじたゆう)[後・七世 竹本住大夫(たけもと・すみたゆう)] 三味線=四世 野澤錦糸(のざわ・きんし) ■人形 忠兵衛=吉田玉男(よしだ・たまお)/梅川=三世 吉田蓑助(よしだ・みのすけ)/八右衛門、孫右衛門=二世 桐竹勘十郎(きりたけ・かんじゅうろう) ■スタッフ 製作・監督・編集=マーティ・グロス/撮影=岡崎宏三、小林秀昭/音楽編集=カール・ジットラー(Carl Zittrer)/音響・音楽監修=武満 徹/製作=安武 龍/字幕=ドナルド・リチー、マーティ・グロス/演出通訳=エイデルマン敏子/録音=西崎英雄/テレビ版イントロダクション=ジャン・ルイ・バロー (c) 1980 Marty Gross Film Productions Inc. |
||||
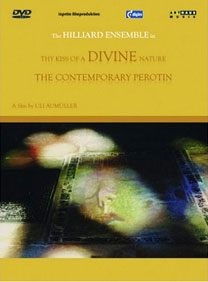 |
『ヒリヤード・アンサンブル/「神が宿った汝の口づけ」~ペロタンの時代』(DVD) ヒリヤード・アンサンブルによるノートル・ダム楽派の作曲家ペロタンの演奏といえば、ECM New Series に優れた録音が残されているが(■)、これは2005年に制作された映画仕立てのDVD。日本語字幕つきなのが有難い。(総収録時間:380分) ペロタン(ペロティヌス)は、音楽史上で個人名として現れる最初期の作曲家のひとりであり、その素性には依然として謎が多い。この映像作品では、音楽史家、音楽社会学者、劇作家、文化史家たちが登場し、シンポジウムでの口頭発表や舞踊劇の創作などを通じて、作曲家ペロタンの精神世界を検証していくという、推理小説のような構成。その合間に、ヒリヤード・アンサンブルも画面に登場して歌い、音楽学者の提案で違った歌い方に臨むシーンも。映像は、現実と虚構のあわいのなかで進んでいくが、ペロタンの崇高な音楽だけは、つねに確かな指標として超然と佇立している。持続音の上で旋律細胞のユニット群が反復されていく響きのテクスチュア。バーネット・ニューマンの絵画が脳裏をよぎる。 1枚目のDVDには上記の映画作品。2枚目のDVDには、映画の素材となったシンポジウム「誰がペロティヌス・マグヌスであったか
-
伝説か歴史か」と、ラジオ番組「ペロティヌス・マグヌス
-
フィルム・プロジェクト実現に向けての構想」その他を収め、さらに別途付属のCD盤には、映画内でヒリヤード・アンサンブルが歌った演奏音源がすべて収録されている。 |
|||
| 付録 私自身が制作に携わった2つのCDシリーズに関するメモ |
||||
 |
『寺山修司ラジオ・ドラマCD』(8枚)
■ この企画は音源の探索や権利処理の面で大変苦労が多く、時間もかかった。なぜ古いラジオ・ドラマが商品化されないのかが身に沁みて判った次第。ずらりと並んだ針穴に忍耐強く糸を通していく煩瑣かつ地道なプロセスが延々と続く。したがって必然的に関係者の方々の御支援なくしては、これらの作品のCD化は到底実現不可能であった。 ラジオ・ドラマは日本のすぐれた文化遺産である。この8枚のCDは、そのごく一部でしかないが、こうして後世に残せたのは大きい。ラジオ・ドラマは小説と同じで、聴き手(読者)が作品の細部のイメージを自らの想像力で作り上げていくものだ。だから一度聴いた作品は、自分自身の内面を映した鏡となって記憶に残り、すなわちそれが自らの分身となる。この濃密な驚くべき体験は、実際に味わってみないと分からない。どの一枚でもよいので手に取って頂ければと思う。忘れ難い「体験」の訪れと同時に、もう一人の自分を「作り上げる」過程を通じて、世界を感覚する意識回路に変化が生じてくるはず。 『中村一郎』/『大人狩り』 『ジャズのための楔形文字』、『モダンジャズのための詩「壁に頭を」』など、音楽権利上の問題や現在の差別コードとの抵触によって収録できない作品があったのは残念だった。それと、寺山修司の死の翌年に製作され、1984年12月24日~28日にかけて、NHK・FM「ふたりの部屋」で放送された『赤糸で縫いとじられた物語』(演出=多田和弘、出演=中尾幸世、柴田侊彦)は、放送局に音源は残っていたが(声と背景音楽の最終ミックス済テープのみ)、使用されたクラシック音楽の演奏者等が特定できず、権利処理の可能性が絶たれたことで、収録できなかった。そうでなくとも、音源のシンクロ使用(ドラマなどの背景に音源を使用する)に関して、海外権利者との間で国際的な料率の基準はなく、まずは交渉窓口を探し出し、実演家の了解を取り、金銭面で納得できる数字で折り合ってとなると、やはりCD化の実現は極めて難しい。また、ラジオ・ドラマではないけれど、1984年度にACCを受賞した、「ソニーカセットテープ
ラジオ・コマーシャル
寺山修司シリーズ」も印象深いものだった。目の見えない子供たちが色を音で表現する90秒のドラマ。音源はこれを製作した広告代理店に残っているのだろうか? |
|||
 |
『武満徹
室内楽作品集「響きの海」/アンサンブル
タケミツ』(全5巻) ■ これだけの豪華なメンバーが集まって武満作品を一緒に演奏する機会は、もう当分の間ないだろう。岩城宏之さんが亡くなる少し前に、武満作品の楽譜の曖昧さについて語っていた。記譜に不完全なところがあり、細部の判断やテンポなど、練習の場で作曲者本人に確認して進めてきた部分がかなりあったことなど。これは、多くの武満作品の初演・再演に関わってこられた岩城さんの言葉だけに重い意味があると思う。そして、オーケストラ作品ばかりでなく、室内楽作品においても同様の問題が存在していたことが、この室内楽全曲演奏会という企画の、そもそもの出発点になっていたのであった。(詳細はCD解説書に掲載) クラシックというと、楽譜上にすべてがあり、演奏家はそこから自身の創意で音楽を作り上げていく、という見解が一般的であり、もちろんそれは正解なのだが、しかしそのことだけに執着すると、音楽作品の大切な別の一面を見失うことになる。音楽には、楽譜に書かれていないことのなかにも大切な要素がある。その音楽が実際に立ち顕れるための、想像力の基点となるもの、作品にアクセスするための鍵、気配、ニュアンス、文法(シンタックス)、感情の論理、空間や時間の概念、等々。どれもが言葉や記号に置換するには限界のあることばかりで、これはどんな時代のどんな作曲家の音楽に対しても共通して言えることである。 アンサンブル タケミツのメンバーが望んだのは、たまたま自分たちが作曲者の身近で演奏していたことで知り得ることができた、スコアには書かれていない作曲者自身の好みや判断──とりわけ出版譜と食い違うテンポの問題は大きく、武満徹自身「そのうちなんとかしないといけない」と語っていたという──を演奏の記録として残すことで、将来の演奏家が武満作品の楽譜に取り組む際に、その解釈の方向性に示唆を与えることができると信じたからだった。「けっしてこういう風に演奏するべきだというのではありません」と、彼らもブックレットに掲載された序文で語っている。今後の演奏の可能性を縛るためでなく、逆に、新たな創意と想像力を膨らませるための契機として、自分たちの解釈を参考にしてほしいということなのである。 ライヴ・レコーディングだけに、演奏会場の客席ノイズも目立つが、しかし、ここで聴くことができる演奏は、どれも楽譜を通じて最大限に引き出し得る響きの多様な海で満たされている。聴衆との緊張した関係も音楽の表情に生気を与えていて、これこそライヴならではの良さだろう。マスター音源は会場日時ごとに録音特性が大きく異なっていたため、マスタリング作業には慎重を期して時間を要したが、関口台スタジオの金子さんによる細心のエンジニアリングによって、演奏の臨場感と音の質感をマッチさせた素晴らしい音に仕上がっている。何度繰り返し聴いても、音楽のなかに、その都度新たな発見がある。 |
|||
 |
Toru Takemitsu Resonant Sea Chamber Music Complete Editions Special CD 武満 徹 響きの海 室内楽全集 特典CD(非売品) 武満 徹・講演とシンポジウム「音楽の可能性について」 秋山邦晴/磯崎 新/大江健三郎/武満 徹/山口勝弘/司会・武田明倫 録音=1990年12月15日(土)18:30 サントリーホール 小ホール (P) 2006 Tokyo Concerts, Inc. / King Record Co., Ltd. / Printed in Japan. / MONO / Not for sale SSX-162 / 163 CD 1 (75:38) 講演「音楽の可能性について」 武満 徹 1 「こんなにたくさんの方が……」 4:13 2 「ここで言われている音楽とは、どういうものなのか……」 9:07 3 「1950年代に、ヨーロッパに現れた前衛音楽……」 6:13 4 「タケミツの音楽には日本人としてのアイデンティティがない、と……」 7:23 5 「今世界で起きつつある変化、一人一人が表現者となって……」 6:47 6 「重層した、多義的な表現の世界のなかに身を置いて……」 4:41 シンポジウム「音楽の可能性について」 秋山邦晴/磯崎 新/大江健三郎/武満 徹/山口勝弘/司会・武田明倫 7 はじめに 武田明倫 2:42 8 音楽のディスタンスと開かれた関係 山口勝弘 7:10 9 既成のもの、自分の思い込みからの解放 大江健三郎 9:43 10 アヴァンギャルドとキッチュ 磯崎 新 9:26 11 音楽の認識の構造が変わった 秋山邦晴 8:04 CD 2 (72:02) シンポジウム「音楽の可能性について」(続き) 秋山邦晴/磯崎 新/大江健三郎/武満 徹/山口勝弘/司会・武田明倫 1 「これまでの部分は……」 武田明倫 1:25 2 僕自身の伝統と所属の問題 武満 徹 ほか 13:07 3 自己目的化した世界から外に出る 山口勝弘 4:47 4 クリシェとアイデンティティ 大江健三郎 4:56 5 クリシェとアイデンティティ(続き) 大江健三郎 4:04 6 今なぜブラームスか 武満 徹 10:20 7 白い皿と絵つけの皿 磯崎 新 7:48 8 新しい創造力/想像力 秋山邦晴 6:04 9 最後に一言ずつ 武田明倫 0:36 10 「ジョン・ケージが言ったように……」 秋山邦晴 1:18 11 「可能性をどうやって探すかという仕事……」 磯崎 新 3:51 12 「武満徹が生きた時間の積み重ね……」 大江健三郎 4:41 13 「テクノロジーがもたらす新しい芸術環境……」 山口勝弘 5:05 14 「いつも気になっているのはマルセル・デュシャン……」 武満 徹 2:50 15 「ありがとうございました……」 武田明倫 1:00 |
|||
| ところで、この全集はECMのマンフレート・アイヒャーとスティーヴ・レイクにもメッセージを添えて送ってある。アイヒャーがタケミツにどう取り組むか非常に興味がある。ずっと期待して待っているのだが、なかなか重い腰を上げてくれない。 ロザムンデ・クァルテットならば、《ア・ウェイ・ア・ローン》、《ランドスケープ》、そしてハインツ・ホリガーを加えた《アントゥル=タン》という構成で。また、チェロとピアノのための名曲《オリオン》を、トーマス・デメンガ、アニヤ・レヒナー、ロストロポーヴィチ、ハインリッヒ・シフという異なるチェリストの演奏で並録、というのも実現できたら面白い。合間には、弦楽器のための図形楽譜作品《コロナ》と《アーク》を入れる。──しかし、やはり、時機を待つしかないのだろうか。ドイツではタケミツ受容が進んでいないことも理由のひとつかもしれない。 そういえば小澤征爾と大江健三郎の対談書『同じ年に生まれて』のなかで、大江さんが、タケミツの死後、ストルツマンがインタヴューに答えたときの言葉を紹介されていた……。 「宇宙に花が咲いてて──どういうかたちで木があるのかわからないけど──花の木があって、その花房が垂れているように、武満さんの音楽を聴いていると、宇宙のなかに武満さんの花が咲いていることが分かる」……と。それを受けて、小澤さんが、リチャード・ストルツマンとその息子がクラリネットとピアノのデュオでタケミツ最後の作品、フルート独奏曲《エア》をジャズ風にアレンジして、吹きながら客席へと歩いていったときの感動を語っていた。「武満に対する愛情があふれてました。」 |
||||
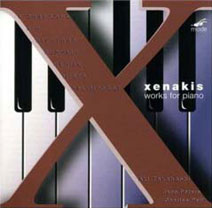 |
<JazzTokyo 2006年この一枚> 『Iannis Xenakis :
Complete Works for Piano Solo / Aki Takahashi』 2000年リリース作に全面リマスターを施し、世界初録音となる初期作品『ピアノのための6つの歌』を加え一段と輝きを増した宝石のような一枚だ。 最高難度の技巧を要求するクセナキスの作品は限られた数の演奏者しか近寄ることを許さないが、なかでも高橋アキは生前の作曲者から特別に認められていた存在。楽譜に記された音符の現実化に可能性の極限まで努め、それがゆえに、存在(有)と非在(無)を結ぶメディエイター(調停者)として、瞬く音群の光のなかへ消えることができる稀有なピアニストである。 明滅する光の向こう側では、日常の小さな出来事と遥か彼方で起こっている事態が結びつき、往還する。たとえば『ヘルマ』を聴いていると、庭に雨の雫がぱらぱらと落ち始め、やがて本降りとなって風で雨足がゆらぎざわめき…といった情景が、いつしか宇宙の無限遠で渦巻く星雲へと変成し、音を聴いている自分が時空を超えた「どこか」「だれか」に掏り替わっていく。悠久の時を超えて息づく、神々と人間の崇高な対話篇といった趣も味わい深い。 詩的な優美さに溢れた高橋アキのピアノは、クセナキスの音楽が自然世界への注目を起点とする本質的にロマンティックなものであることを明らかにしているように思う。 |
|||