VOL.01
2001.04.01
矢 多 羅 の マ サ ラ
YATARA NO MASARA
![]()
月光茶房
![]()
VOL.01 2001.04.01 |
矢 多 羅 の マ サ ラ YATARA NO MASARA
|
月光茶房 |
原田正夫
Masao Harada
| VOL.01 | part 1 150 DISKS OF JAZZ ▼ |
| part 2 |
| NEW ARRIVAL |
『ギター弾きの恋』 (ソニー・エンタテイメント) |
|||
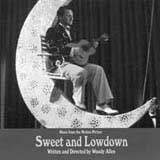 |
同タイトルの映画のサントラ盤である。ウディ・アレンの監督最新作で、主役のジプシー・ジャズ・ギタリストに扮するは、若いのに「怪優」とまでいわれてるショーン・ペン。1930年代の設定の話で、なおかつスイング・ジャズ好きのウディ・アレンの映画だけに30〜40年代スタイルのジャズがたっぷりと聴ける。そしてこの映画のもうひとつのミソは主役のギタリストがジプシーだという点だ。ところで「ジプシー」は民族の蔑称すなわち差別用語だから呼称として使わないようにしようという向きもあるが、ロマのジャズ・ギタリストといっても一般には通じないので、「ジプシー」で通す。ウディ・アレンが映画の主人公をギタリストでしかもジプシーの、としたのはジャンゴ・ラインハルトを当然意識してのことだろう。映画の中でもウディ・アレンは主人公に「ギタリストで No.1 はオレだ。ジャンゴを除けばな」と言わせている。ジャンゴは30年代中期から50年代初めまで活躍したジャズ・ギタリストの草分けのひとりで、ベルギー生まれのロマ、いわゆるジプシーだ。1930年代といえばスイング・ジャズ全盛期、ギターがまだリズムを刻むリズム楽器の一種にすぎなかった頃に、ソロというか曲のテーマ・メロディを奏でる楽器として、ギターをジャズの前面に担ぎ出したのがヨーロッパのジャンゴ・ラインハルトである。素晴らしさはその功績だけでなく、彼の奏でるギターの音色のロマンチックな魅力にもある。ジャンゴの死後、現在に至るまで多くのギタリストに影響を与えた、その音色の甘いせつなさにジプシーの「血」を垣間見ようとするファンは多い。このサントラ盤にはそんなジャンゴ・スタイルの曲でギターがフィーチャーされる。映画でショーン・ペンがギターを弾くシーンに使われているものだ。実際はアメリカのジャズ・ギタリスト、ハワード・アルデンが弾いているが、映画ではそのアルデン録音の音に、猛練習の末、ピタリと指使いを合わせるショーン・ペン。見上げた役者魂というべきで、「怪優」とはヒドいよね。 | ||
『ステファノ・ディ・バティスタ』 (as.ss.) (東芝EMI) |
|||
  (1)
|
昨年の暮にUK(イギリス)ブルーノートからリリースされたバティスタのソロ・アルバムの国内盤である。前作は自身のグループでの吹き込みで、こちらも素晴らしいアルバムだった。バティスタはイタリアの若手というよりもう中堅どころのアルト&ソプラノ・サックス奏者。彼の繰り出すジャズは、とにかくキレがいい、勢いがある、自作曲もイイ。このアルバムでは現代ジャズの至宝エルヴィン・ジョーンズがドラムスだ。1曲目の冒頭、ピアノやベースが入ってくる前、エルヴィンのドラムスだけをバックに吹くバティスタのソプラノ・サックスを聴いただけで、いいアルバムを買ったと納得するはずだ。メインストリーム・ジャズの好盤。大推薦盤です。 ちなみに上記の前作『ア・プリマ・ヴィスタ』の国内盤はオリジナルのUK盤に比べて音のヌケが非常に悪かった。ワタシはそれに懲りて昨年UK盤で本アルバムを買ったので、この国内盤を実際には聴いていない。故に何とも言えないのだが、心配な方はUK盤を買われたし。バティスタのスペルは Stefano Di Battista。左の写真(1)がそのアルバム『A Prima Vista』。トランペットのフラヴィオ・ボルトとのクインテットで、腰のすわったキレのいいストレートなジャズが堪能できる。彼らのデビュー・アルバムがフランスの Label Bleu から出た『Volare』(2)で、このアルバムを聴くとこの時点でグループがすでに完成していたことがわかる。バティスタとフラヴィオ・ボルトが参加して、彼らの名を一躍高めたアルバムがミッシェル・ペトルチアーニのフランスの Dreyfus 盤『Both Worlds』(3)で、こちらはセクステット編成のアルバム。晩年のペトルチアーニに非常に高く評価されていたこの二人は、やはり一緒に組んだ時に1+1以上の力を発揮するようだ。それぞれのソロ・アルバムにお互いが数曲参加しているのだが、そのトラックが他のどのトラックよりイキイキとした表情を見せているのが面白い。 |
||
『Quadros Modernos』 Toninho Horta, Chiqito Braga, Juarez Moreira (g.) (QM0001) |
|||
 |
ジャズではなく、ブラジル音楽だが、ボッサではない。ギター等の弦楽器のアンサンブルによるインストゥルメンタルというべきか。ブラジルのトニーニョ・オルタ、シキート・ブラ−ガ、そしてジュアレス・モレイラの3人のギター奏者が繰り広げる穏やかな弦の響きの重なり。『この3人のギタリスト(ヴィオラオン奏者)による、ブラジルはミナス地方の香り漂うインストゥル音楽』である。『 』内の文章は、月光茶房元スタッフにして、ブラジル音楽に深くのめり込んでいるユアサ君によるこのCDの紹介文(メール文)からの抜粋だ。ワタシはこのCDを渋谷のタワレコで一聴、惚れ込んで購入したが、ブラジル方面に疎く、紹介するだけの知識を持たない。よって、この項は彼の文章に全面的に頼ることにする。 『ガット・ギターとカバキーニョ(ギターよりも高音部を担当している楽器)、エレクトリック・ギターを三者が曲ごとに持ち替えながら』演奏されるこの音楽は……『ブラジルもその地域によってケッコウ、音楽に特徴がありまして。個人的に思うのは、リオやバイーアに比べてミナス地方というのは、かなり土着的なニオイが強い音楽というコトなんですが、このアルバムはミナスのアクがありながらとても優雅。メロディを慈しむように、穏やかに重ねあわせ、また、三様にからみ合う、ふくよかなギター・カバキーニョの響きにミナスの“音”霊を感じます…とは、称えすぎか?』 いやいや、その表現は大袈裟にあらず。表面的には慎ましいけれど、その慎ましさの奥に確かに音霊(オトダマ)ともいうべき音楽への真摯な信仰を感じる。これはジャズに限らず全ての音楽ファンに薦めたい。『それにしても、ため息がでるほど素晴らしい』……そう、それがこの『クアドロス・モデルノス』。ワールド・ミュージックのブラジルのコーナーにあります。 |
||
『The Diamond Mountain Sessions』 Sharon Shannon (accordion) (Grapevine) |
|||
  (1)
|
ワタシのジャズ歴はまだ20年に満たない。アイルランドやイングランドのトラディショナル音楽に惚れ込んだのは大学生の頃だから、こちらはもう30年近くファンであり続けている。この手の音楽、今はケルト・ミュージックと呼ばれていてモードな雑誌で特集を組まれることもあり、昔を思えば隔世の想いを禁じえない。さて、このCDはアイルランド・トラッドのアコーディオン奏者シャロン・シャノンの新作で彼女の4枚目のアルバムにあたり、確か国内盤もリリースされているはずだ。シャロン・シャノンはロック・バンドのウォーターボーイズのアルバムやツアーに参加したりと、トラッド・ミュージックの狭い枠に収まらない自由な音楽性を持った若い世代のミュージシャンで、91年の最初のソロ・アルバムや、イギリスのレゲエ&ダブのデニス・ボーヴェルと組んだ5曲を含む 2nd 『Out The Gap』(1)は、自然に音楽の境界を超えていく彼女の柔軟性が反響を呼んだ。特筆すべきは、伝統的なトラッド・スタイルとその枠外のスタイルとを無理なく、シャロン・シャノンの「トラッド」として一体化してしまう、彼女の気負いの無さだ。そしてトラッドを、いや音楽そのものに対する彼女の誠実さがどのアルバムからも伝わってくる。前作 3rd 『Each Little Thing』(2)と同じく本アルバムもトラッド・チューンが中心だが、前作同様、いやさらに彼女の音楽がより自然に、そして深みを増しているように感じる。曲によってドーナル・ラニーを始め様々なミュージシャンや歌手が参加しているが、ばらついた印象が無いのも今までどおりである。 | ||
『The Green World』 Dar Williams (SSW) (Razor & Tie) |
|||
  (1) |
90年代からこの新世紀にかけてのアメリカの女性SSW(シンガー・ソングライター)を代表するとまで言われるようになったダー・ウィリアムスの待望の新作である。97年の 3rd 『End Of The Summer』(1)から3年ぶりの新譜だ。この『End Of 〜』で彼女の評価は決定的なものになったのだが、デビュー・アルバムからこの新作まで、ソングライティングも含め彼女の基本的な持ち味は変わっておらず、曲の聴かせ方の洗練の度合いが『End Of 〜』で高まったのがその要因かもしれない。本作も1曲ずつじっくり聴くと、曲ごとのアレンジや演奏の精緻さに感心するが、凝っていると感じさせないその自然さが素晴らしく、評価もセールスも良かった前作のプレッシャーを感じさせない見事な仕上がりになっている。彼女はあまりカントリー臭さのないSSWで、ローラ・ニーロやジャニス・イアンのような都会的なSSWの系譜に属するといえる。そして、本人が意識しているかどうかは不明だが、作る曲やその歌い方に彼女の先祖のイギリスはウェールズのトラッドの香りが感じられ、個性と才能にさらに奥行きを与えている。国内盤もリリースされている。 | ||
『Live At The Dolder Grand Hotel, Zurlch』 The Winners (TCB) |
|||
 |
ECM等は別格だが、ジャズのレーベルは勢いのある旬の時というのがある。スイスのTCBはリリースするアルバムがメインストリーム系の好盤ぞろいで、現在、時の勢いを感じるレーベルのひとつだ。このアルバムは雑誌「jazz 'n' more」にて99年度のスイスの最優秀ジャズ・ミュージシャンに選出された4人による、チューリッヒのホテルでのライヴ盤である。ワンホーン・カルテットで、トランペット(曲によってフリューゲルホルン)が60歳になるフランコ・アンブロゼッティ。その演奏は若々しく、瞬発力もあり、アンブロゼッティ健在である。そしてバッキングにソロにと、演奏の要となるピアノはティエリー・ラングなのだが、やはりこのアルバムのキー・パーソンはラングだ。Plainis Phare 時代に比べて UK Blue Note から発表するアルバムにあまり良さを見出せなかった人は、このライヴのラングを聴いてあらためて彼を見直すのでは。レギュラー・グループでないだけに、曲目はスタンダードやジャズ・スタンダードの有名曲ばかりだが、4人のコンビネーションは申し分なく、一体となってドライヴする。1曲目「枯葉」、アンブロゼッティのソロが終わって、ラングのソロが始まってしばらくすると、CDのジャケットを取り出し、記載されているベーシストやドラムスの名前をもう一度チェックせずにはおれなくなるはずだ。 | ||
『Gift』 Stephen Keogh, Bill Charlap, Louis Stewart, Mark Hodgson (Ashbrown Productions) |
|||
 |
ピアノ、ギター、ベース、ドラムスのカルテット編成で、ジャケットには4人の名前が並列表記されているが、リーダーはドラムスのステファン・コーのようだ。録音はアイルランドのダブリンとなっている。ビル・シャーラップがこのアルバムのためだけにダブリンを訪れたとは考えにくいから、ツアーがクラブ・ギグのおりに同地で吹き込んだものと思われる。普通はこのアルバムを買われる方はピアノのシャーラップがお目当てだろうか。吉祥寺のユニオンで新着輸入盤を物色していた時に店内でかかっていたのが本CDで、SPから流れてきたギターの音色の美しさとそのスムースな音使い……ディスプレイしてあるジャケットのところに文字どおり飛んでいったら……ビンゴ! ルイス・ステュアートだった。そう、ワタシのお目当てはこのステュアートのギター。基本的にはメインストリーム系の人で、ジョー・パスのように美しい音色が嬉しいアイルランドのギタリスト、ルイス・ステュアート。コンテンポラリーなジャンルには手を広げないし、マイナーレーベルへの録音が多いので本邦では無名に近い。が、メインストリーム系とはいっても、その音楽性には懐の深いところもあって、ギター好きの人の間では知る人ぞ知る存在でもある。このアルバムのステュアートも実にいい。もちろんシャーラップもセンスのいいピアノを聴かせてくれる。これは「他人には教えたくない」系の魅力あふれる「贈り物」。あなたも、ぜひ…… |
||
|
|||