VOL.02
2001.06.11
矢 多 羅 の マ サ ラ
YATARA NO MASARA
![]()
月光茶房
![]()
VOL.02 2001.06.11 |
矢 多 羅 の マ サ ラ YATARA NO MASARA
|
月光茶房 |
原田正夫
Masao Harada
『矢多羅のマサラ』は「月光茶房」が推薦する音盤(CD・アナログ)を紹介するフリー・ペーパー。あるHPに連載しているジャズ入門のためのアルバム・ガイド『150 DISKS OFJAZZ』をプリントして店に置こう、というアイデアから出発したものだが、ジャズ以外の新譜や推薦盤も掲載しようということから、このフリー・ペーパー発刊の運びとなった。 『矢多羅のマサラ』で紹介するアルバムは月光茶房で実際に聴くことができる。店ともども、お見限りなきよう御贔屓に。 |
| VOL.02 | part 2 NEW ARRIVAL ▼ |
| part 1 |
part 3 UNFOGETTABLE ! / Ah, Tadon Kozo ! ▼ |
| 150 DISKS OF JAZZ |
最近はほとんど映画館に足を運ばなくなった。若い頃にたくさん観たというのでもないが、音楽同様に映画にも心のベストテンがある。『天井桟敷の人々』(リアル・タイムで観たわけじゃない、念のため)や『にがい米』そしてフェリーニの作品の数々やトリフォーの『緑色の部屋』は忘れられない映画だ。何度観ても感動するユル・ブリンナー主演の『王様と私』も。あっ、『サイレント・ランニング』なんてB級SFも結末のせつなさが故に忘れられない。そして…… 大学生の頃に観たバーブラ・ストライサンド主演の映画『追憶』。レッド・パージの嵐の中で、仕事のために赤狩りの体制側にくみしてゆく、ロバート・レッドフォード扮する夫のハベル。友人のため、いや何よりも謂れの無い言い掛かりには絶対に屈しようとしない自身の哲学を貫こうとする、バーブラ扮する主人公ケイティ。自身と彼の生き方に超えられない大きな溝を見い出したケイティは、愛してるが故にハベルを理解し、そしてその愛から身を引く。おぉー、今想い出しても、泣けるぞ。 以来、バーブラの歌う『追憶のテーマ(The Way We Were)』は心の一曲になった。なのに、どうしたことかサントラ盤を買いそびれたまま20年以上過ぎてしまい…… 先日渋谷のタワレコで、やっとそのサントラ盤(CD)を購入。ウチに帰って早速CDプレーヤーにセット。よかった……「心の一曲」は昔のまま、その輝きを失ってなかった。それより驚いたのが、このアルバムに収められている他の曲だ。映画のどのシーンに使われたのか全く記憶にない。いや驚いたのは、記憶力の衰え……じゃなくてね、『The Way We Were』以外の数々の曲がスイング・スタイルのジャズだったから。 |
|||
| ハリウッドには多くのジャズ・マンが集まっていた。ニューヨークの方でジャズの興隆があっても、ハリウッドにはミュージカルや映画産業があり、ソング・ライター、アレンジャーそしてスタジオ・ミュージシャンとしてロスやサンフランシスコには仕事がたくさんあった。演奏や即興の革新性を競うコンボ主体のジャズが脚光を浴びるのは1950年代に入ってからだ。ミュージカルの主題歌がヒットし、そしてミュージカルの音楽はごきげんにスイングしていた。そう、ロックがポピュラー・ミュージックの中心になる以前は、ジャズはポピュラー音楽と分けへだての無い関係だったのだ。 だから、ミュージカル映画でなくとも全盛期のハリウッド映画のサウンド・トラックは、驚くほどジャズ・スタイルのものが多い。『追憶』は1973年の映画だ。ハリウッドはニュー・シネマの時代を迎えており、ポピュラー音楽もロックが中心の時代。映画の時代設定がいくら40年代から50年代とはいえ、70年代制作の映画にスイング・ジャズがこんなにふんだんに使われている事は新鮮な驚きだった。 |
|||
006 |
フランク・ロンソリーノ (tb) 『フォー・ホーンズ・アンド・ア・ラッシュ・ライフ』 (東芝EMI) |
||
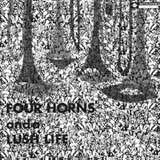 |
原盤もCDもジャケットにリーダー・ミュージシャンの名が無く、上記のタイトルだけである。昨年出たこの国内盤CDではリーダー名がラス・ガルシア・ウィズ・フランク・ロンソリーノという扱いになっている。ラス・ガルシアはハリウッド映画の音楽も数多く手掛けた名アレンジャーで、本アルバムでは4本のトロンボーンのアンサンブルを見事に聴かせる編曲と指揮を手掛ける。フランク・ロンソリーノは50〜60年代に西海岸で活躍したトロンボーンの名手で、本アルバムで大きくフィーチャーされている。 単調になりがちなトロンボーン4本の音の重なりに、ガルシアは1本のバリトン・サックスを加えることにより、アンサンブルに厚みとキレを与えている。柔らかいトロンボーンの音色の重なりが、実に気持ちよくスイングする。そしてソロをとるロンソリーノのトロンボーンの自由闊達で豪快なこと! 前回のゴンザルヴェスのアルバムの紹介でもふれたが、このスイング感は現代のミュージシャンには出せない。上記の『追憶』に収録されているジャズのスイングはやはり70年代のミュージシャンのもので、同じスイングでも……何と言ったらいいか、つまり……カタい。そう、スイングが固い。ロックのリズムが体に染み込んでない人達のスイング、もうそれは音盤の上に記録されたものでしか聴くことができないのかもしれない。このアルバムをヘッドフォン・ステレオにセットして初夏の陽ざしの中、「スイング」して欲しい……ぜひ。 |
||
007 |
キャノンボール・アダレイ (as) 『サムシン・エルス』 (東芝EMI) |
||
 |
単に「ジャズ」というと捉えどころがないが、「モダン・ジャズ」というと俄にイメージが鮮明になってくる。歴史的にいえば1940年代末から50年代末の概ねコンボによる演奏のジャズを指す。モダン・ジャズを気取ってダンモなんて言っていた、かつては。今は省略するけど、昔はひっくり返すのがイケてたのだ。都会の夜の薄暗いバー…煙草の紫煙…バーボン…不良(無頼とかヤンチャではなく)…ハードボイルド…そこに男と女がいて……なんてイメージがモダン・ジャズにはある。暗ぁ〜い。確かに。一方、モダン・ジャズはガキにゃあ解らない、大人の文化……そんな雰囲気をまとっていたのも確かだ。今どき、そんなこと言っても誰もうなずかない。当の大人がだらしないしね。 一般的にジャズといえば、このモダン・ジャズの持っているイメージが先行する。若い女性をターゲットにしたジャズ・アルバムをレコード会社が出すときはこのイメージが逆に邪魔になるらしい。そこでソフト・イメージとオシャレ感でパッケージングする。バカいっちゃあいけない。モダン・ジャズそれ自体は暗くも気取ったものでもない。最高にヒップな音楽なのに。さて、そのモダン・ジャズの中の最もモダン・ジャズたるアルバム、それがこの『サムシン・エルス』だ。レーベル契約の関係でアルト・サックスのキャノンボールの名義になっているが、このアルバムのリーダーはトランペットのマイルス・デイヴィス。多くを語る必要なし。最高にヒップで最高にセンシティヴなこのジャズ史上の「奇跡」を知らずに21世紀を迎えたならアナタは不幸すぎる。知らなきゃ知らないで困ることはないけれど……。 |
||
008 |
ビル・エヴァンス (p) 『ワルツ・フォー・デビー』 (ビクター・エンタテインメント) |
||
 |
これもモダン・ジャズを代表する1枚、それどころかジャズ・ファンの人気投票でいつも1位に輝く永遠のジャズ・アイテム。『サムシン・エルス』もこのアルバムもジャズ・アルバム・ガイドでは必ず紹介されるもので、20世紀の世界遺産ともいうべきものなのだ。月光茶房はBGMにジャズをかけている。グレン・ミラーから最新の輸入盤までかけるし、ガラス張りのレコード室も持っているが、ジャズ喫茶ではない。スタッフのアルバイト採用もジャズが好きかどうかでは決めないし、結果、ほとんどのコはジャズに興味がない。が、歴代のアルバイトがみんな好きになるミュージシャンは決まってビル・エヴァンスで、特にこのピアノ・トリオによるライブ盤がやはりダントツ人気。ちょっとジャズの雰囲気に浸りたい人から、新譜CDやオリジナル盤を買うのに毎月お小遣いがいくらあっても足りないワタシみたいな者まで、みんなに愛されるアルバム……それがこの『ワルツ・フォー・デビー』。 ビル・エヴァンスは50年代から1970年代にかけて常に第一線で活躍したアメリカのユダヤ系のピアニスト。たくさんの吹き込みを残したがトリオでのアルバムが多く、人気が集中しているのもトリオ・アルバムだ。ベースやドラムスを従えて4ビートでスイングするピアノ・ジャズの世界に「幻想的」だとか「ロマンティック」とか形容される世界を溶け込ませたエヴァンス。彼がいなけゃリューイチ・サカモトの『エナジー・フロウ』だって生まれてない。 |
||
009 |
ジョー・パス (g) 『インターコンチネンタル』 (ビクター・エンタテインメント) |
||
 |
ギターは管楽器やピアノと比べると音が小さい。だからジャズの歴史の中でソロ楽器としてギターが力を発揮するのは、マイクロフォンやアンプによる音の増幅という手段をギターが手に入れてからだといわれている。そんなこともあってか、ギターは脇役的な役回りがあり、ジャズ・ギターの奏法に革新をもたらしたギタリストはいても、ジャズの潮流を変えたギタリストはいない。だからといって、管楽器やピアノ中心のジャズに比べて、ギター主体のジャズが音楽として劣っているわけでは決してない。 が、サックス奏者やピアノ・トリオのアルバムに比べて、ギター奏者のアルバムの売り上げが総じて低いのがニッポンの現状だ。モダン・ジャズが人気のあった頃、ジャズ・ファンがレコードを買おうとする時にまず確認したのが、そのアルバムの楽器編成に、まずオルガンが入ってないかどうか、次にコンガ等のラテン系パーカッションが入ってないかどうか、さらにギターが入ってないかどうか、なんだよ……という事を「大先輩」から聞いたことがある。さて、このアルバムはギターとドラムスにベースというトリオ編成。アメリカのジャズ・ギターの名手ジョー・パスが1970年にドイツのMPSに吹き込んだこのアルバムは、響きの良い録音とあいまってギターによるジャズの心地よさを存分に味わえる。 |
||
010 |
Moving Hearts (group) 『The Storm』 (Tara Records) |
||
 |
エスニック音楽やワールド・ミュージックの盛況が一段落しても根強い人気があるのが、ブラジル音楽と、ケルト・ミュージックといわれるアイルランド等のトラディショナル・フォーク。保守的だったアイルランドやイギリスのトラディショナル・フォーク界もロックの洗礼を受けた1970年代、エレクトリック化してロックのリズムを取り入れる若いミュージシャンが現れる。80年代から90年代にかけて、そうしたエレクトリック化やドラムスの導入も板につき、数々の優れたアルバムが生まれるが、1989年リリースのこのアルバムもその1枚。アイリッシュ・トラッド独特の楽器に、曲によってエレクトリック・ギターやベース、そしてサックスやシンセ、さらにコンガ等のパーカッションも入る。 ロックやラテン音楽とジャズがシンクロして生まれた「フュージョン」におけるリズム・アプローチやサックス、キーボードのフィーチャーのしかたと、アイリッシュ・トラッドが見事に一体化した傑作がこの「ザ・ストーム」。アイルランド移民が持ち込んだフォーク・ミュージックが、アメリカのフォーク・ミュージックの原型。そしてそれは、アフリカから黒人が持ち込んだ音楽と共にジャズのルーツ・ミュージックでもある。そのジャズの「ルーツ」が巡り巡って、ジャズから生まれた音楽=フュージョンと再び融合(フュージョン)したわけだ。 現在、このアルバムは輸入盤CDで手に入る。ワールド・ミュージックのフロアの「アイルランド」のコーナーにある。 |
||