彩耳記
saiji-ki
| 23 | オレゴン |

BECOME, SEEM, APPEAR 6:34
from 《In Concert / Oregon》 (Vanguard VSD 79358) 【A面2曲目】
1975年4月にニューヨークのヴァンガード・スタジオで行なわれたライヴ録音で、ヴァンガードからの4枚目のアルバム《イン・コンサート
In Concert》の収録作品です。国内盤LPでの邦題は「出芽」でした。ポール・マッキャンドレス(オーボエ、イングリッシュ・ホルン、クラリネット、フルート)、グレン・ムーア(ベース、ヴァイオリン、ピアノ)、ラルフ・タウナー(ギター、ピアノ)、コリン・ウォルコット(タブラ、シタール)による、緊密なインプロヴィゼーション。オレゴンが奏でる音楽が放つ魅力の本質がここにあります。
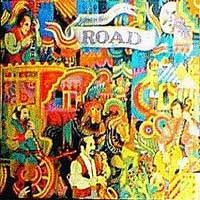
ICARUS 4:30
from 《ROAD / The Winter Consort》 (A&M SP-4279) 【A面1曲目】
さて、いったん時計の針を戻して、次はオレゴンの結成以前、ポール・ウィンター・コンソートによる1970年の名作ライヴ・アルバム《道(ロード)
Road》からの1曲です。ラルフ・タウナーの名曲「イカルス
ICARUS」は、このアルバムが初出になります。アポロ15号のクルーが、本作を月面への旅に持って行き、2つのクレーターを、本作収録曲の"Ghost Beads"および"Icarus"と名付けた、というエピソードがあります。たしかに宇宙を思わせる幻想的な曲です。パーソネルは、ポール・ウィンター(アルト・サックス)、ラルフ・タウナー(リュート、各種ギター)、デヴィッド・ダーリング(チェロ)、コリン・ウォルコット(シタール、パーカッション)、グレン・ムーア(ベース、エレクトリック・ベース)、ポール・マッキャンドレス(イングリッシュ・ホルン、オーボエ)。
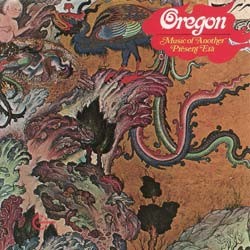
SAIL 4:31
from 《Music of Another Present Era / Oregon》 (Vanguard VSD 79326) 【A面3曲目】
ヴァンガード時代の幕開けを告げる、オレゴンの1972年デビュー作です。アルバム・タイトルは「もうひとつの同時代の音楽」と名付けられていて(国内盤LPでの邦題は「北の星」)、新しい航海に乗り出す彼らの気概を感じさせます。この時点で、メンバーは20歳代後半〜30歳代前半(タウナーは1940年生まれ)。「帆 SAIL」は当時28歳のコリン・ウォルコットの作曲。東洋的な時間感覚の導入と斬新な和声と旋律の見事な調和という、これぞオレゴンと呼べる個性をすでに確立しています。
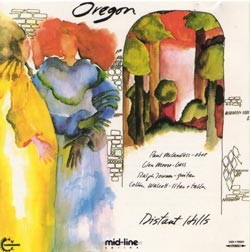
Distant Hills 6:34
from 《Distant Hills / Oregon》 (Vanguard VSD 79341) 【B面1曲目】
「オレゴンの最高傑作」との呼び声が高い1973年のアルバム《遙かなる丘
Distant Hills》。B面1曲目のアルバム・タイトル曲はラルフ・タウナーの作曲。ポール・マッキャンドレスが奏でるオーボエの旋律は、不安と幻想と夢にみちた不思議な世界を感じさせます。ちなみに4年後の1977年、ラルフ・タウナーがオレゴンと並行して結成していた、ECMレーベルにおける新バンド「ソルスティス
Solstice」──メンバーは、ラルフ・タウナー、ヤン・ガルバレク、エバーハルト・ウェーバー、ヨン・クリステンセンの4名、70年代ECMの頂点を刻んだグループ──の第二作《Sound And Shadows / Ralph Towner, Solstice》(ECM 1095 ■)でもこの曲が1曲目に演奏されていました。
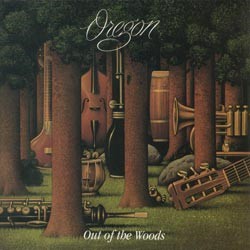
Cane Fields 4:37
from 《Out of the Woods / Oregon》 (Elektra 6E-154) 【A面4曲目】
A面4曲目「きいちごの草原
Cane Fields」、ポール・マッキャンドレスの作曲。[4]と続けて聴き比べてみると、民謡風の素朴な抒情性が後退して、やや思索的な深みや抽象的な気配が勝ってきています。この時期、タウナーとウォルコットが頻繁に関わっていたECMレーベルのマンフレート・アイヒャーの神通力がここまで及んでいたのかどうか・・・
という深読みはさておき、《アウト・オブ・ザ・ウッズ〜森の中から》という邦題の本アルバムは、森のなかに楽器が佇む素敵なジャケット・カヴァーに包まれたエレクトラ移籍後1978年の傑作です。録音場所はパット・メセニー・グループの《アメリカン・ガレージ》(ECM 1155)の録音でも使用されていた、マサチューセッツ州
Massachusetts ノース・ブルックフィールド
North Brookfield の雄大な自然の中に建つロング・ヴュー・ファーム・スタジオ
Long View Farm Studio(■/■)です。
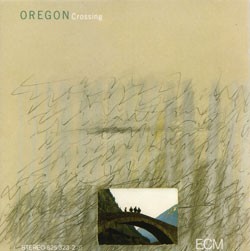
Alpenbridge 6:26
from 《Crossing / Oregon》 (ECM 1291) 【A面3曲目】
そして最後の曲は、エレクトラからECMへ移っての第二作《クロッシング Crossing》(ECM 1291 ■)から、「アルペンブリッジ Alpenbridge」です。本作は1984年10月の録音ですが、その翌月、メンバー全員が乗った車がアウトバーンでクラッシュし、コリン・ウォルコットとECMのスタッフの2名が死亡するという悲惨な事故が起きます。ウォルコットは39歳でした。翌1985年、発売された本作を手にした世界中の多くのファンは、大きな哀しみとともに、これまで素晴らしい音楽を聴かせてくれたコリン・ウォルコットへの感謝の念を一層深めました。
私が最初にオレゴンの音楽を聴いたのは、ヴァイオリニストのズビグニェフ・セイフェルト(当時の国内盤LPでのカナ表記はズビグニュー・ザイフェルト)Zbigniew Seifert との共演による1978年作《ヴァイオリン Violin》(Vanguard
VSD 79397)でしたが、その次に聴いたアルバムがこの《Crossing》でした。
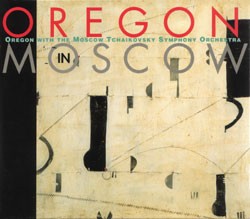
創造的な音楽に取り組むということは、精神そのものに取り組むことだと思う。音楽の創造とは、精神の問題なのだから……。
他の精神遍歴のように、外的なものを多くは含んでいないが、創造するということによって、人は他人の前に、あるいは自分自身の前に、自分を曝け出すのだ。
創造とは、自分が何者で、何を目指しているかを、真に反映することなのだ。
僕が音楽を演奏したり、練習したりする時の精神状態は、瞑想にふけっている時のそれとよく似ている。バンドの中のあらゆる事に気を配ることで、高度の集中力が身についてくる。
人々が僕達の音楽を聴きに来る時は、自分達にも出来るのではないか、自分達も音楽を理解し、音楽の中に入り込むことが出来るのではないか、ということを知りたくて来るのだと思う。音楽それ自体は独立したものであるにせよ、音楽は決して限られた者だけの特権ではないのだから……
何となく、ある種のスタイルが出来始めている気がしないでもない。僕等はお互いに、統一しようとか、グループとしてこじんまりまとまろう等とは思っていない。勿論、自分達の聴いたことのある曲、好きな曲を演奏はするが、スタイルというのは、常に二次的に派生するものだと思っている。初めから、“こういうものを”という目標がある訳ではなく、結果として現在の僕達の音楽が出来ただけだ。作曲をする時も、僕としては一人一人の才能を生かそうとしているだけなのだ。
だから、僕等としては、同じ演奏を二度繰り返すようなことはしたくないと思っている。ベスト・テンに入るか入らないか、という事だって、たまたまソノリティが良かったからかも知れないし、聴衆が、会場が良かったからかも知れない。だから、僕達は、その方が良いと分かれば、曲の途中でだって、どんどん楽節を書き加えていくことにしている。
それが僕達のやり方だし、4人しかいないんだから、協力体制は充分というものだ。
僕等は音楽が好きだからやっている。常に他のメンバーと自分を結びつけ、彼等に耳を傾けるように注意している。全てが自然に、しかも他人のプレイの中から生まれ出てくるのを見る、それが自由な音楽の大切なところだと思う。自分のパートだけを弾いているだけなんて思ったこともないし、他の仲間も、それぞれ自分のパートだけに専念しているのでは無いと、お互いに信じ合っている。誰かが何かをすれば、自分はそれに興味を持ち、自分が何かを語れば、仲間は必ずそれに反応を示してくれる。全てがそんなふうに、うまく絡まり合っているのだ。
(以上は、『冬の陽/オレゴン』1975年国内盤LP[キングレコード
/ Vanguard SR-3183]ライナーノートからの抜粋。訳者不明)
堀内宏公
Hiromasa Horiuchi
![]()
| ▼ ロヴァの耳
多田雅範 OLD vol. 007 より、「ラルフ・タウナー」 |
■ Oregon Official Web Site