| 1 |  ECM 1053 ECM 1053 |
Michael Naura | Vanessa | ||
| 2 |  ECM 1207 ECM 1207 |
John Abercrombie / Ralph Towner | Five Years Later | ||
| 3 |  ECM 1220 ECM 1220 |
Mike Nock | Ondas | ||
| 4 |  ECM 1251 ECM 1251 |
Dino Saluzzi | Kultrum | ||
| 5 |  ECM 1346 ECM 1346 |
Terje Rypdal & The Chasers | Blue | ||
| 6 |  ECM 1428 ECM 1428 |
Egberto Gismonti Group | Infância | ||
| 7 | 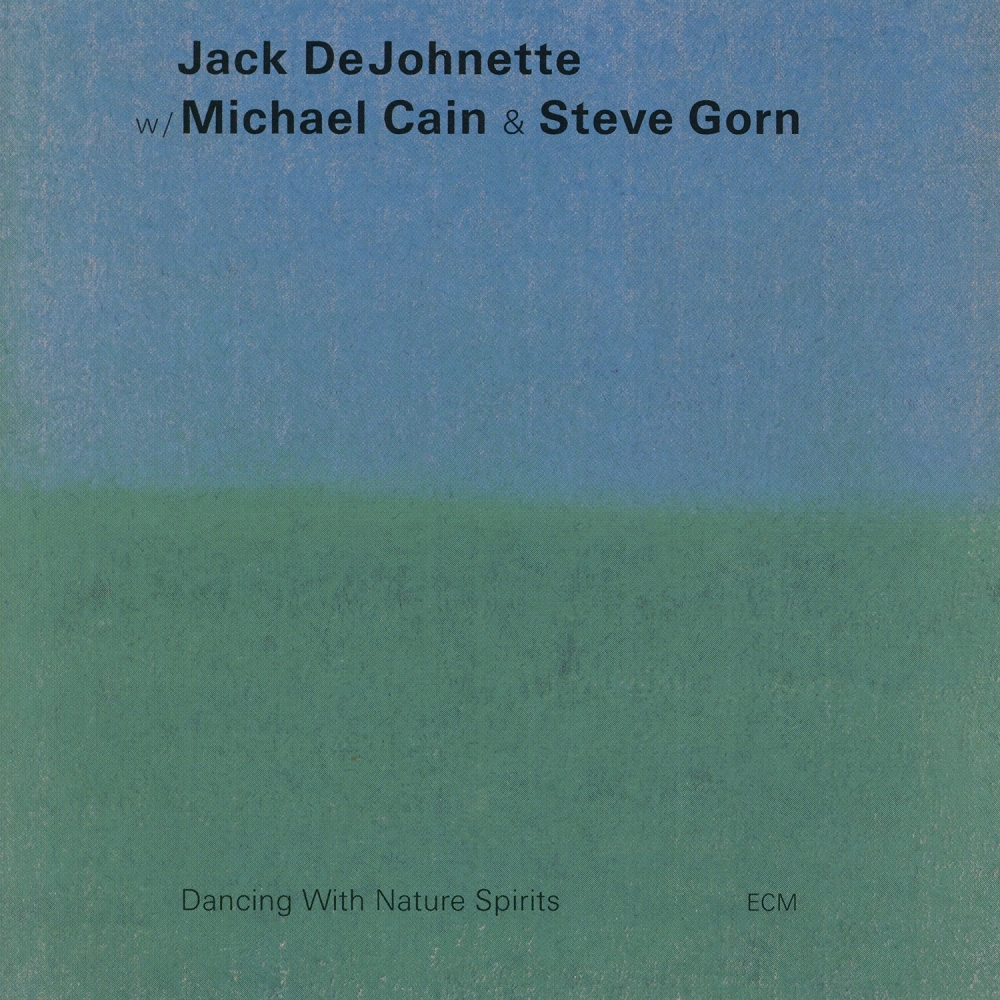 ECM 1558 ECM 1558 |
Jack DeJohnette | Dancing With Nature Spirits | ||
| 8 |  ECM 1721 ECM 1721 |
Michael Mantler | Songs and One Symphony | ||
| 9 | 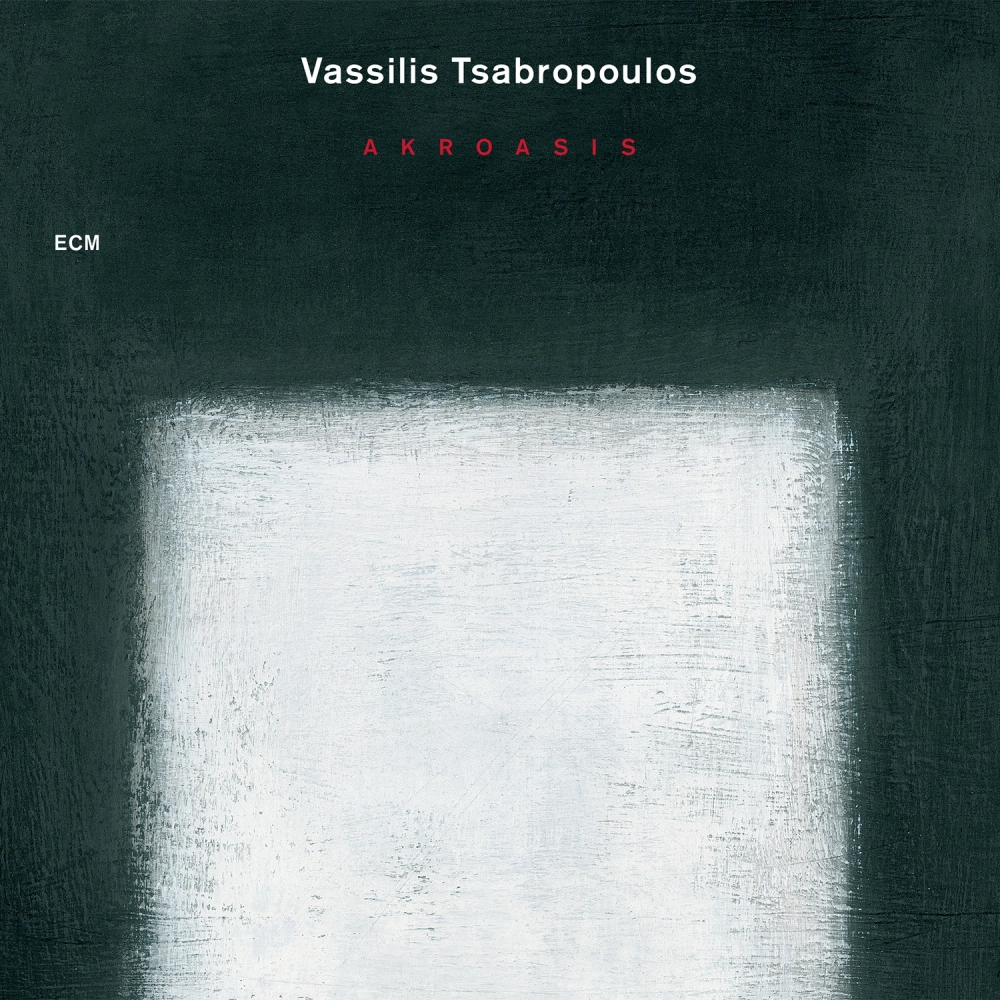 ECM 1737 ECM 1737 |
Vassilis Tsabropoulos | Akroasis | ||
| 10 |  ECM 1996 ECM 1996 |
Sinikka Langeland | Starflowers | ||
| 11 |  ECM 2056 ECM 2056 |
Ketil Bjørnstad | The Light | ||
そもそも選択と定置は音楽との出会いに役立つものだろうか。他人も自分と同じように聴けるはず、つまり自分が感じている魅力は他人も味わえるはずという信念や思い込みがなければ、それは単なる好みの押しつけでしかない。 しかも、自分の思いや考えを他人に伝えようと熱心になるあまり、それが要らぬおせっかいとなって、音楽を聴く際に特権的に許されている思いがけない発見や予測できない不安定な状態といったもの――明確に定義できない曖昧で開かれた体験の種子を抱えた状態にできるだけ長く留まり、自らの力で参照点を見つけ、進む道を探し出そうと試みること――を逆に聴き手から奪い去ってしまい、さらに他人から与えられた枠組みの範囲内で音楽を聴いたり、他人が与えた評価・解説の「正否」の判断やその「追認」といったものが聴くことの目的にすり替わってしまうとしたら、役立つどころの話ではない。 音楽を聴いて何かが「わかる」というのは、結局は「謎」や「わからない」ことの豊かさを知ることや、理解し損なうことと無関係ではない。知識に回収された体験は、聴取とはちがう次元で利用される材料にすぎない。 音楽によって触発され、他の何かや別の何かに変化していく可能性のなかに、未知へと浸透していく体験がはぐくまれる。そこに聴取の実質があるとすれば、個人的な感動の比較や順位付けにどれほどの意味があるのだろう。解読可能な体験を求めたり、あるいはそれを仮定する聴き方とは、結局は、「わかる」ことの学習や、「わかった」ことの復習という側面に引き寄せられるばかりで、肝心な「わからなさ」の手前を気づかない間に通りすぎてしまう。 とはいえ、違った角度からものを見るために補助線を引いてみたり、道に迷ったときの目印を掲げてみたりすることは、うまくすれば誤解やすれ違いや偶然などの助けも借りつつ、自分だけの思いがけない音楽地図を作り出すきっかけとなるかもしれない。(もちろんそうならないことのほうが多いとしても) まず11枚を選ぶ条件として、自分がカタログで執筆したものは除いた。そして『ECM catalog』を読んで、音楽の感じ方が改めて揺り動かされ、新しい「聴こえ方」の体験があったものを重視した。序列は問わないため掲載は番号順。 |
||||
| 1 |  |
ECM 1053 Michael Naura | Vanessa 久しぶりに聴いてみると、フランスのジャズ・ロック・バンド「マグマ」の70年代前半の音の気配を感じさせる。不安定な和音のアルペジオやリフを、単純な拍子を軸に据えて旋律のシンコペーションで自由に揺らすやりかた。同じモチーフを何度もなぞるようにして密度とうねりを引き出し、隙間をあけて積み上げた壁の間を行き交う意識の流れを作り出す。共演のクラウス・トゥーネマンは「世界最高峰のファゴット奏者」とも呼ばれる名手で、1962年から78年まで北ドイツ放送響で首席奏者を務め、本作はその時期の録音ということになるのだが、正直に言ってバランスを欠いた惨憺たる演奏で、ミキシングもよくない。だが捨てがたい味もあって、もどかしい妙な気分になる。 澤野工房から復刻されたミハエル・ナウラ・クインテット《EUROPEAN JAZZ SOUNDS》(1963年録音)■
――タビー・ヘイズの「ダウン・イン・ザ・ヴィレッジ」をやっていることでも有名――での欧州風の洗練されたジャズとは全く異質な内容。制御できない不可視の部分や余熱の動力を生かそうとした、やや観念的な色合いが勝った旋法(モード)に根差したフュージョンだが、それは1974年という録音時の音楽状況を考えると、プログレッシヴ・ロックが醸成した新たな響きの質感がナウラの音楽に逆流して生まれた特異な風景だったのかもしれない。企図を超えた交配の妙とでもいうか。ドイツでは数年前に『ナウラボックス』という6枚組CDが出ていて、オーソドックスからフリーまで、時代ごとに結成していたバンドの録音を拾遺して、幅広いキャリアを俯瞰している。自作の詩や自伝風のテクストの朗読もふんだんに収録され、単なる作品集とは趣が異なるつくり。エバーハルト・ウェーバー在籍時のクィンテットの演奏も少しだが聴ける。 |
||
| 2 |  |
ECM 1207 John Abercrombie / Ralph Towner | Five Years Later 今年2010年は7月17日の梅雨明け以来、連日異常なまでの猛暑が続いている。灼熱のなかで揺らめく大気をぼうっと眺めていると、耳の奥で本作が鳴り始める。私にとってこれは夏を象徴する一枚。 ジョン・アバークロンビーとラルフ・タウナーのギターが、意識の朦朧となった気怠い夏の午後を描いた淡彩画のスケッチ帖。視線は焦点の合わないまま空間を漂い、会話は途切れがちに、深まることもなく過ぎていく。この二人だからこそ、の、落ちそうで落ちない響き、あるいはもうすでに落ちているのに浮かんでいる、といったような、微妙な間合いによる残像。北園克衛の詩を初めて読んだときに感じた、世界が記号化されていくプロセスを追ったコマ送り写真のような印象が本作の響きの中にもあって、そのせいで親しみ深く思われるのかもしれない。そうした共感がなければ、きっと不連続の演技の羅列に聴こえるだろう。 |
||
| 3 |  |
ECM 1220 Mike Nock | Ondas タイトルはイタリア語、スペイン語で共に「波」の複数形。ジャケットも波の写真をトリミングと拡大率を変えて黒地の上に並べたもの。海に注ぐ光、水面の色合い、波の形、三枚の写真の調和と均衡は、本作の音楽のイメージと一致している。三人の演奏には、展開も、挑発も、交差もない。ひたすらに揺れながら打ち寄せ、砕かれて沈む引き潮となって、水をとらえる重力と浮力のあわいに沿って進んでいくだけだ。 ヨン・クリステンセンのドラムは定型ビートを外れているからこそ、うねる波の動きを繰り返し表出している。それは後年、ECM究極の一作であるケティル・ビョルンスタの《海》(ECM 1545)において最高位の到達を示す。本作はその序章でもあるが、すでに終章を先取りしていたともいえる。波、すなわち、揺らぎ。そして永劫回帰。 |
||
| 4 |  |
ECM 1251 Dino Saluzzi | Kultrum タイトルの「クルトゥルン」[註]とは、南米チリの原住民マプーチェ族の巫女が儀礼のときに使う太鼓のことで、Cultrún, Cultrum, Kultrung, Kultrum, Kultrun とも表記される。近藤元子さんによる「マプーチェ族の音楽とその文化(チリ民俗音楽について 3)」という報告がある(■)[「日智商工会議所」HP(■)内に掲載。「智」とはチリの漢字省略表記]。
サルーシはアルゼンチン出身だが、南米各地の古い民俗芸能や民族音楽にも早くから深い関心を寄せていた。種々の南米の先住民の文化を知り、スペインによる植民地化を通じた文化の変容の歴史を知り、軍事政権下での民衆の抵抗運動と歌の歴史をまなび、そうした音楽を聴くことで、ディノ・サルーシの音楽の聴こえ方も大分違ってくるかもしれない。 異文化の本質など、書籍を読んで知識を得たり珍しい録音をいくら聴いたりしたからといって簡単に分かるようなものではない。けれども、「分かろう」「分かりたい」と考えて何かをしてみるということは、じつは「分かる」ということよりも大事だったりする。 本作はバンドネオン、声、打楽器、笛を多重録音して作られている。トンスタジオ・バウアーでの録音、エンジニアはマルティン・ヴィーラント、アイヒャーのプロデュースによる、独特のエコーとリヴァーブを駆使したECM特有のサウンド。多くの「ワールド・ミュージック」を特徴付ける雰囲気過剰でコンテクストを説明したがる音作りの方向性とは一線を画したものだ。 ここには、音色や旋律に潜む素朴さが滑らかにつながって風景を描き出すといったような安心できる脈絡はない。むしろ、いくつもの写真を床中にまき散らして、それを一枚ずつ味わいながら視線を移すことから生まれてくる、想念や歩行のリズムと間合いこそが、聴き手ごとに異なる道標(みちしるべ)となる。それは詩集を読む体験に近いのではないか。少し前に読んだ詩行の記憶が現在出会った言葉と共震を始め、あたらしく違った意味を伴いながら再帰する。本作を聴いているとそういった体験が頻繁に起こる。葉陰や石の裏や水辺にそっと記された夢の物語の徴候(サイン)の数々。 以下、収録曲の詩的なタイトルを紹介する。 (1)「クルトゥルン・パンパ(序章とマランボ)」。 (2)「ガブリエル・コンドル(呼びかけと歌)」。 (3)「平和の水」。 (4)「鳥と赤い花の咲く木」。 (5)「アラウカの儀礼[雨の歌/チョイケ/ワイニョ]」。 (6)「川、そして祖父」。 (7)「留まる手順」。 (8)「太陽のために、雨のために」。 |
||
| 5 |  |
ECM 1346 Terje Rypdal & The Chasers | Blue テリエ・リピダル[タリエ・リプダル]Terje Rypdal のギターとキーボード、ビョルン・ヒェレミール[シェルミール] Bjørn Kjellemyr のベース(エレクトリックとアコースティックの両方)、アウドゥン・クライヴ Audun Kleive のドラムとパーカッション。1984年結成のトリオ「チェイサーズ」の2ndアルバム(1986年録音)である。リリース時にはプログレッシヴ・ロック風、ヘヴィー・ロック風の面持ちで登場したが、当時のロックに比べると音色が全体に安っぽく感じられ、その分、サウンドの装飾面ではなく各奏者が対峙する「間」の感覚や構成面に耳の焦点が結ばれていった。曲自体に留まらずアルバム全体の構成も力ずくでねじ伏せたいびつな外観に映るが、そのバロック的なポジションにこそ本作の魅力はあった。 痛みを刺激で覆い隠す作法と痛みを痺れで忘却させる作法とを同時に塗り重ねてみたときに何が起きるか。過剰な暴力性が白濁した不協和音へと流れ込み、不定形の塊がゆっくりと前景を横切って、呼吸する青い空間を引き寄せる。焦燥のロマンではなく、「不可知の雲」の神秘を間接的に描くというECMらしいプレゼンテーションだ。 ロックの外見を身にまといどこにも着地しない宙吊り状態を噴き上げ続ける冷徹で快楽的なサウンドは、1985年録音のデビュー作《チェイサーズ》(ECM 1303)から本作《ブルー》(ECM 1346)を経てさらに加速を深め、キーボードのアットレ・バッケン Atle Bakken を4人目のメンバーに加えてライヴを重ねる。1988年録音の三作目《ザ・シングルズ・コレクション》(ECM 1383)では、ハードロック/ヘヴィメタル/ニュー・ウェイヴ/プログレ/ジャズのミクスチャーによる偽悪的なサウンドをきらめかせ、これがバンド名義では最後の作品となる。とはいえ、「チェイサーズ」としてのライヴ活動はアットレ・バッケンを含む4人編成で1991年まで継続していた模様。その後も1992〜96年にかけてオリジナルのトリオ編成で活動。その間、1994年にはリピダルのリーダー作《イフ・マウンテン・クッド・シング If Mountains Could Sing》(ECM 1554)に「チェイサーズ」の3人が揃って参加している。また同年フィンランドで開催されたポリ・ジャズ・フェスティヴァル Pori Jazz Festival では、3人が「チェイサーズ」を名乗って出演している。 チェイサーズの名義で録音された、《Chaser》(ECM 1303)1985年、《Blue》(ECM 1346)1986年、《The Singles Collection》(ECM 1383)1988年の三枚のアルバムは、1947年8月生まれのリピダルが不惑を通過する前後に叩きつけた永遠の青春の輝きと言ってよい記念碑である。 ところで最終作の《ザ・シングルズ・コレクション》には逸話がある。3日間で録音を完了した本作の中で、アットレ・バッケンはキーボード、シンセサイザー、シンクラヴィア、編曲、オーケストレーションを担当して大きな貢献を果たしているが、自身の作曲作品も3曲提供している。だがこのときバッケンの作品の録音後に彼自身が行ったミックスに対し、音がハード過ぎるとアイヒャーが駄目出しをした。これにバッケンが怒って、両者が険悪な状態に。結果的にアイヒャーは本作の録音エンジニアを担当していたヤン・エリック・コングスハウクに指示して、バッケンの曲をより柔らかい音のミックスにやり直させ、曲の長さも相当短くカットしてしまう。バッケンは音楽家としての自身のプライドから、もはやこれは自分の仕事とは呼べないものだと判断して、ジャケットに「Allan Dangerfield」という偽名をクレジットとして掲示するよう要求。なお、このバッケン自身のミックスについては、元メンバーとその周辺では、「こっちのほうが烈しく熱くて良かったのに」という声が呟かれていたとも。まあしかし・・・このサウンド指向でECMからリリースするということ自体にそもそも無理があった。 |
||
| 6 |  |
ECM 1428 Egberto Gismonti Group | Infância まず本作CD盤におけるノイズについて述べておく。(3)「Meninas」の4分48秒の大きなデジタル・ノイズの存在である。同箇所はLPレコードにおいては何の問題もなく再生され(同時発売のカセット・テープでも確認したが、やはり何の問題もなし)、またドイツ盤CDと日本国内盤CDの両方で同じ現象が発生することから、このノイズはCDのオリジナル・マスター上にあるノイズだと思われる。CD化のマスタリング時に発生したノイズではないだろうか。 ECMとしては珍しい「キズ」をもつ盤だが、全編を覆い尽くす極上の質感は、何度聴いても新鮮な発見に溢れ、酔わされる。おそらく本作はほとんどの音符がスコアに綿密に記譜されていると思われ、テーマに基づく即興もほとんどないが、個々の音にはある具体的なイメージが仕組まれているようで、その寓意性によって、聴き手の心のなかには物語を語り聞かされているように景色や情感が自然と浮かんでくる。ここには器楽の響きと同時に隠された言葉の力があるように思う。 ジスモンチのアルバムはどれも一期一会の魂の発露で輝いている。比較的よく聴くのは、本作のほかに《ZigZag》(ECM 1582)や二枚組の《Sanfona》(ECM 1203/04)などだ。 オーケストラ作品集《Meeting Point》(ECM 1586)も空を飛んでいるような心地になる。「第24回<東京の夏>音楽祭2008」ではジスモンチのオーケストラ作品を特集した個展が紀尾井ホールで開催され、沼尻竜典指揮、東京フィルハーモニー交響楽団とともに、ジスモンチ自身もピアノとギターの独奏者として出演した。なお、このコンサートについては、音楽評論家の澤谷夏樹さんが特にジスモンチの編曲に対して示唆的な批評をお書きになっている。■ その他、ガルバレク、ヘイデンとの2枚や、ECMがディストリビュートしているジスモンチ自身のレーベル「Carmo」の諸作も素晴らしい。 |
||
| 7 | 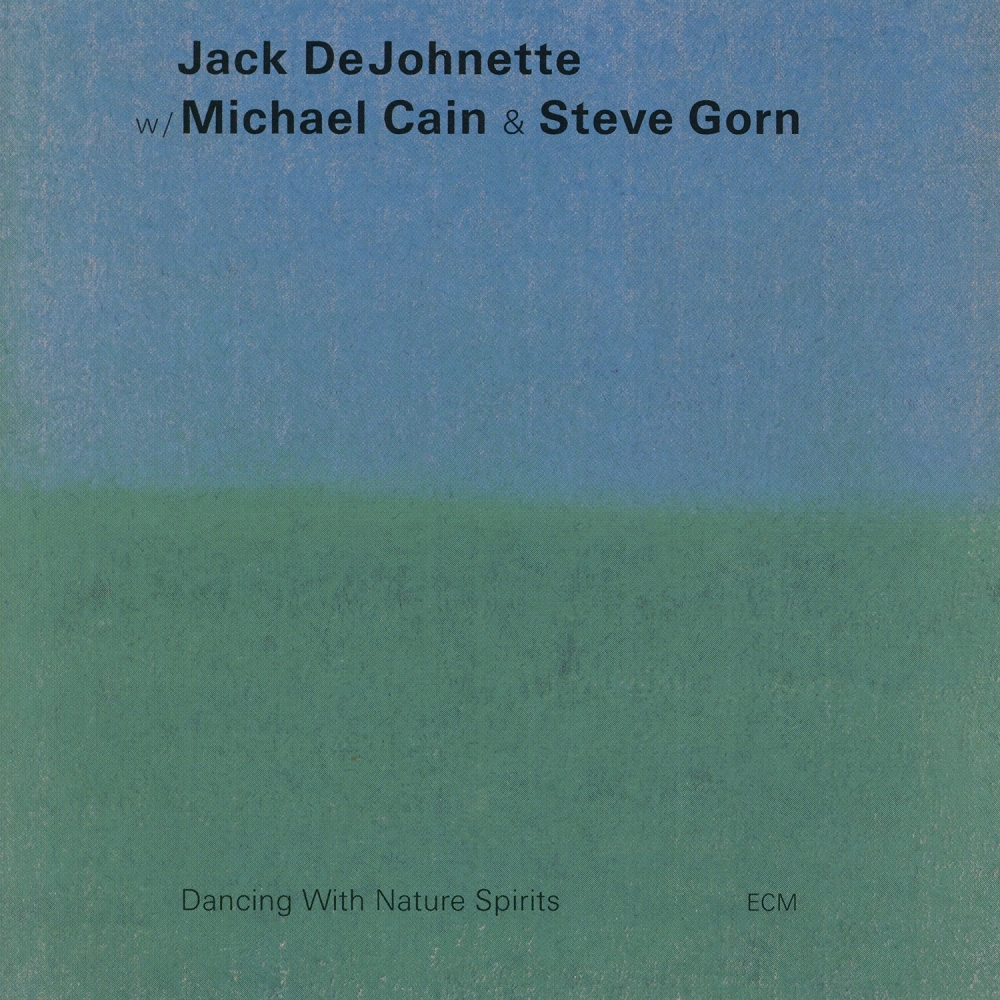 |
ECM 1558 Jack DeJohnette | Dancing With Nature Spirits 隠された言葉の力、といえば、ジャック・ディジョネットの本作である。ちょうどアイヌと北方民族の芸能のCD制作の仕事をしていた時機に、本作の聴こえ方が突然変わった。個々の音が「言葉」として聴こえ始めたのである。 このアルバムでは、ジャズ・ドラマーとしてのジャック・ディジョネットを期待しても全く裏切られる。ここでディジョネットはアメリカ先住民の血をひく自身のDNAに従った響きを織りなして、ビートやハーモニー、インタープレイなどからは離脱した、音の自然な呼応の成り行きに従うことに専心している。また本作ではマイケル・ケイン(ピアノ)の参加が大きな鍵となっている。クロマティックな色彩を滲ませた民族音楽的なリズムが躍動するケインのハイブリッドなピアノ・サウンドは、水平線の目印と共に重力の役割を果たしていて、スティーヴ・ゴーンのバンスリ(笛)、クラリネット、サックスが、動物や森の聖霊に憑依するのを自由に試させながら、ディジョネットの純粋なスピリットを穏やかな仕方で解放することに成功している。これは配置の妙というものだろう。 三者の呼び交わしの向こう側には鬩ぎ合う原初の音がある。その音を巡っての親密な対話に耳をすませば、けっして説明や解読に向かわない個々の発語の動機が直接伝わってきて、音楽の聴こえ方は相当に違ったものとなるだろう。そうなれば、演奏しているのは彼ら三人でなく自然の聖霊、祖先の魂であることが自明となる。彼ら三人は、目の前の音を離れたところで聴き、音に触れて他者と震動を共有するという立場を崩していない。つまり聴き手にも演奏に参加する隙間が残されている。こういった音楽と向き合うと、音楽を聴くことが秘められた精神の旅でもあることを実感する。 |
||
| 8 |  |
ECM 1721 Michael Mantler | Songs and One Symphony マイケル・マントラーは1943年ウィーン生まれ。ウィーン音楽大学でトランペットと音楽学を学んだ後、1962年に米国へ渡ってボストンのバークリーに行き、1964年にニューヨークへ移ってセシル・テイラー他と演奏を始める。音楽家が経済的に自立して活動するための運動体を摸索して自主組織 Jazz Composers' Orchestra Association(JCOA)を設立。1968年、独奏者にセシル・テイラー、ドン・チェリー、ラズウェル・ラッド、ファラオ・サンダース、ラリー・コリエル、ガトー・バルビエリを迎えて2枚組LP《THE JAZZ COMPOSER'S ORCHESTRA》(JCOA 1001/2)発表。続いて1968年から71年にかけて《ESCALATOR OVER THE HILL》を録音。1969年にはチャーリー・ヘイデンのリベレーション・ミュージック・オーケストラの録音にカーラ・ブレイと共に参加。 1972年には従来のレコード会社に頼らない自主流通を始め、1973年にマントラーとカーラ・ブレイの音楽を主に扱うWATTレーベルを開始(現在WATTはECMがディストリビューションを担当)。ウッドストック郊外にスタジオを建設。非商業的なジャズの制作を続けるため、各種財団からの支援を受ける。 エドワード・ゴーリーやハロルド・ピンター、サミュエル・ベケットをテクストに使った作品が多く、ヴォーカリストとしてロバート・ワイアットを起用することでカンタベリー系ミュージシャンとの機縁が深まり、元ヘンリー・カウのジョン・グリーヴスとピーター・ブレグヴァドの《KEW RHONE》(1976)にも参加しているのはプログレ・ファンには周知のことだろう。1982年にはロンドン交響楽団の弦楽オーケストラとの共演で《Something There》を録音。以後、欧州の放送局からの委嘱が続き作曲家としての評価を確立し、ジャズとロックとクラシックの混合によるオリジナルな「語り物」音楽の創作がさまざまに探究されていく。 1991年に米国からデンマークに移住。レーベルもWATTを離れ、その後はECMからのリリースとなる。ECMに移ってからの各作品のクォリティの高さは、『ECM catalog』で各氏が述べている通り。 思えば、マイケル・マントラーほどにECMレーベルだけが含みもつ複雑な感覚的価値の混淆と響き合うことができる存在はいないように思う。しかしその割には日本での関心や注目が低いのはなぜだろうか。 [推測●1] 「過去のイメージ」――ジャズ・ファンの多くは、米国時代のJCOAやWATTでの活動を定点としてマントラーを解釈する傾向が強い。そのため欧州移住後の作品は実態以上にジャズから離脱したものと映り、積極的な興味が持続しない。 [推測●2] 「ロックとの狭い接点」――カンタベリー・ロック・シーンのファンからすれば、ワイアットをはじめ共演者に注目しているに過ぎず、マントラーのジャズ界での活動には関心が向かわない。 [推測●3] 「現代音楽、クラシックの創作哲学とは別物」――現代音楽やクラシック・ファンはジャズ・ミュージシャンが譜面で表現した作品を模造と捉えがちで、それが真剣なものであるほど予断で済まそうとして積極的には近づかない。(逆に日本のジャズ愛好家の多くは「作曲」よりも「演奏」に留意して、音符をスコアに固定することを一義的に評価しない傾向が強い。すぐれたジャズを緻密にスコア化することも、明らかに創造的な営みであるのだが。マントラーの立ち位置は、ここでもますます狭く険しい。) [推測●4] 「外国語のテクストが理解できない」――マントラーの作品は作家や詩人のテクストを伴ったものが多く、文学への関心も共有していないと充分に理解できないものが多いのは確かだ。オースターやベケットの原語での愛読者が日本にどれだけいて、その内何人がマントラーのような不可思議な領域の音楽を愛好するというのか。 デンマーク移住後の作品では、マントラーが発見して常時起用している地元出身ギタリスト、ビャーネ・ロウペの空間を生かした響きと、弦楽合奏による引き延ばされた和音が特徴となっている。ヴィデオも使ったマルチ・メディア作品として構想・発表されたオペラ風作品《The School of Understanding》(初演時のタイトルは《The School of Languages》)(ECM 1648/49)は、CDという音だけのメディアにも関わらず充分に聴き手を引きつける力があって素晴らしいが、ここでは、ドイツのヘッセン放送協会の委嘱作でペーター・ルンデル指揮フランクフルト放送交響楽団という一流演奏陣による純音楽作品《One Symphony》(1998)を含む ECM1721 のひたむきな達成に注目してみたい。 このアルバムは二部構成となっていて、前半には、マントラーが1993年に結成したアンサンブル「チェンバー・ミュージック・アンド・ソングズ」(マントラーのトランペット、ポピュラー・ミュージック出身のデンマークを代表する女性シンガーのモナ・ラーセン、ビャーネ・ロウペのギター、キム・クリステンセンのキーボード、弦楽四重奏という編成)による室内楽伴奏の歌曲が収録されている。 そして後半に収録されているのが、管弦楽曲《One Symphony》。細胞となるいくつかのモチーフを元にして、それを様々な楽器の組み合わせで厚さや肌合いや速度や強度を変容させながら構築した、躍動感のある作品である。複雑な音のベクトルや意味を混在させた観念的世界と向き合った創作ではなく、むしろ響きそれ自体のヴァイタルな運動性と色彩に注目した、シリアスなビッグ・バンド・ジャズをオーケストラに相応しい語法で展開した作品だと捉えたほうが実体に近い。つまり伝統的な西洋楽器や合奏のかたちを使ってはいるが、実質的なスピリットはジャズであって、ここには歴史的なクラシック音楽や同時代の現代音楽との関わりはあまりない。 ECMのウェブサイト内の同作品の説明を読むと(ブックレットに解説やライナーノーツが未掲載の場合でも、90年代後半以降のカタログでは、ECMのサイトで制作の意図や背景、ミュージシャンへのインタヴューなどの豊富な情報が提供されている)、マントラー自身、「新ウィーン楽派や現代音楽の作り出した響きを利用することはあっても、それを使う美学的な意味においては全く関係がない」と語っている。 マントラーの作品のほとんどは歌が重要な役割を担っているが、そこでは旋律、リズム、和声が、いずれかが突出しないように抑制されている。そのためメロディはつねに脱臼・屈折した身振りを示しているが、それはヘンリー・カウやアート・ベアーズ、ロバート・ワイアット、カンタベリー系ロックにも通じるところがあり、これらとも共通する「語り物」としての特徴を持つ。 さらにその作品群を俯瞰したときに浮かび上がるのは、言語の実験によって不条理と向き合う現代文学への共感という大きな特徴である。クラシック以外のバックグラウンドをもつヴォーカリストの起用は、そうした宙吊りになった世界を響きのイメージとして引き出すことにも適い、感情を間接的に扱うことに成功している。オーケストラならではの陰鬱な屈折と、憂愁を内在させた響きによる飽くなき表現の探究。それは画家が作風を変えずに繰り返しキャンヴァスに向き合う態度を思わせる。 ここでは、ジャズがヨーロッパの地層を濾過することで文学的な仕方で内面化されており、そのことによって、シリアスな創造のための踏み台となっている。まさしくヨーロッパでしか成立不可能な宿命にあるユーロ・ジャズの極北のひとつの姿ではないだろうか。マイケル・マントラーのポピュラリティから完全に孤絶した作品群には、歴史と結びついたウィーン精神の甘美な香りと共に、孤独な魂を刺し貫く鋭い刺の痛みが内在しているように思う。
|
||
| 9 | 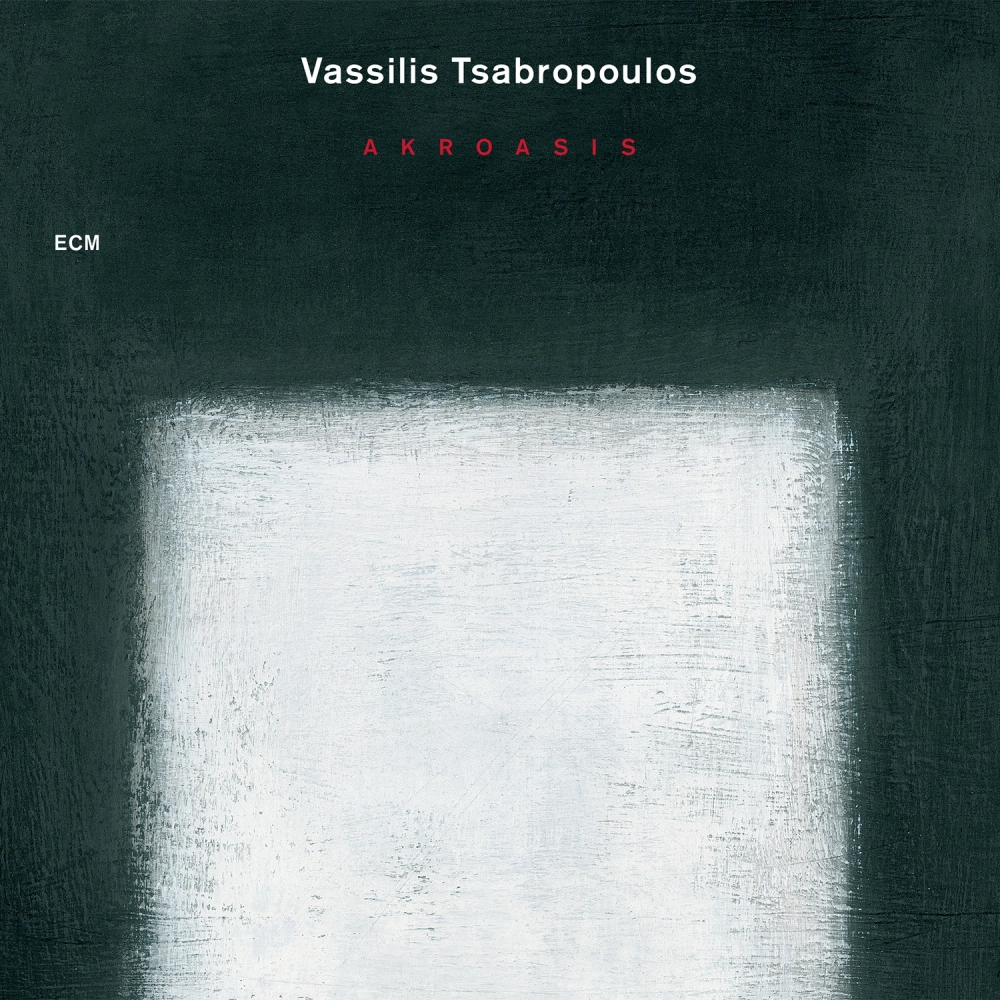 |
ECM 1737 Vassilis Tsabropoulos | Akroasis 『ECM catalog』で稲岡さんのコメントに引用されたヴァシリス・ツァブロプロスによる「表情の異なる八編の詩で綴られた詩集」という言葉が、これらの音楽を見事に言い表しているように思う。最初に聴いたときはピアノの音というよりもピアノの音に近い鐘が鳴っているような雰囲気が印象的だった。それぞれの音がハンドベルのように、別々の人の手で担われて届くように聞こえる。たぶんそれは演奏法の問題というよりは、旋法(モード)に基づいた曲の性格が影響したものだろう。 スリップ・ケースからCDケースを引き出すと、ブックレットの表紙は外ケースと同じような絵がレイアウトされているのだが(よく見ると違う絵だ)、絵の白色と黒色を逆転させて用いている。このデザインは本作の音楽の内容と呼応しているように思う。聴いていると、自分自身の体内でさまざまな刺激や反応、聴き方のアイディアが出てくる。だが、安易にヒーリング(治癒)の目的でイメージの方向性をコントロールせずに自動運転にまかせると途方もない場所に連れていかれることもあるので要注意。東方聖歌に埋め込まれた響きの喚起力はまったく侮れない。 2009年リリースのツァブロプロスのECMでのソロ・ピアノ第二弾《The Promise》(ECM
2081)は録音場所もエンジニアも同じだがアイヒャーによるプロデュースなのでサウンドやアルバム全体の流れに変化が見られる。そしてアニヤ・レヒナーとのグルジェフ作品集(ECM 1888 ▼)は日常の生活風景を一変させる力を秘めていて、ECMの数ある作品の中でも最も霊的な力が強い。 |
||
| 10 |  |
ECM 1996 Sinikka Langeland | Starflowers 今年(2010年)の5月に初来日したシニッカ・ランゲランの東京公演はソロ演奏だった。40人ほどの観客と共に小さな部屋で聴くことができたカンテレの響きは、なんとも幻想的で時が過ぎるのを忘れさせた。CD冒頭1曲目で和音がベンドする箇所がどうやって演奏しているのか分からず不思議に感じていたが、目の前で楽器を操作して同じ音を作り出すのを聴いたとき、新しい風景が視えた。温もりのある自然のなかの孤独だった。 この《スターフラワーズ(星の花々)》はアルヴェ・ヘンリクセンをはじめとするECMと縁の深い精鋭が参加したアイヒャーのプロデュースならではの作品で、近年ではマヌ・カチェの《ネイバーフッド》(ECM 1896)と並んで、ミュージシャンの組み合わせで想像を超えた化学反応を誘発した成功作といえる。 カンテレはフィンランドの伝統楽器だが、近年はコンサート用のカンテレも開発されていて、ここでシニッカ・ランゲランが弾いている楽器も伝統的なものではないようだ。しかも、彼女の奏法は民族音楽としてのカンテレのものとは若干異なった独自の工夫を凝らしたもので、本作で演奏している曲も自作が中心となっている。 曲によって調弦を細かく変更することで倍音の響きが変わり、歌の表情も変化する。歌の主題は自然のなかに潜む聖霊との交感であったり魂の寓話だったりする。万物のなかに神が宿るという観念は、日本でも、先住民であるアイヌのなかに日常の儀礼として受け継がれているが、大切なのは、その感謝を実際の行為として自然に返すことなのだろう。彼女の歌は、歌の内容と彼女自身が本当に一体化していて、彼女自身が森のなかから生まれてきた楽器――響きを宿す器――のように思われた。
|
||
| 11 |  |
ECM 2056 Ketil Bjørnstad | The Light 母国ノルウェーでは音楽家としてだけでなく繊細な意識を備え持つ作家としても著名なケティル・ビヨルンスタ[ノルウェー語の発音は、シェーティル・ビョルンスタ]だが、本作はこれまでに作曲した歌曲を集成したもの。冒頭の4曲はビョルンスタ自身の作詞によるノルウェー語の曲で、『四つのノルウェーの歌』と題されている。残りの曲はジョン・ダンの詩(英語)に付曲した歌曲集『光』。国内盤には後藤誠さんによる丁寧な解説文に加えて、ジョン・ダンの詩篇の翻訳(ジョン・ダン研究者の湯浅信之氏の著作から引用)、ビョルンスタの詩篇は飛鳥ノエル氏の翻訳で掲載されている。本作の内容を充分に味わいたいならば国内盤CDをおすすめしたい。 ビョルンスタのピアノとラーシュ・アンダーシュ・トムテルのヴィオラの伴奏でメゾ・ソプラノのランディ・ステーネが優しく穏やかに歌う。本作全体を柔らかく包んでいるのは、はかないもの、滅ぶもの、過ぎ行くものに対して注がれる慈愛の眼差しである。同時に、そのヴェールのすぐ下には悔悟と自責の苦さと痛みが透けて見える。普通ならば、それらを見せることなく巧妙に隠しつつ仄めかすようなやり方が洗練を生み、表現の深みと広がりへと結びつく。しかし本作では、それらが露出したまま、清楚な魂の美を展覧している。 思い出されるのは、大野一雄の舞踏が湛えていた震動する光、気配の刺繍、生命の綾取り――。身体が、傷つき疲弊して横たわっていながら、なお異界の存在に運ばれながら輝くことを許されているのは、舞踏が、内側から踊るかたちと型を見出す必然を深く願い求めているからであろう。このアルバムに収録された音楽は、どの曲もゆっくりとした動きのフォルムからなり、単純な民謡調の範囲に収まるものだが、どの一曲にもそれぞれの必然との思いがけない出会いの恩寵が伝わってきて痺れる思いになる。《海》(ECM 1545)や《リヴァー》(ECM 1593)をはじめ、やはりビョルンスタの視ている世界は違う。 昨年(2009年)刊行されたECM関連書籍『Windfall Light』にはビョルンスタのエッセイも掲載されているのだが、そこに本作のジャケット・カヴァーに関する話が出てくる。若いカメラマンがフィヨルドを見下ろす場所に建つビョルンスタの自宅にCDのブックレットの中で使う三人の演奏者の肖像写真を撮りにきた際、窓の外の風景がとても美しいからついでに撮影するように勧めたところ、結果的にその写真が表紙を飾ることになったのだという。つまり、アイヒャーとECMに特徴的なのは、考え抜かれたコンセプトや計算されたもの作りの姿勢ではなく、偶発的な出会いのなかに本質的なものと価値を発見する精神的姿勢なのだ、とビョルンスタは述べているわけである。 いまから20年ほど前に、私の妹が海外留学から日本に戻ってきたとき、ビョルンスタがパイプオルガンのために書いた曲を収録した3枚組の箱入LPを土産にもらったことがある。そのときは、音楽の単純な外見ばかりに気を取られてその良さがまったく分からなかった。今、再び聴いてみたらどんな感想を抱くのだろうか。しかしそのレコードは、もう手元にない。(ちなみにそのLPは、ロンドンのレコメンデッド・レコーズが経営するショップで購入したものだと聞いた) |
||
|
||||