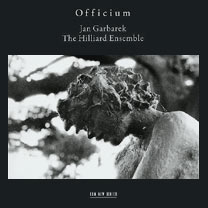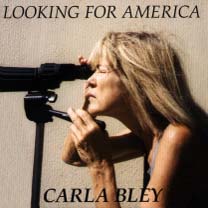|
多田雅範+堀内宏公
初出:CDジャーナル2003年6月号
(連載「レーベル研究・ECM」)
[2004.
1. 22. 改訂]

|
|
| |
hyde(ラルク・アン・シエル)のシングルを聴きながら、その耽美性にデヴィッド・シルヴィアンを連想し、そのシルヴィアンの作品に参加する、「釣りびとが緩やかに凍死してゆくかのような演奏」と形容されるスティーヴ・ティベッツの恍惚ECMサウンドまで、を、耳の手ほどきしてしまう不良中年である、私は。
|
|
| |
ECMはジャズのレーベルでもあり、古楽や現代音楽のレーベルでもある。4ビートのノリや熱いサックスに魅了されるジャズ・ファンからは否定され、録音に対しては「これはこの世のピアノの音ではない」とその虚構性を問題にされ、ジョン・ケージやヘルムート・ラッヘンマンまでを「美しく」録音してしまうことで、クラシック・ファンからも口を歪められてしまう、そんなレーベルでもある。
|
|
| |
マンフレート・アイヒャー 創立者はマンフレート・アイヒャーというコントラバス奏者としてジャズでもクラシックでもそれなりに腕の立つ、グラモフォンでの録音技師の経験もある青年。1943年ドイツの南部の町リンダウに生まれ、6歳でヴァイオリンを手にし、14才でコントラバスに転向。クラシックの音楽大学を出るが、関心はクール・ジャズから前衛ジャズに向かい、マイルス・デイヴィスの《カインド・オブ・ブルー》、スコット・ラファロのビル・エヴァンス・トリオ、アルバート・アイラー《スピリチュアル・ユニティ》に耳を焦がされていた。
|
|
| |
彼はライブ三昧に明け暮れる中で、自分の音楽的素養と録音技術で「今日的」な音楽をドキュメントすべく自らのレーベルをECM(Edition of
Contemporary Music)と名付け、1969年に立ち上げた。
|
|
 |
北欧の4人(ヤン・ガルバレク、テリエ・リピダル、アリルド・アンデルセン、ヨン・クリステンセン)、フュージョン・ブームの口火を切ったチック・コリアの《リターン・トゥ・フォーエバー》(ECM 1022)、さらにキース・ジャレット、チック・コリア、ポール・ブレイらのピアノ・ソロでの録音、これらが評判を得た。
|
|
 |
多くの新しいミュージシャンに焦点をあて、とりわけギタリストの登用(パット・メセニー、ジョン・アバークロンビー、ラルフ・タウナー、エグベルト・ジスモンチなど)が光った。専属ミュージシャンによるソロや様々な組み合わせによる小さなユニットでのアコースティックな表現を制作することで(名作多し)、1970年代を通じて強烈なECMのレーベル・イメージを確立した。ギターに重きを置きながらも、ECMは電化サウンドを排除したが(多くのベース奏者のソロ作が象徴的だろう)、今の視点からみれば、そこでは、西洋クラシック音楽の伝統に軸足を置いた「もうひとつのフュージョン」を試みていたと理解できる。
|
|
 |
1984年にはクラシック・ルートに流通させるための
"ECM NEW SERIES" をアルヴォ・ぺルト《タブラ・ラサ》(ECM 1275)のリリースで開始して、広範な音楽ファンの支持を得ることに成功した。この〈ニュー・シリーズ〉では、その後、アルフレート・シュニトケ、ギヤ・カンチェーリ、ジェルジ・クルターグ、ギャヴィン・ブライヤーズ、ハインツ・ホリガーといった作曲家を取り上げつつ、ハイナー・ゲッベルスの舞台音楽やエレニ・カラインドルーの映画音楽、ヘルダーリンやT.S.エリオットの詩の朗読、さらにはジャン=リュック・ゴダール監督作品のセリフ・背景音入りのフル・サントラ(映画と全く同じ長さのCD)などもリリースしている。
|
|
| |
ジャズとクラシックの素養を持つアイヒャーは、その耳の経歴を青年期から幼年期へと遡行するかのようである。
|
|
| |
アイヒャー帝国の迷宮 ECMは創立してから34年が経ち(2003年現在)、カタログは900を超えようとしている。各国のジャズやクラシックの権威ある音楽賞はすべからく手にしている。と同時に、ほとんど無名でありながら聴く者を美に痺れさせる隠しキャラ的名盤も多数存在する。"the most beautiful sound next to
silence" この「沈黙に次いで最も美しい音」をサブ・テーマとするECMレーベルの統一感は、アイヒャーの「君たちは意のままに演奏して良い。だが服従せよ」、と言わんばかりの徹底さによる。作品にはそこにもうひとりのミュージシャンが参加していると評され、"produced by Manfred Eicher" のクレジットは、もはや伝説化して語られている。
|
|
| |
しかし問題はこの「美しさ」だ。ツェランやカフカ、ヘルダーリンを引用した解説文やアートワークを含めたドイツ人らしい徹底した仕事には、まさにヨーロッパの、ゲルマン民族のガイストを感じるが、醒めた知性に潜んで狂気に反転するような美しさが問題なのだ。見る者の内面に痕跡を残すかのようなジャケットやインナー・スリーヴの選択、これもアイヒャーの監修・判断によるものだ。
|
|
| |
私は読者に助言する、ECMの迷宮に手を伸ばしてはならない――。

|
|
| |
ECMセレクション
―― 多田雅範+堀内宏公
が選ぶ8枚のアルバム
 Album cover
reproduced by courtesy of ECM Records, Munich
●ジャケット写真はECM Recordsの許諾のもと、掲載しております。(musicircus)

|
|
| |
ヤン・ガルバレク+ヒリヤード・アンサンブル
Jan
Garbarek | The Hilliard Ensemble
《オフィチウム
Officium》 ECM
1525 (1994) |
|
|
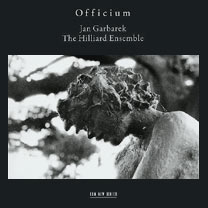 |
古楽合唱団〈ヒリヤード・アンサンブル〉とヤン・ガルバレクのサックスを組み合わせた世界的なベスト・セラー《オフィチウム》の天上の美しさは、あまたのヒーリング・ミュージックを駆逐さえした。16世紀スペインの作曲家クリストバル・デ・モラレスの曲を聴いたアイヒャーは、その感激に、即座にガルバレクの音を思い描いたという。 |
|
| |
キース・ジャレット Keith Jarrett
《ケルン・コンサート
The Köln
Concert》 ECM 1064 (1975) |
|
|
 |
ピアノ・トリオ〈スタンダーズ〉の活動で、かつてのピアノの貴公子は今ではジャズ・ピアノの帝王の座に君臨している。ここでは彼の人気を決定付けたピアノ・ソロ作品群から、当時の若者に「ひとはここまで美しい音楽を作れるのか」と陶酔させ、70年代のジャズ喫茶ではリクエスト禁止指定まで受けた、“時代の名作”を。 |
|
| |
ポール・ブレイ/ゲイリー・ピーコック/ポール・モチアン
Paul
Bley | Gary Peacock | Paul Motian
《ノット・トゥー、ノット・ワン
Not
Two, Not One》 ECM 1670 (1998) |
|
|
 |
耽美で官能的な美しさを弾く不良ピアニスト──この点で対抗できるのはコンボ・ピアノの渡邊琢磨だけだろう──であるブレイだが、“スタジオに駆けつけ、タクシーを外に待たせている間に弾き終える”という、彼の即興魂は(深いぞ!)、ゲイリー・ピーコック、ポール・モチアンとの35年ぶりの邂逅でも不変であった。新たなる名盤の誕生。 |
|
| |
ジョー・マネリ/バール・フィリップス/マット・マネリ
Joe
Maneri | Barre Phillips | Mat Maneri
《テイルズ・オブ・ローンリーフ
Tales
of Rohnlief》 ECM 1678 (1999) |
|
|
 |
ECM第2のプロデューサーとして辣腕を奮うスティーヴ・レイク。老怪人ハル・ラッセル(ECM 1455, ECM 1484, ECM 1498)、エヴァン・パーカーの音響ユニット(ECM 1612, ECM 1693, ECM 1852)、英国トラッドの伝説ロビン・ウイリアムソン(ECM 1732, ECM 1785)……。そして、微分音による微細なソノリティの変化に、能や狂言の表現形態とも通ずる発見をもたらすこのジョー・マネリ(ECM 1597, ECM 1617, ECM 1661)。(本作国内盤CDの福島恵一氏のライナーノーツを当サイトに復刻掲載
▼) |
|
| |
ラルフ・タウナー Ralph Towner
《アナ ANA》 ECM
1611 (1997) |
|
|
 |
バルトーク+ストラヴィンスキー+スパイク・ジョーンズ……。子供の頃に聴いていた響き。タウナーの跳ね上がるようなギターのつまびく美しさの謎は、彼の幼少期の耳にあったとのこと。「Joyful Departure」は地中海に囲まれたパレルモ(彼が住む)に降り注ぐ太陽の眩さを音像にしたかのよう。ついに、タウナーは、名作《ダイアリー
Diary》(ECM
1032)[1974]を超えるギター・ソロ作品を作ったのだ。前半がクラシック・ギター、後半が12弦ギターによる演奏。武満徹に捧げた曲も収録。 |
|
| |
ディノ・サルーシ Dino Saluzzi
《アンディーナ
Andina》 ECM
1375 (1988) |
|
|
 |
冬空に打ち上げられ音もなく散りゆく花火の響き。このバンドネオン奏者の登場は衝撃だった。喪失した故郷への強烈な想いと生き残ってしまった者の夜の孤独を描く、アストル・ピアソラ以降に(タンゴとも訣別して)出現するに相応しい音だ。抑え切れない生々しい演奏は安易な自然讃歌を突き崩す。初期の《Kultrum クルトゥルン》(ECM 1251)、《Andina
アンディーナ》(ECM
1375)、《Mojotoro モホトロ》(ECM 1447)は、いまだに胸を掻きむしるものだ。
註記:
「クルトゥルン」はチリの先住民マプーチェ族の巫女が儀礼で用いる太鼓。Cultrún, Cultrum, Kultrung,
Kultrum, Kultrun とも表記されます。
『ECM catalog』の初版(河出書房新社刊、2010年)では、ECM 1251のタイトル「Kultrum」のカナ表記を「クルトラン」としていますが、その後、南米音楽の専門家の方が「クルトゥルン」と表記していることが分かりました。現地マプーチェ語の発音だと「クルトゥン(アルファベットで表記すると
kulxug )」
が近いようです。(アクセントは後ろの
u、すなわち「トゥ」の音)
◆発音(音声ファイル):現地語発音
■
◆マプーチェ族の音楽とその文化(チリ民俗音楽について
3)
/近藤元子 ■
|
|
| |
アルヴォ・ペルト Arvo Pärt
《テ・デウム Te Deum》 ECM
1505 (1993) |
|
|
 |
旧ソ連バルト三国のひとつ、エストニア出身の作曲家ペルトの作品を規定する、東方正教会と中世の音楽の研究を通じて獲得されたティンティナブリ(振鈴)様式とは、他者と神への“祈り”の導入にほかならない。「私の音楽は、あらゆる色を含む白色光に喩えることができよう」という発言はあまり知的ではない気がするが、無私の宗教的崇高を呈示できる才能とはそういうものなのかもしれない。 |
|
| |
メレディス・モンク Meredith Monk
《ヴォルケイノ・ソングズ
Volcano
Songs》 ECM 1589 (1996) |
|
|
 |
モンクは変幻自在のヴォーカリゼーションによって“声楽音響劇”という新たなスタイルを築き上げた。ここでは声を純粋に楽器のように扱いながら、次第に自然描写への傾倒が明らかになった本作を挙げた。アカペラ・デュエット「Walking Song」の突出した美しさにも注目。モンクのアルバムはどれも忘れがたい。郷愁と優しさに満ちた《ドゥー・ユー・ビー
Do You Be》(ECM 1336)、壮麗なオペラ《アトラス》(ECM 1491/2)、そして屹立した世界を見せたECMでの記念すべき第1作《ドルメン・ミュージック
Dolmen Music》(ECM 1197)(トリオ国内盤LPのタイトルは『ニューヨークの子守唄』。竹田賢一氏のライナーノーツを当サイトに復刻掲載
▼)。 |
|