|
|
|
|||||||
 |
高橋悠治の肖像
高橋悠治の音楽を聴いていると、世の中のほとんどの音楽とは違った体験が訪れる。起承転結や劇的でリニアな展開はまずない。どこかに行き着くことが大事なのではなく、その場で明滅し、揺れ動き、あるいは迷いながら進み、後戻りし、やり直しながらさまようことが、違った手順で繰り返される。はじまりも終わりもない。霧が立ち込めたと思うと強い陽射しが結晶をきらめかせ、すべてが静止した黄泉の世界にいるのかと思うと、魚群や鳥の群れと一緒に空と海に溶けてしまっていたりもする。呪文かと思うと、「あのね」と語りかけてくる親しい打ち明け話だったりもする。期待は満たされないし、予感は裏切られる。そうかといって、聴き手の数だけ違った音楽がそこにあるといったものでもない。もともと番地がないにも関わらず、手紙は何度も書かれて投函される。一音、また一音と。 赤瀬川原平の路上観察やトマソン物件の報告写真に見入っているとき、高橋悠治の音楽を思い浮かべることがある(その逆は、滅多にないが)。ありふれた景色(地)のなかに異様な光を帯びた物語(図)がじわりと浮かび出る瞬間の、そのはかなく、落ち着かない、曖昧さと明晰の間をブランコのように往復する波の運動と向き合うとき、自分と世界が反転するような意識にとらわれる。そのときには、人も音も、すでに向こう側の世界にいるのだろうか。だが分かってしまえばゲーム(勝負)はそこで終わり、日常の目覚めた言葉の論理に縛られる。だから終わりそうで終わらず、あるいはゲームが始まっていたことさえ分からなくして、中心は置かず、起点は省かれ、記憶もできるだけあちこちでばらばらに消えていくように、おぼろげな論理だけが足もとを微かに照らしている。 風景と音それ自体は中間領域でゆらめきながらどこにも着地することはない。上下の層に移動するための梯子、または、岸の隔たりに架け渡す橋を見定めつつ、そうした経路の意味を無化する仕掛けと視線が、つねに作品の内側に隠されている。聴き手を強制してどこかへ連れて行くことをせず、興奮させ盛り上げることもなく、道端で風に揺れる花びらのように穏やかなあり方。これらは、新たな観点で構成された「語り物音楽」ではないだろうか。 アート&テクノロジーの過去と未来 |
||||||
 |
|
||||||
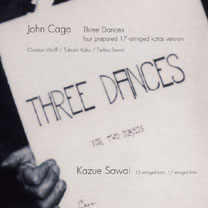 |
ジョン・ケージ:3つのダンス/沢井一恵
|
||||||
 |
平曲/須田誠舟
「平曲」は盲目の琵琶法師が平家の盛衰を弾き語ったもので、「平家琵琶」、「平家」とも称される。昨年の「この10枚」では今井勉検校の平家琵琶のボックスCDを選んだが、薩摩琵琶の伝説の名手・辻靖剛と平曲研究の第一人者・金田一春彦に師事したこの須田誠舟の平曲もじつに見事で比類がない。収録曲は、「祇園精舎」、「木曾最期」、「大原御幸」で、1997年11月6日紀尾井小ホールでの収録。監修は師の金田一春彦。モノラル録音だが、独特な音律と産字による語りの世界に深々と浸るには充分。(発売元→ ■) なおジャケット・デザインは造型作家で「大岡信ことば館」副館長の岩本圭司によるもの。外縁部分に版画特有のにじみを残したままレイアウトされており、それが、収録された琵琶の音と絶妙に相互干渉していて秀逸だ。「大岡信ことば館」の展示空間構成も写真で見る限り素晴らしく、JR三島駅北口から東に徒歩1分という好立地なのでいつか訪ねてみるのが楽しみだ(■)。ミュージサーカスでの私のコーナー名「彩耳記」は大岡氏の著書名から頂戴したものである。 |
||||||
 |
MAPUCHS /
CHILI(チリ、マプーチェ族の音楽)
ディノ・サルーシが南米の空想的民俗音楽を奏でたアルバム《Kultrum クルトゥルン》(ECM 1251)のイマジネーションの源泉に導かれるようにして出会った。ジャケットにはなぜか日本語で「世界のこだま」という文字が配されているが、解説書はすべてフランス語。ごく一部、英語の曲目解説も掲載。 川田順造の《サバンナの音の世界》(▼)でも感じたことだが、無文字社会の言葉と声には瑞々しい力が溢れている。 マプーチェ族の音楽とその文化(チリ民俗音楽について
3)/近藤元子 ■ |
||||||
 |
Zen Hoyo,
Liturgie du bouddhisme zen(音禅法要)
禅に音を通じて触れることを目的としてツトム・ヤマシタが創始した「音禅法要」は、パリなど海外でも行なわれている(2009年秋のパリ公演はインターネットで中継され、本サイトでも案内ページを特設した ▼)。大徳寺では2008年以降、毎年音禅法要が行なわれており、私は縁あって2009年4月25日の法要に参加した。 雨音と鳥の啼き声だけが聞こえる静寂。僧侶の唱える経文。広がっては静まるサヌカイトの響きの波紋。そこに観想した悠久の大宇宙の生々流転。 日本財団ブログから(2009年音禅の記録動画あり)
■ |
||||||
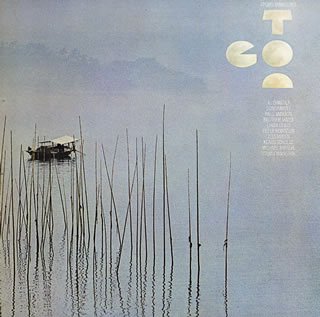 |
|
||||||
 |
メルシー/マグマ
10代半ばの頃にある輸入盤ショップの店長が、「キミの好みなら、まず《マグマ・ライヴ》(2 LP)は絶対に聴いた方がいい。ちょうどアメリカのトマト・レーベルが再発してうちにも数セット入荷する予定だから取り置きしておこう。分割払いでも構わないし・・・」と薦めてくれたのがマグマの音楽との出会いでした。(ちなみに、その日購入したLPがツトム・ヤマシタ《Go Too》だった) この1984年発表の《メルシー》というアルバムは、SHM-CD盤の解説書に「MAGMA信者の多くが評価しない不運のアルバムである」などと書かれている。たしかに当時「ファンキーで明るいマグマ」に幻滅したファンは多かったようだ。私は7インチのドーナツ・シングル盤(JARO 4195/A面「OH OH BABY」、B面「OTIS」)を聴きながら、でもこの「明るさ」は光の方へ進んでいるのだから、むしろ当然なのだと合点が行き、直後にマグマが活動を一時停止して「オファリング」に移行したときも違和感はなかった(むしろ“Offering”のほうが光と闇のコントラストは深い)。クリスチャン・ヴァンデールはジョン・コルトレーンとオーティス・レディングへの共振を隠していない。 TV出演時の「OTIS」の演奏
■(YouTube) |
||||||
 |
響(kyo)/藤原道山、冨田勲
遅まきながらCDを購入したのは昨年の秋だったが、日本音階を使ったメロディを主体に、冨田勲が得意とする印象派風のオーケストレーションで色付けされたシンセサイザーと藤原道山の相性の良さにあらためて惹きつけられた。古典に、クロスオーバーに、現代音楽にと、縦横無尽の活躍を続ける藤原道山の演奏は、いつどの会場で接しても聴き手を納得させる次元の高いものばかりで、彼が演奏する以上、凡作は存在しないとまで言いたくなる。 5曲目「仏法僧に寄せる歌」は、愛知県鳳来寺山を舞台とした2006年の野外シンフォニーの主題曲だが、このプロジェクトは、冨田勲が60年以上前に出会った当地の仏法僧の鳴き聲の美しさに鏡岩という自然の反響壁が影響しているのではと直感して行なった音響実験と関連している。ライナーノーツには、この鏡岩に面した地にかつて豊川海軍工廠があり、終戦のほぼ一週間前にその工場だけを襲撃にきた124機のB-29から3,000発の絨毯爆撃を受け、そこで働いていた女工さんたちが犠牲になったことが記されている。地元出身の冨田勲にとって、このシンフォニーはレクイエムでもあった。 本作にはその他全14曲が収録されているが、最後の曲「お爺さんの里」で聴ける藤原道山の愛娘の歌声が可愛らしい。 鳳来寺山
鏡岩のサラウンド音響を求めて ■ |
||||||
 |
ジョナサン・ハーヴィ(ハーヴェイ):弦楽四重奏曲(全4曲)他/アルディッティ四重奏団
“musicircus”の開設時に多田さんと21枚の「金字塔」アルバムを選んだ際、私はラ・モンテ・ヤングの「ドリーム・ハウス」、黛敏郎「涅槃交響曲」、吉増剛造「石狩シーツ」、ピリスの弾くシューベルト「幻想ソナタ」と共に、ジョナサン・ハーヴェイ jonathan harvey の《bhakti(バクティ)》を挙げた。(▼ musicircus Disc Award; masterpieces. 21 discs first announcement in Nov. 2002 ) 今回ジョナサン・ハーヴェイが来日して行なった講演のなかで、最近完成したばかりだという短いドキュメンタリー・フィルム「Towards and Beyond」(約48分)が上映された。じつはこの作曲家が語る言葉には過度に観念的なところがあり、正直に言って理解し難い面も色々あるのだが(昨年春秋社からジョナサン・ハーヴェイ自身が書いた著書が翻訳刊行されたが、私には書かれている内容がほとんど分からなかった)、しかしこの映像作品はハーヴェイの音楽の核心を非常に明解に捉えていたように思う。いつかもう一度見たいと願っている。 |
||||||
 |
SOUND SPACE
EXPERIMENT; Steel Drum Works Selection/Kuniko Kato(加藤訓子)
このときの公演については、私は以前 JazzTokyo にレポートを書いている(当サイト内「彩耳記」に転載 ▼)。終盤の瞑想的なシーンについて、「加藤のパーカッションもピアニッシモとなり、英語による詩の朗読を交えて──“Eternal”という言葉が耳に残る──散発的に音が響く。身体の微細な動きに潜んでいる、強く、激しい、止むことのない力の波。充溢する振動。」と書いたのだが、今このCDを聴く限りは、“Eternal”という言葉が出てこない。うううん、あれは幻聴だったのだろうか・・・。 昨年(2010年)、埼玉芸術劇場で体験した「STEEL DRUM WORKS」は鮮烈だった。アサヒアートスクエアでの初演を記録したDVDもコンサート会場で販売されているが、一般発売はされていない。しかしながら、この作品は会場で聴かないと本当のところは何もわからない(DVD抜粋はこの加藤訓子HP内のページで試聴できる ■)。音楽空間クリエーターの宮本宰とのコラボレーションにより会場内に設置されたスピーカー自体も独立した楽器として操作され、スティーヴ・ライヒ作品の加藤自身による編曲版では、生演奏と共に、事前に録音された多声部が各一台ずつのスピーカーで絶妙なバランスで再生/演奏されて、えも言われぬサウンド・スペースを作り出す。(加藤訓子による渾身のスティーヴ・ライヒ作品集CDは今年発売の予定) 嬉しいことに今年2011年の春に「STEEL DRUM WORKS」は愛知と横浜で再演されるようだ。 Pro Sound Review Multi-Channel Sound System & Design |
||||||
 |
柴田南雄とその時代
第一期
今回フォンテックから新たに発行された『柴田南雄とその時代・第一期』は、だが上記のレコードやCDとは違った意味合いをもっている。その収録音源と映像のほとんどが、柴田家に保存されていた貴重な資料群だからである。鑑賞を目的とした録音や撮影ではないため状態が良くないものもあり、DVD『宇宙について』などは一般的な商業作品の基準では普通は発売されないだろう。しかし、柴田家の応接室に招かれて、膨大な数の古いオープンリール・テープやビデオ・カセットから選りすぐりの資料を体験していると思ってみればよいのであって、唯一残る貴重な演奏を体験できることは、画質や音質の瑕疵をあっさりと覆い隠す。たとえば『宇宙について』第5章「山田の<おらッしャ>」に移る際、演奏者が楽譜を上手の台に次々と投げ棄てていく場面を見ながら、わたしは当日会場で体験したのとまったく同じ衝撃に襲われた。本質は確実に「記録」されていたのである。 繰り返しがきかない一度きりの時間と場所で許された演奏には、その背後に熟考と瞬間的な冒険の賭けが潜んでいる。本作にはそうした営みが生む、固有の瑞々しい鼓動が溢れている。そして、西洋音楽に対し弛まぬ批評精神を貫き、音楽を「知的な遊び」として探究した柴田南雄という存在を通じて扉が開かれた、「日本の音楽」との新たな遭遇のよろこびにも耳と心を傾けたい。2011年秋の第二期の刊行が楽しみだ。 彩耳記 No.2 「柴田南雄の《追分節考》と《ふるべゆらゆら》」
▼ |
||||||
|