| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画
|
| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |
▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |
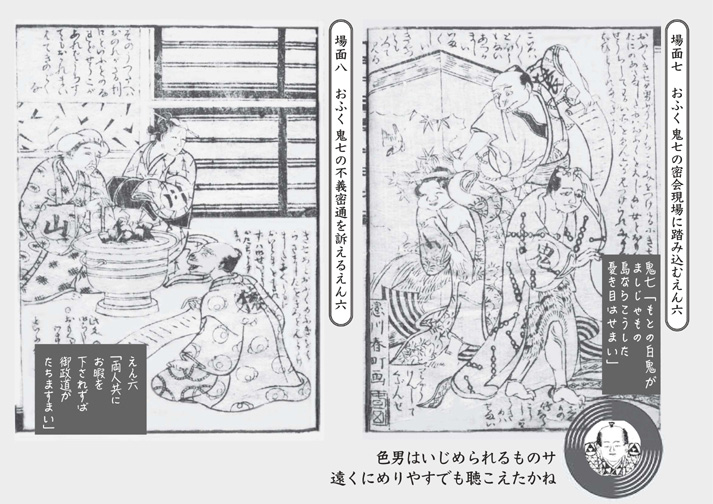
場面七
おふく鬼七の密会現場に踏み込むえん六
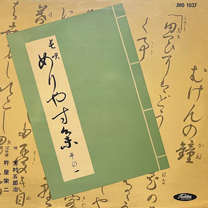
十吋盤『めりやす その一』(東芝JHO-1037)
演者;芳村五郎治(長唄の唄方)、杵屋栄二(三味線)
「もとの白鬼がましじゃもの。島ならこうした憂き目はせまい」
場面八
おふく 鬼七の不義密通を訴えるえん六
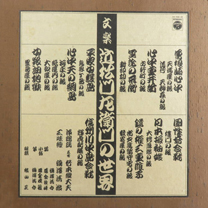
十二吋盤『文楽 近松門左衛門の世界』(コロムビアWX-7081-7090)
演者;五世竹本織大夫(浄瑠璃)、鶴澤清治(三味線)他