| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画
|
| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |
▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |
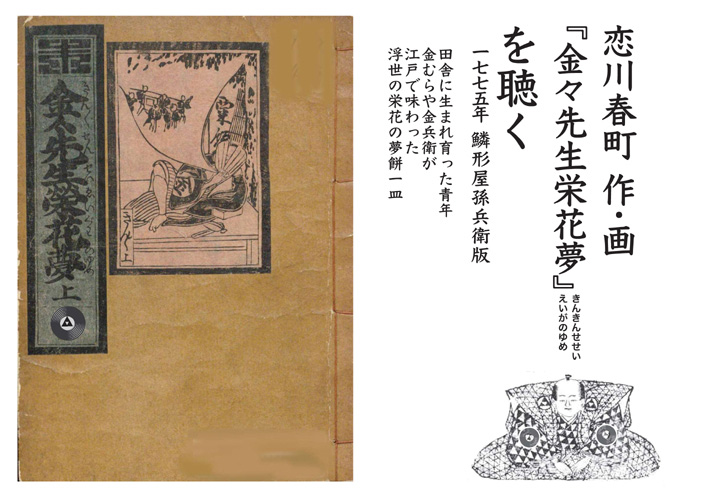
序
|
||||||||
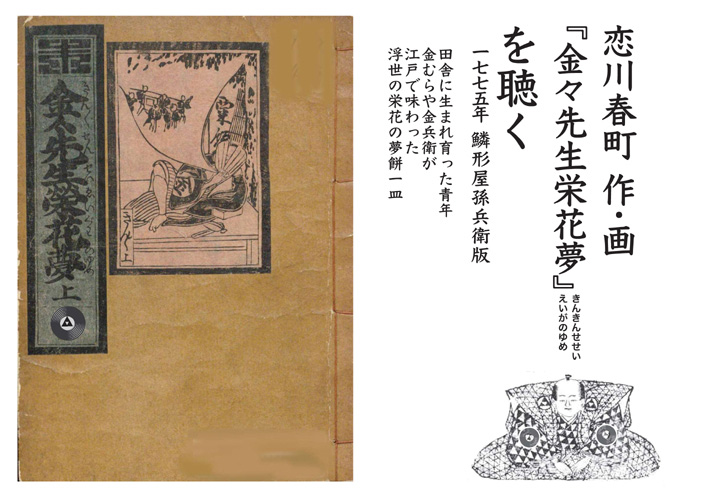 |
||||||||
序 |
||||||||
| 恋川春町[こいかわ はるまち]と音楽ということでは富本節[とみもとぶし]を真っ先に思い浮かべた方もいらっしゃると存じます。と申しますのは、NHK大河ドラマにも出てきた富本午之助[とみもと うまのすけ](後の富本豊前太夫[とみもと ぶぜんだゆう])をはじめとする太夫、富本節の曲調を完成させたと伝わる名見崎徳治[なみざき とくじ](三味線)などを、もじった名前で登場させて、富本節の大宣伝とも読めるような様相を呈している『参幅対紫曽我[さんぶくついむらさきそが]』(1778)があるからです。 |
||||||||
| しかし今回、もっと多種の声曲[せいきょく]が聴こえてくる戯作[げさく]ということで選んだのが『金々先生栄花夢[きんきんせんせいえいがのゆめ]』(1775:鱗形屋孫兵衛[うろこがたや まごべえ]版)です。恋川春町がテキストも画も手がけた意欲作で、黄表紙最初期の最重要作です。 |
||||||||
| この戯作は、中国の唐の時代の小説に出てくる故事「邯鄲[かんたん]の枕」(「邯鄲」「邯鄲の夢」「一炊の夢」とも)に倣っています。一言で申せば、いろいろあったと思ったのに全部束の間の夢の中の出来事だったかぁ、というものです。私たちも子供時分に習ったような覚えがありますよね。この故事は、日本で古くから芸能(能「邯鄲」他)や文芸に活用されてきました。『金々先生栄花夢』は、片田舎に生まれ育った青年 金むらや金兵衛[かなむらや きんべえ]が、お金持ちになり浮世の楽しみを味わいたくて江戸に出てきて随分遊んだけど、束の間の夢だったという大筋です。恋川春町は地方大名の家臣(江戸常勤)です。能・狂言は教養・嗜みだっただろうと思います。謡曲「邯鄲」のみならず、他の謡曲ももじりを加えた形でとりいれられています。 |
||||||||